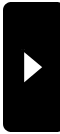2009年04月27日
雨の楠公祭


昨年の楠公祭はお天気に恵まれ多くのイベントをのぞき回った。本年は雨模様の天候で各種のイベントも縮小気味のようだ。生誕地での式典はテントの中だし、観心寺での行列は開催が不明だし、建水分神社(たけみくまりじんじゃ)での奉納演舞は順延となった。時間の都合で奉納演舞の一部のみを覗かせてもらった。高校生の和太鼓グループで太鼓演奏と傘を使った民族舞踊を披露してくれた。神様への奉納という次第だろう。お若い人々が伝統芸能に情熱を傾けてくれることは非常に喜ばしい。歴史と伝統への畏敬と継承があってこそ、始めてアイディンテティを持った民族として生き残っていけるのではなかろうか。
地元の高校生による和太鼓の奉納です。

傘を使った演舞、演目は田原坂。

楠公さんが戦死されて600年以上も経つが、こうして多くの方々が今も参拝を続けておられる。たった一人の人間がもたらす影響力の大きさに改めて感服せざるを得ない。生物的には非常にかよわな微々たる存在にすぎない1個人が、時代をまたいで生き残っていく。個人の持つ思想性や生き様のもたらす力に畏敬の念を持たざるを得ない。心して肝に銘じておきたい。

さて奉納演舞の後は恒例の餅まきとなった。神職の方が櫓にのぼり、かけ声と共に多くの餅が飛び交ってくる。1日順延となったので餅は結構堅い。顔に当たって悲鳴を上げる子どもたちも出てくる。それでも人をかき分けての拾いあいだ。小生も参加させてもらって、今年は4個ほど拾った。縁起物なので大事に頂くことにしよう。うち1個には当選チケットがはいっており記念品との交換というおまけまでついてきました。ラッキーなひとときでしたね。こうした伝統行事はあちこちで取り組まれておりますが、大事に継承していきたいものです。

2009年04月20日
春ごと(名句又は米久とも)
ご馳走作りの立役者はこれでしょう。銀シャリ程おいしい食が他にありますでしょうか。

山間地の農作業はかなり厳しい。今のように軽トラや耕耘機のような便利な道具があったわけではなく、動力と言えばせいぜいが牛の力ぐらいであった。しかも急な傾斜の棚田で一枚あたりの耕地面積は狭小、片道数キロも離れた田畑に通うことも珍しくなかった。そんな環境下で体を休め新たな鋭気を養う必要性が極めて高かったのだろう。さまざまなお祭りや行事が工夫されたようだ。春ごとは4月の下旬、地域の神社仏閣のお祭りに併せて、ご馳走を作り遊山見物する習俗だったようだ。いわば忙中閑ありの骨休めだったのだろう。
自称シェフ軍団が勢揃いです、さてどんな料理が飛び出すのやら。

おっ、これはすごい、桜のチップによる本式の燻製料理です。

きりたんぽ(もどき)も焼き上がってきたようです。

我々の復活では神社仏閣との連携まではおぼつかないが、ご馳走を作って今は盛りの花見物としゃれこもうとの魂胆だ。無論、異論のある方などお一人もないだろう。会場は持尾城趾、かの楠木正成公が作られた城塞群のひとつでる。何とも見晴らしのいい場所で、本丸跡からは大阪平野が一望できる。かっての戦の折りには遠征軍の鎌倉軍勢が来襲するのを見張っていたのではなかろうか。当然、地元の方々もお招きしてのお祭りとなった。人材豊富な集団のこと、大概のことは自前で調達できる。飯炊き屋も焼き鳥屋もピザ屋も串カツ屋もコーヒー屋もきりたんぽ屋も・・・・・・・・・・・・・・・・何でもそろっているのである。2時間ほどかかって程よく仕上がってくれた。昼食と兼ねてさあ宴会だ、おっとっと、車の方はノンアルコールでっせ。
うろうろそわそわ、臭いに引き寄せられるのかな。

ベビーカーでのご来場もありーです。しっかり食べてや。

ピザ屋の営業も始まったようです。無論、石窯焼きですよ。

ご馳走が多すぎてどこから食べたらいいのか皆さんお困りのようで。小生が最もお気に入りだったのは下記の画像です。これを食べますと何といいますか、無上の幸福感に包まれ、至福の一時となります。自宅ではどうあがいても食べることができない最高の料理ではないでしょうか。担当シェフのUさんは、意図的に作ったのだとのたまってますが、さあそれはどうだろうか。
本日最高の料理でした。これに勝る食べ物を小生は知りません。

2009年04月09日
桜並木の街道
当地では桜が満開です。まさに春爛漫といった景観ですね。


元々桜はあまり丈夫な樹ではないですよね。「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」とも言い伝えられるように、桜を切るのは馬鹿だとされてきました。つまり剪定が桜にとって非常に悪い、というか切り口から雑菌がはいって腐りやすいのですね。公園等で管理状態を見てますと、剪定した場合には腐敗防止の防腐剤みたいなものを塗布しておられるようです。
幹から直接咲き出した花もいいものです。枝振りはありませんが。

桜を愛でようとおもえば、山手に植えるのが一番でしょうが、一般的には街道筋に植栽される事例が多いようです。古来から日本人に愛された来た樹木、出来れば生活に密着した場所で、との思いがあるのでしょうか。街道筋の桜と言えば思い起こされるのが故佐藤良二氏である。ご存じの方も多いだろう、太平洋から日本海まで続く桜の回廊を作ろう・・・・・・・・・・見果てぬ夢を追いかけ続けた御仁である。国鉄バス(当時)の車掌をしていた同氏は、給与の大半をつぎ込み生涯を費やして2000本の桜を植え続けられたとか。世間や親族や家族からは変人扱いされながらも、信念は変わらなかったようだ。健康に恵まれなかった同氏は志半ばの47歳で急逝されたが、現在は地元の方々がその意志を引き継いでおられるとか。
太平洋と日本海を結ぶ程の規模はありませんが。当地の桜の回廊です。

佐藤良二氏が乗務しておられたのは国鉄名金急行線(現在は廃止)で、名古屋と金沢を結ぶ長距離バスである。国道156号線といったほうがわかりやすいだろうか。かの荘川桜で有名な所だ。余計な解説を加えるよりは、直接ご覧になられることをお勧めしたい。季節的には4月の上旬から中旬にかけてであろうか。沿線には宇野千代女史の「淡墨の桜」で著名になった樹齢1500年ともいわれるエドヒガンの淡墨桜(うすずみざくら)があるので、お立ち寄りを願いたい。開花期は相当な混雑となるので、華やかさはないがオフシーズンが狙い目かもしれない。古木が発する不思議なオーラーに魅了されるかも知れませんよ。
この界隈は樹齢30年くらいでしょうか。

2009年04月08日
さくら祭りの開催
日頃の行いが良かったのでしょうか。昨日の雨とはうってかわり、朝から晴れ上がってくれました。絶好のさくら祭りとなったようです。当地での桜の満開は4月の上旬、時期的にも最適な日取りですね。早朝から仲間達が準備にはいっているかと思います。昨年はスタッフとして参加しましたが、本年は勘弁してもらって撮影班に回ることとしましょう。10時に駐車場の河内小学校に着いたら満車状態でした。少々待って隙間を探してもらい入庫、地元の方々も心待ちにしておられたようで早めに満車となったようです。町のシャトルバスも出てますが、徒歩で弘川寺へと向かいます。道中、裏山に咲くヤマザクラも満開のようです。山が白く彩られております。西行法師も草葉の陰で見とれておられるのではないでしょうか。
弘川寺の桜も満開となりました。絶好のさくら祭りです。

寺内に入ると里山倶楽部のNsさんとKsさんに鉢合わせ、植樹班のスタッフとして待機しているのだとか。若いお二人が休日をこうして森の保全と植栽に費やしてくれていることを、とても嬉しく思います。華やかな遊び場がたくさんあるだろうに、土にまみれ藪を切り開き、苗木を植え、花々を育ててくれるお若いカップルに幸多かれと願わずにはいられません。記念植樹の場所は弘川城趾、ここから急坂を1時間ほど登った山の中腹にあります。家族連れや子ども達に事故がないように、安全に留意した引率をよろしくお願いします。
植樹班の集合です。家族連れで弘川城趾まで山登りを。

さてイベント会場を覗いてみましょう。こちらでも里山倶楽部の面々が大活躍中です。毎年のことで手慣れたもの、テキ屋さんよろしくお客の呼び込みも堂に入ったものです。輪投げや竹細工、太鼓作りに米粉パンの焼き方教室、里山商品の販売、里山倶楽部の活動紹介・・・・・・・・・・・・・エリアが広がっていきますね。無論、他の団体さんや地元のお母さん方の出店もあります。各種のボランティア団体も展示を行っているようです。まずは仲間内の店舗から紹介しましょう。
自作のパン焼き器です。子ども達が大好きですね。新婚のIkさんが店開き。

こちらは手製の輪投げのようですね。京都から駆けつけたInさんがスタッフに。

こちらは竹工房のようですね。Uさん、Okさん、Omさんが活躍中です。

料理名人のKさんがヘビパン作りの指導を。地元産の米粉パンです。

こちらは里山倶楽部のパネル展示、PR活動も抜け目がありません。

本日は竹炭コーヒーではなく里山商品の販売のようです。Naさん。

さてさて手前味噌の画像ばかりでもつまらないですよね。他の活動も紹介しましょう。ボランティア活動中のささゆりさんや米粉パンの工房やお汁粉屋さんや里山商品の販売や青物野菜や植木の販売やら・・・・・・・・・・・・・・・・多種多様なお店が並んでいます。全部をお見せできないのが残念ですが、来年のお祭りには是非ご参加下さい。来春も多分四月の第一日曜日(4月4日)かと思います。
ささゆりさんによる焼き餅販売。ヤキモチはお得意?。

米粉を使ったパン屋さんです。道の駅で販売している方かな。

桜の下での会食は楽しそうですね。甘いのがよく売れています。小生も汁粉をば。

人出も多くてどのお店も大繁盛のようですね。

お天気に恵まれて皆さん楽しそうです。やはり春先は桜の花見物でしょうか。日本人にとって桜は特別な花なんでしょう。かってテレビで放映してましたが、国鉄バス(当時)の車掌をしていた方が太平洋から日本海まで続く桜並木を作りたいと願い、生涯を桜守りとして捧げたお話がありました。実話だそうです。数年前につれあいと当該の桜を岐阜の山中に訪ねましたが、街道筋に古木がひっそりと息づいていました。今も地元の方々の手によって大切に守り育てられているようです。

2009年03月30日
弘川寺さくら祭り
例年のことだが、4月の第一日曜日には弘川寺でさくら祭りが開催される。河南町の古刹である弘川寺はご存じの方も多いだろう、かの西行法師の終焉の地でもある。河南町の花が桜、それに西行法師が愛した花も桜ということもあって、ここにはたくさんの桜樹が植え込まれている。無論、里山倶楽部の面々の力によることが大きい。毎月裏山にはいり、桜守りとして樹の手入れを行っているのだ。前置きはそのくらいにしてさくら祭りの概要をお知らせしておこう。
弘川寺の正門付近。河南町の奥座敷、葛城山の山麓にあります。

弘川寺のさくら祭り
◇期 日 平成21年4月5日(日曜日)
◇時 間 午前9時30分~午後3時
◇会 場 弘川寺およびその周辺
◇交 通 富田林駅から金剛バスで約30分 終点の弘川
寺で下車 徒歩数分
◇車 河内小学校が駐車場となります。 無料です。

少し早めに弘川寺を訪ねてみたが、桜は開花が始まったところ。丁度、お祭りの日曜日あたりが満開かも知れない。前日の4日はライトアップも想定されているようで、かの橋下知事も参加される予定とか。寺内で草刈りをやっていたおじさまが刈払機を止め、4日には是非おいでやと誘ってくださった。あいにく所用があって参加は困難だが、夜桜もいいものだろう。お好きな方は飲み物持参でご参加を。(付近には店舗等は全くありません)
寺内の一角、枝垂れ桜が見事に咲いていますね。

周辺部も一面の桜ですね。

弘川寺は西行法師の終焉の地と書いたが、北面の武士(現在の皇宮警察官に相当だろうか)として活躍していた彼が、妻子を捨て身分を捨て何故放浪生活に至ったのか今も謎のようである。失恋説もあるようだが定かではない。明確なのは各地を流浪したあと晩年をこの地で過ごしたようだ。そして辞世の歌とも評される下記の和歌を残して73歳で亡くなったとか。
ねかはくは 花のしたにて 春しなん その
きさらきの もちつきのころ (山家集)

2009年03月22日
彼岸会
お彼岸の花として似合いそうですね、確かユキヤナギだったお記憶してますが。

気になってご近所の墓地を覗いて見たが、線香の香りも新たな花もあまり見かけなかった。お彼岸の墓参の習俗も薄れてきたのだろうか。残念なことである。人間はとかく自分の力のみで生きているかのような錯覚を持つが、因果応報は世の習い。親の因果が子に報い・・・・・・・・・・とは人形浄瑠璃の世界かな。いやいや、やはりご先祖様の功徳(功罪)が子孫に大きな影響を与えているのは間違いなさそうですね。我々が今日、平穏に健康で暮らしておれるのはご先祖様の施された陰徳のおかげと考えた方が理にかなっているようですし、人間としての生き様にも合致するのではないだろうか。そう思うと、折々の伝統行事や習俗を大事にしなければと再認識しておる次第です。
ハナモクレンでしょうか。今が盛りのようですね。


彼岸とは仏教用語として使われていますが、語源はサンスクリット語の波羅蜜多(はらみつた)にあるそうです。意味は煩悩と迷いの世界(此岸)から脱却した、悟りの境地・世界を指しているようですね。小生のように、日々、煩悩と迷いに悩まされる身には、縁遠い世界のようです。もっとも良くしたもので、我々のような迷える者を彼岸へと導いてくれるのが地蔵菩薩、いわゆるお地蔵さんですね。笠地蔵などの民話でご存じでしょうが、もっとも身近な先達ではないでしょうか。この界隈の路傍にも、たくさんのお地蔵さんが祭られています。ご先祖様達はその意味と役割とを、しっかりと認識しておられたようですね。
今年は早いようですね。ホラッ・・・・・・桜の花が。

お彼岸にはいり、柄にもなくお地蔵さんの事を考えてみました。墓参もかなわぬ不幸者の、小さな戯言かも知れませんね。近くにお墓がある方は、まだ間に合います、明日にでもお訪ねしてください。笑顔のご先祖様が出迎えてくれるかも知れませんよ。
サザンカの花はもう終盤のようですね。


2009年02月04日
鬼は外へ
鬼は外、福は内・・・・・・・・・・・どこかで聞いたような台詞ですね。最近はこうした行事をあまり為されないのか、豆まきの音や逃げ回るお父さんの姿をめっきり見かけなくなりましたね。寂しいかぎりです。本年は2月4日が立春、その前日である3日が節分である。各季節の始まりをそれぞれ、立春・立夏・立秋・立冬、というが特に立春は1年の始まりとして特別視されたようだ。従ってその前日の節分はいわば大晦日に相当する。1年間の邪気を払い去り新年の無病息災を願ったのが始まりのようだ。我々の少年期にはどこの家庭でも節分の行事があり、年の数だけ豆を食べたものだが。いつから廃れてしまったのだろうか。伝統行事を大事にしない民族は根っ子(世間ではアイデンテティーとか言うそうな)を失ってしまうと思うのだが。英語をしゃべれるようにはなっても、語れる内容が無くなってしまうのではなかろうか。
節分の豆まきが始まります。豆と餅とが大量に降ってくる。

降りしきる雨の中を、善男善女が続々と集まってきます。
さてこの行事、鬼は外、と大声で叫びながら豆をまくのだが、鬼って一体何だろうと疑問に思われた事はありませんか。行事の来歴から考えると、1年間の災難や邪念やいやなこと等を指すのだろうと推測されます。ただそれ以外にも鬼の出番がありますよね。桃太郎伝説、大江山の酒呑童子の話、神隠しの民話、鬼畜米英(古いかな・・・)、鬼ごろし(これはお酒か)・・・・・・等々。各地には鬼を使った地名や氏名等も残っているようです。当地にも「鬼住」という地名の集落が昔には存在してました。ここには鬼が住んでいた?。
少年期に小生が考えたのは、まず1番目は外国人説。赤鬼・青鬼の外見からきたもので漂着した外国人では・・・・との想像です。2番目が山人説、農耕生活になじまない暮らし方をする人々が山間に住んで里人と対立したのでは・・・・・との想像です。3番目が異分子説、和を尊ぶ農耕社会では多数説と異なった考えは排斥されます。ムラから追放された人々が山に籠もった・・・・・・との想像です。いずれも子どもの発想ではありますが、本当の実態は何だろうと現在でも疑問に思っています。
小生の戦利品です。撮影を続けながらいただくモノはちゃっかりと。
そうそう舞台の紹介が遅れました。ここは南河内の古刹である観心寺、言わずと知れた楠公さんこと楠木正成の学問所として著名な場所ですね。金剛山の中腹にあります。高野山真言宗のお寺で、住職の永島さんは楠公さんの語り部でもあります。本山で役職を勤める傍ら高野山大学で教鞭も執っておられます。本日は餅まきに狂奔する我々をにこやかに見守っておられました。せっかくですから観心寺のスポットを何カ所かご紹介しましょう。
門前では大量の椿が販売されていました。

斎戒沐浴のミニチュアでしょうか。心身を清めてからの参拝はマナーでしょう。

祈りの形は線香とローソクを手向けてからでしょうか。
無心に祈り続ける人々。
合掌

日本人の7割は無宗教ではあるが無神論者ではない、と言われております。特定の宗派に帰属するのではないが信仰心は持っているといった意味でしょう。日頃お寺や教会に行かない人でも初詣に出かけたり神社で七五三を祝ったり教会で結婚式を挙げたり・・・・・・・しますよね。こうした日本人の持つ宗教への寛容さは、非常に優れた資質ではと思っております。一神教の価値観では、異なったカミは異端であり敵であり聖戦の対象であるのでしょう。各地の紛争をみていると、彼らの論理では世の中は安寧とはならないような気がします。麻生さんに広い世界で頑張っていただかないといけないのでしょうが、さて。

2009年01月12日
えべっさん
なんとも簡素なえべっさんです。無論、巫女さん等は不在。

もっとも地元の方々にはそんな詮索は不要であろう。お地蔵様によく似た存在だろうか、風景の中にとけ込まれた生活と一体となったお宮さんのようである。師匠にも聞いてみたが、昔からあるで・・・・・・・・ということで来歴等は不明のようだ。無論、山間部の小さなえべっさんのこと、妙齢の福娘や巫女さんがおられる訳ではない。また笹を販売して収益をあげられる訳でもない。地元の方々が集まって信仰しておられるだけである。外部の者が参拝することはまずなさそうである。小生がカメラ片手にのぞいていたら、おばさま方が怪訝そうに見つめておられた。
出会戎のにぎにぎしい幟たち。

画像をみていただいたらご理解いただけるが、何ともかわいらしい簡素なえべっさんである。今宮戎と比較するのが無理な話だが、これでも列記としたえべっさんなのだ。お宮の大小でご利益が変わる訳でもないだろう。商売繁盛、笹もってこいこい・・・・・と願っておこうか。
村の衆がたくさんで準備作業を実施中。

かすかに見えるのが出会橋、そして集落の名称が出会地区・・・・・・・・ここいらから「出会戎」の名が付けられたのであろう。地区は下赤坂城趾(楠公さんの城塞群の一つ)の入り口付近に相当する。何らかの因縁があるのだろうか。車で通ったらまずは気づかないような位置にある。小さな路地の奥まった場所だ。
出会橋かいわい、地元の典型的な山村風景だ。

えべっさんが終わると正月も終わったという印象になる。15日の小正月までが松の内で、いわゆる正月期間にあたるのだが、最近は7日で松の内を終わり、「とんど焼き」を行って正月を閉める所が多いようだ。そういえば学校も7日あたりまでが冬休みのようですね。いずれが正統かは別として、事実上正月も終わり、新年が回転し始めたようです。皆様方も新たな抱負の下に志操堅固な日々を送っておられることでありましょう。本年のご多幸とご健康を陰ながら願っております。
2009年01月07日
とんど焼き
とんど焼きは通常小正月の15日に実施します。各地で似たような風習はあるかと思いますが、当地では書き初めと注連縄の焼却とがセットになっているようです。本日はまだ松の内ですが、少々早めのとんど焼きを実施することに。無論、会場は谷間の農園です。年末から下準備は重ねておりました。地主のばあさまの森がブッシュ状態だったので、刈り込んでいたのです。雑木や刈草やツルなどが結構たまっております。とんど焼きも長丁場となりそうですね。
小生のとんどです。注連縄や練習用に作った注連縄等も準備してきました。

注連縄は、正月神の存在される空間を示すための結界と言われております。従って、正月が終わる小正月になって神が天界へと帰られたら結界の表示は不要であり、とんどを焼ことで結界を閉じているという意味があるようです。また新年にあたって無病息災を祈る、といった意味も込められているようですね。伝統的な風習は残しておきたいものです。私宅にはまだ正月神はいらっしゃるようですが、少々早めのとんど焼き、神を追い出すようで恐縮ですが焼かせていただきましょう。
雑木が乾燥しきれていないようですね。なかなか燃えません。
くすぶって暖まってようやく本調子が出たようです。薪の炎が見え始めました。
炎が見え出すと伝統行事というより完全な火遊びですね。少年の日に戻って薪を放り込んでいきます。薪の炎には特別な魔力があるようで、人の心をとらえて放しません、熱中させてしまいますね。幸い十分なほどの雑木を切り出しています。たぶん全部を消化するのに一日がかりでしょう。
十分な炎が出てきました。大きな薪を入れても大丈夫なようですね。
少しづつ大きめな薪を放り込んでいきます。
太めの薪も十分に燃え上がってくれました。

遠くからも煙が上がっております。小生と同じく早くも正月神の追い出しにかかった人があるようですね。彼の御仁も正月2日から仕事始めと言い出してるかも知れませんね。当地は勤勉な農家が多いようです。
田んぼの端でとんど焼きが始まったようです。
朝の9時頃からとんどを初めて、ほぼ燃え尽きたのが午後の4時過ぎ、あたりは少々肌寒くなってきました。これで準備したものの丁度半分です。時間切れもあって残りの部分はまたの機会といたしましょう。伝統行事の復活なのか単なる火遊びなのか定かではありませんが、本人は生真面目に地域の風習を守ろうとしているようです。本日は七草がゆの日、こちらは山の神にお願いしてかゆを相伴することといたしましょう。当地には河内の茶がゆという郷土食もあることですし。
ほぼ燃え尽きたようですね。

2008年12月30日
餅つきの音
昔からの言い伝え、「駕籠に乗る人かつぐ人、そのまたワラジを作る人・・・・・・」ご存じの方も多いだろう箴言である。得てして大名行列で注目するのは駕籠に乗る人なんだが、本当に凝視しなければならないのはワラジを作る人ではなかろうか。いつの世も何処の世界でもスポットライトを浴びることなく黙々と任務を遂行する人々がある。彼らは当然のことして任を果たしておられるのだろうが、その恩恵は計り知れない。定刻少し前に持尾城趾に上がってみると、案の定、準備作業に汗を流す数人のメンバーが・・・・・・。UさんOkさんNsさんの方々である。聞くところによれば昨日も餅米の準備や洗い作業に奮闘しておられたようだ。仲間達が喜んでくれれば、そうした思いが己を捨てた行動へと駆り立てるのであろうか。刮目して感謝すべき軍団である。
ペンより重い物を持ったことがないので・・・・・。腰に響きますね。

80年ほど使い込まれた臼です。旧家の蔵にはお宝が眠ってますね。

ちびっ子達も集まって賑やかに餅つきが始まった。里山倶楽部の恒例行事でもある。無論、こうしたイベントの言い出しっぺはUさんだ。率先垂範して作業に当たっておられる。概ね一人5キロの予約、全部を消化するには結構な時間がかかりそうだ。杵と臼を使った伝統的手法の餅つきである。子ども達が喜んでくれるのが何よりのご褒美だろうか。

まずは餅米を洗うことから。実は
昨日にUさん達が前もって準備し
て下さってたのだ。
ザル一杯が蒸し器の一杯分、重
さでは2.5キロ程度。1.5キロが
概ね一升ですので容積は換算し
てみて下さい。

蒸し器に移し替えました。
一人で5キロ予約が大半ですの
で、2回蒸して一人分の下準備
というとこでしょうか。

みごとなへっついさんでしょう。
無論、自作のかまどです。
4個の蒸し器を一度に蒸すこと
ができます。燃料も又自家製の
薪ですね。
昼食はもちろんつきたてのお餅ですね。例によってKさんが豚汁の準備を。料理名人との評判の高い方で、その腕前はプロ並みか。大鍋でぐつぐつ煮込んだ豚汁には、思わず顔がほころびますね。子ども達もうれしそうです。立ち食いながら何度もお変わりしています。
猪鍋に勝るとも劣らぬ美味です。山で食べる豚汁は又格別、食も進みます。

そうこうしてる間にも餅が仕上がっていきます。これはお鏡かな。

おっととっと、本日は首謀者のUさんの誕生日でもありました。否、彼の誕生日祝いに餅つきを?・・・・・・・・・。それが真実かもしれませんが、まっ良しとしましょう。里山倶楽部のお嬢さん方が準備してくれたケーキがなんともかわいげです。ローソクを吹く彼のうれしそうな表情をどアップで。

餅つきも佳境にはいって終了したのが午後の4時頃、もう日も陰って少々肌寒くなってきます。ありがたいのはやはり火の気、焚き火の炎がなんとも人の心と体を暖めてくれます。いつまでも見つめていたい炎のぬくもりです。
薪を使った焚き火ほど、ありがたいものはないですね。

できあがった餅を土産に自宅へ直行、車のトランクを開けて呆然、持尾城趾にカメラを入れたリュックとジャンバーを置き忘れた。なんともとんまな次第である。やむを得ないのでバックしてみると、SzさんとNsさんがまだ滞在しておられた。Szさんは仕事中、Nsさんは梅の小枝をカットしておられた。昼間に隣地の梅の木で剪定中だったのだが、剪定枝を残しておられたようだ。 「おばあちゃんが梅の花が好きなので、持ち帰って花を咲かせ、見せてあげようと思ってます」 との言葉が、なんとも心暖かく風雅に響いてくる。雅とはまさに彼女のような心情を指す言葉ではなかろうか。
東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ
太宰府へと左遷された道真公が京を去るにあたって詠まれた和歌だが、梅の花に寄せる想いが切々と伝わってきます。梅花の放つ高貴なたたずまいと香りとが人の心を捕らえて離さぬようですね。時代が変わり人が変わっても梅花に寄せる想いは変わらぬようです。おばあちゃんのうれしそうな笑顔が想像できますね。
2008年12月28日
残し柿の風習
みごとな食欲ですね。次々とヘタのみの果実となっていきます。

郷にいれば郷に従えでしょうか、小生も見習うべき風習だと思っています。13年程前に植えた柿の木が庭先にあります。富有柿ですが沢山実りました。摘果等をやっていないので小粒ですが、量だけはしっかりありますので、残し柿としました。毎日たくさんの訪問者がおいでのようです。代表選手は、メジロ、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、ごくまれにキジバトでしょうか。山間部とはいえ結構民家が密集した場所です。彼らは人の目を気にもせず、ついばんでいます。山も食糧難でしょうか、それとも心臓に毛が生えているのかな。
本日の訪問者はスズメ君のようですね。彼も柿が大好きです。

共同農園の近くにも柿の木がありますが、同様に鈴なりのままです。全部を小鳥たちに残したのでしょうか。今日はかなり冷え込んで、時折には白いものが舞っています。彼らもしっかり食べ込んで皮下脂肪を蓄えないと冬場を超せないでしょう。なんとか無事に、春の訪れを楽しんで欲しいと願ってます。とんびくらぶの果樹園にも彼らと共有できる果樹木を植えたいものです。今のところは、柿、プラム、サクランボ、程度でしょうか。柑橘類も温州ミカンが無いので、ちょっと困難ですね。ブルーベリーなど植え込んだら小鳥のレストランになってしまうか。人間様に全く収穫が無いというのも辛いですね。

放置ではなく小鳥たちの為に収穫
しないのでしょう。

ともあれ、ご先祖様が残して下さった貴重な遺産を大事に伝え残したいものです。果樹木を植え、形としてこの風習を見聞きさせてあげるのが一番かと思います。子ども達にも充分理解できる内容です。
だいぶ食べられましたが、私宅の柿も結構残っています。

2008年12月26日
とんど焼きの準備?
森の手入れは冬場のほうがいいですね。作業が容易です。

注連縄は各家庭に正月神をお迎えするにあたっての結界だそうな。いわば神様が存在される空間(神域)と一般の空間とを分離する境界の役を果たしている。15日、正月が終わって役割を終えた神様を天に帰し、結界を解くのがとんどの役割であったのだろう。今も各地で実施されているのだろうか。一神教の世界観を持つ方々には理解不能かもしれないが、この国には実に沢山の神々が存在しておられる。注連縄も玄関先に飾るだけではない、玄関、台所、納屋、子ども部屋、果ては車やトラクターにまで飾り付ける。根底にあるのは何処にも神々が宿られるとの発想だ。神様のオンパレードである。この包容力があって始めて世がまとまっていけるのではなかろうか。21世紀以降は日本の時代、そう信じるのもここにある。絶対神の考えを持つと異なるものは悪となり、いわゆる聖戦の思考が生まれてしまう。
早めに切ったものは乾燥してきました。焼却準備OKかな。

さてさて前置きが長くなってしまった。今、とんどを実施するのではない。下準備とも思しき作業をやっているのだ。例によって地主のばあさまの森である。90歳に近いばあさまが森の手入れなど出来るわけがない。荒れ果てているのは何処も同じ、見かねた小生がボチボチと刈り込んでいるのだ。立木を倒すのは容易だが、トゲの付いたブッシュ類は苦手である。厚めの作業着を着込み帽子や軍手やゴーグル等で武装する。手袋は皮のほうがいいかな。長めの刈り込み用の鎌で切り込んでいく。遅々として進まぬ作業だが、そこはそれ、時間の経過と共にそれなりには仕上がっていく。
いい薪になりそうです。焚き火の炎が待ち遠しいですね。

刈り込んだ雑木やブッシュ類もそこそこに貯まってきた。乾燥させておいて15日あたりに燃やしてあげようと思う。ここは人里離れた山間部の谷間、人様に迷惑がかかるような場所でもないのだ。焚き火は実に楽しい。木が燃える炎を見つめていると太古の原始人に戻ったかのような感覚にとらわれる。思えば火の扱いをマスターしたご先祖様は歓喜されたのではなかろうか。これほど暖かで人の心を癒してくれるものはないだろう。ガスや石油では駄目なのだ。
とんど焼きの暖炉はスタンバイ状態。いつでもOKです。

年末も押し迫ってきた。山の神からは、早く年賀状を作れと脅迫されている。パソコンに向かっているより山での作業が快適なのだが、そうもいかぬようだ。浮き世に生きる身、賀状や大掃除や買い出しや孫のお守りや・・・・・・・・小生にとっては雑用がわんさかと持ち込まれる。周囲によって生かされている命、お役に立つのであれば一肌脱ぐのが高倉健の役目、イヤ違った市井の個人の勤めでもあろう。せっせと体を動かしましょうかな。どちら様もいいお正月を。
2008年12月21日
注連縄作りに挑む
正月も間近に迫った師走、迎春の準備をしなければと柄にもない発想にひたり、注連縄作りにチャレンジすることに。生まれて初めての体験である。注連縄は購入する物、そう思いこんでいた。だが南河内の山里に暮らし始めて、うん十年・・・・・・・・・・・・よくよく観察してみれば、当地には家庭での注連縄作りの伝統が残っていた。もっとも過去形で語らねばならないのが残念ではあるのだが。古老が生きておられる間に技術の伝承をと殊勝な心がけで探していたら、滝畑の山奥で注連縄作りの講習会があるのだとか。絶好のチャンスと時間を割いて参加してみた。地元の区長をしておられたTnさんが伝統技術の保持者であられ、滝畑に昔から伝わる注連縄作りをご存じの無形文化財(?)でいらっしゃるようだ。願ったりかなったりの機会である。
山里は寒い、赤々と燃える囲炉裏端から離れたくなかった。

茅葺きの古民家が会場だ。まるで日本昔話の世界である。

会場は滝畑に伝わる古民家の一角、庭先をお借りして講習が始まる。伝統技術の保持者であられるTnさんの勇姿を覗いてみよう。地元で植木職をしておられる長老だ。子どもの時分から親御さんに仕込まれて覚えたのだとか。現在は地域でも作れる方が少なくなったそうだ。
本日の講師であるTnさん。まずは素材のワラ打ちからスタート。

受講生もワラ打ちに。午前中が滝畑仕様、午後が街中仕様の作成予定だ。

これが滝畑バージョン、ひも状の形をした注連縄である。

滝畑地区は石川の上流地域にあたり、河岸段丘に川沿いに作られた集落である。ダム建設で多くの民家が地区を去られたそうだ。残った人々も高台のわずかな土地に移り住まれ、生活も一変してしまったようだ。川が生活の原点で、注連縄も川の上流を上手として飾るようだ。つまりひも状の細い部分が上流に向くように設置するそうだ。川に直角となる民家は東が上手の方角に当たるのだとか。

小生の練習用作品、まず最初
はワラの撚り方の習得から。
見てると簡単そうだが、やって
みるとなかなかに困難。

玄関先に飾ってあった作品、こ
れも一種の注連縄なのだろうか。
なんと、この講習会は昼食付きだった。弁当を持参したのだが、おいしそうな茶がゆ定食、地元の郷土食だそうな。こちらをいただこう。ダイコンの煮込み鍋まで添えてあった。素材はすべて地元の滝畑地区で取れたものだそうだ。調理は、自称料理名人の地元の奥様。

午後は一般に市販されてる街中バージョンの作成。講師のTnさんがお手本を示して下さる。午前中で要領を飲み込んだのか、皆さん鮮やかな手つきで取り組んでいかれる。小生は不器用を地でいくようなタイプなので、思うようには作れない。撮影中心となってしまうようだ。
講師の動きを時系列で追ってみよう。まずは3本のワラを撚っていく。

だんだんとそれっぽくなってきた。

後は形を整えて飾り付けを実施するだけですね。

これは小生の作品、少々貧弱な注連縄ではありますが。土台のみです。


飾り付け用の青物、山で採取したも
のだ。
1,ウラジロ
2,ヒイラギ
3,ユズリハ
4,モッコク
この他に和紙で作る御幣があ
る。折り方が難しい作り方だ。
御幣の折り方の講習、ここでもTnさんが大活躍。地元のお宮さんも彼の作品。

残念ながら時間切れで最後の飾り付けまでには至らなかった。だが、作り方の骨子は皆さん飲み込まれたようだ。材料さえ入手できれば一人でも作れそうな気配である。主となる素材のワラは餅米用のワラを稲木で天日干ししたものでないと役に立たないようだ。今風のコンバインによる収穫だと入手できない素材である。稲作の機械化と共にこうした伝統文化も消え去っていくのだろうか。岩湧山の茅場が目の前だ。山頂は快晴で小春日和みたいな雰囲気である。山へも登りたいのだが、時間が足りない。
岩湧山の山頂付近、目の前に広がっている光景だ。

2008年11月13日
延命寺にて
朝から晴れ上がりかっこうの行楽日和となりました。遠隔地へ出かけるほどのゆとりはありませんが、何、この近在には素敵な場所がわんさかとあります。本日は紅葉の名所として知られた延命寺を訪ねてみよう。金剛山の中腹に存在する、真言宗御室派に所属するお寺である。開基は弘法大師空海と伝えられている。まだ少々早いかなとも思ったが、11月の中旬ともなれば里へも紅葉が降りてくる季節、心配もいらないだろう。案の定、道中の小道でもあちこちで紅葉が。里も秋真っ盛りのようだ。
延命寺の正門。寺内は既に紅葉が真っ盛りのようですね。

寺内に足を踏み入れるとあちこちから紅葉のモミジが覗いてくれます。名所と言われるだけの価値はありそうです。平日にもかかわらず大勢の参拝客がおられます。信仰心というよりは紅葉見物の行楽客のようですね。ただ山間部だけあって、リュックを背負ったハイカーが多いようです。天見から延命寺それに観心寺と繋がるハイキングルートが好まれているようですね。



このお寺には樹齢1000年と言われる、夕照のモミジが存在します。大阪府の天然記念物にも指定されており、何ともいえない貫禄と風情を漂わせております。一見の価値ありでしょう。森にはいると、1000年とはいかなくとも、歳月を重ねた樹木によく遭遇しますが、一種独特な存在感があります。人間も同じかも知れませんが、歳月の重さが風格とある種の哲学とを育てあげるのかも知れませんね。
樹齢1000年とも言われる、夕照のモミジ。
境内で、偶然にも以前の職場の同僚であったTnさんと出会いました。休暇をもらって紅葉の撮影に来たのだとか。退職時以来ですので、何年ぶりの再会でしょうか。元気そうな姿に一安心です。数年以内には農へ転身したい、と意外な豊富を語ってくれました。仕事熱心な男でしたが、組織人としての役割に疑問と苦悩を抱いておるようでした。奥方とは、しっかりコミニケーションを図っておきや・・・・・・・・・・と言う程度のアドバイスしか出来ませんでしたが。

神社やお寺には何か不思議な力が存在するのか、人の心を和らげ平らかにする独自な空間のようですね。格別、深い信仰心など持っていなくとも、不思議と改まった素直な心境へと変化させられます。神様や仏様の力・・・・・・・・と言えば言い過ぎでしょうか。勇気と活力が湧いて来ないとき、お寺や神社を訪ねてみませんか。鎮守の森が放っている摩訶不思議なエネルギーで、充電され触発されるかも知れませんよ。
2008年10月28日
宮入は何時
水の配分権を持つ神様といっても良いだろう。名前からして水分神社なんだから。正式には建水分神社(たけみくまりじんじゃ)という。金剛山を背後に控えた高台にたつ。農耕社会の基本財産である水を管理する神ともいわれ、下流域の集落を管轄下に置くようだ。秋、10月には収穫を祝って祭礼が実施される。下流域の集落から20台くらいの地車が出て、集落を練りあるいた後、一斉に宮入を行うのだ。神社が高台で地車が入れないので、少々下の広場に神様がお移りになり、この広場を神社とみなして宮入を行うのだ、20台あまりの地車が集結してパフォーマンスを行うので相当賑やかである。この宮入をねらって撮影に出かけたのだが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
ここもご祝儀のオンパレードだ。皆さん太っ腹なようだ。

駐車場に車を止めたところで師匠に出会った。カメラ担いでなんや、と問われたので上記の事情を話すと、宮入は昨日やでとの一言。土日が祭礼なのだが、通常山場は最後と踏み日曜に出かけたのだ。ところがどっこい、この地では土曜日に宮入があり、日曜日はそれぞれの集落で練り回すのだとか。ガックンである。事前に確認しなかったのが悪いのだが、そんなことありかい、の心境である。土地によって風俗も慣習も異なるのがあたりまえ・・・・・・・・・・・・・・・理屈はわかっているのだが。
地元、水分の地車が練りから帰ってきた。1台のみの地車だ。さびしい。



どこも過疎化して地車の引き手がなくて困っておられるが、この地は心配ご無用のようだ。地車を引いているのは、文字通りの青年たちである。大阪市内まで一時間以内という通勤利便性が青年たちを生まれ在所に残してくれているのだろう。ありがたいことである。欲をいえば彼らが農の後継者として活躍してくれれば、と願うのだが。ちと困難かな。
大半の農家は稲刈り完了だ。収穫の喜びの秋祭りだろう。神への感謝の日。

日にちの取り違えというドアホな一日だったが、それなりに楽しいひとときだった。これが宮入の本番であれば、20台ほどの地車が集結し、河内にわか等も演じられてそれはそれは盛り上がる。露店も並び、大勢の観客でごった返すのだ。ムラの活気がよみがえる二日間、毎日がこれだけの熱気を感じられれば最高なんだろうけど。他の日は、静かでゆったりとした時間が流れていく。
2008年10月27日
渋柿隊
渋柿隊のエース、Kさんが突撃します。

畑に出向くとKさんも出動中だったので、柿もぎへとお誘いする。高枝鋏や剪定鋏それにビニール袋などを準備してUターンだ。渋柿は共同農園と私宅との中間ぐらいにある。いわゆる谷間の農園の側なのだ。柿の木は3本、市場ではヒラタネと呼ばれる薄型の渋柿である。一般的には炭酸ガスで渋抜きして生食用として市販されている。我々はこれを干し柿と焼酎+お風呂での渋抜きに挑戦するのだ。昨年は干し柿はうまくいったのだが、渋抜きには失敗した。今年は再度のリベンジ、なんとか甘柿として食してみたいものだ。


渋抜きは至って簡単。柿のへたを取り、そこに焼酎を塗布する。その後ビニール袋に封印してさらにビニール袋に包み、一晩お風呂の湯につけるだけ・・・・・・・・・たったこれだけの方法に昨年は失敗したのだ。

柿好きなKさんは喜び勇んでもぎ取り中、都合でこれなかったUさんにも持ち帰るとか。大きなビニール袋3個が一杯となったようだ。さて皆さん、渋抜きに成功なされるか。後日の体験談が楽しみである。Kさんによれば甘柿より渋抜きした渋柿のほうが甘いとか。ご先祖様たちはそれをご存じだったのだろう、あちこちに植え込んであるのは大半が渋柿のようだ。



さてこの渋柿だが干し柿と渋抜きとがうまくできるか、後日のお楽しみというところだろうか。かっての人々はこうして身近にある食材を保存食として活用されていたようだ。残念がらそうした生きる知恵も次第に失われつつあるように見受けられる。我々がこだわってこうした活動を続けるのも、ご先祖様たちの知恵を喪失したくないからだ。ブログをご覧の方々も是非に挑戦してみてください。自給率が40パーセントを下回ったと心配するよりも、身近の食材を活用するのが先決でしょう。お金ですべてが解決できるとは思いません。知恵ある生活を取り戻しましょうよ。
採取した渋柿は干し柿にしました。渋抜きにも挑戦します。

そうそう柿のことでご紹介しておきましょう。和歌山との県境に岩湧山がありますが、ここの南山麓に葛城町・高野口町(現在は合併して橋本市になっているかも)という里があります。ここの柿は滅法おいしくて、ここの柿を食すると他産地の柿は食べれない位です。地元の方が「日本一の柿の里」と自称されるだけのことはあります。機会がありましたら、是非一度お試しください。
2008年10月13日
秋祭りが始まった
秋祭りのハイライトは地車だろう。何ともきらびやかだ。

聞くところによれば。秋祭りのために1年間があるのだとか。1年かけて準備し、祭りの前後には仕事も家庭もほったらかし、もっぱら祭りに専念する。会社の年休なども、この時期まとめて消化するそうだ。近くの旧村に覗きに出掛けた。北村と南村とに分割されているらしく、地車も2台が出張って競い合っていた。


何とも可愛らしいのがちびっ子の引き手達。はっぴ姿もさまになっていて、彼らを見つめているだけでも祭りが楽しくなってくる。当地の秋祭りは泉州地区のような激しさはなく、統制の取れた祭りで老若男女がそろって楽しんでいる。マスコミ受けはしないかも知れないが、集落の人々にとっては季節のよき催しなのだ。
地車のかわいらしい引き手達。


地元の人間にとっては典型的な秋の歳時記。秋祭りで地車を引かないと季節が変わらないのだろう。稲刈りも終了し、1年分の食の確保も出来た事だし、骨休めと祝宴とを楽しもうとの伝統だろうか。世にハレとケがあるように、羽目を外す日々もあるほうが仕事にも集中できるかな。子ども達にとってはお小遣いもいただけるかもしれないしね。
車と一緒ですね。コーナーリングが難しそう。

大工方とか言うそうです。屋根に登るのは腕と度胸を見込まれた選ばれし者。

地域の方々から沢山のご祝儀が集まったのでしょう。村々のあちこちには沢山の提灯が張り出されています。金額の多い順番かな。一応。順不同とは記載してありましたが・・・・・・・・・・・・。まっ、どうでもいい事だけど。こんな提灯パネルが辻ごとにたくさん立っていますね。村の衆の力のいれ具合が分かるというものです。まさに秋祭りのために1年がある???。

2008年10月06日
天野山観月まつり
当地に天野山金剛寺という古刹があります。うかつなことに、ここで18回にもわたって観月まつりが開催されていることをついぞ知りませんでした。このお寺はかって南北朝の時代に、後村上天皇の行在所がおかれた場所でもあります。いわば一時期皇居であった訳です。まつりは、天皇がこのお寺の観月亭で月見をしながら都をしのばれたという故事にならっているそうです。本日は公家衣装や女官姿の女性達が往事を再現し、琴・尺八等の演奏の中で優雅に野点が催されました。又、剣舞や詩吟或いは和太鼓の演奏やライブなども披露されました。残念ながら所用で2時間程度しか時間が取れなかったので、全部は堪能できませんでしたが。
天野山金剛寺の観月亭から、お月見をされる後村上天皇?

お月見とは邦楽がよく似合いますね。和服姿の方々が琴や尺八の演奏、剣舞などを披露してくださいました。数点を画像で紹介しましょう。なかなか優雅な雰囲気です。赤い毛氈を引いた腰掛けで、抹茶と和菓子をいただきながら拝見しました。天野酒の振る舞いもあって左党の方にはたまらない催しですね。ちなみに天野酒はこのお寺で作られているそうです。
琴と尺八の演奏です。いいものですね。

ご当地ソング?「楠公の歌」。例の青葉茂れる桜井の・・・・・で始まる歌です。

剣士による剣舞、太刀はどうやら真剣のようです。後に試し切りの演武もありました。

観月まつりは観光協会の主催によるものですが、山奥の古刹でこうした雅な催しが為されるのも、なかなかもいいものです。足の便が少々悪いので、車がないと訪問しにくいのが難点でしょうか。ここは又紅葉の名所でもあります。当地は11月の中旬以降でしょうか。寺内を流れる小川沿いに植えられた楓が真っ赤になるそうで、楽しみにしております。
寺内を流れる小川と坊のひとつ。この周辺が紅葉の名所となるようです。

レンタル衣装で往事をしのぶ若い方々。
地元名産の特売会場も。商魂たくましいのは何処も同じでしょうか。

訪問したのは夕刻でした。本番となるのは夜間のようですが、残念ながら本日は満月ではありません。29日が新月でしたので、半月の少し手前というとこでしょうか。それにしても山寺の回廊で天野酒を酌み交わしながら名月の観賞・・・・・・・・・・・・・・なんとも優雅な一時ですね。BGMとして琴や篠笛の音が流れてくれれば最高の雰囲気でしょう。当地は和歌山との県境ちかく、開発されたとはいえ、まだまだ往事を忍ばす環境が残っています。紅葉の折にでも、是非ご訪問下さい。
2008年09月19日
観月夜
台風の影響でしょうか、週末は荒れ模様のようですね。久方ぶりの天候の崩れです。もっとも農作物にとっては恵みの雨かもしれません。物事は多面体として、視点を変えて考える必要がありますよね。数日前は良いお天気がありましたので、観月を楽しませていただきました。今年は暦がうまくいったのか、14日が中秋の名月、15日が満月でしたよね。15日は曇っていましたが、14日の中秋と16日はうまく出てくれました。画像は両日のものです。
遠方に見えるのは狐火? 実はお隣の団地の明かりなんです。幻想的ですね。

70ミリでねらってみました。さすがに遠いですね。

150ミリ位だったと思います。少々大きくなりました。

300ミリで撮ったものをトリミングしてます。兎さんは見えないようです。
日本の歳時記を考えるには旧暦を使うのが便利なんですが、旧暦のカレンダーの販売など少ないですよね。中秋の名月は旧暦の8月15日、旧暦はご存じのように新月が1日で一月が始まります。そして15日前後で満月、今年はちょうど15日が満月でしたね。旧暦と新暦(現在使用しているグレゴリー歴)とでは、1ヶ月前後の時差がありますので、換算が面倒ですね。
旧暦の季節配分は、1月~3月が春、4月~6月が夏、7月~9月が秋、10月~12月が冬、となっています。ですから8月15日はちょうど秋の真ん中に当たるんですね。従って「中秋の名月」とか。ちなみに「仲秋の名月」とは秋を三つに区分した真ん中の月という意味だそうです。いわゆる8月中の月ということでしょうか。小生はこれが理解できず、ごっちゃに使っていました。
名月からさらに一週間くらい前の画像です。

月はなんとも幻想的で不思議な魅力(魔力?)を秘めていますね。多くの詩人や歌人が月への想いを歌(詩)に託したはずです。古くはかぐや姫の物語など極めて日本的ですね。ちなみに、西洋社会ではオオカミ男の伝説ぐらいしか聞きませんが、なんとも野暮な話です。
名月とは邦楽がにあいそうです。来月上旬、当地の古刹で観月会が開催されます。久方ぶりに古典的な雅を楽しませていただこうと、わくわく致しております。
2008年09月13日
秋は栗ご飯から
栗の木がすっかりと色づいてきました。青々とした葉っぱの合間から、弾けたイガの隙間から、焦げ茶に色づいた栗の実が覗いています。もう完熟だよ、早く取っておくれよ・・・・・・・とでも言いたげに。体内時計でも持っているのでしょうね。この季節になると決まって弾けてくれます。谷間の農園に苗木を植えて8年あまり、今では実りを期待できるまでに育ってくれました。桃栗3年柿8年・・・・・とか言いますが、栗の木は割と早めに実を着けてくれますね。ありがたいことです。私宅ではもっぱら栗ご飯、栗の渋皮煮といった手間暇かかる料理(菓子作り?)は苦手のようです。
谷間の農園でも立派な栗の実が。

小生の栗取りは以下のとおり。手に持つのは小型の鎌、まずもってこれで完熟した栗を枝からたたき落とします。イガが痛いので足で踏んづけて固定し、鎌で裂け目を広げて中の実を取り出します。木が高いときは高枝ばさみなども効果的ですね。長い竹でたたき落とすのも簡便でやりやすい手法かも。
百均で購入した小型の鎌、栗の実拾いと管理機の泥落としに最高です。
10分程でこれだけ収穫、栗ご飯1回分はありそうですね。
持ち帰った栗の実は包丁で割り、渋皮をはいでしまいます。そして水につけ込んで少々のあく抜きと鮮度の保持、あとは適度な大きさに細分しご飯と一緒に炊き込むのみです。いとも簡単な作り方。秋ならばでの料理でしょうか。栗ご飯が出てくると秋の到来を実感しますね。
ちょっと目には里芋のようですが、今年の初物の真正なる栗です。
次回のとんびくらぶは草刈りと栗拾いの予定、早生の栗の木があるので収穫期の実が沢山待ちかまえているのでは。ひょとしたらアケビの実もなっているかも。昨年も一昨年も栗とアケビとを一緒に撮影したように記憶しているが、多分。栗の茶色とアケビのピンク色とが不思議とマッチングするのですね。山里の秋は静かに深まっていきます。果樹をほうばり、紅葉を愛で、青空を堪能して、季節の移ろいを楽しみましょう。四季が豊かな国に生まれた者の特権です。
本年初の栗ご飯です。ライトが強すぎて色合いが飛んでしまいましたね。
2008年09月09日
おっちゃん・おばちゃんバンド
サニーサイドメモリーのバンドマン達。

フラットマンドリンを持たれたこのリーダー氏、ヴォーカルをも担当されたのだが、とても素敵な歌声だった。たき火を囲みながら老人が孫達に語りかけている・・・・・・・・そんな雰囲気をもった暖かで伸びやかな歌声がホール一杯に響き渡った。久方ぶりにいい歌声を聞かせていただいた。かってドングリバンドの演奏会を聞きに行ったことがあるが、その折にも素敵な歌声と出会った。ヴォーカル担当はNkさん、透き通るような歌声は、山から湖水へと舞い降りてくる一陣の涼風を想わせられたものだ。
興味のあられる方は、富田林市の公式HPをオープンし、左端にある「web web radio とんだばやし」というアイコンをクリックしてみてください。彼らが作曲した富田林小唄があります。軽やかなバンジョーの響きにのったサニーサイドメモリーの歌声が聞こえてきますよ。
オレンジ合奏隊の演奏です。ハーモニカが中心。

こちらは和音くらぶと言う名称のグループ。結成して1年あまりとか、平均年齢68歳という典型的なシニアのバンドだ。尺八とオカリナが中心のバンドで、かっての文部省唱歌や童歌などが得意分野のようだ。老人ホームなどの慰問演奏に引っ張りだこであるとか。老いて尚盛ん・・・・・・・・・・・と言えば失礼かな。
和音くらぶ

こちらはやまゆり隊という名称の大正琴のバンドだ。河南町のご婦人方なので、地域の花ヤマユリを採択されたのだろうか。シニア層と見受けられるが、とても若々しい。

プカプカバンド。全員がハーモニカで構成するバンドだ。

全部の演奏を覗くことは出来なかったが、何とも素敵な時間を過ごさせていただいた。それにしても楽器の弾けるシニア層が、かくも多いとは。全く持ってうらやましい限りである。生活の中に音楽がある、それだけでどれほど豊かな人生がおくられることか。オオカミの遠吠えではないが、満月の夜、古城の石垣の上で夜風にひたりながら篠笛を吹いてみたら・・・・・・・・・そんな妄想も抱いてはおるのだが。
2008年09月07日
シニア団塊ボランティア
行政体を代表して河南町の武田町長が開会のあいさつを。

このお祭りの特徴は行政体を超えた横断的な取り組みが為されていることだろう。橋下知事の道州制を先取りしたのかな。主たるイベントとしてパネルディスカッションが開かれた。各行政体からは代表的なボランティアグループがパネラーとして参加されている。
司会者のHa氏と4名のパネラー。左端のご婦人は手話通訳者。

河南町からはわが里山倶楽部副代表のOn氏、富田林からはくすのき塾のKt氏、河内長野からは観光ボランティアのH氏、大阪狭山からは熟年いきいき事業実行委員会のHt氏、の4氏がパネラーだ。議論のテーマーは以下の3点である。
(1)南河内で活動している市民活動について紹介し、活動の楽しさ・やりがいについて語ろう
(2)各団体の活動の悩みや課題を出し合って、シニア・団塊の世代が元気に地域で活動でき
る条件について考えよう
(3)南河内地域全体の活性化に向け、シニア・団塊の世代が地域に果たせる役割について
考えよう
2時間という限られた時間のため、十分な討議が出来たとは言いにくいが、各団体の活動状況や問題点、今後の取り組み等については参加者にも理解されたのではなかろうか。聴衆の反応も好意的で、質問や提案等も相次いでいた。
パネラーとして報告する里山倶楽部のOn副代表。

一方、ホールや通路等では各種のボランティアグループが店開き、およそ40近くの団体である。パネル展示や資料配付、相談員の配置や湯茶の接待までするところも。各団体とも新規加入者の獲得に積極的なようだ。里山倶楽部もアンテナショップを開き、マドンナ達を先頭に顧客の開拓を展開。
里山倶楽部のブース。早速、顧客の候補者が。

各団体ともに積極的です。仲間は多い方がいいですもんね。




真正面から問いかける団体も。

60歳でリタイアしたと仮定して平均寿命から考えたら20年前後の自由時間が・・・・・・・・・。今の中高年は元気な方が多い。その元気さを我が身とわが家族の為にだけ使用していいものだろうか。子育てが終了したら、家族への一応の責任は果たしたと解釈し、以降は別の次元からの行動を起こされてはいかがだろうか・・・・・・・そんな問いかけを発しているように感じられた。それにしてもどの団体さんもどのメンバーさんも非常に活動的である。とてもじゃないが、粗大ゴミとして自宅で寝そべっている暇はなさそうだ。
2008年08月10日
盛夏到来
PLの花火大会も過ぎ、暑さもひとしおの盛夏となりました。各地の集落からは盆踊りなのか河内音頭の演奏が聞こえだしています。とある集落の分踊り大会を覗いてみました。河内っ子の河内音頭に寄せる思いは格別なようです。村々に音頭取りの名人と称される方々が多数おられ、セミプロとして各地の盆踊り大会に出演されてるようです。今回のぞいた集落は新興地の故か音頭取りではなく機器による演奏でした。
雷雨もあがり、涼やかな夜風の下で踊りまくる。

オープニングは夕刻の4時、まだ日差しがきつい中、地元高校の太鼓クラブの面々が出演して歌や踊りを披露してくれました。グローバリズムとか称するアメリカ文化の猿まねが流行っていますが、彼らの演目は伝統芸能に即したもの。ローカリズムこそ文化の神髄ではと喝采したくなるような取り組みです。歌あり踊りあり笛あり太鼓あり・・・・・・・・・今後の活動を期待したい若者達です。




途中ではにわかに雷鳴が轟き、大変な豪雨となりました。お客さん達はテントに避難したり自宅に戻ったり、それでも雨のなかで再開を待つ人々もたくさんおられました。河内っ子の面目躍如かな。



でも日頃の精進がよろしいのか、30分程で雨もあがってくれました。雨がなければ又踊り。まったく河内の人間と盆踊りとは切っても切れない仲のようです。DNAの中に組み込まれた独自の集積回路が存在するのでしょうか。ともあれ、普段は疎遠であった近隣の方々とも親しくなれる格好の場所なのかもしれませんね。ご先祖様達はそうした効用を含んだうえで伝統として残してくれたのかな。


2008年08月03日
PL花火大会
毎年8月1日はPL教団の花火大会である。当地のイベントというより、もはや全国ブランドではあるまいか。各種のツーリストがツアーを組んでお客様をご案内する。従って当日はお昼過ぎくらいから大混雑となる。沿線の商店はにわかに活気づいて、従業員も一気にふくれあがる。空き地などは臨時駐車場となり、場合によっては法外な料金を請求されることもあるとか。年に一度の稼ぎ時なのかな。マスコミの報道では17万人位の観客数だったそうだ。
教団のシンボルタワー。南河内のランドマークだ。

この花火大会だが、打ち上げ数が10万発から一気に2万発となり、物議をかもしたそうだ。教団の説明では数え方の変更とか。なんでも従来は、発射された花火の数ではなく天空で散らばった花火の数をカウントしていたそうだ。早い話が猟銃から1発散弾の弾丸を発射して、一発としてではなくその後に散らばった散弾の数を数えていたとか。常識的には、ライフルから飛び出した弾丸の数でカウントすべきだと思うが。まあっ、どうでもいいことだけど。

250人程の花火師が参加されたそうだが、花火はまさに芸術品。一瞬にして消え去っていくところが日本人の感性に合うのだろう。春の桜に酔うのと同じ心情かな。次々と打ち上げられる花火が圧巻だ。とあるビルの屋上に上らせていただいたので、仕掛け花火は見えない。上空にあがったのを遠くから眺めているのである。



PLの花火大会を見ると真夏だなと感じてしまう。南河内ではPLの花火が節目となっており、これからが夏本番。各地で盆踊り大会が頻発する。小生の場合も地元の町会で夏祭り担当となっており、中旬に盆踊りをメインとしたお祭りを開催する。当地一帯は河内音頭の本場であり、生粋の河内っ子は一晩中踊りに酔いしれるのだ。

花火師の方々は、たった1時間強ほどの演出のために1年間かけて準備をされるそうだ。火薬を扱うので危険でもあるだろうに、一瞬の感動を堪能してもらう為に、1年間黙々と前準備を続けられる姿に敬服する。どんな仕事でも一緒だろうが華やかな場面はほんの一瞬なのである。下積みの永い準備期間が必要な事は、どこの世界でも同じではなかろうか。1年間の準備期間の結晶が一瞬にして消え去って後には何も残らない、これが又いいことなのだろう。
2008年07月12日
れんげ祭りー2
本日のクライマックスである護摩供養と火渡りの儀式が始まった。修験道で一番華やかな場面かもしれない。それぞれの行為に意味があるのだろが、理解できずとも、一種荘厳な雰囲気に包まれながら進行していく。まずは古参と覚しき山伏が出て、口上を述べ始める。開会宣言みたいなものだろうか。

続いて弓矢のうち込みが始まった。これも意味のある儀式なんだろう。よく理解できない口上を述べながら、東西南北の四ヶ所に向かって矢を射るのだ。打ち込まれた矢を拾うとご利益があるのか、大勢の人が駆け寄っていた。

若き修行僧が松明に点火して貰う。晴れの舞台のようだ。点火された松明を持ち、一定の歩行法に則りながら祭壇(と呼ぶのかどうかは不明だが)に進み出て、やおら点火。最初は小さな炎であったが、次第に大きな炎と変わり杉の青葉が囂々と燃えだした。山伏の読経のなかで、願い事が書かれた護摩木が次々と祭壇に投じられていく。




本山の大先達も動き出された。これから一番重要な儀式を執り行われるのだろう。従者の山伏を従え、所定の場所へと進まれる。

祭壇の火が下火になった頃、火渡りの準備が始められた。そして、その周囲では山伏達の奇妙なダンスが始まったのだ。ヨガのポーズみたいな形をとりながら、呪文をとなえつつ祭壇の回りを一周するのである。意味のある行為なんだろうが、何とも魔法使いの呪術のような印象を受けてしまう。


さて、いよいよ火渡りの儀式だ。ここでも日本の伝統に則った。即ち「指揮官先行の原則」である。転法輪寺の若き住職が先陣を切って、塩で清められた祭壇の前に立たれた。炎が吹き出している祭壇の上を素足で渡っていくのである。織田信長の火攻めにあわれた武田軍の快川和尚が「心頭を滅却すれば火もまた涼し」と喝破して亡くなられたようにはいかないものである。無事に渡れるのかと案じていたが、十字をきりながら渡り終えられた。


住職に続き、次々と山伏達が渡っていく。小生も渡らしてもらおうと考えたのだが、後ろを見るとあまりにも大勢の信者さん達が順番待ちをしておられた。とてもじゃないが下山時間に間に合わない。確か昨年もそんな状態で諦めたようだったが。
2008年07月11日
れんげ祭りー1
南河内の東部、奈良県との県境には、金剛・葛城の連峰がそびえ立っている。標高は1000メートル前後に過ぎないが、結構山は深い。ここは修験道の開祖といわれる役小角(えんのおづぬ)が最初に修行をした場所として知られている。飛鳥時代に奈良県の御所市付近に生まれた彼は、日夜金剛葛城に登って修行に励み、時には雲にのって空を駆けたとも伝えられている。奈良時代が始まる少し前に、箕面の山で入寂したとも言われている。毎年7月7日は彼の命日、金剛山では「れんげ祭り」を行って彼の遺徳を偲んでいる。
メインスタジアムの転法輪寺。ここは葛城神社との神仏混合だ。

転法輪寺は真言宗醍醐派に所属する。宗派とは、宗教界の派閥といえば叱られるかな。古来から自然発生的に始まった山岳宗教が、弘法大師や伝教大師によって真言・天台の大きな組織に集約され、明治維新まで興隆を極めたが明治政府の廃仏毀釈によって廃れていった・・・・・・・というのが受験用日本史の知識だったような。
京の醍醐寺から一行が到着された。本社の社長さんにあたる御方。
信者の方が続々と登って来られる。普段でも登山者の多い山だが、今日は格別のようだ。無論、大半のかたが白装束で、各地のお堂などでは般若心経の静かな読経の声が流れてくる。

正午から祭りは始まった。ホラ貝を持った山伏を先頭に、お寺や神社或いはお堂などを粛々と参拝する。時折聞こえるホラ貝の音や読経の声が、静かな山域を震わせる。あまりにも多数の山伏のため、時間調整が必要なようだ。





転法輪寺の若き住職。彼は「司講」という組織を結成し、真言密教に則った修験道の復活をめざしておられるようだ。参加者も次第に増え、毎月修行日を定めて祈りの回峰行に励んでおられるそうだ。ちなみに修験道とは、人間が外界を感知するための感覚機能である五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を山岳修行によって鍛え上げ、五感を超えた超能力(現在科学では説明不可の意)としての第六感を獲得しようとの活動のようだ。
転法輪寺の若き住職。宗教界のイノベーターとなられるか ?

祈りの回峰行を終えた山伏達が戻ってきた。さあ護摩供養と火渡り儀式の始まりだ。今年は、何とかして小生も火渡り儀式に参加しようと願っているのだが。

2008年05月29日
春季大祭
本日はお不動さんの春季大祭、当初の予定ではカメラを抱えて一日張り付く段取りだったが、諸般の事情で二時間程度しか時間が取れなくなった。これでは全体像がつかめない。やむを得ないので、念願だった山伏の行進と護摩会場の撮影に限定することにしよう。駅前に着いたのが10時半頃、駐車場のおっちゃんに行進は11時からと聞き、車を預けて山門に向かう。参道は善男善女で一杯だ。
寺内は人が一杯。やはり例月祭よりは参拝者が多い。

神域への侵入者に大あわて。法力での阻止は困難だったか。

座り込んでないで、神域をガードしないと。結界を破られますよ。

斎戒沐浴とまではいかないが。 大量の護摩木


時間が迫ってきた。山門に戻り、山伏一行の到着を待つ。これが本日のメインとなる撮影対象だ。かすかにホラ貝の音が響いてくる。どうやら到着のようだ。
独特な衣装だ。それなりの由緒があるのだろうが、小生には不明。




見事な行列だ。およそ200名近くの山伏たちであろうか。これだけの修験者がそろう大祭も珍しいのではなかろうか。専用の装束に身を固め、粛々と行進は続く。時折ひびくのはホラ貝の音。確かに壮観なのだが、何かものたりない。何であろうかと思案してて、ふと気づいた。そうだ読経がないのだ。毎年7月7日は金剛山のれんげ祭り、この時もたくさんの山伏が参加されるが、読経しながらの回峰行となる。お経の故なのか、場所によるものなのか、修験者全部が一体となった読経の声は、まるで天からの贈り物、天女のメロディのような心地よさだ。優秀なグリークラブに勝るとも劣らぬ雰囲気である。宗教者は音楽の持つ効用をフルに活用すべきではなかろうか。確かに駅前から山門までの長い坂道を、読経しながらの行進ではたいそう辛い事とは理解できるのだが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
2008年05月01日
楠公祭・春祭ー2
春祭の神事も無事に終了し、奉納太鼓の演奏となった。わざわざ広島から来演してくれた、太鼓ユニット我龍のグループである。竹内孝志さんをリーダーとする若手の太鼓打ちだ。舞台衣装や坊主頭に、一瞬その筋の方かとも思ったが、なかなか礼儀正しい若者だった。挨拶の中で、自分達なりに楠公さんについて勉強したうえで参加したこと、名将の御霊の前で演奏できるのをとても光栄に思っていること・・・・・・・・・・等々を静かに語っていた。



様々な太鼓を自在に操り、リズミカルな演奏に多くの聴衆もうっとり。神社の境内と和太鼓演奏とはよく似合っているようだ。楠公さんもひょっとしたら出陣の触れ太鼓と勘違いされるかも。

彼らはなかなか芸達者で、獅子舞のパフォーマンスも見せてくれた。子ども達は頭を噛まれて思わず泣き出す幼児も。


篠笛の演奏も始まった。


最後は「餅まき」となった。祝い事の最大のイベントかもしれない。モチはかっては山里のハレの日の食べ物だった。その餅を皆で取り合いして喜びを分かち合う、今風に言えば「喜びのシェア」とでもいうのだろうか。おそらくは、全国各地に残っている風俗ではなかろうか。カメラ片手に撮影を続けながら、小生もちゃっかりと6個も拾っていた。


2008年04月30日
楠公祭・春祭ー1
4月25日は楠木正成こと楠公さんの生誕日と伝えられている。彼は、地元千早赤阪村から出自した最大の偉人だろう。誕生日を村中で盛大に祝うのもある意味当然かも知れない。楠公祭・春祭として、各地からの来訪者も含め、毎年多数の参加で開催されている。まずは式典から始まった。生誕地での神事である。
神職の登場。これからは神事なので撮影は中止とします。


約1時間に及ぶ神事も無事に終了した。次々と参拝される方々の名を聞いてびっくり、地元のみならず神戸の湊川神社、島本町、四条畷市、神社庁、政治家、行政関係者、各種団体・・・・・・・・・・多数の方々の参加である。楠公さんが今も尚、いかに多くの人々に影響を及ぼしているのか、再認識する。名誉や栄達或いは一族の繁栄などは求めず、己の志操に殉じた高潔な精神に人は惹かれるのかもしれない。
幼稚園の子ども達が登場し、奉納太鼓の演奏を行ってくれた。年長組らしく、音程もしっかり取りながら、聞かせる演奏となった。わずか4~5歳位でみごとなものである。楽器の弾けない小生は、うらやましい限りだ。


会場を建水分神社に移し、春祭として趣を変える。ここは楠公さんの御霊を祭る神社でもある。季節の花シャクナゲが見事に咲き誇っていた。いい雰囲気だ。建水分神社でも新たな神職が登場し、神事が始まるのだが、参加だけさせてもらって撮影は控えておく。



楠公さんの御霊を守っているのだろうか。護衛の兵士達が無言のまま、警護の任務についていた。忠実な兵士のようだ。最後まで楠公さんに従った楠木軍の若武者達であろうか。



2008年04月24日
山里の春ごとー3
午後の部は社長訓辞、イヤ違った代表による歓迎の挨拶から始まった。シャイな社長は少々照れくさそうに、山奥までのお運びに感謝と春ごとの趣旨説明を行う。それにアイリッシュフルート奏者のHATAOさんが、わざわざ持尾城趾まで出向いての演奏を実施されることの紹介をも。

子ども達(大人の方が多いか)は花より団子のようだ。バウムクーヘンは別腹らしい。しっかりと焼き込んでいる。山の上でのお菓子はまた格別なんだろう。


小腹を空かすために、子ども達(キッズクラブという名の里山体験倶楽部があるのだ)の秘密基地を探訪するミニツアーを実施する。詳細は明日にでも紹介したい。民家をのぞいたり、野花を愛でたり、土の小道を踏みしめたり・・・・・・・・・・・かれこれ1時間近くも歩き回っただろうか。
さあ、いよいよ演奏会の開催だ。葛城連峰をバックにフルートとバイオリンの共演だ。

お弟子さん達も共演を始める。実は当倶楽部のメンバーがHATAOさんのフルート教室に通っていたのだ。






彼女たちが吹いているのはティン・ホィッスル、HATAOさんのがアイリッシュフルート、いずれもアイルランドの民族音楽で使用される楽器だ。ケルト音楽といったほうが早いだろうか。ティン・ホィッスルは日本の子ども達が使用しているリコーダーによく似ている。ブリキ製の縦笛だ。安価に購入できるそうで、軽くて小さいので山での使用には向いているかも。そのうち里山倶楽部楽団が出来たりして。


何かひとつ楽器を弾ける方をとてもうらやましく思う。音楽のある生活、楽器を弾ける生活を夢見るのだが・・・・・・・・・・・・・・・手も足も出ない。悲しい事だが、出来ないものは出来ない。せめてしっかりと聞かせていただこう。

 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン