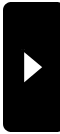2010年12月10日
日だまりの剪定作業
初冬の果樹園風景です。まだ秋っぽい印象ですね。

シイタケほだ木用の原木を確保、一寸一休みですか。

果樹園は変形的な地形で、一等地は東南向きの斜面、残りが東向きと北西向きの斜面とで構成しています。東南向きの斜面には桃、ビワ、ナシ、レモン、ウメ、柚子、ブドウ、プラム、栗、ヤマモモ等々を植栽しています。東向きの斜面には各種の柑橘類とキウイやウメや栗など、北西向きの斜面ではカキや栗やカリンやサクランボなどが頑張っています。本数も多くて正直いいますと剪定作業が行き届いてないのが実情ですね。ウメは前回に結構剪定してますので、本日はカキやナシを主体にしましょうかな。そうそう病気で実を付けなくなったサクランボ2本を伐倒との話も出ております。チェーンソーが最も活躍する場面ですね。
伐倒斑も剪定班も順調に進行中の模様ですね。


病気のサクランボが倒されました。チップ用にいかがでしょうか。

冬場にはいりますと、例年の行事としてシイタケの植菌作業もあります。植菌は伐倒して1~2ヶ月寝かせた原木が必要で、必然的に本日の伐倒作業が要求されますね。収穫も皆の楽しみでしょうから、本日のミッションはかなり多めのようです。数名づつチームを組んで作業を分担することに。小生は参加されて日も浅いTy氏とペアで剪定作業班に、途中各チームの名(迷?)プレーも参観に案内しておきましょう。剪定は切り落とすのは簡単ですが、剪定枝の撤去作業があり結構めんどいものです。現場で焼却処分が出来れば楽なんですが、水気のない山中でのたき火は御法度でしょう。黙々と隅の集積場へと運びます。
伐倒された切り口を物珍しそうに覗きこむTy氏、街中では見られませんよね。

次の獲物を狙うハンター達、次回は木登りしての枝打ちとか。

収穫作業がお好みの方も多いようでして。

剪定斑、伐倒斑、収穫斑、竹林の間伐斑・・・・・・・各位が得意分野で熱中作業です。気心の知れた腕自慢の仲間達なので放置しておいても大丈夫、時間配分を考慮しながら程よく休息しながらミッションを片付けていきます。今日はリーダーのIk氏が豚汁の準備を、山中で暖かい豚汁を頂きながらの昼食は格別ですね。無論、恒例のコーヒーも準備されており、取れ立てのシイタケを炭火焼きで頂戴しながらワイワイガヤガヤ。中高年の井戸端会議みたいなものでしょうか。食後には、料理自慢のKさん手作りによるイモクッキーが配分されました。体力勝負でダイエットに励んでますのに、ウエストが危険ラインの85センチを突破しそうですね。
伐倒したサクランボには野鳥のマイホームがありました。子育て完了かな。

一度ご馳走したいですね。炭火焼きのシイタケ、美味しいですよ。

おじ様達の井戸端会議が始まったようです。作業の合間の骨休め?

2010年11月16日
休眠期にはいった果樹園作業
さあ草刈りをと張り切るNk氏、肝心の雑草がないですね。

退院後日も浅いのに駆けつけてくれたMz氏、ボチボチでいいですよ。

こうなってきますと炭火をおこして焼きシイタケ・・・・・・人生楽しまなくっちゃあ、と言うのが暗黙の了解。作業は後回しにしましてコーヒータイムです。炭は勿論、他の仲間達が焼き上げてくれた物、クヌギやコナラを原木とする当地産の黒炭です。マングローブの勢いよく燃え上がる炭ではありませんよ。コーヒーはインスタントながら山の中で頂く一杯は至福の一時ですね。たっぷりとした休息時間を堪能して再び作業開始、草刈りが余り必要ないので剪定作業にかかります。果樹園の命はこの作業に尽きるかと思いますね。そう言いながら充分な剪定技術を持ってるとは言い難く、見よう見まねの剪定作業です。徒長枝のカットは第一基準、それに太陽光線が全部の葉に行き渡るように混み合った枝をカットしていきます。大きな枝はチェーンソーで小さな物は手鋸で処理します。皆さん手慣れたもので、小気味よいエンジン音が響き渡ります。
花より団子、イヤ違いました。シイタケですね。焼きシイタケ最高です。

お化けシイタケ、直径が30センチ近くあります。

奥方の薄味に閉口とのたまわるIk氏、たっぷりと醤油を。

仲間の衆は大半がNPO法人里山倶楽部で基礎教育を受け、数年間の実践過程を経由して従事しています。従って、目標だけ設定すれば放置して置いても大丈夫なのが非常に有り難いですね。気心の知れた作業技術に習熟した仲間の存在ほど安心できるものはないようです。少々持ち上げすぎたようですね。頑張って継続していただきましょう。剪定は作業後の撤去作業がやっかいです。コレを処理しておかないと春先に草刈り作業が出来ないのですね。半年先、1年先を見据えながら作業を進めていきます。そうそう肥料の散布も必要ですね。俗にお礼肥とも申しますが、秋に実ってくれた果樹木達にご苦労様の感謝を込めて提供する物です。
綺麗に整備された果樹園でしょう、仲間達の努力の賜です。

のんびりと散策してるだけでも楽しくなってきますね。

若干のパラ付きはありましたが、作業が困難になるようね天候でも無く順調に完了しました。11月から3月位まではこうした作業がメインとなります。柑橘類の収穫も始まりますので、ミカン等をほおばりながら楽しく作業したいものです。そして果樹木の更新もこの季節、残念ながら途中で害虫に食害されたり病気になったりで、命を失う果樹木も少なくありません。代替木の植え込みも大事な作業となってきます。購入資金に乏しいのが難点ですが、次の世代のためにも植え続けておきたいものです。
お礼肥を播いておきましょう。安価な鶏糞ですが気持ちの問題で。

渋柿やカリンそれにキウイは残ってましたね。お土産です。

カリンの蜂蜜漬けを作るんだと張り切ってますが。高くつきますよ。

2010年07月05日
エンジンの音ごうごうと
ノウゼンカズラが咲き始めました、夏ですね。

静かなること林の如く・・・・・・・・・・4サイクルの特徴でしょうか。

果樹園だけあって木陰が多いのが救いでしょうか、刈払機を担いだ仲間達が思い思いに散らばっています。2サイクルの甲高いエンジン音が響き渡りますが、作業が順調に進んでいる証拠でしょう。幸いなことに仲間達は何れも刈払機やチェーンソーの達人ばかり、何も心配なく作業の進行を見守っておれば充分です。これが技術水準にバラツキがありますと、危険性が急に高まってしまいます。それなりの配慮が要求され、進捗度が落ち込んでしまいますね。マイ刈払機を持参する者も増加しました。一定のレベルに達すると、どうしても自分専用機が欲しくなるようです。メンテなどもやりやすいし、機器の状況も把握しやすいので推奨すべき方向でしょうね。
おニューのマイ刈払機の登場です。気合いがはいっています。

スタートは同じでも皆違う方向を目指しますよ。何の心配もいりませんから。

彼方此方で刈り込んでますが、刈り込む前と後とを比較してみて下さい。画像ではわかりにくいかと思いますが、50センチ以上1メートル弱位の段差が見受けられます。前回刈り込んで1ヶ月も経過していません。それでこれだけの伸びなんです。10月位まではこのような雑草との格闘戦が続きます。ちょっと楽になってくるのは11月に入ってからでしょうか。
自宅でゴロゴロされて奥方から睨まれておられる方、仲間にはいられませんか。エネルギーの発散場所はイヤという程ありますよ。全身から汗が噴き出すほどの作業量ですから、ダイエットには最適かも知れません。無論、生活習慣病などは無縁の存在かと思います。
重たい26ccエンジンを選択されましたか。

それにしても山の中で汗だくになって作業することがどうして楽しいのか、説明を求められても回答出来ませんが、まあ一度体験してみて・・・・・・・・・・・そう答えておきましょうか。嬉々とした仲間達の姿を拝見されたら、自ずと納得されるかと思います。世間的にはアホみたいな行為、だがやってる当人達にとっては至高の価値が存在するのでしょうね。
一番大事な事は、適度な休息と水分補給。きちんと守っておられますね。

2010年06月29日
プラムの樹
全く数年ぶりに真っ赤なプラムを見る事が出来ました。

この色合いが何とも言えません。グリーンの葉と似合っていますね。

かって祖先達は、「渇しても盗泉の水を飲まず」・「李下に冠を正さず」といった箴言を親から子へと言い伝えてきた。そうした伝統がここ60年ほどの間に完全に失われ、何時の間にか何でもありの軸無し航法へと変化してしまったようだ。進駐したGHQの狙いが半世紀を経て見事に結実したのだろう、戦略眼の鋭さと遠大さとに感服する思いである。そうした経緯を思い出させるプラムの樹なんだが、不思議なことに今年は少ないとはいえ実が付いている。真っ赤に熟したプラムを見るのは久方ぶり。実にいい光景だ。仲間の衆がジャム用に持ち帰るほどには無さそうだが、試食を楽しむ程度には確保できてるようだ。
数個をもいで試食してみましたが完熟のようです。タイミングを外さぬように。

プラムの樹も品種によって或いは植栽場所や育て方によって収穫期は変化する。果樹園のプラムは概ね6月末が収穫期、ここ数日が該当日であろう。小生が谷間の農園に植え込んでるプラムも10本ほどあるのだが、未だ実は青々している。樹齢3年ほどの樹が5本、1年ほどの樹が5本存在する。3年物は樹高4メートル程になり、僅かながら実を付けだした。完熟してくれるのを楽しみに待ちたいものである。
こちらはマイ農園のプラムの樹です。まだ青々していますね。

樹高4メートルぐらいありますが、まだ3年物。実の負担は大きいようです。

真夏の信州でアルプスから帰宅する際は、プラムの大袋がお土産だった。現地の直売所には安くて芳潤なプラムが山積みされており、立ち寄るのが楽しみでもあった。しかも実が大きくて我々の栽培品の数倍はある。ここにもプロとアマとの相違が存在してるようで、力量の差を痛感させられる。果樹木も自然農法を気取った放置樹では満足な実を付けてくれないのだろう。肥料や水分や雑草の処理や剪定など、施行しなければならない領域は無数に存在するようですね。
中央下段がプラムの樹。ここには5本植え込んでます。

2010年05月06日
草刈り戦争が始まった
現在の果樹園はこんな状態です。野ウサギ達の天国でしょう。

備品の刈払機が不足気味なので、皆、個人用のマシーンを持参しての作業です。見ていますとメーカーも機種も様々、眺めるだけでも結構楽しいものです。爆音が響き渡り、散らばったメンバーが一斉に刈払機を回し始めます。小生はチェーンソーを抱えて桜の救出に。予て気掛かりだったのですが、ツルに絡まれて覆われ、太陽光線もあまり届かぬような桜が1本ありました。しかも真横の檜が枝を伸ばして余計に薄暗くなっています。まずは檜を伐倒、玉切りして処分です。その後桜に登ってツルの伐採作業、桜は日陰の故か弱くなっており、足の置き場に気を遣います。結局、役に立ったのは手鋸と鉈でした。樹上では使える用具も限定されます。2時間ほどかかってツルを除去しました。さすがに樹冠部分は不能でしたが、根元を断ち切ってますので時の経過で腐朽するでしょう。
とんびくらぶが誇る草刈り隊の精鋭達です。




樹上におりますと仲間の爆音がよく聞こえます。散らばりながら各位が頑張って刈り込んでくれてるようです。作業の進捗具合は音を聞いてますと概ね理解できます。極めて順調なようです。ここの果樹園も面積がそこそこ広大なので草刈りも大変です。全面を刈り終わった頃には、次の雑草が伸びきっている・・・・・・そんな感じで半年ほどが過ぎていきます。どうにか楽になるのは11月にはいってからでしょうか。それまでは草刈り戦争・・・・・そう全く戦争と言っていいほどの内容です。打ち勝って行くには、刈払機の台数如何、これに尽きますね。手慣れたスタッフが数多くそろって刈払機を振り回す、これしか方法論はないようです。あっ、除草剤などは使用しませんので、悪しからず。
ちょっと一休み、水分補給が欠かせません。脱水症にはご注意を。

タケノコ班も絶好調の収穫のようです。ネットが効いてますね。

年代物ですが未だ現役です。スチール製の020T型マシーン。

昼食は暑いのでブルーシートを広げ、陰の下での食事となりました。暑すぎますが、冷たいジュースなどではなく熱いホットコーヒーを戴きます。体は冷やさぬ方が快適なようですね。Kさんがボンタン等を使ったママレード(かな?)を差し入れです。器用な方で、山の幸を上手に使いながらデザートや料理を創り出されます。前身は、シェフ、大学教授、営業マン、農業人、果樹農家、医薬品販売業・・・・・・・・・・・・・・様々な憶測が飛び交いますが、本人はニヤニヤと笑っているのみ、正体は不明ですね。
Kさんは美女軍団を引き連れて野ウサギ作戦に。

野ウサギには食べさせないぞ・・・・・・・・・・・・

食後は又もや草刈り作業の続行、kさん他数名は果樹木への金網張りを担当します。ここらは野ウサギの活動地でもありますので、若芽は食害に遭いやすいのです。小生の分担は杭作り、これまた鉈と手鋸の活躍ですね。実況放送は画像でご覧になって下さい。果樹園を維持管理していくのは、なかなかに大変な作業です。本当は消毒作業が必要なんですが、農薬への嫌悪感と経費不足で実行できていません。従って店頭に並ぶような見栄えのいい果樹は収穫しづらいですね。まあ、仲間内で消費する分ですから良しとしましょうか。
2月に伐倒したキハダ、見事な萌芽更新です。

里山の名花ササユリも生き抜いてくれてました。

2010年05月05日
タケノコ騒動終焉記
藤の花が咲き誇っているんですが、この画像ではわかりませんね。

山は新緑の一色なんですが、映えませんね。

分担するのはKさんと小生の2名、撤去作業だから2名もおれば充分です。支柱に軽くネットを縛ってるだけですから、解いて巻き込んでいけばOKです。小枝や草等が巻き付いていて、言葉で言うほど簡単ではありませんが、1時間強で撤収完了。回収したネット類は来年まで丁重に保管します。来年の春先、又もやシシ達への闘争心丸出しでネットを張り巡らすでしょう。ある種のゲームみたいな感覚かも知れません。連中も知っていて、ニヤニヤしながら藪陰から見守ってるいるかも知れませんね。回収作業を続けるさなか、チラホラ藪を眺めていますと結構タケノコが出来ていますね。ネット類を回収したら今夜にでも連中が出張るでしょうから、目に付く範囲は掘り出して置きましょうかな。収穫結果は画像のとおりです。
張り巡らしていたネット類を撤去します。

小枝や雑草が絡んでいて撤去がしづらいですね。

黙々と撤収作業を、発案者のKさんです。

画像で状況がおわかりかと思いますが。雑草が結構伸び出しました。又もや草刈りのシーズン到来のようです。今から10月頃までは、雑草の成長と草刈りとのイタチごっこみたいな関係が続きます。刈払機が多数有ればいいのですが、共用備品が少ないので作業効率が今ひとつなんです。どこかに刈払機を4~5台寄贈してくれそうな篤志家はおられませんでしょうか。さて今後の活動は草刈り中心として、収穫の見込みは如何にと見回ってみましたら,Kさん曰く、「実の付きが芳しくないな、今年は出来悪いで」。今の時期でしたら、柿、プラム、梅、桃、カリン、栗等がそれとなくサインを送っているようです。小生が見ても皆同じようにしか見えませんが、Kさんには明確な違いが判別できるようです。
ちょっと捜しただけでこれだけの収穫が、シシ達が喜びますね。

昼前には撤収作業とタケノコ掘りも完了しましたので共同農園へ。米作りの準備作業である、種籾の目覚ましをお手伝いしなければなりません。要するに水の交換です。ゲストハウスを覗きますと、何とOkさんが先着で既に交換済みでありました、ありがたや。水交換が不要であればお互いに自前の農作業となります。夏野菜の準備で追われっぱなし、発芽した苗類にも水やりが必要です。この時期は作業が多くて、なんぼ時間があっても不足気味、その割には体の方が動いてはくれないのですが。まあ、ボチボチとやっていきましょう。
西瓜の定植も完了のようです。キャップが保温と防虫の効果を。

腰が痛い、といいつつも作業は続きます。インゲンの用地のようです。

<お詫び>
ブログの容量制限を気にし過ぎまして、画質を落としすぎました。おかしな画像となって
しまいましたね。元に戻しますのでしばらくご容赦下さい。撮りだめ画像なのであと数日
は続くかと思います。
2010年04月14日
とんだハプニングで
この沼地から奥が我々の果樹園フィールドです。

ベースの野小屋に荷物を置いてスコップを取り出し、皆の後から探索に。皆さんなかなかタケノコ探しがお上手で、既に籠からは大物が何本も顔をのぞかせている。小生が見つけるのは小物ばかり、皆が見捨てた後かもしれない。それでもご機嫌で撮影を続けていたら突然異変が。シャッターが降りなくなってしまった、電源はオフにならない、ズームは効かない、各種のスイッチは動かない・・・・・・・・・・・突然死なのか。折角の撮影チャンス、皆の衆の活躍場面は全く撮影していない。予備のカメラは持参していない。絶体絶命・・・・・・・・・・・ということで作業前半の一部しか画像がありませんが、悪しからず。
愛用のパナソニック・ルミックス、6年半ほど酷使してます。

突然の異変で困っています。とりあえずはコンパクトで代用を。

Uさんの読みは的確で、雨上がりという条件も幸いしたのか、タケノコがあるある。人数分以上に掘り出しました。今回は予想以上の収穫だったので、イノシシ防除のネット類を提供して頂いたKさんのお友達にお届けすることに。半信半疑だったイノシシネット、理由は不明ですが意外と効果が高いようです。昨年も本年もネットを張り巡らした後はシシの襲撃が見あたりません。単なる偶然なのか、明確な防除なのか・・・・・・学問的な裏付けはありませんが、我々にとっては大きな武器となっております。三重にネットを張り巡らす手間は大変ですが、シシ達の蹂躙ぶりに悩むよりは余程にいいですね。イノシシの襲撃に悩んでおられる方は、騙されたと思って一度実践してみられたら如何でしょうか。無論、髪の毛がはいった袋を程よくぶら下げることもお忘れ無く。
こんな軟弱なネット類がどうもシシ達には効果的なようですね。

小生が見つけ出すのは小物が多いようです、仲間が見捨てたヤツかな。


果樹園もそろそろ青い雑草が伸び出してきました。これから10月頃まで毎回草刈りの連続と思っても相違有りません。刈払機が活躍する場面ですね。一寸油断しますと50センチ位は簡単に伸びてくれます。面積が半端ではないので機械力に頼っても思うようには捗りませんね。トラクターのような乗用式の草刈り機が欲しいところです。
前回のとんびくらぶは所用で欠席しましたが、仲間達が柑橘類を植え込んでくれてました。ここはゴマダラカミキリムシが活躍するフィールドで毎年のように被害にあっています。専業の果樹農家のように動力ポンプを使用して農薬散布すればいいのですが、経費の問題と農薬への嫌悪感から有用な実効策が取れていませんね。かろうじて根元をビニールで被膜する程度でしょうか。その代わりと言ってはなんですが、ママレードなどにも安心して柑橘類を使用できますよ。
仲間の衆の籠には大物がずらり・・・・・・・・・・・

大きめのをめっけ、兄弟なのか側にはもう二本がくっついて。

2010年04月09日
お届け物は山の幸
掘りあげた数少ないタケノコを、お裾分けしていただきました。

GHQの隠れた目的は日本人の精神の破壊にあったようだが、節操もなく見事な協力者に変身した教育関係者も少なからず存在されたようだ。残念なことだが、その効果は絶大で、日本人としてのアイデンティティもプライドもそして郷土への愛着も失われてしまったかのように感じる。先日レポートした河南町の、「美しい河南町条例」はこうした風潮へのアンチテーゼではあるまいか。無論、小さな街の小さな試みなんだが、その意味するところは非常に大きいと思う。この街は、かって存在した美しき日本人の復活を意図しておられるのでは・・・・・・・・・・・そう推測して大きな期待を込めて見守っている。この4月から施行された条例、大化けすることを念じたい。
皮を剥きますと次から次へ、皮の量だけが増加していきます。

中身はすこぶる僅少に、タケノコの特徴ですね。

さて肝心のタケノコなんだが、盗掘者達が気づかぬ隠れた場所にはかろうじて残っていたようだ。参加したメンバーで分配されたようだが、ご丁寧に欠席の小生にまでお裾分けの栄誉にあずかった。始めて参加されたとらちゃんが立ち寄って届けて下さったのだが、少ないタケノコなので恐縮している。折角のお裾分けの品、大事に活用せねばと夕餉の膳にご登場願うことに。タケノコはラッキョウと一緒で、皮を剥いていくと次第に小さくなり、食べれる部分は僅少となるのだがそれも又よし。山の神に願って調理して貰ったのが下記の2品、本年最初のタケノコ料理です。苦労して探し出し掘りあげていただいた仲間の衆に感謝して、いただきます。
タケノコの木の芽和えです。

同じくタケノコの土佐煮です。

山の恵みは旬の時期にしか入手出来ません。しかも気象条件や環境の変化等で、必ず捕捉できるとは限らないところが、人間を謙虚にしてくれますね。有り難い、と感謝しながら頂くのは精神の健康にとってもすこぶる効果的です。タケノコのみならず山菜等も同じ事ですが、所有者が存在しない野山や田畑はあり得ません。節度をもった行動が要求されますよね。美しき日本人、過去形ではなく現在進行形で語りたいものです。
2010年03月28日
不思議なる出逢い
プラムの花が満開です。今年も豊作の予感。

頭の黒いイノシシが狙っているかも、要注意ですね。張り込みますか。

さて一人ではネットも張れず、竹の伐採等にはいりましょうか。筍を育成するには親竹が必要なのは異論がないでしょう、他の動植物と全く同じ原理ですね。その親竹を必要最小限度残して他の竹は除去しようと思っています。果樹園の事ですから、筍も大事ですが本来の果樹木の生育がもっと大事な仕事、太陽光線を確保しなければなりません。陰樹といって日陰を好む樹木もありますが、果樹は全部が基本的に陽樹といっても過言ではないでしょう。即ち、太陽光線が不十分では発育出来ず、実りも期待できないですよね。日陰を作るような竹林は除伐するに限ります。小生は竹林伐採用には型枠大工さんが使う目の細かい鋸を使用しています。これがすこぶる快調で、生竹なら難なく切り捨て可能です。倒して適当に裁断し積み上げておきましょう。恐縮だが撤去作業は4日の例会時にお願いしましょうかな。
ビワの木が倒壊していました。虫にやられたようですね。

倒壊したビワの根元部分です。食い散らされてますね。

レモンの木も倒壊です。犯人はゴマダラカミキリかな。

機嫌良く作業を続けていると、麓の穂から何やら人影が・・・・・・・・・スワ、筍泥棒さんか?。注意して見るとほおかぶりした奥方風の女性で、足下を見つめながら登ってこられる。どうやらワラビ、ゼンマイ等の採取組のようだ。取れますかな・・・・・・・ふいに声がけするとビックリ仰天、泡食ったような表情でおびえておられる。まさか人がいるとは想像もされなかったようだ。落ち着いてもらって話を聞くと、地元のご婦人で妙齢(?)のおばあさん、推察どおりでワラビ・ゼンマイの採取に毎年来訪されてるようだが、人に出会ったのは始めてとか。息子さんは府警本部にお勤めのようで、「俺の立場もあるので、他人さんの山で山菜採りなどしないでくれ」と常に言われておられるとか。思わず苦笑しながら聞いていたのだが、事故がなければいいのだが。山菜採りの方が山で熊やシシに襲われたとか滑落されたとか、よくニュースにありますよね。
竹を切りまくっています。撤去作業が必要ですね。

同じく枝切りしたものも除去しないと草刈りが不能ですね。

とんだハプニングで作業も中断してしまったが、竹の伐採や樹木の枝切りそれに残骸の処理などやらねばならない作業はてんこ盛り。それとブドウ棚の建設が中断したままなので、こちらも完成させないと。農作業も遅れ気味・・・・・・・・・・・・春先には仕事が混み合うとは言いますが、まさに始まってしまったようですね。のんびり出来た農閑期はおしまい、繁忙期へと変わってしまったようです。筍堀りにゆったりした時間がとれるかどうか、定例会では作業の方を優先させないといけないようですね。
2010年03月20日
縄張り攻防戦
イノシシとの攻防戦に燃えるKさんです。本日は二日目。

昨年度使用した物も再利用します。

kさんが準備されたロープはおよそ3000メートル、ネットの上下に通しますので延長1500メートル、これで筍の発生予定地をぐるりと覆ってしまうつもりです。昔、イギリスの農業史でエンクロージャーなるものを習いましたが、それの日本版でしょうか。イノシシは図太い格好に似ず、運動能力には素晴らしいものがあります。疾走力、攻撃力、破壊力、ジャンプ力・・・・・・・・何れを取っても人間が適いそうにもありません。尋常な手段では当然の如く負けますよね。考える葦は考えます、彼らの弱点は何ぞやと。そこでKさんが到達したのが、前回ご紹介しましたネット戦法。幸運にも昨年度はこの戦法が効果を発揮したのか、軽微な被害で済みました。
徐々に防御線が出来上がって来ますね。

我らの果樹園です、こんな環境で作業中なんですよ。

本年度もネットを張りつつけているのですが、三重構造のため時間のかかること。なかなか全体を囲うことが出来ません。途中、邪魔になる竹の伐採もやりながらですから、ある意味しょうがないですかね。お天気は上々、作業自体は楽しくやれます。本日は快晴に近く、ポカポカ陽気は眠気を誘う程で、こんな時に屋内での仕事を為さってる方が気の毒に思えます。どうもお天気に誘われたのか、隣地の竹林で何やら人声と物音が。どうやら筍掘りの作業中のようですね。隣地の所有者は確か遠隔地の方と聞いていたが、わざわざお出でになったのかな。それとも?
筍の出現予定地 パートワン

筍の出現予定地 パートツウ

Kさんと挨拶がてら出向いて筍掘りの条項を観察、しばし話し込んだら、「地の者じゃけん・・・・・」とかの発言が。判明しました。どうやら地権者の自称お友達の方のようです。春先になりますと、こうした自称お友達の方がしばしば竹林を徘徊されています。トンガに図田袋、足回りは長靴か地下足袋、汚れてもいい服装・・・・・・・・・・いわゆる完全装備の出で立ちで、明らかなる確信犯のようですね。まあ、あれこれ言うような野暮な真似は致しませんが。イノシシに捕獲されるか、自称お友達に捕獲されるか、結果は同じ事のようですから。ただ何処の竹林も整備不良で筍の出来は芳しくないようです。竹林の整備、それは一言でいいますと「傘をさして歩ける程度」と表現されています。人工林と同じく、除伐や間伐が必要なんですが、事実上の竹藪となってるところが大半ですね。
第二陣の防御ネットを張り終えました、但し、まだ三重とはなってません。

午後2時にKさんのお友達(ホンマの)が共同農園に来訪されるので、1時半で作業ストップ。やはり完成は困難で、もう一二度の作業が必要なようです。今月中に時間を確保できるか、思案のしどころですね。筍は食いたし時間は少なし・・・・・・両天秤はイカンのでしょうが、悩むところです。
マンリョウも金網で大事に保護を。

2010年03月18日
宴の跡に腹立てて
破られたバリケードに呆然とするKさん。

左側隣地の竹林から右側の我が果樹園へと侵入しています。

昨年は大丈夫だったし今年もOKだろう・・・・・・・・そんな甘い期待はものの見事に裏切られた。竹林を回って見ると、至る所に彼らの宴の跡が。まだ地表面に出ない筍を探り当て、掘り出して皮だけ残し綺麗に賞味なさっておられる。あまりの見事さにただ呆然と佇むのみ。どうやら第一陣の筍(長男坊と称している)は全滅のようだ。第二陣(次男坊と称している)の筍はしばしの後になるだろう。それも無事に地表に出現してくれるかどうか。来月初旬にとんびくらぶの筍掘りが想定されているが、肝心の筍が皆目存在しない可能性も高い。彼らが彼方此方と荒らし回って、筍に飽きた頃を見計らった方が賢明かも知れませんね。
シシ道です。夜半に矢印のように通行してるようですね。

さて嘆いていても始まりません。何らかの対策をということで、Kさん発案の必殺技を繰り出しましょう。昨年度も実施しましたが、ツル性野菜用のネットそれも超長い物を三重にセットして防御陣とするのです。か細いネットですが、三重にしているのと、ふわっと設置してるのとで、意外と破壊できないようです。それに彼らの嫌いな人間の髪の毛をぶら下げておきます。何故かイノシシ達は嫌がって近寄らないようです。彼らの習性を読み込んだKさんの作戦勝ちでしょうか、昨年度はおかげさまで筍にあずかりました。
連中の宴の跡です。穴ぼこだらけですね。

筍は全てが未だ地中にあります。それを探索して掘り出してます。

中身は全部賞味してご丁寧に皮のみを残しています。

長男坊は全滅としても次男坊には間に合わせたい、そう願ってネット張りを始めました。本日はKさんと小生の2名のみ、作業は遅々とした歩みですが、とりあえず1ヶ所目は出来上がったようです。画像で紹介しておきましょう。こんなネットで効果あるのか、と疑問視されるでしょう。我々も半信半疑だったのですが、被害が少なかったのが何よりの証拠かと思います。とりあえず髪の毛は間に合ってないので、Kさん懇意の散髪屋さんに期待しておきましょう。それにしてもイノシシとの飽くなき対抗戦、知恵比べでもあります。基本的には、動物界と人間界との境界線が不明瞭となってしまった、ここに原因が存在するのでしょう。いわゆる耕作放棄地、休耕地等の存在です。彼らにすれば当然のテリトリー内だとの判断でしょうね。
報復合戦を狙うKさん、執拗にネットを張り続けます。

人間と動物との共存といいますか棲み分けは不可能ではないと考えます。国境線も同じ事ですが、主権者としてここから内はわが領土との明確な主張は必要不可欠です。彼らは少しづつ踏み込みながら、テリトリーの拡大を図っている訳でして、この一線を越えたら事と次第によっては攻撃するぞ、との厳然たる意思表示が必要です。イノシシ達も馬鹿ではありません。だめ押しの確認が不可能、人間どもの抵抗有り、と悟ればそれなりの対応を図ります。か細い三重のネットは、この境界線の明確な意思表示、彼らに対する愛のメッセージなんです。
この軟弱なふわふわ感が嫌なようですね。それと髪の毛が。

とりあえず第一陣のネットは張り終えました。

◇◇◇◇ とんびの仲間達へ ◇◇◇◇
3月中にネットを張り巡らしておかないと、筍にはありつけないかも。平日作業です
が、出動可能な方は現場に集合をお願いします。詳細はKさんへメールにて。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2010年03月09日
すれ違いの植樹
ブドウの栽培予定地です。まだ建設途上ではありますが。

ゲストハウスには素敵なお土産が待っていました。取り立てのシイタケと八朔です。連続雨天がシイタケには最適だったようで見事な成長ぶりです。八朔も完全無農薬の安心果実、有り難い品々です。土砂降りの中で作業をやってくれて、参加しなかった我々への配慮まで・・・・・・・・・・・・頭が下がります。それにしても、どうしてここまで作業に執着するのかと考えてましたら、苗木の植栽があったのですね。多分、先に手配して苗木を購入しておいたのでしょう。ブドウの評価が高かったので、ブドウの苗木を買い込んで早く植樹したいとの想いが強かったのでは・・・・・・・・・・・・・・・・・多分、そんなところでしょうか。それにしても有り難い話。ブドウは今まで取り組んでいない樹種、これからの果樹園活動には願ってもない果樹木です。
ゲストハウスには素敵なお土産が。ここまでの配慮はなかなかに。


さっそく果樹園に覗きに出かけました。案の定、小屋前の棚には植えたばかりのブドウの苗木がちょこまかんと座ってはりました。品種はキャンベルのようですね。自家受粉で栽培しやすい樹種だと聞いています。収穫期は9月頃でしょうか。ブドウは栽培地を選ばない、というか肥料分の少ない山地の方が向いてるようです。水捌けが良くて日当たりの良い場所が適地のようで、棚のある場所はブドウのための土地のような気がします。数年後の収穫を楽しみにしたいと思います。ブドウを使って、どぶろく葡萄酒を密造したら・・・・・・・・・・・税務署がうるさいですかね。
選択されたブドウの苗木です。しっかりと支柱腋で頑張ってました。



柑橘類も植え込んでくれたみたいで、八朔や甘夏の苗木を見受けました。野ウサギ防止用の金網も設置してくれています。柑橘類は野ウサギ対策もですが、ゴマダラカミキリへの対策も欠かせません。苗木が活着したら地表面近くの幹をビニール被膜した方が良いようですね。消毒作業が出来ないのと、農薬使用への抵抗感が強いので、他の手段を活用せざるを得ないようです。せっかく植栽いただいた苗木類、大事に育てていかねば。果樹木は木材ほどではありませんが、植栽から収穫までに幾多の年数を要します。場合によっては、収穫は次の世代で・・・・・・・・・・そんな事態も想定されますが、国家百年の計とまでは申しません、長期戦で参りましょう。
こちらは柑橘類です。どうやら八朔と甘夏のようですね。


沼では、誰も来ないだろうと安心しきった水鳥たちが遊んでましたが、小生の足音で飛び去りました。鴫とカモの仲間のようです。せっかくの憩いの時間をつぶして申し訳なかったのですが、仲間達の活動ぶりを記録に留めたく、あえて覗きに出向いた次第。水鳥くん達、ごめん。
水鳥たちを驚かした現場です。夕刻には戻ってくれるでしょう。

まだまだ栽培予定地はしっかりと控えております。

2010年02月12日
新たなるチャレンジ
ブドウの栽培予定地です。東南向きの下り勾配、最適条件では。

代々の先輩方は柑橘類や柿、栗等がメインで、ブドウへのチャレンジは無かった。好みの問題もあるかも知れないが、基本にはブドウはプロ農家の作品で素人が手出しし難い領域との思い込みがなかっただろうか。モノの本を調べてみると、ブドウ栽培は土質を選ばず肥料分もあまりいらず、どちらかというと痩せ地に向いているのだとか。しかも自家受粉で異品種を必要とせず、栽培も容易なようだ。ただ日照条件と水はけの良さだけは要求されるようで、この点は栽培予定地について全く問題なし。偶然にも皆の希望と諸条件とが旨く合致してくれたようだ。
ブドウの栽培現場です。ツル性果樹なので棚の整備が必要ですね。

当地にもブドウ栽培の伝統があってメイン品種はデラウエア、例の種なしブドウである。知人にブドウ農家があって数回手伝いに行ったが、ブドウは最初から種なしだと思っていた。ジベラリンという農薬で種無しにするとは想像すら出来なかったのだ。我々がとんびくらぶの果樹園でどんなブドウ品種を選択するか、好みが分かれるところだが、ポピュラーなのはデラウエアだろう。但し、あまりにも一般的すぎて面白みに欠けるのは否めない。巨峰やマスカット或いはピオーネやキャンベルといった品種がおもしろいかも知れない。商品栽培を想定しているのではないから、冒険してみるのが楽しいかも知れませんね。
巨峰 デラウエア


ブドウと共に挙がっているのが柑橘類、なかでも現在栽培していない温州ミカン。これも当地には赤阪ミカンの伝統があって広く栽培されていたのだが、収益性で廃れたようだ。温州ミカンのいい面は、その場で即座に食べれること。果樹園で作業の合間にもぎ取って食べながらの作業を楽しみたい・・・・・・・・・・どうやらそんな願望が根底に潜んでいるようですね。いいことかと思います。温州ミカンの栽培条件もブドウと似たようなもの、案外の適地かも知れないですね。ただ柑橘類はゴマダラカミキリムシの食害に遭いやすい特性を持ちます。私宅では地表面の幹回りに厚手のビニールを被膜して防除していますが、結構有効なようです。温州ミカンを植栽するのなら、こうした手段を講じる必要がありますでしょう。
ここらは柑橘類の予定地としましょうか、第一候補は温州ミカンのようです。

何れにしましても今回の嬉しき悩み事は、年末から煩瑣な業務を厭わずに出荷の労を取っていただいたIKe氏とK氏のご尽力によるもの、心より御礼申し上げたいと思います。
手入れの行き届いた果樹園、夏場は雑草のジャングルと化します。

2009年11月02日
実りの収穫
巨大シイタケ、大きいのは直径20センチ位あります。

小学生の僕も収穫参加、但しこの子はシイタケが大嫌いとか。

思えばこのシイタケ工房、数年がかりで作り上げたものです。クヌギをチェーンソーで伐採し玉切りしてほだ木を作りました、菌床栽培が主流ですが、我々のはこだわりの原木栽培です。市中に出回ってるようなメイドインなんとかの商品とは異なっています。手間暇掛けて作ったシイタケ、おいしく無かろうはずがないでしょう。年に数回は収穫可能なようです。本日は小学生の僕も参加して収穫を手伝ってくれました。初めての体験だとか。2月に植菌した原木もそろそろ栽培位置に配置換えしなければならないようですね。
シイタケ工房の全容です。こんな環境下で栽培しています。

ほだ木の役目を終えたのは放置してますが、誰かが動かしてる?

このシイタケのほだ木ですが、役目を終えて老朽化したものは放置しています。カブトムシの寝床へと有効活用が可能だからです。ところがこの元原木がどうも動かされてるみたい、どうやらカブトムシの幼虫を狙った業者の仕業ではとの推定です。完全な私有地で本来であれば立ち入るのさえ憚られる状態なのに、平気で荒らし回っています。確信的な犯罪行為ですね。
甘柿、渋柿・・・・・・様々な柿が収穫出来ました。

こちらは柚子です。鍋シーズンに入り重宝しますね。

こちらはキーウィの収穫です。肥料不足か少々小ぶりですね。

皆さんそれぞれ好みがあるようで、やはり自分の好きな果樹の方へ向かいますね。甘柿・渋柿・レモン・柚子・キーウィ・シイタケ・・・・・・・本日の戦果はこんなところでしょうか。無論、収穫の暁の前にはたゆみなき下準備の作業が継続したことをお忘れ無く。労無くして収穫はあり得ません。働かざる者食うべからず・・・・・・この箴言も同じ意味合いなんでしょう。それにしても気がかりなのはレモンの木が2本も枯れ始めていること。原因は多分ゴマダラカミキリムシかと思います。根本の幹に卵を産み付け食い破りながら成長する奴ですね。防除には専用の薬剤もありますが、活動期に何回も塗布しなければなりません。小生が採用している手法は、廃棄物の肥料袋(ビニール製)を根本に巻き付けるだけ、これでゴマダラは卵の産み付けが不能となります。地元の古老に教わった昔からの智慧です。
枯れ始めたレモンの木、ここまで来るともう助からないですね。

廃棄物の鉄パイプ、ツル性の果樹には宝物です。

Nkさんが廃棄物の鉄パイプを沢山入手し自分のトラックで運んでくれました。これはツル性の果樹にとってとても有り難い資材です。強固な棚を作ることで、果樹が日当たり良く繁茂し沢山の果実を実らせてくれます。キーウィやブドウなどには最適でしょう。現在ここではブドウ栽培を行っていません、次はブドウの植樹を・・・・・・・・・・・皆の願望は膨らむ一方のようです。Nkさんの配慮に感謝、次回の作業から棚作りに取りかかりましょう。
2009年10月05日
今日も森の整備に
道具の手入れは入念に、チップソーは適度の交換を。

愛用のマシーンで刈りまくっております。雑草も若干弱くなったような。

果樹園の中には森として残した場所が数カ所ある。通常はシイタケのほだ木置き場として活用しているのだが、散策できるような場所に変更し、森林浴が楽しめるようにしたい。希望は果てしなく広がるが、最初の一歩は除伐から。早速作業に取りかかろう。直径が数センチの灌木は手鋸で、概ね5~6センチ以上の径はチェーンソーでと使い分ける。中には灌木とは言い難い直径20センチクラスもあるが、無論チェーンソーの対象木となってしまう。目立ては得意ではないがマシーンは快調だ。滞るようなことも無く、作業は順調に進んでいく。
結構、林床も明るくなってきました。これなら散策可能かな?

日差しは強烈ですが、林内は涼やかです。冷房完備かな。

気をつけるのが、シイタケのほだ木には光線が届かず、尚、林内は明るく照射するという整備方針。相反するようだが必要条件なのだ。午前中かかって一ヶ所の森を整備した。随分と明るくなった散策用の森、画像でご確認下さい。森はやはり明るく太陽光線が届くような雰囲気が望ましい。かっては薪炭林として有効に活用され、人の手も頻繁に加わっていたのだろう。その当時はどこの森も散策可能な雑木林ではなかっただろうか、もう一度蘇らせたいものである。
整備しますと結構いい雰囲気に変化します。薄暗い森は嫌ですね。

午後の部は例の如く収穫作業に従事する。果樹園の楽しみは、やはり果実の収穫であろう。さすがに栗は収穫期を終えたとみえ皆目付いていない。柿の実が本番のようだ。それに柚子とキーウィを試験的に収穫してみる。レモンは今年は表年のようだ、嫌と言うほど実が付いている。余程嬉しいのかNgさんがニンマリしている、頭の黒いイノシシに食い散らされないようご注意あれ。
早々とコーヒーを作り出す人も。熱源は仲間達の自作の炭です。

柿の収穫は皆さん手慣れたもの、高枝鋏を利用して上手に取り込んでいく。竹籠があっという間に満杯になる。甘柿が丁度頃合いなのか、いい色つやだ。かじってみても結構甘くなっている。渋柿もあるのだが、さすがに手を伸ばす御仁はなかったようだ。本当は甘柿より渋柿を渋抜きした方が美味しいのだが・・・・・・・・・・・・面倒なのだろうな。
Mzさんが語っておられた。「今の日本人は食を海外に依存し、自分達で生産しようとしない。何れ食の欠乏が始まり、都会の人が金品を携えて農家回りを始めるぞ」、と。戦中戦後の風物詩が再現されることを願わないが、現状のままだと有り得ない話ではないだろう。
収穫班が柿のもぎりに出発しました。さて取れるかな。

名人がチャレンジ中です、さすがに早い。

ここの果樹園も先輩方の尽力で今日の姿がある。次の世代の為にも新たな苗木を植え続けなければならないだろう。我々には資金力は乏しいが、意気込みと行動力には不自由しない。できるだけ安価に苗木を仕入れ、時間をかけて育て上げたいものだ。果樹園と散策できる森とが調和を保って併存する姿が一番望ましい。時間はかかるだろうが、仲間達との協働で完成させたい理想像でもある。
こんな豊かな自然環境の下で、日々遊び惚けております。

2009年09月14日
栗拾いも柿もぎも
早生種の柿の実をねらいます。充分に食用可能です。

仕事人は道具の点検と整備に余念がありません。今日も刈りまくるぞ。

まずは例によって草刈り作業から開始しましょう。持ち寄った刈払機はメーカーも機種も様々、各位が好き勝手に好みで選択しております。やはり嗜好があるとみえ、どこの機種がいいの悪いの・・・・・評論家並みの機種判定談義が続きます。仲間内での人気機種はジェノアの製品、ハスクバーナーとの連携プレーが高く評価されているようです。但し、ホームセンターでは見かけませんね。林業者相手の専門店に出かける必要がありそうです。
各自好みが違いますもんで。メーカーも機種もバラバラです。

キーウィのツルに絡まれた八朔の救出作戦です。鎌が主役ですね。

この草刈り作業ですが、作業中にちょっとした事故が発生してしまいました。油断があったのでしょう。状況を聞いて見ますと、刃に絡んだツルをエンジンONのまま除去しようとしたようです。回転数が低かったのが救いだったようですが、初歩的なミスですね。マシーンに馴れて来た頃が一番危ないです。幸いにして軽傷で済んだから良かったものの、動脈切断など起こしますと、まさに命取りとなります。皆さんもご注意あれ。便利な道具は危険な道具でもあります。
看護師さんが応急処置を。天使に見えますね。

痛い目にあって始めてわかる基礎の大事さ。出来れば痛い目に遭わないで。

さてお楽しみの柿や栗ですが、そこそこ実っています。例によってイノシシが暴れ回っているようで、爪跡と思しき土壌の乱れが至る所にあります。栗の木や柿の木の下は多数です。夜間に徘徊して落下した木の実をパクついているのでしょう。彼らも命ある身、食べないと生き残れないです、人間様との激しい競争ですね。誰かが言ってました、栗も柿もいらんからイノシシ1匹欲しいなあ、と。どうやって捌くのか難題が待ち受けてますのにね。
柑橘類がやられています。犯人はテッポウムシ。

こいつがテッポウムシです、大きくなったのがゴマダラカミキリムシですね。

緑がかって未成熟みたいですが、無茶甘かったです。早生種の甘柿です。

雨上がりの炎天下です、水分を補給しながら休息しながらの作業となります。雑草の伸びが半端ではないので刈払機も一度では切れません。二度三度に分けて刈り取っていきます。鎌よりは効率的ですが。面積が広いと台数と人数が必要ですね。月に1~2度位の草刈りでは現状に追っつけないですね。完全に負けています。
しばしばの休息が必要不可欠ですね。

里山の名花ササユリが、来年の開花準備を始めていました。

地元の名峰金剛山です。そういえばしばらく登っていないなあ。

2009年07月06日
当てが外れたスモモ取り
みごとなスモモですね。微かには残っておりました。

残念ながら楽しみは帳消しとなってしまったが、作業は予定通り実施する。夏は雑草の繁茂期、刈っても刈ってもなんぼでも伸びてくる。刈払機をありったけ引っ張り出して果樹園全体に散らばっていく。危険性が高いので、かなりの間隔を空けて作業を継続する。蒸し風呂のようで相当に暑い。シャツは汗びっしょりとなるが構ってはおられない。時々燃料を補給しながらかなりの面積を刈り上げる。使い込んで行くほどに刈払機も調子が悪くなり、調整作業に入る者も出て来た。チップソーがやられやすく、交換するかグラインダーで削り込むか・・・・・・・・・我々の果樹園にはグラインダーがなく新品のチップソーと交換しか選択肢がないのだ。グリースも塗り込んでおこう。
刈払機を分解しています。刃の交換とグリースアップのようです。

例によって元気印のUさんのようですね。メカには堪能。

応援団が横からチャチャを入れてるようです。

暑さと疲れでへとへとのメンバーを気遣ってかNkさんがコーヒーを入れてくれました。山中でいただく熱々のコーヒーは格別のものがあります。インスタントであろうとチェーン店の某スター◇◇◇を上回るほどの飲み味でした。疲労回復には熱いコーヒーが最適かも知れませんね。
コーヒー準備中のNkさん、気分的には野点の感覚でしょうか。

先月の作業日には大量のスモモを気遣って支え棒を作ってあげました。それほど鈴なりのスモモだったのです。それが本日は大半が無くなって微かに残っているのみ、残念でたまりません。小生も持ち帰ってジャムを作ろうと張り切っておったのですが。下記画像をご覧下さい。鈴なりの枝が垂れ下がって地面に届きそうでした。

頑丈な支え棒で枝の垂れ下がり防止を
行ってました。
大量のスモモだったのです。

残った僅かなスモモを必死になって収穫します。無念さがにじみ出てるような後ろ姿ですね。来年は作業日の設定に人間の都合ではなく果樹の都合を優先するような配慮が望まれますね。リーダーのIkさん、確実な記録をよろしくお願いします。

高枝ハサミを持ち出して
僅かに残ったスモモをねらいます。

Uさんが鎌を振るっています。キーウイが八朔に巻き付いて太陽光線を妨害しているようです。どちらを残すかの選択で彼は八朔を選んだようでした。何、キーウイは又伸びてきますもんね。
八朔を選択し、キーウイを刈り取ります。無論、巻き付いてる部分だけです。

スモモは残念ながら上述のような内容で、僅かにご相伴にあずかったのみでした。とてもじゃないですがジャムは無理のようです、来年までのお預けでしょうかね。でも作業は予定通り進捗しましてかなり綺麗に仕上がりました。もっとも一週間もすれば又元の状態に戻っているかもしれませんね。限りない挑戦が続いていきます。
右上の藪は意図的に残したミョウガの大群落です。

2009年06月08日
ビワと梅との大収穫
梅もビワも大豊作のようですね。コンテナが次々と満杯に。

3名の仲間が刈払機を担いで草刈りへ、いずれ劣らぬ猛者達だ。何処の作業現場でもまず刈払機に手を伸ばす。草刈り大好き少年の集合体のようですね。毎度の事ながら夏場は雑草の伸びが半端ではない。全面的な草刈りをしても2週間もすれば元の木阿弥だ。作業の頻度を上げ、刈払機の台数を増やす必要がありそうだ。



梅もぎ班はブルーシートを引っさげて各梅の木に。根本周りにシートを敷き、木を揺すって落とそうとの魂胆のようだ。確かに高枝ハサミでは効率が悪すぎる。揺すっても落ちなければ棒で叩いてでも・・・・・・・・・木登りしながら棒で小枝を叩きまくる。梅の実が次々と落ちてくるのだが、頭に当たると結構痛い。どうも今年は豊作のようで、大粒の実が鈴なりだ。シートで拾った実を籠に集めるのだが、まさに一網打尽といった感じ。あっという間に竹籠が満杯となる。何度も運んで午前中だけでコンテナ3箱がいっぱいになった。
一度にたくさん集めたい・・・・・・・実は大変な欲張りなんだ。


今年のビワは糖度がのって超甘ですねん。

おいしそうでしょう。作業開始前に十数個食べてしまいました。

果樹園にはあいかわらず素敵な野草が咲き乱れております。何枚かを紹介して起きましょう。里山の名花ササユリも咲いていましたが、やや満開を過ぎたような気配でした。昨日のブログにきれいなササユリを掲示してますのでお好きな方はこちらをどうぞ。例によって名称も調べ切れてないのですが、野草の醸し出す素朴で清楚な美しさをご堪能下さい。
ミョウガの藪の中にさいていました。

これはわかりました、アザミですね。道筋に真っ盛りです。

いい色合いなんですが、何の花かは不明です。

本日は所用があったので昼で退散しました。作業が気がかりでしたが優秀なとんびのメンバー達、後顧の憂い無く下山できるのが一番有り難いことです。午後も草刈りに梅やビワの収穫にと大活躍してくれることでしょう。山里の田圃にも水がはいったようです。田植えもまもなくで棚田のそこかしこから蛙の鳴き声が響き出すのもまもなくでしょう。良い季節となりました。
シシ除けネットの回収も無事に終了したようです。


2009年05月08日
命輝く果樹園
打ち込んだ杭から新芽が発芽してます。まか不思議な現象。


キハダを伐倒してからそう日数が経過してなかったとは言え、強靱な生命力に感動します。人間もかくありたいと思うのですが、個体としてはか弱い存在ですよね。せめて、考える葦とかで他の方法論でカバーすることに致しましょうか。他にも命の輝きが垣間見られます。カメラもってこいよ、と大声をあげていたOkさんの現場に走ってみましょう。里山の名花ササユリの群生です。といっても数は少ないのですか。
ピンクは目印のリボンです、花ではないですよ。

来月、梅雨入りと同じ頃に咲き出します。薄いピンクの可憐な花です。

Nkさんの大好きなレモンにも花の準備が始まっていました。こちらもピンクの蕾です。まもなく開花・受粉・結実と進んでいきます。収穫は冬場ですね。レモンよりもユズのほうが使い勝手はいいようです。家人からはユズの持ち帰りをと頼まれますね。Nkさん宅は奥方のお酒用みたいですが、重宝されているようです。完全無農薬での栽培ですから、某国から薬漬けで長距離搬送されるものとはひと味違っております。かぶりつきでも大丈夫ですよ。
レモンの花です。なかなか見る機会が無いと思います。

昨秋から冬にかけて棚作りに励んでいたキ-ウィにも花が咲きました。雌花なんですが一緒に植えた雄花が開花していません。これでは受粉が叶わないので少々困っております。同時期に咲いてくれないと結実が困難ですよね。専門のKさんに事後処理を委ねる事と致しましょう。
キーウィの見事な花が咲き始めました。植栽後初の開花です。


最後にもうひとつ命の不思議さをご紹介しておきましょう。萌芽更新(ほうがこうしん)と呼ばれる現象で、多くの広葉樹で見られ、針葉樹では出来ない芸当です。伐倒した樹木から枝が伸びだし、親木の根の力を活用して急成長する現象です。クヌギの木などはこの性質を利用して炭や薪などを製造していました。下記の画像がクヌギです。伐倒してシイタケのほだ木に活用したのですが、切り株から新芽が出て枝が大きく伸びています。これで伐倒後2年ほどしか経過していません。成長の度合いが、苗木植えと全く異なっておりますね。
画像下部の大きな塊が切り株です。2本の新芽は10センチ位に成長してます。

2009年05月07日
柳の下のドジョウ
お好きな武器をもって散開していきます。激しい雑草です。

さっそく獲物を持って散開していく。最低でも5メートル以上の間隔を開けるのが絶対条件だ。刈払機での事故は結構多い。一番危ないのが転倒とキックバックそれに不用意な接近であろう。適度な休息を挟みながら刈り上げていく。さすがにエンジン付きだけあって鎌とは雲泥の差だ。安全面での配慮さえ出来ればこれに勝る道具はなかろう。教育研修の徹底と体調管理それに自己責任の原則を守りたい。幸いにしてとんびくらぶの仲間は優秀だ。細心の注意を払いながら慎重に作業を進めてくれる。事故が起これば本人のみでは済まない。場合によっては集団としての行動自体が停止されてしまうかもしれないのだ。
このマシーン、本日は不調のようです。キャブレーターでしょうか。

刈払機の熱血派です。燃料が無くなるまで止まりません。

忙中閑あり、作業の合間に楽しむことも忘れない。このゆとりが事故防止にも繋がっているのだろう。皆さんの動きを覗いてみよう。まずは長老のKさん、得意の摘果作業中だ。ビワがお好きとみえ、コレ私のと言いながらビワの実につばをつけ・・・・・・。続いてOkさんから呼び声、カメラもってこっちこいや。どうやら里山の名花ササユリを見つけたようだ。開花期は来月だがその準備はできてるようだ。雨に霞むササユリの、控えめな美しさには魅了されてしまう。開花期をねらった再度の訪問が必要なようだ。Nkさんはレモン大好き人間、薄いピンクの花が咲き出したレモンも見逃せない。二人三人と立ち寄って覗き込む。
Kさんは大好きなビワの摘果作業中です。夢見るのは収穫の場面 ?

ビワ君もしっかりと実をつけてくれています。摘果が大事ですね。

まだまだ残っていました、巨大なシイタケが。半分乾燥状態かな。

こちらも2回目のタケノコ掘りです。まだまだ出ています。

小雨模様の天候ではありましたが何とか作業は継続できました。本日は草刈りが大半、春から夏にかけてはこれが日課となります。刈払機の操作に関してはベテラン揃いですので進捗度は早いのですが、何せ面積が広い。一日や二日で終了できるようなヤワな作業ではありません。夏場にかけては頻繁に来訪しないといけないようです。梅取りやプラムの収穫などもありますし、折々に参集することにしましょうかな。
作業の合間の一休み、人間休息も大事ですよ。事故防止には一番です。

ヤマツツジがひっそりと咲き誇っていました。

2009年04月14日
筍掘りまくる
イノシシに負けていませんでした。立派な筍が続々と。


それにしても彼はどこでこんな知識を仕入れていたのだろうか。イノシシとお友達とも思えないのだが。家人が語っていた、あの方は多分、大学の農学部あたりで講義をしておられた教授だったのでは、と。一度確認しておかねばならないだろう。最も、笑っているだけで本当のことは話さないだろうけど。
獲物を見つけたぞ・・・・ハンターの目が光りますね。


昼間の休息には早速の焼きタケノコ、軽く炭火で焼いて醤油を付けただけなのだが結構においしいのである。一汗かいた作業の後、しかもロケーション抜群とあって、タケノコの味も代わってくるのかも知れない。山中での果樹園作業にはこうした余録があるので、皆さんいそいそとご出勤遊ばすのかな。タケノコが終われば次はサクランボ、その次は梅、その次はプラム・・・・・・収穫予定が控えている。当分、嬉しい悲鳴が続きそうだ。特に青梅の人気は高い。梅干しは無論のこと、梅ジュースというかサワーというのか真夏に打って付けの飲み物が作れるのだ。暑さ知らずで働ける特効薬みたいなものである。木登りして一個づつの収穫は面倒だけど、それ以上の喜びが待っていますね。
要所要所にぶら下がっているのが髪の毛の入ったビニール袋。

抜群の効能を発揮した模様ですね。

さてここで皆の衆の活躍ぶりを覗いて見ましょう。大半は既に掘っていましたが、まだまだ収穫をとハンターの動きは隙がないようです。主な道具はやはりスコップとクワ、地面に出るか出ないかのタケノコを素早く見つけ慎重に堀り上げます。頂部の向きから根の張り具合を想像してスコップを1~2度、上手な方はこれで収穫です。あまり上手でない方は何回もスコップをふるわねばなりません。斜面を壊さないように願いまっせ。


お土産が多いのはいいのですが、タケノコは重たいですね。車までよっこらせで運びます。今夜は奥方が腕をふるわれ様々なタケノコ料理が食卓を賑わすことでしょう。人間はお腹一杯になれれば幸せだとか・・・・・・・・某哲人が語っていましたっけ。ご家庭が円満であられることを切に願っております。
2009年03月21日
燃える男達
WBCではないがシシ達との攻防戦に情熱を傾け続ける男達がいる。戦果は連戦連敗のようだが屈するところを知らず、日々精進を重ねながら戦法を磨いている。敵は野戦の名手、そう簡単に対抗できるとも思えないのだが、そこはそれ、日本蜜蜂と同じで一寸の虫にも五分の魂と言うではないですか。黙ってムザムザとオオスズメバチの餌食になるのは耐えれないですよね。地上戦の原則はバリケード作りから、これは日清・日露は言うに及ばず現在も通用する戦法ではなかろうか。いかにしてバリケードを作るのか、画像でもって覗いて見ましょう。
画像下側がシシたちの通路と思しき場所です。高さ約1.5メートルの防御策。

資材の孟宗竹はふんだんに存在します。これを切り倒して防御策とするのです。高さは1.5メートル位、シシ達はパワフルですから完全防御は困難ですが、すんなりとは通行できないはずです。いやがって他へ迂回してくれれば少しでも防御となります。仲間達も燃えているのか楽しんでいるのか、次々に孟宗竹を伐倒していきます。ノコギリの切れ味もさえているようです。いいノコギリを購入したのかな。
急な傾斜地で次々と孟宗竹を切り出します。滑落しないように。

孟宗竹の整備にもなりますね。一石二鳥か。

翻ってKさん達はネット派のようです。こちらもしつこくネットを張り続けています。イノシシへの対抗意識が強烈なようです。Kさんからは、タケノコの前にもう一回ネット張りをやろうよ、と呼びかけのメールが流れていました。今年こそは、の執念がひしひしと伝わってきますね。ネットも強度はないのですが、シシにとってはいやな存在でしょう。心理作戦か。
柔よく剛を制す・・・・・・・・こんな箴言もありましたね。知恵者のKさんです。

名コンビは連携プレーでネットの補強を。
さてさて腹が減っては戦も出来ぬ・・・・・・・とはご先祖様達が残してくれた生活の知恵。体力勝負なのでガソリンの補給をしておきましょう。シイタケ工房の現地でもあります。自前の食料でちょっと一休みと致しましょうか。素材は新鮮なのがふんだんにあります。熱いコーヒーと炭火焼きのシイタケ・・・・・・・・・何とも言えない美味です。もっとも体調が優れなかった小生は、この焼きシイタケに当たったようなんですが。トホホ。
おつまみに最高ですね。熱いコーヒーとも良く似合います。
現場にはシシ達の食後の残骸が残されていました。やはり、夜な夜なとこの界隈を集団で闊歩しているようです。何せ夜行性なので対面する機会は無いのですが、出会ったら石を投げつけてやろうと思っています。
タケノコが食害されて皮だけが現場に残されています。
2009年03月18日
シイタケ工房繁盛記
毎年の事ながら、この時期はシイタケ工房の繁忙期である。シイタケの植菌作業が始まるのだ、というより少々遅い位か。準備の加減でいつも3月にはいってしまう。我々のは言わずと知れた原木栽培である。最近は手間暇を厭うのか菌床栽培が主流のようだ。だが食感と味は原木栽培の方が数段上のように思う。古代の中国では日本のシイタケは不老長寿の秘薬として珍重されたとか。不老長寿の効能はともかくとして、栄養価の高い茸には相違あるまい。鍋料理などには欠かせない食材である。発がん性を押さえる薬効もあるとかないとか・・・・・・・・の噂も存在するが。このシイタケの植菌にはそれなりの資材が必要である。早朝から軽トラで搬送してくれはったUさんとOkさんに感謝しつつ、重い資材を一輪車で運び上げる。山の中腹にある工房まで、数人係でロープを引っ張りやっとこさの運搬である。
立派なシイタケでしょう。某国産ではなくわが工房の作品です。

作業は原木に穴を開けることから始まります。既に切り倒して玉切りしていた原木(クヌギやコナラなど)に電動ドリルで等間隔に穴開けしていきます。直径9ミリ深さ20ミリ程度、菌の大きさに合わせた穴です。シイタケ植菌用の専用の刃が売られていますのでこれを使用します。穴あけした場所に菌をハンマーで打ち込んで行くだけ・・・・・・・・・作業は至って簡単です。皆さん、無我夢中で作業に取り組んでいますね。カブトムシを追っかける少年のようです。
まるで永遠の少年のようですね。全神経が植菌作業に集中・・・・・・ですか。

バリケード組と二手に分かれて作業中です。ただ黙々と・・・・・・・・・・・。

さてここで用具類を紹介しておきましょう。都会暮らしでシイタケ栽培などご縁のない方も多いでしょうし、場合によってはいずれ俺もと思案しておられる方もあるかも知れませんね。ご参考になれば幸いです。そうたいした資材が必要な訳ではありません。ただ山中での作業は発電機が入用なのがネックでしょうか。画像にはありませんがハンマーとコードも必要ですね。
発電機です。山中での作業には必携ですね。動力はガソリンエンジンです。
電動ドリルです。シイタケ植菌の専用刃を使用します。
シイタケ菌です。500個で1400円程度。

袋の中身です。菌を植え込んだコマがはいっています。
作業はいたって簡単ですね。上述したように開けた穴に上記画像のコマをハンマーで打ち込んでいくだけです。問題なのは作業よりも原木の保管場所でしょう。日陰で直射日光が入り込まない場所、出来れば少々湿っぽい場所が最適です。欲を言えば晴天が続いた日にはホースで水まきなど出来れば最高なんですが・・・・・・・・・・・・なかなかですね。菌にもよりますが一般的には春と秋の二回はシイタケが出来るようです。かようにシイタケは手軽に出来ますので興味をお持ちであればチャレンジしてみてください。ホームセンターなどで植菌済みの原木を売っていますよ。
我々のシイタケ工房です。数カ所あります。少々日光が入り込んでますが・・・・・。

2009年03月17日
ノックダウン
地元の名山である金剛山、最近はご無沙汰続きですね。

この金剛山から連なる岩湧山で今週は茅刈りの予定でした。彼の地の茅は全国コンテストで優勝するほどの品質、全国の文化財にとってなくてはならない資材のようです。仲間達と一緒に茅刈りを行い、少しでもお役に立てればと願っていたのですが、残念でたまりません。又1年後に備えたいと思っています。
2009年03月13日
シシ除けバリケード
孟宗竹の伐倒部隊です。張り切ってますね。シシへの対抗意識か。

本日はその対策事業・・・・・・・・ということで孟宗竹を切り出し、竹のバリケードを作ります。無論、彼等の方が一枚上手、竹のバリケードくらいでへこたれるよなヤワな存在ではありません。防御困難なのは承知の上ですが、無作為でやられっぱなしというのも頭に来ますしね。かって65年程の昔、B29の撃墜訓練に竹槍の練習をした民族があったそうですが、笑えぬ話です。Kさんが準備してくれはったネットも活用します。
本日初参加のTy氏も切り出し応援です。傾斜地に苦戦してますね。

孟宗竹の切り出しは刃の細かいノコギリを使用します。型枠大工さんが使うコンパネ用のノコギリが最適かなと思います。生の孟宗竹はおもしろいほど簡単に伐倒できますね。皆さん楽しみながら次々と伐倒していかれます。これを通路に沿って並べていくのです。トタン板程の強度はなく、あくまでも心理的な威嚇程度でしょうか。KさんとNgさんはネットをはっています。このネットも防鳥用で強度は皆目無し、あくまでも心理的な抵抗にすぎません。無いよりは増しかな。
シシへの防御能力はありませんが、嫌がらせかな。

下記の画像は我々の大事な果樹園です。この楽園をシシたちの運動場と化するのには耐えられませんね。一番いいのはトタン板で防御することですが、残念ながら広い面積の故、資金が続きません。




皆の衆の作業を支援するかのようにKさんは得意の腕をふるっておられます。本日のメニューは甘酒、疲れた体には格好のエネルギー源ですね。毎回、違ったメニューで皆を楽しませてくれはります。
甘酒の製造中です。山の中での一杯は最高ですよ。

バリケード作りと並行して、ロープの格納装置作りも行いました。伐倒用のロープがうまく格納できず苦労してましたので、帽子掛け用の資材を購入し、小屋の壁に打ち付けてロープ用としたものです。簡単な作業ですっきりと収納できました。仕事は用具の整理整頓が基本中の基本、そのためには収納に工夫が必要ですね。
ロープもすっきりと収納できました。

さてさて本日もしっかり働いた皆の衆にはお土産を準備しましたよ。完全無農薬栽培の八朔と取れたてのシイタケです。持ち帰ってご家族で夕食を楽しんでください。また、喜んで次回も送り出していただけますよ。家族の理解と笑顔の応援があってこそのボランティア活動、山のお土産が多少なりとも役に立ってくれれば幸いですね。
完熟した八朔です。ビタミンCの多用で風邪防止を。

立派なシイタケでしょう、菌から育てた自家製ですよ。

2009年02月03日
今日も山の中
いつものメンバーが次々に集まってきました。精鋭達の集合でしょうか。鉈や鋸やロープや剪定鋏など思い思いの武器を携えての山入りです。無論、大好きな弁当はリュックに忍ばせています。「怪我と弁当は自分持ち」・・・・・・・・・・これがボランティアの鉄則なんです。いわば自己責任の下での山遊びとでも申しましょうか。今日の予定は以下の4点です。1、巨木であるプラムの剪定 2,シシ除けのバリケード構築 3,八朔の全収穫 4,剪定枝の撤去 こうした作業を手分けしながら進めていきます。まずもってプラムの剪定ですが、当地のプラムは巨木になりすぎて収穫が出来にくい状態となっています。栄養分も全体に廻りかねているようなので、簡略化しようとの作戦です。こうした作業には木登り名人のIさんが最適でしょう。本人もその気で張り切っています。
木登り名人が登っての剪定作業です。幹がかなり大きめですね。

プラムもこんなに高いと収穫できないですね。

プラムの巨木が2本あります。剪定が悪いのと大きすぎるのとで実なりが少々悪くなってきました。そこで思い切って大胆な剪定作業を選択したのです。高枝鋏が届かない所は切断、樹勢が弱い枝は切断・・・・・・・・・・といった荒治療です。本来なら切断箇所には防腐剤等の塗布が必要なんですが、次回にアルミ箔でも貼り付けようかと思案しています。


本日初デビューのMzさん、剪定の名手です。黙々と作業中。
若手のホープIzさんも剪定作業と格闘中。だいぶ慣れてきたようです。

さてお次の作業はシシ除けのバリケード構築です。当地には昨年あたりからイノシシが出没し、かなりの被害を被っています。地元の方の話では20頭ぐらいの集団だとか。まもなく筍の季節、昨年はだいぶと食い尽くされました。防御を急がないと。竹を切り出し、イノシシが超えれない程度の高さに剪定枝や笹を積み上げていきます。効果は疑問ですが、黙ってのやられっぱなしには耐えれません。攻撃は最大の防御といければいいのですが、敵は夜行性。今頃は藪の中でお昼寝でしょう。
右上が我々のフィールド。敵は左の竹林から襲撃するようです。


昼食後は八朔の全部を収穫することに。物知り博士のKさんによれば、既に収穫適期は超過しているとか。収穫したあと1ヶ月程度は寝かさないと食べ頃とはならぬようです。本日は全部を収穫し、小屋の中で熟成させることにしました。
まずは大好きな腹ごしらえを。奥ではコーヒーが出来ています。
やはり収穫作業が一番楽しそうですね。
さあ収穫物を小屋に格納しましょうか。来月用ですね。 
すっきりしない天候でしたが、最後まで持ってくれました。雨さえ降らねば作業は継続できます。次回はシシ除けのバリケード作りの徹底とシイタケの植菌作業、それに苗木の植栽等がまっています。臨時の作業日も設定しないと間に合わないようですね。各位の畑もジャガイモの植え付けが始まってきます。冬場は暇とかいってましたが、どうやら農閑期は終了のようですね。こうした野遊びがお好きな方、是非仲間にお入り下さい。愉快なワル達が歓迎しますよ。
2009年01月21日
里山の学校生と
毎年恒例となった、「里山の学校」生徒さんに参加してもらっての協同活動である。朝からあいにくの天候だったが、とんびの仲間も学校の生徒もそろって活動開始。本日の仕事は以下の4点である。 1.梅の木の剪定作業 2.椎茸のほだ木作り 3.キーウイの棚作り 4.収穫作業・・・・・・・・・生徒さんもお見えなのでお土産が必要ですね。早速手分けして作業に入る。椎茸のほだ木はNsさんとOkさんの分担、Nsさんは女性ながらチェーンソーの名手。安心して任せておける。お二人の活動ぶりは下記の画像でご覧ください。
調子の悪いチェンーソーをうまく使いこなしていますね。

1メートル単位くらいで玉切りの目印を入れていきます。

ソーチェーンがへたりきってますが、かろうじて切れてます。
さて里山の学校の生徒さんには梅の剪定作業をやっていただきましょう。年末に大半は終了してますが、一部に徒長枝をあえて残した樹もあります。こちらで体験していただき、剪定枝を処分してもらいましょう。果樹園の基本作業です。剪定鋏と手鋸でうまい具合に剪定作業が進んでいきます。昨年と引き続き2回目の参加の方も。
 梅の木に上って余分な枝をカットしてもらいます。
梅の木に上って余分な枝をカットしてもらいます。

剪定枝がたくさん出てきましたね。処分も大変そう。
さてさてキーウィ班をのぞいてみましょう。棚がうまく出来上がっているかな。昨年植えたキーウィですが、うまく活着してくれたようなのでマイホームを造ってあげようとの魂胆です。数年先には収穫が可能でしょう。生食もいいですが、ジャムを作ったら美味ですよ。
いいコンビで仲良く共同作業を。お二人が資材を提供してくれました。

キーウィ棚の全景です。数年後にはここにキーウィがたっぷりと・・・・・・・。
棚を補強するために竹を切り出してくる者も。
人間にはお土産が必要ですよね。今日は里山の学校の生徒さんもお見えなので、土産の収穫もやっておきましょう。天候が怪しげなので、先に収穫作業を優先しましょう。本日のお土産は、八朔、キーウィ、レモン・・・・・・・・・・・の予定です。ビニール袋にたっぷりはいるように収穫しなくっちゃあ。
八朔の収穫風景です。皆さん目の色が変わっていますね。
武器を持って突撃開始の合図を待つ。

作業に収穫にと一暴れしたらおなかもすきました。昼食にしましょう。自家製のテーブルをセットし弁当を広げます。今日はNtさんが当地のシイタケをたっぷり入れた豚汁を作ってくれはりました。寒空の中での温かい汁はなんともありがたいものです。準備が大変だったろうと思いますが、皆の喜ぶ顔が楽しみだとか。ありがたいご配慮です。ホットコーヒーまで準備してありました。謝、謝、謝。
これが噂の豚汁。近場にはイノシシがたくさんいるようですが・・・・・・・・・・。

暖かい汁付きで皆さんしあわせそうです。冬場は大助かりですね。

茶色いジャケットがNtさん。黙々と豚汁を作っておられます。

2008年12月08日
12月7日定例会報告
数日前の嵐のような雨とは打って変わり、天気晴朗、風なし、ぽかぽか陽気・・・・・・ひょっとしたら春先ではないか。そんな感じの一日でした。絶好の作業日よりというか里山遊びの最適日というか、屋外に出ているだけで幸福になってくるようなお天気でしたね。都合で1時間ほど遅れての参加でしたが、早速に作業開始。本日の予定は、1渋柿周辺の除伐 2キーウィの棚の作成 3テーブルの設置 4果樹の収穫・・・・・・・の4点です。手分けしての分担作業で、既に進行中のキーウィ棚の作成に参加します。3年ほど前に植えた雌雄の樹が大きくなっており、ツルをはわせる棚が必要となったのです。4人がかりで一応の作業を完了し除伐の応援に。こちらは渋柿の周辺に存在する必要としない樹木を伐倒する作業です。
親子での果樹棚の作成?・・・・・・・そんな感じにも見えますね。



11月の定例会で渋柿を収穫しましたが、やはり日当たりが悪く充分な実りがありませんでした。来年の収穫を期待して周囲の太陽光線を妨害している樹木を伐倒します。光合成が出来にくい場所では成長も果実もあまり期待できないようですね。チェーンソーの最も得意とする作業分野のようです。
一番バッターはOkさん。目立て不良かな、白煙が出てますね。

早速の調整を。自作の専用目立て台です。素材はNkさん提供のミシンでした。

手鋸で頑張るメンバーも。チェーンソーよりは安全ですか。

作業も楽しいですが、もっと楽しいのが収穫でしょう。果樹園の大いなる魅力でもあります。本日収穫可能なのは、キーウィ・レモン・しいたけ・ゆず、それに食するのは来月ですが熟成用の八朔あたりでしょうか。手分けして収穫作業にはいります。籠と鋏を手にそれぞれお好みの樹に。
キーウィの収穫です。たくさん実っています。小生はジャム用に。

Nkさんはレモン好き。何でも奥様の飲酒用に必要だとか。愛妻家?。

数日前の雨で大量発生したようです。

玉手箱ならぬ果樹籠を背にゲストハウスへと帰りましょう。
すぐやる課制作の簡易脱着式テーブル。杭の上に天板を載せるだけ。
ポカポカ天気に恵まれて作業も収穫も順調にはかどりました。皆の衆も奥方へのたくさんのお土産を両手に満足そうです。果樹園の仕事はこれがあるのでやめられないですね。苗木を植えてから収穫まではかなりの年数を要しますが、それだけの価値はあるかと思います。本日のキーウィ棚の主人公もあと2~3年で実ってくれるのではと期待してます。昨年、小生が植えたカリンも7~8年後にはカリン酒が楽しめそうです。次の世代のためにもせっせと苗木を植栽しておきましょう。
2008年11月04日
11月2日定例会報告
果樹木が休眠期にはいりつつあります。かっこうの剪定の季節となりました。というわけで、本日は果樹園の選定作業にはいります。皆さん草刈りと思って段取りしておられましたが、雑草は前回で大半の処理ができ伸びも少なくなってきました。春先までは時折の草刈りで十分かと思います。果樹木も多種多様ですが、やはり優先するのは梅の木でしょう。梅は2月に花が咲きます。それまでに剪定を終えておき、余分な枝はカットして樹形を整えておかねばなりません。花の咲き具合によって6月の収穫も変わってきますね。大粒の立派な梅を収穫したいものです。
何だかんだと言っても、皆さん草刈りがお好きなようで。


梅の木は夏の間に相当大きくなったようです。今年の新枝がたくさん伸びています。よく言われることわざに「桜切るバカ、梅切らぬバカ」という言葉があります。梅の木は思い切って大胆に剪定するのがコツなようです。特に徒長枝と呼ばれる、天に向かって垂直に伸びた枝には実がつかぬようです。全面的にカットしていきます。
垂直に伸びた緑の枝が徒長枝です。全部カットします。
根元には剪定した小枝が次々と貯まっていきます。
剪定した小枝がたくさん貯まってきました。毎年正月あけには、里山の学校の受講生がフィールドに来られるので、彼らの作業用に残しておこうとの陰謀がまとまりつつあります。焼却できればいいのですが、ここは水気のない山間部、ちょっと危険ですね。作業をやっていたメンバーもいつしか収穫にはいっています。やはり楽しみの方が優先するようで。いくつかの光景を覗いてみましょう。
これはユズですね。成長の遅い樹で収穫まで20年ほどかかるとか。


渋柿君です。昨年近隣を伐採したので実り始めました。

リーダーのIkさんはさすがです。柿の木をせっせと剪定しています。柿も、来年大粒をねらおうと思えば選定作業と肥料やり、それに摘果作業が必要ですね。渋柿も渋抜きの手法がマスターできましたし、来年は甘い渋柿を堪能することと致しましょう。
柿の木の選定作業中です。太陽光線が十分にあたるように。
おやおや、こちらは違った楽しみのようで。イノシシにやられなかった(おこぼれかな)立派な椎茸があったそうです。さっそくユズを使って炭火焼きでお昼の食卓に。無論、こうした作業は料理自慢のKさんの独壇場ですね。


2008年09月16日
9月14日定例会報告
大変な情報が飛び込んできた。早朝からネット張りに励んでいる農家の方と遭遇し、挨拶がてら話していたら、イノシシが集団で夜な夜な徘徊しているとのこと。それも20頭くらいの大家族のようで、写真も撮られたとか。我々のフィールドは独立系の森で、いわば集落のあいまに森があると言う状況だ。山間部からシシがフィールドに至るには集落の間を抜けなければならない。そんなことはできないだろう、と安心しきっていたのだが。予感させるような現象はあった。タケノコが食いちぎられたり、椎茸が全滅していたり、獣道らしき踏み後があったり、囲っていた笹百合の開花地が荒らされていたり・・・・・・・・・・・・・・・。こうなってくると根本的な対策が必要だが、シシ相手に完全防御は難しい。
落下した栗の実も食いちぎられている。上手に食べているようだ。

農家の方と防御策を協議中 この一本道に柵を作る案も


おかげで、落下した栗を拾おうとの予定も変更だ。弾けた状態で木の上にあるものを取るしかないようだ。今日は収穫も少ないかな。イノシシも味を覚えたら定期的にやってくるだろう。先程の農家の方もサツマイモ畑が全滅だそうだ。
ぼやいていても始まらないので作業開始。あいかわらず雑草の山だ。

作業後の光景、ヤブがすっかり無くなっています。

作業の合間には栗の実が気になるのか、高枝鋏を持ち出して栗の木に向かう人も。秋の味覚のほうが作業より楽しいですよね。わかります、その心境は。

探しても落下したのは無いです
ね。シシたちが先に食べました
から。

結構、収穫もあったようです。籠が
半分ほど埋まりました。
下記の画像をご覧下さい。下部の中央から右上に向かって一本の筋らしきものが走っているのがおわかりでしょうか。踏み固められた通路のようですね。どうやら彼ら、イノシシたちのスーパーハイウエイのようです。夜な夜なこの道を通って田畑を荒らしに通っているのでしょうか。
イノシシ用の高速道路 ?

ともあれ今日も良いお天気です。難儀な話も持ち上がってきましたが天気晴朗、空は真っ青に澄み渡り、秋まっただ中といった印象ですね。ありがたいことです。コマーシャルではないですが、今日も元気だビールがうまい・・・・・・・・・とまいりましょうか。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン