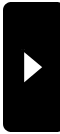2010年12月28日
農園も仕事納め
本日は暮れの28日、各種官庁は御用納めのようで22年も終わりつつあります。小生の農園も本日が仕事納め、年内作業は終了とし、しばしの冬休みにはいります。当地も霙混じりの真冬気象となって農園作業も厳しくなってきました。最後のチェックに見回りますと、例によって例の如く、シシ達が暴れ回った痕跡がくっきりと残っております。思えば22年はシシ達に蹂躙された1年でした。春先のジャガイモから始まってエンドウにタマネギ西瓜に南瓜にサツマイモにと1年を通して襲撃されっぱなし、苦心したネット戦法も農園全体を覆うには至らず完敗でした。
年内最後の大仕事、残ったミカンの枯れ木を処理します。

枝は手鋸で処理しましたが、幹はチェーンソーで。ラクチンですね。

一昨年位までは来訪はあったものの被害は殆ど無し、昨年は多少の被害程度、それが本年は年中通しての襲撃です。異常気象が原因かとも想像してますが、基本的には彼等のテリトリー内に食べるものが無くなってるのでしょう。本日などは酷いもので、ミカンの根っこを掘り起こしていました。ミミズがいるような土壌条件でもなく、根を食べるのかと不思議に思っています。現時点では谷間の農園には作物がなく、折角のお立ち寄りにも関わらず、食いはぐれての苛立ちなんでしょうか。周囲の農地も全てが耕作放棄、かろうじて耕しているのは小生の農園のみです、最後の期待を此処にかけて来訪したのかと思えば、哀れにすらなってきます。
伐倒したミカンの老木です。カミキリムシの痕跡がしっかりと。

根元付近にに産み付けられた卵が幹内で成長し食害します。

穴は食い破られた跡ですね。動脈が決壊したような感じです。

最後の仕事は先日レポートしましたミカンの後処理。残っていた幹類をチェーンソーで伐倒しました。2本の樹が枯れ死したのと先に伐採して幹だけ残っていたのが3本、都合5本分の除去です。枝や幹は積み上げておいて、正月のとんど焼きに使用する予定です。小生の田舎では「鬼火」と言ってましたが、樹木や竹で櫓を組み円錐形の形を作り上げます。中に稲ワラや柴或いは雑草類を詰めて燃えやすい条件を作ります。小正月の15日早朝に燃やし、餅を焼いて五穀豊穣や家内安全、健康長寿などを祈念する伝統行事です。当地では「とんど焼き」と呼称してますが、最近はあまり見かけなくなりました。
例によってシシ達は暴れ回っておりますね。

証拠の足跡が明瞭に残っています。

とんど焼きは子ども達が主役なんですが、指揮統率するガキ大将が不在、縦の子ども社会も崩壊してしまったようです。第一、野外で遊びまくる子どもの姿などまるで見ることが困難ですね。得意だった電子産業も韓国勢に追い越され、第二位と誇ったCDPも中国に抜かれ・・・・・凋落の我が国の姿は意外ととんど焼きと連動してるのかも知れませんね。遊び惚けた少年期を持たなかった子ども達は、大人になっても気力を振り絞って立ち向かう事は不能なんでしょうか。
いろいろありましたが、農園も静かに暮れていきます。

植栽できるか不明だけど、新年もよろしく。

年内最後の大仕事、残ったミカンの枯れ木を処理します。

枝は手鋸で処理しましたが、幹はチェーンソーで。ラクチンですね。

一昨年位までは来訪はあったものの被害は殆ど無し、昨年は多少の被害程度、それが本年は年中通しての襲撃です。異常気象が原因かとも想像してますが、基本的には彼等のテリトリー内に食べるものが無くなってるのでしょう。本日などは酷いもので、ミカンの根っこを掘り起こしていました。ミミズがいるような土壌条件でもなく、根を食べるのかと不思議に思っています。現時点では谷間の農園には作物がなく、折角のお立ち寄りにも関わらず、食いはぐれての苛立ちなんでしょうか。周囲の農地も全てが耕作放棄、かろうじて耕しているのは小生の農園のみです、最後の期待を此処にかけて来訪したのかと思えば、哀れにすらなってきます。
伐倒したミカンの老木です。カミキリムシの痕跡がしっかりと。

根元付近にに産み付けられた卵が幹内で成長し食害します。

穴は食い破られた跡ですね。動脈が決壊したような感じです。

最後の仕事は先日レポートしましたミカンの後処理。残っていた幹類をチェーンソーで伐倒しました。2本の樹が枯れ死したのと先に伐採して幹だけ残っていたのが3本、都合5本分の除去です。枝や幹は積み上げておいて、正月のとんど焼きに使用する予定です。小生の田舎では「鬼火」と言ってましたが、樹木や竹で櫓を組み円錐形の形を作り上げます。中に稲ワラや柴或いは雑草類を詰めて燃えやすい条件を作ります。小正月の15日早朝に燃やし、餅を焼いて五穀豊穣や家内安全、健康長寿などを祈念する伝統行事です。当地では「とんど焼き」と呼称してますが、最近はあまり見かけなくなりました。
例によってシシ達は暴れ回っておりますね。

証拠の足跡が明瞭に残っています。

とんど焼きは子ども達が主役なんですが、指揮統率するガキ大将が不在、縦の子ども社会も崩壊してしまったようです。第一、野外で遊びまくる子どもの姿などまるで見ることが困難ですね。得意だった電子産業も韓国勢に追い越され、第二位と誇ったCDPも中国に抜かれ・・・・・凋落の我が国の姿は意外ととんど焼きと連動してるのかも知れませんね。遊び惚けた少年期を持たなかった子ども達は、大人になっても気力を振り絞って立ち向かう事は不能なんでしょうか。
いろいろありましたが、農園も静かに暮れていきます。

植栽できるか不明だけど、新年もよろしく。

2010年12月23日
白菜の鉢巻き
寒くなってきましたね。当地も昼間はそうでもないのですが朝晩はめっきり冷え込みます。野菜達も冬場を好むのもありますが、大概は寒さの被害を受けてしまうようですね。ハウス栽培を行う方は心配不要でしょうが、我々のように完全露地派には一工夫が要求されます。資材も知恵もあまり無いのですが、師匠や周囲の仲間の衆を見習いながらボチボチと寒波対策を。本日は白菜の霜対策を少々、と言ってもたいしたことはなく紐で括るだけです。
師匠の白菜畑です、残った白菜は紐で括っていますね。

上記の画像は師匠の白菜畑ですが、残った白菜には紐が巻かれていますね。霜が降るのは自然現象で如何ともし難いですが、被害を最少限度に留めようとの工夫なんでしょう。こうしておきますと外部の葉は霜にやられても内部の巻いた部分は助かります。鍋用の白菜としては充分使用可能ということでしょう。不肖、一番弟子の小生も早速真似ることにしました。手間暇かからず白菜の保全が可能とあらば非常に助かります。結構賞味したりご近所にあげたりで残りは少ないですが対処しておきましょう。
小生も真似して稲ワラで括ってみました。これで霜防止となれば
大助かりです。費用も手間もかからず。

白菜が其処彼処に数個づつ残ってますので、飛び歩きながら。

米作りで発生した稲ワラを保管しております。これで軽く縛っておけばOKでしょう。それにしても農家の方々の創意工夫にはいつもながら感心します。里芋の地中保管などもそうでした。費用も手間暇もそうかけずに物事を解決していく、其処には智慧と創意工夫が満ちあふれているようですね。「自給自足の生活」・「独立自尊の生活」とは、かような暮らしぶりを言うんでしょう。肝に銘じておきたいと思います。
バックはソラマメです。少々大きくなりすぎで1メートル弱あります。
師匠には正月明けには収穫出来るぞ・・・・・・・と笑われてますが。

師匠の白菜畑です、残った白菜は紐で括っていますね。

上記の画像は師匠の白菜畑ですが、残った白菜には紐が巻かれていますね。霜が降るのは自然現象で如何ともし難いですが、被害を最少限度に留めようとの工夫なんでしょう。こうしておきますと外部の葉は霜にやられても内部の巻いた部分は助かります。鍋用の白菜としては充分使用可能ということでしょう。不肖、一番弟子の小生も早速真似ることにしました。手間暇かからず白菜の保全が可能とあらば非常に助かります。結構賞味したりご近所にあげたりで残りは少ないですが対処しておきましょう。
小生も真似して稲ワラで括ってみました。これで霜防止となれば
大助かりです。費用も手間もかからず。

白菜が其処彼処に数個づつ残ってますので、飛び歩きながら。

米作りで発生した稲ワラを保管しております。これで軽く縛っておけばOKでしょう。それにしても農家の方々の創意工夫にはいつもながら感心します。里芋の地中保管などもそうでした。費用も手間暇もそうかけずに物事を解決していく、其処には智慧と創意工夫が満ちあふれているようですね。「自給自足の生活」・「独立自尊の生活」とは、かような暮らしぶりを言うんでしょう。肝に銘じておきたいと思います。
バックはソラマメです。少々大きくなりすぎで1メートル弱あります。
師匠には正月明けには収穫出来るぞ・・・・・・・と笑われてますが。

2010年12月15日
エンドウの発育状況は
冬越し野菜の定番はやはりエンドウでしょうね。発芽したエンドウを如何に小さいままで冬越しさせるか、そこに百姓の知恵と腕が要求されます。成長させればエエやないの・・・・・・これが通常の発想だろうが、どっこいそうは問屋が卸さない。天敵とも思える霜や雪が待ち伏せている。50センチから1メートル位にもなると、たちまち霜にやられ茎が凍傷にかかって枯れてしまう可能性が高いのです。最適な状態は20センチ~30センチ程度で成長を止め、周囲を防寒グッズで覆ってやることだろう。活躍するのが稲ワラ或いは籾殻であろうか。いずれも米作りの副産物である。
小生のエンドウです。ようやく発芽して成長を始めたところでしょうか。

遠目で見るとこんな感じ。左がキヌサヤ右がスナックエンドウです。

他の冬越し野菜であるニンニクやタマネギ或いはラッキョウやソラマメはそれ程でもないのだが、エンドウは滅法寒さに弱いようだ。周囲をビニールで囲って保温してやる御仁も存在される。小生達が行っているのは、霜よけの籾殻蒔きと稲ワラによる若干の外気防止だろうか。画像でご理解頂けるでしょうが、もう少し大きくなれば稲ワラを立てて風を塞ぐようにしている。当地ではこの程度の対策で充分な冬越しが可能だ。春4月、花が咲き始めたらあとは収穫を待つのみ、エンドウの困難さはこの冬越しだけでしょうか。
こんなに大きくなったエンドウも。正月に否3月に賞味をと考えた、あの方です。

ツル有りとツル無しの品種がありますが、ツル有りの方が栽培が容易なようです。難点はネットや支え棒等が必要なこと。我々は支柱を立ててネットを張っております。畝は南北に作った方が日照条件が良く、実の付きも多いようですね。エンドウの収穫と前後してインゲンの種蒔きとなりますが、同じマメ科の故ネットの再利用が出来ないのが悩みですね。エンドウの後作は大抵がキュウリかニガウリとなりそうです。コレですと連作障害も出ず、ネットの再利用も可能で三方良しと皮算用しているのですが。
当地ではツル有り種をネット利用で栽培との手法が多いですね。

この冬は厳冬の予想とか。どの程度の寒波か不明ですが、野菜達にとっては辛い季節となりそうですね。ホウレンソウや白菜など寒波で甘さが増すような野菜もありますが、霜や雪に負ける物も多いですね。人間様と同様に、体は暖めておくのが成長には具合がよろしいようで。
小生の農具小屋です。壁面もネット利用でエンドウ栽培を。

小生のエンドウです。ようやく発芽して成長を始めたところでしょうか。

遠目で見るとこんな感じ。左がキヌサヤ右がスナックエンドウです。

他の冬越し野菜であるニンニクやタマネギ或いはラッキョウやソラマメはそれ程でもないのだが、エンドウは滅法寒さに弱いようだ。周囲をビニールで囲って保温してやる御仁も存在される。小生達が行っているのは、霜よけの籾殻蒔きと稲ワラによる若干の外気防止だろうか。画像でご理解頂けるでしょうが、もう少し大きくなれば稲ワラを立てて風を塞ぐようにしている。当地ではこの程度の対策で充分な冬越しが可能だ。春4月、花が咲き始めたらあとは収穫を待つのみ、エンドウの困難さはこの冬越しだけでしょうか。
こんなに大きくなったエンドウも。正月に否3月に賞味をと考えた、あの方です。

ツル有りとツル無しの品種がありますが、ツル有りの方が栽培が容易なようです。難点はネットや支え棒等が必要なこと。我々は支柱を立ててネットを張っております。畝は南北に作った方が日照条件が良く、実の付きも多いようですね。エンドウの収穫と前後してインゲンの種蒔きとなりますが、同じマメ科の故ネットの再利用が出来ないのが悩みですね。エンドウの後作は大抵がキュウリかニガウリとなりそうです。コレですと連作障害も出ず、ネットの再利用も可能で三方良しと皮算用しているのですが。
当地ではツル有り種をネット利用で栽培との手法が多いですね。

この冬は厳冬の予想とか。どの程度の寒波か不明ですが、野菜達にとっては辛い季節となりそうですね。ホウレンソウや白菜など寒波で甘さが増すような野菜もありますが、霜や雪に負ける物も多いですね。人間様と同様に、体は暖めておくのが成長には具合がよろしいようで。
小生の農具小屋です。壁面もネット利用でエンドウ栽培を。

2010年12月06日
襲撃予想はあるけれど
先生(師匠)も走る月とか言われる師走の季節となりました。春は長雨、夏は猛暑、さて冬場は暖冬かと思いきや酷寒の予想とか。どうした気象条件なのかよくわかりませんが、異常であることは事実のようです。農閑期にはいって農作業は一段楽したものの、のんびりと冬眠とも参りません。ましてや酷寒の予想であれば、冬越しするソラマメやエンドウ或いはニンニクやタマネギなどの手当も必要でしょう。さてどうしたものかと思案すれど、生来のズボラ稼業の身、簡単には行動が伴わないようです。そう言いながら谷間の農園に出向くと、シシ達の襲撃以来の放置状態、収穫出来るような作物もなく、緑少なき農園はどことなくうらぶれた状況で場末の趣ですね。コレでは百姓失格ですね。
しばらく放置していた谷間の農園、どことなくうらぶれた表情ですね。

早速気を取り直しまして、とりあえず耕耘作業をとミニ耕耘機を引っ張り出しました。耕作を続けている畑地なので耕土は柔らかく、大きなパワーの大型耕耘機は必要ありません。又、山の段々畑が続く傾斜地では利用も不可能に近いですね。抱えて運べるミニ耕耘機が最適かと思えます。但し、最初の開削はスコップと長柄の鍬が必要ですから、どうしても体力勝負となりがちですが。年数を経たマシーンながらすこぶる快調、パワーの少なさは如何ともし難いですが、10センチ~15センチ程度の耕耘作業は楽に可能ですね。本田宗一郎氏開発の4サイクルエンジンには脱帽します。
耕耘作業を行ったら、早速夜間の訪問者の足跡が。

耕耘機が不要な程の掘り返しですね、多分シシ達の仕業でしょう。

数日がかりで耕耘作業を片付けましたが、やはりシシ達は日夜来訪のようです。耕耘した畑にはくっきりと足跡が残っていました。夜間に来訪し食べ物を捜しているようですが、何も無いので苛立っているのでしょう。耕耘機が不必要なほど綺麗に耕してくれた畑もありました。耕耘作業のみで作物に手出ししないのであれば仲良く共存可能なんですが、優勝劣敗の原則は強烈で、一夜にして丸裸となりがちですね。数ヶ月かけて栽培した農産物が一晩で無くなる歯がゆさ、体験為されないと実感できないかと思います。生物多様性を守れ、自然との共生・・・・・・・そういったかけ声が何とも空しく響き渡りますね。
とりあえず棚田の上部から耕耘作業を進めてはおります。

中段位までは作業が進捗、これで訪問者がなければ万々歳ですが。

さて小生の谷間の農園、耕耘作業を行って耕作準備にはいったものの、植え付けていいものか悩んでおります。シシ達の襲撃は不可避、農園全体を電気柵かネットで覆えばある程度防御は可能かと思います。但しかなりの面積、半端な工事ではありません。しかもシシ達は防御出来たと仮定しても、敵はシシのみにあらず。アライグマやハクビシンといった小動物も存在します。彼等は電気柵やネットを突破するのは容易なようで、まさに打つ手無し。共同農園でもすぐ近くまでシシ達の登場があるようで、師匠は目撃されたとか。中山間地の農業は危機的な状況ですね。
最後の高揚でしょうか、紅葉の輝きも一段と冴え渡ります。

近くの雑木林も晩秋から初冬へと変わりつつあります。来秋までの見納めでしょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇ おことわり ◇◇◇◇◇◇◇◇
誠に有り難い事に、読者の方から「アクセスして更新がなければつまらない」とか「記事内容と登載日に若干の時差が」といったご叱声をいただいております。諸事情ありまして、原則として火木土の登載想定で再スタートを切りましたが、大阪南東部のローカルなニュースをお待ちの方が意外と多いようです。毎日登載が望ましいのでしょうが物理的要因もありますので、月~金の登載、土日の休載という想定で再再スタートとさせて頂きます。途中の息切れもあるかと思いますが、可能な限りは継続したいと願っています。今後ともよろしくお願いします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
しばらく放置していた谷間の農園、どことなくうらぶれた表情ですね。

早速気を取り直しまして、とりあえず耕耘作業をとミニ耕耘機を引っ張り出しました。耕作を続けている畑地なので耕土は柔らかく、大きなパワーの大型耕耘機は必要ありません。又、山の段々畑が続く傾斜地では利用も不可能に近いですね。抱えて運べるミニ耕耘機が最適かと思えます。但し、最初の開削はスコップと長柄の鍬が必要ですから、どうしても体力勝負となりがちですが。年数を経たマシーンながらすこぶる快調、パワーの少なさは如何ともし難いですが、10センチ~15センチ程度の耕耘作業は楽に可能ですね。本田宗一郎氏開発の4サイクルエンジンには脱帽します。
耕耘作業を行ったら、早速夜間の訪問者の足跡が。

耕耘機が不要な程の掘り返しですね、多分シシ達の仕業でしょう。

数日がかりで耕耘作業を片付けましたが、やはりシシ達は日夜来訪のようです。耕耘した畑にはくっきりと足跡が残っていました。夜間に来訪し食べ物を捜しているようですが、何も無いので苛立っているのでしょう。耕耘機が不必要なほど綺麗に耕してくれた畑もありました。耕耘作業のみで作物に手出ししないのであれば仲良く共存可能なんですが、優勝劣敗の原則は強烈で、一夜にして丸裸となりがちですね。数ヶ月かけて栽培した農産物が一晩で無くなる歯がゆさ、体験為されないと実感できないかと思います。生物多様性を守れ、自然との共生・・・・・・・そういったかけ声が何とも空しく響き渡りますね。
とりあえず棚田の上部から耕耘作業を進めてはおります。

中段位までは作業が進捗、これで訪問者がなければ万々歳ですが。

さて小生の谷間の農園、耕耘作業を行って耕作準備にはいったものの、植え付けていいものか悩んでおります。シシ達の襲撃は不可避、農園全体を電気柵かネットで覆えばある程度防御は可能かと思います。但しかなりの面積、半端な工事ではありません。しかもシシ達は防御出来たと仮定しても、敵はシシのみにあらず。アライグマやハクビシンといった小動物も存在します。彼等は電気柵やネットを突破するのは容易なようで、まさに打つ手無し。共同農園でもすぐ近くまでシシ達の登場があるようで、師匠は目撃されたとか。中山間地の農業は危機的な状況ですね。
最後の高揚でしょうか、紅葉の輝きも一段と冴え渡ります。

近くの雑木林も晩秋から初冬へと変わりつつあります。来秋までの見納めでしょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇ おことわり ◇◇◇◇◇◇◇◇
誠に有り難い事に、読者の方から「アクセスして更新がなければつまらない」とか「記事内容と登載日に若干の時差が」といったご叱声をいただいております。諸事情ありまして、原則として火木土の登載想定で再スタートを切りましたが、大阪南東部のローカルなニュースをお待ちの方が意外と多いようです。毎日登載が望ましいのでしょうが物理的要因もありますので、月~金の登載、土日の休載という想定で再再スタートとさせて頂きます。途中の息切れもあるかと思いますが、可能な限りは継続したいと願っています。今後ともよろしくお願いします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2010年11月28日
玉葱の定植を終えて
年内最後の大仕事、タマネギの定植が完了しました。血液サラサラの主役であるタマネギは可能な限り大量に栽培する必要性があります。本年の植え付けは、早生種が150本、中生種が250本、晩生種が200本、都合600本の植え付けです。全部が成長してくれれば万々歳なんですが、そう甘くは無いですよね。歩留まりが8割程度と想定してもそこそこの収量は確保出来そうです。ご近所にもお裾分けが可能なようで、とりあえず取らぬ狸の皮算用としておきましょう。
まずは暖をとって・・・・・・・そんな季節にはいってきましたね。

マイ農園のタマネギ畑です。今のところ順調な生育を。

タマネギは種蒔きから始める手法もありますが、小生達は専らネギ苗を購入するようにしております。市販苗は50本単位で300円から400円程度、11月の初旬から中旬頃が当地の植え付け時期となります。従って今頃は店頭からも消え去っているでしょうね。ネギ苗の便利さは一度始めると病みつき、種蒔き手法に比べて遙かに楽で安全です。栽培も手間暇かからず放置状態でも可能です。草抜きが面倒ならビニールマルチを使用すればOKですし、初めての栽培品目としては最適ではないでしょうか。
早生種の150本です。4月の収穫を目論んでいます。

同じく中生種の250本、こちらがメインでしょうか。

保存用の晩生種200本です。大器晩成型ですね。

ネギ苗を早生種、中生種、晩生種と3種類に区別してますのは収穫のタイミングによります。当地ではそれぞれ、4月、5月、6月の収穫となります。こうしますと畑が順番に空きますし、新鮮なタマネギが順序よく賞味出来ます。保管スペースも少なくて済みますね。有り難い事です。タマネギという野菜は重宝で何にでも使用可能、残すのは皮ぐらいで全てを使い切りますね。長期保存は難しいですが、日陰で風通しのいい場所に吊しておきますと結構もってくれます。こんな便利な野菜ですから、空きスペースがあれば是非に植え込んで下さい。食料は自作するのが一番の安全策ですよ。
大先輩のU氏は里芋掘りのようですね。赤い帽子がお似合いで。

仲間の衆も大半が完了された模様ですね。畑を覗いても寝転んだネギ苗が青々として光っています。根が定着しますと直立不動となるのですが、しばしの時間は必要なようです。寒さにも結構強く、稲ワラやビニール囲等は設置しなくとも大丈夫なようです。小生も仲間の衆もマルチをあまり好みませんので草抜きだけは必須作業となります。それも冬場はあまり必要性がなく、本当に手間知らずの野菜で助かります。エンドウはとっくに種蒔きしておりますので、これで年内作業は完了みたいなもの。春先のジャガイモまで冬眠と参りたいですね。
何方かが植え込まれたのでしょうか。道路脇で静かに咲き誇っていました。
多分、ノボタンかと思いますがどうでしょう。

少々バックして撮影しますと。樹木のようですね。

まずは暖をとって・・・・・・・そんな季節にはいってきましたね。

マイ農園のタマネギ畑です。今のところ順調な生育を。

タマネギは種蒔きから始める手法もありますが、小生達は専らネギ苗を購入するようにしております。市販苗は50本単位で300円から400円程度、11月の初旬から中旬頃が当地の植え付け時期となります。従って今頃は店頭からも消え去っているでしょうね。ネギ苗の便利さは一度始めると病みつき、種蒔き手法に比べて遙かに楽で安全です。栽培も手間暇かからず放置状態でも可能です。草抜きが面倒ならビニールマルチを使用すればOKですし、初めての栽培品目としては最適ではないでしょうか。
早生種の150本です。4月の収穫を目論んでいます。

同じく中生種の250本、こちらがメインでしょうか。

保存用の晩生種200本です。大器晩成型ですね。

ネギ苗を早生種、中生種、晩生種と3種類に区別してますのは収穫のタイミングによります。当地ではそれぞれ、4月、5月、6月の収穫となります。こうしますと畑が順番に空きますし、新鮮なタマネギが順序よく賞味出来ます。保管スペースも少なくて済みますね。有り難い事です。タマネギという野菜は重宝で何にでも使用可能、残すのは皮ぐらいで全てを使い切りますね。長期保存は難しいですが、日陰で風通しのいい場所に吊しておきますと結構もってくれます。こんな便利な野菜ですから、空きスペースがあれば是非に植え込んで下さい。食料は自作するのが一番の安全策ですよ。
大先輩のU氏は里芋掘りのようですね。赤い帽子がお似合いで。

仲間の衆も大半が完了された模様ですね。畑を覗いても寝転んだネギ苗が青々として光っています。根が定着しますと直立不動となるのですが、しばしの時間は必要なようです。寒さにも結構強く、稲ワラやビニール囲等は設置しなくとも大丈夫なようです。小生も仲間の衆もマルチをあまり好みませんので草抜きだけは必須作業となります。それも冬場はあまり必要性がなく、本当に手間知らずの野菜で助かります。エンドウはとっくに種蒔きしておりますので、これで年内作業は完了みたいなもの。春先のジャガイモまで冬眠と参りたいですね。
何方かが植え込まれたのでしょうか。道路脇で静かに咲き誇っていました。
多分、ノボタンかと思いますがどうでしょう。

少々バックして撮影しますと。樹木のようですね。

2010年11月21日
初冬期の豆談義
師走が近づいてきました。農作業も佳境を越え、ボチボチ農閑期へと突入です。エンドウとタマネギの手当が終了すれば年内作業はほぼ完了、心して正月を迎えようとの心境になります。仲間の衆も概ね予定通りの進捗で、エンドウもタマネギも植え付けが終わりつつあるようです。こうなってきますと先に植え込んだソラマメの成長談義が始まりますね。やれ伸びすぎだ、イヤ遅い、霜にやられるぞ、茎が折れちゃうぞ・・・・・・賑やかなことで雀の集団のようでもあります。「祭り太鼓は土の中」との師匠の言葉の如く、10月の秋祭りと前後して植え込んでますので結構大きくなってるんですね。
小生のソラマメです。仲間内では一番大きいようですね。

竹の横棒を張って倒壊防止に。根元は稲ワラで保護しています。

こうなってきますと豆の越冬対策が肝心になってきます。ソラマメは成長すれば1メートル~1.5メートルにもなります。茎の伸び具合が激しいので、冬越しを失敗すればいとも簡単に折れて立ち枯れとなってしまいますね。皆さん創意工夫がお得意のようで、知恵のせめぎ合い。可能であれば1本づつ支柱を添えればいいのでしょうが、現実には困難ですね。手間暇かけずに豆を丈夫に育てる、ここらが腕の見せ所でしょうか。
Kさんのソラマメ、溝の中に植え込んで順次土寄せの算段の模様。

Okさんのソラマメ、まだ小さいので稲ワラのみで大丈夫なようです。

まずは小生のソラマメ、植え付けが一番早かったようでかなりの大きさです。茎が曲がりかけてるので、竹の横棒を張り倒壊防止、根元には稲ワラを敷き詰めました。Kさんの豆は溝の中、成長に合わせて土寄せを行う算段のようですね。Okさんの豆は未だ小さく稲ワラでの支えのようです。霜や雪からの冷害防止には籾殻や稲ワラが結構役に立ちます。当地位の気象条件だとビニール囲までせずとも、籾殻・稲ワラで充分な保温対策となります。稲ワラを立てて囲えば一寸した温室並みの効果となりますね。
噂のエンドウですが、今回は正月に間に合うのかな。チト遅いようですね。

エンドウも同じように発芽して10センチ~20センチ程度で冬越しとなります。対応策はソラマメと同じで、保温効果を如何にして確保するか、この一点に尽きますでしょう。確実なのはビニールで囲ってあげること、但し規模が大きくなると少々困難ですね。我々のは小規模なので、これまた稲ワラで代用することが多いです。Kさんのようにビニールで簡易温室を作り、正月にエンドウの収穫をと目論む奇特な方もおられます。今年も花は咲いてましたが、正月に賞味したとの話は聞きそびれましたね。さて次なる正月も間近ですが、如何に。
全くの雲無し、正真正銘の快晴ですね。

マイ農園の周囲です。こんな光景に包まれますと、心身が急速充電されますね。

小生のソラマメです。仲間内では一番大きいようですね。

竹の横棒を張って倒壊防止に。根元は稲ワラで保護しています。

こうなってきますと豆の越冬対策が肝心になってきます。ソラマメは成長すれば1メートル~1.5メートルにもなります。茎の伸び具合が激しいので、冬越しを失敗すればいとも簡単に折れて立ち枯れとなってしまいますね。皆さん創意工夫がお得意のようで、知恵のせめぎ合い。可能であれば1本づつ支柱を添えればいいのでしょうが、現実には困難ですね。手間暇かけずに豆を丈夫に育てる、ここらが腕の見せ所でしょうか。
Kさんのソラマメ、溝の中に植え込んで順次土寄せの算段の模様。

Okさんのソラマメ、まだ小さいので稲ワラのみで大丈夫なようです。

まずは小生のソラマメ、植え付けが一番早かったようでかなりの大きさです。茎が曲がりかけてるので、竹の横棒を張り倒壊防止、根元には稲ワラを敷き詰めました。Kさんの豆は溝の中、成長に合わせて土寄せを行う算段のようですね。Okさんの豆は未だ小さく稲ワラでの支えのようです。霜や雪からの冷害防止には籾殻や稲ワラが結構役に立ちます。当地位の気象条件だとビニール囲までせずとも、籾殻・稲ワラで充分な保温対策となります。稲ワラを立てて囲えば一寸した温室並みの効果となりますね。
噂のエンドウですが、今回は正月に間に合うのかな。チト遅いようですね。

エンドウも同じように発芽して10センチ~20センチ程度で冬越しとなります。対応策はソラマメと同じで、保温効果を如何にして確保するか、この一点に尽きますでしょう。確実なのはビニールで囲ってあげること、但し規模が大きくなると少々困難ですね。我々のは小規模なので、これまた稲ワラで代用することが多いです。Kさんのようにビニールで簡易温室を作り、正月にエンドウの収穫をと目論む奇特な方もおられます。今年も花は咲いてましたが、正月に賞味したとの話は聞きそびれましたね。さて次なる正月も間近ですが、如何に。
全くの雲無し、正真正銘の快晴ですね。

マイ農園の周囲です。こんな光景に包まれますと、心身が急速充電されますね。

2010年11月09日
血流の応援隊
血液サラサラ・・・・・・・こんなコマーシャルを見聞された事がおありではなかろうか。火付け役は某国営放送局のテレビ番組だったようですが、多くのメディアで利用され流行語ともなったようです。人間の体内には血管が存在し、動脈や静脈と呼ばれるところを血液が流れて人間の体を動かしている事は小学生でも知っていますよね。この流れが止まったり滞ったりしますと、さあ大変、脳梗塞や心筋梗塞といった怖いレッテルが貼られてしまいますね。従って血液がサラサラ状態となるような料理を食べましょう・・・・・というのが上述流行語の本旨のようです。健康に不安がありますと各種のサプリメントに頼りがちですが、本来は食事や運動等で基礎体力を作り上げるのが王道でしょうね。
Kさんのタマネギ畑、極早生種です。定植時は横倒しでしたが、すっくと立ち
あがっていますね。強靱な生命力です。

料理につきましては、発言する資格がないのですが、要は多種類の食品をバランス良く摂取して必要とされる栄養素を毎日小刻みに体内に送り込むことでしょうね。外食主体となりますとそこらが心許なく、意識して補填する必要がありそうです。基本は山の神の手料理に尽きますでしょうね。出来うる事ならば、素材を自作して山の神に調理していただく、このパターンが理想像かと思います。少々手前味噌となりますが、小生の周囲にいらっしゃる仲間の衆は大半がこの形態です。無論、肉や魚類は困難ですが、代用できるような食品も多々存在しますよ。お坊さんに長寿が多いのも、ひょっとしたら肉や魚を遠ざけておられるからかも。
小生も早生種を150本購入してきました。取り急ぎ定植を。

タマネギの定植予定地です。準備だけは早くから。

毎度の事ですが話が横道に逸れますね、タマネギの定植を記述しようと思いましたのに。11月にはいりまして、タマネギの定植とエンドウの種蒔きシーズンとなりました。この両者を片付けますと、年内の大きな仕事は終了です。タマネギは大別しますと、早生種、中生種、晩生種、それに赤タマと4種類に分類されます。急ぎますのが早生種、早々に苗が無くなってしまいますね。Kさんは既に定植完了、小生も本日150本購入してきました。順調に成長すれば4月の収穫でしょうか。中生、晩生は6月~7月頃となります。このタマネギが、噂の血液サラサラの主役だそうですね。学問的な裏付けはわかりませんが、タマネギを大量に摂取してますと、血流がスムーズとなり介護保険のお世話になるようなことも避けられるとか。
本日のお花畑は、ラッキョウ畑です。結構きれいなもんでしょう。

これがラッキョウの花、お目にかかることは少ないかと思いますが。

そんな噂を信じまして、小生としては毎年大量に植え付けております。概ね400本~500本位でしょうか。無論、全部が発育する訳でもなく、収穫量は少々落ちますが、ご近所に差し上げる分も充分確保出来ます。毎日タマネギをせっせと食べまして血液サラサラと参りたいものです。血流が充分ですと体も温まり、冬場の作業も苦になりませんよね。冷え性の小生はタマネギの摂取が不十分なのかな。
自然観察としゃれこんで農園の周囲を散策してみましょう。ザクロにも似通って
いますがサザンカのようですね。

ご存じのカラスウリです。カラスが食べるのかな?

野生の渋柿です。干し柿に活用できるような代物ではございません。

Kさんのタマネギ畑、極早生種です。定植時は横倒しでしたが、すっくと立ち
あがっていますね。強靱な生命力です。

料理につきましては、発言する資格がないのですが、要は多種類の食品をバランス良く摂取して必要とされる栄養素を毎日小刻みに体内に送り込むことでしょうね。外食主体となりますとそこらが心許なく、意識して補填する必要がありそうです。基本は山の神の手料理に尽きますでしょうね。出来うる事ならば、素材を自作して山の神に調理していただく、このパターンが理想像かと思います。少々手前味噌となりますが、小生の周囲にいらっしゃる仲間の衆は大半がこの形態です。無論、肉や魚類は困難ですが、代用できるような食品も多々存在しますよ。お坊さんに長寿が多いのも、ひょっとしたら肉や魚を遠ざけておられるからかも。
小生も早生種を150本購入してきました。取り急ぎ定植を。

タマネギの定植予定地です。準備だけは早くから。

毎度の事ですが話が横道に逸れますね、タマネギの定植を記述しようと思いましたのに。11月にはいりまして、タマネギの定植とエンドウの種蒔きシーズンとなりました。この両者を片付けますと、年内の大きな仕事は終了です。タマネギは大別しますと、早生種、中生種、晩生種、それに赤タマと4種類に分類されます。急ぎますのが早生種、早々に苗が無くなってしまいますね。Kさんは既に定植完了、小生も本日150本購入してきました。順調に成長すれば4月の収穫でしょうか。中生、晩生は6月~7月頃となります。このタマネギが、噂の血液サラサラの主役だそうですね。学問的な裏付けはわかりませんが、タマネギを大量に摂取してますと、血流がスムーズとなり介護保険のお世話になるようなことも避けられるとか。
本日のお花畑は、ラッキョウ畑です。結構きれいなもんでしょう。

これがラッキョウの花、お目にかかることは少ないかと思いますが。

そんな噂を信じまして、小生としては毎年大量に植え付けております。概ね400本~500本位でしょうか。無論、全部が発育する訳でもなく、収穫量は少々落ちますが、ご近所に差し上げる分も充分確保出来ます。毎日タマネギをせっせと食べまして血液サラサラと参りたいものです。血流が充分ですと体も温まり、冬場の作業も苦になりませんよね。冷え性の小生はタマネギの摂取が不十分なのかな。
自然観察としゃれこんで農園の周囲を散策してみましょう。ザクロにも似通って
いますがサザンカのようですね。

ご存じのカラスウリです。カラスが食べるのかな?

野生の渋柿です。干し柿に活用できるような代物ではございません。

2010年10月31日
主役の交代期
当地は秋祭りのシーズンです。10月の第2土日が羽曳野や河内長野の、第3土日が富田林や千早赤阪村のといった案配で祭りが進み秋たけなわでしょうか。このシーズンになりますと冬野菜の或いは来春用の野菜類が緑の衣を現してきます。9月中旬から末頃が種蒔きでしたので、発芽してヨチヨテ歩きの幼児が出現したと言うところでしょうか。画像をご覧になられた方が早いかと思います。耕作者によって種類は異なれど、あちこちで似たような現象が生じておあります。反面、消えゆく作物もありまして主役の交代期といった感じでしょうか。小生の畑では秋ナスとピーマンが枯れ始めました。
猫じゃらしです。ホンマにネコの好物でしょうか。戯れてるのを見たことないのですが。

ナスもピーマンもよく頑張ってくれました。両者共に夏野菜です。7月~8月が最盛期で沢山の実を提供してくれました。一端、休息期があったものの、再び復活して秋ナス或いは秋ピーマン(?)として活躍してくれました。有り難い話で、僅か半ダース程の植え付けだったのに、ご近所に配っても余るほどの収穫でした。反面、過日のレポートのように谷間の農園に植え付けた物はシシやハクビシン或いはアライグマに襲撃されことごとく全滅でした。カラスやキジの来訪などかわいらしい限りです。
ピーマンです、7月からの頑張りで流石に萎れてきました。

ナスです。ピーマンよりは元気ですが、収穫は無理ですね。

さて幼児となった各種の野菜達、冬場の試練が待っています。まだ植えてないエンドウ(当地では11月種蒔き)等も含め、冷害への防衛策が要求されます。東北や北海道のように零下十何度といった極寒の地ではありませんが、山間部のため結構冷え込みますので疎かには出来ません。現地調達の資材ではダントツなのが稲ワラと籾殻でしょうか。両者共にこれから発生します。最も、コンバインを使った効率的農法では稲ワラが入手不可なので、必然的に天日干し農法が要求されますね。幼児の根元に籾殻を蒔き、周囲を稲ワラで囲うだけでかなりの効果があがります。お試しになってみて下さい。
期待を込めたニンニク、青森県に負けたくないのですが・・・・・・・・・・・・・

ソラマメ(お多福豆)です。小さい状態で冬を越したいのですが。

お馴染みのニンジン、これは放置でも大丈夫でしょう。

冬野菜の定番、大根です、寒さはお好み?

シュンギクです。これも冬型、寒さはお好みなようですね。

牛蒡、地下に潜ってるから大丈夫かな?

猫じゃらしです。ホンマにネコの好物でしょうか。戯れてるのを見たことないのですが。

ナスもピーマンもよく頑張ってくれました。両者共に夏野菜です。7月~8月が最盛期で沢山の実を提供してくれました。一端、休息期があったものの、再び復活して秋ナス或いは秋ピーマン(?)として活躍してくれました。有り難い話で、僅か半ダース程の植え付けだったのに、ご近所に配っても余るほどの収穫でした。反面、過日のレポートのように谷間の農園に植え付けた物はシシやハクビシン或いはアライグマに襲撃されことごとく全滅でした。カラスやキジの来訪などかわいらしい限りです。
ピーマンです、7月からの頑張りで流石に萎れてきました。

ナスです。ピーマンよりは元気ですが、収穫は無理ですね。

さて幼児となった各種の野菜達、冬場の試練が待っています。まだ植えてないエンドウ(当地では11月種蒔き)等も含め、冷害への防衛策が要求されます。東北や北海道のように零下十何度といった極寒の地ではありませんが、山間部のため結構冷え込みますので疎かには出来ません。現地調達の資材ではダントツなのが稲ワラと籾殻でしょうか。両者共にこれから発生します。最も、コンバインを使った効率的農法では稲ワラが入手不可なので、必然的に天日干し農法が要求されますね。幼児の根元に籾殻を蒔き、周囲を稲ワラで囲うだけでかなりの効果があがります。お試しになってみて下さい。
期待を込めたニンニク、青森県に負けたくないのですが・・・・・・・・・・・・・

ソラマメ(お多福豆)です。小さい状態で冬を越したいのですが。

お馴染みのニンジン、これは放置でも大丈夫でしょう。

冬野菜の定番、大根です、寒さはお好み?

シュンギクです。これも冬型、寒さはお好みなようですね。

牛蒡、地下に潜ってるから大丈夫かな?

2010年10月24日
とある日の畑風景
時刻は午前10時、昼前の快適な時間帯である。勉学に仕事にと成果が捗る時間帯なのに、のんびりと畑で豆むしり。どうやらKさん達のようだ。本日は自宅近辺のお友達も同行とみえ、仲良くの収穫作業。多分、本目はサツマイモ堀りであろう。街に住まれる方々にとっては、農作業と収穫は格好のレジャーなんでしょう。サツマイモ堀り等、幼児でなくとも興奮しますよね。お土産付きでしっかりと楽しんで下さい。小生の芋畑も本日で収穫完了です。分量が少ないので、ご近所にお裾分けしたらなんぼも残りませんでした。谷間の農園がシシ達の襲撃で全滅したのが痛かったですね。
本日は街のお友達を同行のようですね。サツマイモ掘りかな。

まずは三度豆の収穫から、今夜はビールで乾杯かな。

収穫は人間のみならず他の生物でも同じようです。食物連鎖とかの難しい話は別として、食べていかない事には生きてゆけないのが自然界の掟。彼等も必死のようです。それにしても実に巧妙にトラップを仕掛けておりますね。農作業の合間に顔に纏わり付いて難儀するのですが、怒る気にもなれません。生きていくのは大変な事、お互い様かな。一日にどの程度の収穫があるのか不明ですが、ひたすら待つしか無さそうです。忍耐と瞬発力、一瞬のチャンスに全てを掛けて待ち構えているのでしょう。ご苦労様です。
天高くクモ肥ゆる秋、但し収穫があればの話ですが。

獲物がかかったようですね。忍耐のしがいがあったようです。

残った僅かな芋を掘り出して見ました。ネズミにやられていますね。モグラが穴を掘り、その穴をネズミが再利用しています。芋畑の中に高速道路が作られているようで、芋の囓りっぷりも堂にいっています。サツマイモとジャガイモの被害が多いようです。ネズミも美味しい物を選択してるようで、被害は根菜中心ですが、大根やカブはあまり狙われませんね。それに葉物類もほとんど被害が無いようです。彼等なりの選択基準があるのでしょうね。
かなり太めの芋が多かったですね。小ぶりな奴が食べやすいのですが。

見事に囓られています。モグラ穴を利用したネズミの仕業です。

Uさんの畑を覗いて見ましょう。ちょっと珍しい豆が。ナタマメと言いまして、名前の通り鉈に似た豆です。形もサイズも鉈似でして、概ね30センチ前後はあります。ナタマメ茶などに利用するのと、福神漬けに活用されてるようですね。数年前に小生も栽培しましたが、活用方法が見つからず廃棄処分としました。Uさんがどのように活用するのか興味深いですね。
ナタマメです、個人的に使用するならナタマメ茶位でしょうか。

バナナ並ですね。30センチはありますよ。

本日は街のお友達を同行のようですね。サツマイモ掘りかな。

まずは三度豆の収穫から、今夜はビールで乾杯かな。

収穫は人間のみならず他の生物でも同じようです。食物連鎖とかの難しい話は別として、食べていかない事には生きてゆけないのが自然界の掟。彼等も必死のようです。それにしても実に巧妙にトラップを仕掛けておりますね。農作業の合間に顔に纏わり付いて難儀するのですが、怒る気にもなれません。生きていくのは大変な事、お互い様かな。一日にどの程度の収穫があるのか不明ですが、ひたすら待つしか無さそうです。忍耐と瞬発力、一瞬のチャンスに全てを掛けて待ち構えているのでしょう。ご苦労様です。
天高くクモ肥ゆる秋、但し収穫があればの話ですが。

獲物がかかったようですね。忍耐のしがいがあったようです。

残った僅かな芋を掘り出して見ました。ネズミにやられていますね。モグラが穴を掘り、その穴をネズミが再利用しています。芋畑の中に高速道路が作られているようで、芋の囓りっぷりも堂にいっています。サツマイモとジャガイモの被害が多いようです。ネズミも美味しい物を選択してるようで、被害は根菜中心ですが、大根やカブはあまり狙われませんね。それに葉物類もほとんど被害が無いようです。彼等なりの選択基準があるのでしょうね。
かなり太めの芋が多かったですね。小ぶりな奴が食べやすいのですが。

見事に囓られています。モグラ穴を利用したネズミの仕業です。

Uさんの畑を覗いて見ましょう。ちょっと珍しい豆が。ナタマメと言いまして、名前の通り鉈に似た豆です。形もサイズも鉈似でして、概ね30センチ前後はあります。ナタマメ茶などに利用するのと、福神漬けに活用されてるようですね。数年前に小生も栽培しましたが、活用方法が見つからず廃棄処分としました。Uさんがどのように活用するのか興味深いですね。
ナタマメです、個人的に使用するならナタマメ茶位でしょうか。

バナナ並ですね。30センチはありますよ。

2010年10月06日
シシ達の大暴れ
所用や天候不順があって数日間畑への訪問を怠っていた。谷間の農園を久方ぶりに訪ねると、アッと言ったまましばらく絶句。まるで耕耘機を走り回らせたような状況、いわずと知れたシシ達である。3年ほど前までは平和であった。カラスの襲来を防ぐ程度でのどかな農園生活だったのだ。一昨年あたりだろうか、年に数回害獣がはいったような形跡があった。昨年から今年にかけてはまるで常時の襲撃である。たいした農作物も作っていないのだが、ミミズが目的なのか湿気のあるような場所は荒らし放題だ。本日なんか全面的に耕耘機を掛けたような案配、耕作する意欲も失せてしまう。
まるで耕耘機で走り回ったような状況ですね。連中の痕跡です。

全部の畑が斯様な状況です。スタバとして使ったのでしょうか。

乾燥地帯でも状況は変わりません。何を作っても掘り返されます。

10段ほどの棚田跡を借用して畑地としてるのだが、その全部に連中の形跡が残されている。呆れたのは大事にしていた栗の木がへし折られ、カリンの苗木も1本が犠牲となっていた。本日は栗の収穫にと皮算用していたのだが、幹を折り枝を持ち出して栗の実は全て食い尽くしていた。全く1個の栗も残っていない。高いところでは2メート以上の位置にあったのだが、飛び上がったのだろうか。折れた幹の姿が無残である。此処まで育てるのに10年程もかかったのに。
収穫しようと思った栗は全て食い尽くされた後でした。

1本の栗の木は中途でへし折られていました。直径
10数センチあります。体当たりでもしたのでしょうか。

折られた小枝はかなり離れた畑に。栗で晩餐会でも開いた?

これだけ好き勝手に荒らされて防御の方法論がないのが辛い。同好の士も同じような状況とみえ、各位のブログ等を拝見してると苦闘されてる姿がひしひしと伝わってくる。場所によっては電気柵ですら無力と化しているようだ。山間の谷間とはいえ、そう奥深い森林地帯ではない。こんな場所にまでシシ達が出没するのは、彼等の居住区に食物が不足してるのだろうか。危険を冒してまで里に出向くのはそれなりの事情があってのことであろう。山間地の農が崩壊して、山と里との区別がつかなくなったのも大きな理由だろうか。金沢市などでは市内にシシ達が出没するとか、里の味を覚えてグルメと化した連中は、いまさら奥山へとは帰れないのかも知れませんね。
まるで耕耘機で走り回ったような状況ですね。連中の痕跡です。

全部の畑が斯様な状況です。スタバとして使ったのでしょうか。

乾燥地帯でも状況は変わりません。何を作っても掘り返されます。

10段ほどの棚田跡を借用して畑地としてるのだが、その全部に連中の形跡が残されている。呆れたのは大事にしていた栗の木がへし折られ、カリンの苗木も1本が犠牲となっていた。本日は栗の収穫にと皮算用していたのだが、幹を折り枝を持ち出して栗の実は全て食い尽くしていた。全く1個の栗も残っていない。高いところでは2メート以上の位置にあったのだが、飛び上がったのだろうか。折れた幹の姿が無残である。此処まで育てるのに10年程もかかったのに。
収穫しようと思った栗は全て食い尽くされた後でした。

1本の栗の木は中途でへし折られていました。直径
10数センチあります。体当たりでもしたのでしょうか。

折られた小枝はかなり離れた畑に。栗で晩餐会でも開いた?

これだけ好き勝手に荒らされて防御の方法論がないのが辛い。同好の士も同じような状況とみえ、各位のブログ等を拝見してると苦闘されてる姿がひしひしと伝わってくる。場所によっては電気柵ですら無力と化しているようだ。山間の谷間とはいえ、そう奥深い森林地帯ではない。こんな場所にまでシシ達が出没するのは、彼等の居住区に食物が不足してるのだろうか。危険を冒してまで里に出向くのはそれなりの事情があってのことであろう。山間地の農が崩壊して、山と里との区別がつかなくなったのも大きな理由だろうか。金沢市などでは市内にシシ達が出没するとか、里の味を覚えてグルメと化した連中は、いまさら奥山へとは帰れないのかも知れませんね。
2010年09月30日
雨後の晴れ間は土いじり
一雨来ましたが、通り過ぎていい天気。こんな日は畑に出かけて農作業・・・・・それが日課でもあります。無論、雨上がりですので畑は少々湿っぽく、畝作りや耕耘作業には向いていませんが。何、畑仕事で時間を持てあますような事は皆目ありません。それこそイヤと言うほど仕事はありますので。農作業の良さでもあり因果でもありましょうか。弥生期の米作りから始まって延々と農作業は続いてきました。農機具の発達で多少楽になったはいえ作業自体が減った訳ではありません。例によって例の如く、不要品の焼却から始めましょうかな。刈り取った雑草達です。
火付けの趣味はないけれど、この炎の色はたまりませんね。

狼煙の練習みたいですね。かってのハイテク通信法?

自治体の条例では野焼きを禁止事項としてる所が多いようですが、山間部で民家が無いような場所なら焼却したほうが合理的だし行政経費も少なくて済みます・・・・・・と勝手に解釈しましてGO。無論、焼却後の灰はカリ肥料として農作物に還元しております。サツマイモを放り込みたいところですが、燃焼時間が少なすぎるようです。それにしても今年は異常気象なんでしょうか。作物の実りは悪いし、彼岸花など少々しか咲かないし、柿などの果樹は実がないし、我が国のみならず世界的な現象みたいですね。ロシアでは旱魃、中国では大水害、南米では寒波とか。他の国でも似たような事例ではないでしょうか。
ようやく彼岸花も咲き始めましたが、例年に比し少なめですね。

渋柿もパラパラです。昨年はKさンと何度も収穫したのですが。

サツマイモ畑を掘ってみましたが、イモが少ないですね。ツルのみがやたらと繁茂しております。このツルですが、どこかの県ではイモより優遇されるとか。ツルを食べない人は県民にあらずとか、所変わればなんとやら。おもしろい現象です。戦時中の代用食としてのツルは、高齢者の方にしか通じない話でしょうね。当時は食糧難で、毎日の食事に事欠いたようですが、天変地異或いは政情不安若しくは外交上の圧力等で現在も可能性はあり得ますね。紙切れに過ぎないドル札を貯め込む事(世間では外貨準備高とか言うそうですね)を否定はしませんが、農産物の増産に使った方がお金は生きてくるかと思いますが。
サツマイモのツル、とある県では芋より重宝されるとか。

小生のナルトキントキも実の入りが悪いですね。

隣の畑を覗きますとKさんが畝立て中、中央部に深い溝を掘っておられます。何ぞや、と聞き込みますと有機肥料を埋め込むのだとか。種や苗の根っこに接触すると作物を殺してしまいます。相当深く埋め込む必要が有りそうですね。小生も同じように真似してやればいいのですが、頭では理解できても体がついて行かず、軟弱小僧の限界を痛感します。Uさんに頂いた白菜の苗、どうやら大半を枯らしてしまった模様。急いで補充用の苗を購入しておかないと、頂き物の苗が見えなかったらUさんに弁明の余地無し、二度とあげないとのご指摘があるかも。
Kさんの畝立てです。高畝で中央部の溝切りが特徴かな。

この深い溝に有機肥料を埋め込みます。

いかにも・・・・・・・・という感じの秋空ですね。

火付けの趣味はないけれど、この炎の色はたまりませんね。

狼煙の練習みたいですね。かってのハイテク通信法?

自治体の条例では野焼きを禁止事項としてる所が多いようですが、山間部で民家が無いような場所なら焼却したほうが合理的だし行政経費も少なくて済みます・・・・・・と勝手に解釈しましてGO。無論、焼却後の灰はカリ肥料として農作物に還元しております。サツマイモを放り込みたいところですが、燃焼時間が少なすぎるようです。それにしても今年は異常気象なんでしょうか。作物の実りは悪いし、彼岸花など少々しか咲かないし、柿などの果樹は実がないし、我が国のみならず世界的な現象みたいですね。ロシアでは旱魃、中国では大水害、南米では寒波とか。他の国でも似たような事例ではないでしょうか。
ようやく彼岸花も咲き始めましたが、例年に比し少なめですね。

渋柿もパラパラです。昨年はKさンと何度も収穫したのですが。

サツマイモ畑を掘ってみましたが、イモが少ないですね。ツルのみがやたらと繁茂しております。このツルですが、どこかの県ではイモより優遇されるとか。ツルを食べない人は県民にあらずとか、所変わればなんとやら。おもしろい現象です。戦時中の代用食としてのツルは、高齢者の方にしか通じない話でしょうね。当時は食糧難で、毎日の食事に事欠いたようですが、天変地異或いは政情不安若しくは外交上の圧力等で現在も可能性はあり得ますね。紙切れに過ぎないドル札を貯め込む事(世間では外貨準備高とか言うそうですね)を否定はしませんが、農産物の増産に使った方がお金は生きてくるかと思いますが。
サツマイモのツル、とある県では芋より重宝されるとか。

小生のナルトキントキも実の入りが悪いですね。

隣の畑を覗きますとKさんが畝立て中、中央部に深い溝を掘っておられます。何ぞや、と聞き込みますと有機肥料を埋め込むのだとか。種や苗の根っこに接触すると作物を殺してしまいます。相当深く埋め込む必要が有りそうですね。小生も同じように真似してやればいいのですが、頭では理解できても体がついて行かず、軟弱小僧の限界を痛感します。Uさんに頂いた白菜の苗、どうやら大半を枯らしてしまった模様。急いで補充用の苗を購入しておかないと、頂き物の苗が見えなかったらUさんに弁明の余地無し、二度とあげないとのご指摘があるかも。
Kさんの畝立てです。高畝で中央部の溝切りが特徴かな。

この深い溝に有機肥料を埋め込みます。

いかにも・・・・・・・・という感じの秋空ですね。

2010年09月25日
種は播き手を選ぶのか
23日秋分の日、未明から当地には雷鳴が轟いた、当然に激しい雨である。冬野菜の種蒔き期だけに雨は有り難いのだが激しすぎるのも考えもので、既に播いた種が流されるやも。自然相手の農は天候の変動にモロに影響を受けてしまう。小雨となるのを待って覗いて見たら、小さな出たばかりの苗が気丈にも頑張っていてくれた。与えられた命を全うせねば、そんな気配が感じられ心強く思える。自らの力で条件を変動できないだけに耐える力は相当なものが与えられているのだろう。数枚画像をアップしておきますが、元気よく育っている苗達です。
夏場に完熟して落下したゴーヤの種が発芽したものです。無論、この時期に
発芽しても成長してゴーヤとなる事は出来ません。

新たな種蒔きを始めてると、又もや師匠の登場。何だか小生の到着を見透かされてるようで、タイミングが良すぎるのに驚嘆させられてしまう。例によって百姓談義が始まるのだが、本日は面白い話が。何と種は播き手を選ぶのだとか。噂の主はホウレンソウなんだが、同じ畝に師匠と師匠の奥方とで種蒔きすると、師匠の播いた分は発芽はするが後日消滅し、奥方が播いた種は無事に生長して立派なホウレンソウとなって食卓を飾るのだとか。畝や肥料或いは石灰の散布量など諸条件は全く同一にもかかわらずである。小生もホウレンソウには苦労する。下記に画像をあげておきますが、発芽までは極めて順調です。その後が問題で黄色くなって成長が悪く、店頭に並ぶような緑豊かな立派なホウレンソウとは成りにくいのです。
噂のホウレンソウです。ここらまでは見事にいくのですが。

シュンギクは丈夫ですね。9割以上の発芽率でしょう。

私的には石灰の加減と肥料不足かと睨んでいるのですが。野菜作りの達人であるKさんに伺ってみると、ホウレンソウは強アルカリ性の土を好み窒素分とリン酸分とが充分に必要だとか。簡略化すれば、石灰を充分に散布して牛糞や鶏糞或いは油かすなどを投与せよとの話であろう。但し、アルカリ性が強すぎても駄目なようだ。石灰による酸性度の中和加減が難しいようですね。もうしばらく間を置いて二番手の種蒔きにはいるが、石灰の加減と元肥の投与を変更してみようかと思案しています。
ニンジンは発芽までの水管理が大変。今回はうまくいきました。

剽軽な師匠に笑わされる事が多いが、「種が蒔き手を選ぶ」との話は非常に面白かった。ホウレンソウには大分痛い目に遭わされてるようですね。最もサトイモなどは村の品評会で特等を取られる程の腕前、多少は向き不向きもあるのかもしれませんね。師匠の不向きは奥方がカバー、何とも夫婦の妙を感じさせるようで愉快な一時でした。それにしても、ベターハーフとはよくぞ表現したものですね。先人の体験的知恵でもありましょうか。
小生の苗床です。第一陣はほぼ蒔き終えました、次は第二陣。

夏場に完熟して落下したゴーヤの種が発芽したものです。無論、この時期に
発芽しても成長してゴーヤとなる事は出来ません。

新たな種蒔きを始めてると、又もや師匠の登場。何だか小生の到着を見透かされてるようで、タイミングが良すぎるのに驚嘆させられてしまう。例によって百姓談義が始まるのだが、本日は面白い話が。何と種は播き手を選ぶのだとか。噂の主はホウレンソウなんだが、同じ畝に師匠と師匠の奥方とで種蒔きすると、師匠の播いた分は発芽はするが後日消滅し、奥方が播いた種は無事に生長して立派なホウレンソウとなって食卓を飾るのだとか。畝や肥料或いは石灰の散布量など諸条件は全く同一にもかかわらずである。小生もホウレンソウには苦労する。下記に画像をあげておきますが、発芽までは極めて順調です。その後が問題で黄色くなって成長が悪く、店頭に並ぶような緑豊かな立派なホウレンソウとは成りにくいのです。
噂のホウレンソウです。ここらまでは見事にいくのですが。

シュンギクは丈夫ですね。9割以上の発芽率でしょう。

私的には石灰の加減と肥料不足かと睨んでいるのですが。野菜作りの達人であるKさんに伺ってみると、ホウレンソウは強アルカリ性の土を好み窒素分とリン酸分とが充分に必要だとか。簡略化すれば、石灰を充分に散布して牛糞や鶏糞或いは油かすなどを投与せよとの話であろう。但し、アルカリ性が強すぎても駄目なようだ。石灰による酸性度の中和加減が難しいようですね。もうしばらく間を置いて二番手の種蒔きにはいるが、石灰の加減と元肥の投与を変更してみようかと思案しています。
ニンジンは発芽までの水管理が大変。今回はうまくいきました。

剽軽な師匠に笑わされる事が多いが、「種が蒔き手を選ぶ」との話は非常に面白かった。ホウレンソウには大分痛い目に遭わされてるようですね。最もサトイモなどは村の品評会で特等を取られる程の腕前、多少は向き不向きもあるのかもしれませんね。師匠の不向きは奥方がカバー、何とも夫婦の妙を感じさせるようで愉快な一時でした。それにしても、ベターハーフとはよくぞ表現したものですね。先人の体験的知恵でもありましょうか。
小生の苗床です。第一陣はほぼ蒔き終えました、次は第二陣。

2010年09月22日
祭り太鼓は土の中
祭り囃子でしょうか、夕刻を回ると太鼓の音が響いて来ます。若い衆が練習に励んでいるようですね。西洋音楽と違って楽譜というものがなく、体で覚えて行くもののようです。祖父母達から親の世代へそして若衆の世代へと代々引き継がれてきた無形の財産なんでしょう。当地は来月の10日前後が秋祭り、豊作への感謝と収穫の喜びとの宴でもあります。丁度見計らったように米の刈り取りが始まります。今月末から来月初めが当地の収穫期、新米の到来ですね。さてこの季節になると来年の準備にはいるものも。「祭り太鼓は土の中」これは師匠の口癖なんですが、作業のタイミングを教える知恵でもあるようです。
遅れていた彼岸花がようやく咲き始めました。但し本数は少なめですね。

噂の主はソラマメ、当地ではお多福豆とも呼んでいます。収穫は来年の5月頃ですが、今自分の季節が種蒔きなんですね。祭り太鼓とは秋祭りの太鼓を指し、太鼓の音が聞こえるときには土の中になければならぬ、との教えです。簡単に表現しますと、当地の秋祭りの時にはソラマメの種蒔きは完了しておけ・・・・・・・ですね。師匠の教えに従い、本日ソラマメの種蒔きを行いました。最初の種は師匠からいただいた物、それを代々自家採取で種取りし栽培を続けています。F1種では無さそうで、出来不出来はありますが結構丈夫で良く実ってくれます。
自家採取のソラマメです。祭り太鼓の前に種蒔きを。

まずは仮配置して豆の間隔を確認します。

畝全体への配置がうまく出来ました。後は埋め込むだけです。

かねて畝には元肥を投じて下準備を施しておきましたが、本日は更に鶏糞を鋤込んでの種蒔きです。昨年は種蒔きの方法論を失敗し、一畝を全滅させましたが、本年はさようなドジは踏まぬようにしましょう。ソラマメはオハグロの部分から根がでてきます。従ってオハグロ部分を下にして地中に埋めるんですが、昨年はこれを逆だと勘違いし、ご丁寧にもオハグロ部分を地表に出して植え込んでました。全滅するはずです。
白菜の苗を頂戴しましたU氏、見事なタイミングで声がけして頂きました。

早速二ヶ所に分散して植え込みました。

無事に完了し、一休みしてますと先輩のU氏登場、「白菜の苗いらぬか、あげるぞ」との有り難いお言葉。実は種蒔きはしてるんですが発芽が思わしくなく、苗購入に走ろうかと思案中でした。グッドタイミングです。遠慮なく頂戴しまして植え込みました。およそ20本、当面は充分過ぎる分量です。あとは種蒔き分の発育をみながらボチボチ充足すれば万々歳ですね。有り難や、持つべきものは友と先輩。
何の花だと思われますか。実はニンジンなんです。

遅れていた彼岸花がようやく咲き始めました。但し本数は少なめですね。

噂の主はソラマメ、当地ではお多福豆とも呼んでいます。収穫は来年の5月頃ですが、今自分の季節が種蒔きなんですね。祭り太鼓とは秋祭りの太鼓を指し、太鼓の音が聞こえるときには土の中になければならぬ、との教えです。簡単に表現しますと、当地の秋祭りの時にはソラマメの種蒔きは完了しておけ・・・・・・・ですね。師匠の教えに従い、本日ソラマメの種蒔きを行いました。最初の種は師匠からいただいた物、それを代々自家採取で種取りし栽培を続けています。F1種では無さそうで、出来不出来はありますが結構丈夫で良く実ってくれます。
自家採取のソラマメです。祭り太鼓の前に種蒔きを。

まずは仮配置して豆の間隔を確認します。

畝全体への配置がうまく出来ました。後は埋め込むだけです。

かねて畝には元肥を投じて下準備を施しておきましたが、本日は更に鶏糞を鋤込んでの種蒔きです。昨年は種蒔きの方法論を失敗し、一畝を全滅させましたが、本年はさようなドジは踏まぬようにしましょう。ソラマメはオハグロの部分から根がでてきます。従ってオハグロ部分を下にして地中に埋めるんですが、昨年はこれを逆だと勘違いし、ご丁寧にもオハグロ部分を地表に出して植え込んでました。全滅するはずです。
白菜の苗を頂戴しましたU氏、見事なタイミングで声がけして頂きました。

早速二ヶ所に分散して植え込みました。

無事に完了し、一休みしてますと先輩のU氏登場、「白菜の苗いらぬか、あげるぞ」との有り難いお言葉。実は種蒔きはしてるんですが発芽が思わしくなく、苗購入に走ろうかと思案中でした。グッドタイミングです。遠慮なく頂戴しまして植え込みました。およそ20本、当面は充分過ぎる分量です。あとは種蒔き分の発育をみながらボチボチ充足すれば万々歳ですね。有り難や、持つべきものは友と先輩。
何の花だと思われますか。実はニンジンなんです。

2010年09月21日
実りと収奪の季節
当地では秋晴れの良いお天気が続いています。澄みきった青空を眺めていますと、まさに収穫の秋。隣は何をする人ぞ、ではありませんが仲間の畑を覗いて見ますと、芋掘りに真っ最中のようですね。立派なサツマイモが掘り出されています。品種はベニアズマとか。栽培技術がなかなか上手なようで、一株にびっしりとイモがぶら下がっています。この調子だと相当な収穫量となりそうですね。小生の芋畑も試掘をやってみる必要があります。これほど見事にイモがはいっているのかどうか。共同農園の方はなんとか期待できそうですが、谷間の農園は獣害でほぼ全滅状態、作物を作る意欲が失せてしまいます。休耕地や耕作放棄地が増加するはずですね。
立派な実がはいっていますね。品種はベニアズマとか。

1株掘ったらこれだけの収穫、プロ級の腕前ですな。

芋掘りに夢中なMt氏、奥方への良いお土産ですね。

さてその谷間の農園、案の定シシ達が遊び回っているようです。野菜類がないので目的はミミズなんでしょう。湿気のある」水路付近をメインに足跡が入り乱れ、彼方此方に掘り返した跡が。何所から襲来するのか不明なんですが、夜な夜なうろつき回って掘り返しているようです。サツマイモもサトイモも連中によって早い段階で全滅しました。今、イモが残っていたら彼等の絶好のエサ場と成ってた事でしょう。シシ達は雑草が生い茂って身を隠す場所を好むとか、せっせと草刈りして見通しの良い大平原にしてしまうのが、出来うる対抗策かも知れませんね。無力感に陥ってしまいがちではありますが。
昨夜も暴れまくったようですね、彼方此方に穴ぼこが。

湿気の多いところを掘り返しています。多分ミミズが目的でしょう。

連中の隠れ場を潰すのが最適でしょう。草刈りに集中して。

都合三ヶ所ほどの田畑を行き来しながら耕作してますが、米の方はおかげさまで無事に完熟期を迎えたようです。良い色合いになってきました。稲刈りまではもう少し。岸和田のだんじりは終了しましたが、当地は来月の10日頃が秋祭り。その直前あたりが稲刈りのシーズンでしょう。台風とシシ達の襲撃が最大の脅威であります、どうかこのまま無事に米作りを完了したいものです。刈り取った稲穂が田圃でハザ掛けされて天日干しされる光景は日本の原風景。失いたくない景観ですね。コンバインの利便性は評価しますが、米のおいしさは天日干しで決まるのではと固く信じております。
黄金色の稲穂となりました。間もなくの収穫と秋祭りを。

立派な実がはいっていますね。品種はベニアズマとか。

1株掘ったらこれだけの収穫、プロ級の腕前ですな。

芋掘りに夢中なMt氏、奥方への良いお土産ですね。

さてその谷間の農園、案の定シシ達が遊び回っているようです。野菜類がないので目的はミミズなんでしょう。湿気のある」水路付近をメインに足跡が入り乱れ、彼方此方に掘り返した跡が。何所から襲来するのか不明なんですが、夜な夜なうろつき回って掘り返しているようです。サツマイモもサトイモも連中によって早い段階で全滅しました。今、イモが残っていたら彼等の絶好のエサ場と成ってた事でしょう。シシ達は雑草が生い茂って身を隠す場所を好むとか、せっせと草刈りして見通しの良い大平原にしてしまうのが、出来うる対抗策かも知れませんね。無力感に陥ってしまいがちではありますが。
昨夜も暴れまくったようですね、彼方此方に穴ぼこが。

湿気の多いところを掘り返しています。多分ミミズが目的でしょう。

連中の隠れ場を潰すのが最適でしょう。草刈りに集中して。

都合三ヶ所ほどの田畑を行き来しながら耕作してますが、米の方はおかげさまで無事に完熟期を迎えたようです。良い色合いになってきました。稲刈りまではもう少し。岸和田のだんじりは終了しましたが、当地は来月の10日頃が秋祭り。その直前あたりが稲刈りのシーズンでしょう。台風とシシ達の襲撃が最大の脅威であります、どうかこのまま無事に米作りを完了したいものです。刈り取った稲穂が田圃でハザ掛けされて天日干しされる光景は日本の原風景。失いたくない景観ですね。コンバインの利便性は評価しますが、米のおいしさは天日干しで決まるのではと固く信じております。
黄金色の稲穂となりました。間もなくの収穫と秋祭りを。

2010年09月20日
秋の収穫は?
暑さ寒さも何とやらのお彼岸が、とうとうやってきましたね。季節の大きな節目で、これから次第に寒くなるというのが常識ですがさて如何でしょうか。猛暑の夏が過ぎましたが余韻たっぷり、日中は結構な暑さです。年末も正月明けも半袖シャツで・・・・・・・・それは無いかと信じたいのですが。さてお彼岸ともなりますとイモの季節、ご存じ中秋の名月にはススキとイモ(サトイモでしょう)をお供えするのが慣わし、サツマイモも収穫の時期に入ります。直売所を覗いてみたら両者ともに販売中でした。小生の芋畑はまだ試掘を行っていませんが、そこそこには出来ているのかな。無論、谷間の農園はシシやハクビシンの餌食で今年は全滅です。
コスモスが満開のようです。秋の到来ですね。

小ぶりですが既にサツマイモの販売が始まっています。

サトイモも同じですね。品種は当地ブランドの石川早生。

大先輩のU氏達は冬場は焼き芋屋に早変わりです。原材料のサツマイモ、沢山作っておられるようだが、シーズン中は賄えるのかな。芋屋も原料自前であればそこそこの収益が見込めるでしょう、だが仕入れての芋屋稼業ではへたしたら赤字経営。何せ、お客さんとの会話が楽しみみたいな案配で収益は二の次、小さな客人が100円玉握ってお出でになると大サービス、商売人とは思えぬような売人だから無理もないですか。畑のサツマイモも、こんな主なら大きく太って沢山実ってと義侠心を発揮するかも知れませんね。
小生のサツマイモ畑、雑草地帯と誤認しますね。

今年はよく取れます、嫁に食わすなの秋ナスです。

ピーマンも頑張ってくれてますね。

夏場は突然変異みたいな天候でしたね。果樹類などは総体に実りが悪く完熟も遅めのようです。野菜類も似たような状況ですが、小生の畑では不思議と茄子とピーマンが盛んに実っています。昨年は全くの不作でしたのに、まさか今年は表年という訳でもないでしょう。肥料や水管理がうまく機能したのかな。作付けのタイミングが悪くて、秋の収穫は上述の茄子とピーマンそれにサツマイモ位でしょうか。ちょっと寂しげですね。先般、種蒔きした大根やニンジン、カブ、ホウレンソウ等は早くて初冬の収穫でしょう。当分は畑からの手土産は期待せず、冬野菜の条件確保に精出す事と致しましょうかな。
相変わらずの火遊び男、若干でも資材があれば即の火付けですね。

シジミ蝶の一種でしょうか、ニラ畑で悠然と休んではります。

コスモスが満開のようです。秋の到来ですね。

小ぶりですが既にサツマイモの販売が始まっています。

サトイモも同じですね。品種は当地ブランドの石川早生。

大先輩のU氏達は冬場は焼き芋屋に早変わりです。原材料のサツマイモ、沢山作っておられるようだが、シーズン中は賄えるのかな。芋屋も原料自前であればそこそこの収益が見込めるでしょう、だが仕入れての芋屋稼業ではへたしたら赤字経営。何せ、お客さんとの会話が楽しみみたいな案配で収益は二の次、小さな客人が100円玉握ってお出でになると大サービス、商売人とは思えぬような売人だから無理もないですか。畑のサツマイモも、こんな主なら大きく太って沢山実ってと義侠心を発揮するかも知れませんね。
小生のサツマイモ畑、雑草地帯と誤認しますね。

今年はよく取れます、嫁に食わすなの秋ナスです。

ピーマンも頑張ってくれてますね。

夏場は突然変異みたいな天候でしたね。果樹類などは総体に実りが悪く完熟も遅めのようです。野菜類も似たような状況ですが、小生の畑では不思議と茄子とピーマンが盛んに実っています。昨年は全くの不作でしたのに、まさか今年は表年という訳でもないでしょう。肥料や水管理がうまく機能したのかな。作付けのタイミングが悪くて、秋の収穫は上述の茄子とピーマンそれにサツマイモ位でしょうか。ちょっと寂しげですね。先般、種蒔きした大根やニンジン、カブ、ホウレンソウ等は早くて初冬の収穫でしょう。当分は畑からの手土産は期待せず、冬野菜の条件確保に精出す事と致しましょうかな。
相変わらずの火遊び男、若干でも資材があれば即の火付けですね。

シジミ蝶の一種でしょうか、ニラ畑で悠然と休んではります。

2010年09月17日
夜半から待望の雨が
とうとう始まりました。夜からの雨で一晩降り続き、翌16日も午前中が雨、午後になって薄日が微かに差し込む天候です。待望の気象条件ですね。永らく晴天続きで種蒔きが出来ず困り果ててましたが、この雨で実行可能なようです。苗床の準備は出来てますので、手持ちの種と苗を少々買い込んで早速作業に着手しましょう。何時ものお店でブロッコリーとキャベツ苗を購入、種蒔きから実施するのが本筋ですが、分量が少ない品目は苗購入で間に合わせます。アブラナ科は蝶にやられやすく、幼苗はネットで囲ってやる必要があります。ヨトウムシにもご注意ですが、その対策は後日に回すということで。
冬野菜のポット苗がてんこ盛り、量が少なければ苗購入もありかも。

分量が多いと結構高価になります。種蒔きから始めましょう。

まずは種蒔きから。準備したのは大根、カブ、牛蒡、シュンギク、ホウレンソウ、ネギ、白菜、レタス、ニンジンの9品目。畝に筋切りをして長柄の鍬で少々固めます。その上に種蒔きして再度鍬で加圧し若干の土を被せます。その上に暑さ防止の為、刈り取った雑草を薄めにかぶせておきます。被せは、発芽が完了するまでの間5日~6日もあれば充分かと思います。この間は水分補給が必要なんですが、雨で土が水分を含んでますので多少は融通が利きそうです。毎度の事ながら種蒔きの最適条件を見いだすのが困難で、今回のようにラッキーな時は少ないですね。
小生の苗床、少量多品種でやっております。

雨上がりの種蒔きが一番ですね。数日曇天が続けば最高ですが。

続いて購入したブロッコリーとキャベツの苗、可愛らしい苗がポットで育っています。土ごと抜き出して50センチ間隔位で植え込みます。両者とも比較的大きくなるので株間の充分な確保が必要ですね。上述しましたが、モンシロチョウはアブラナ科に属する野菜類が大好物で沢山の卵を産み付けます。大きくなったのが青虫、この食害が激しいですね。ネットで遮断するのと最悪の場合は農薬使用で防除するしか無さそうです。無論、薬量やタイミングは慎重に計測します。最近の農薬は進化してまして、残留性が3日とか5日とか短期の物もあるようですね。
まだ固定してませんが、アブラナ科の野菜にはネットが必要です。

ブロッコリーが覗いています、青虫に食われるなよ。

半日掛かりで種蒔きと植栽とを終えました。画像でご覧頂いたらおわかりかと思いますが。結構小さな苗床です。商品化の予定もないので、少量多品種で栽培するように留意してます。いろんな物があったほうが楽しいですよね。それと時期をずらした種蒔きも収穫期が延びますので重宝します。まだスペースは余っていますので残余部分に何を植え込むか、楽しき悩みが続きそうです。
冬野菜のポット苗がてんこ盛り、量が少なければ苗購入もありかも。

分量が多いと結構高価になります。種蒔きから始めましょう。

まずは種蒔きから。準備したのは大根、カブ、牛蒡、シュンギク、ホウレンソウ、ネギ、白菜、レタス、ニンジンの9品目。畝に筋切りをして長柄の鍬で少々固めます。その上に種蒔きして再度鍬で加圧し若干の土を被せます。その上に暑さ防止の為、刈り取った雑草を薄めにかぶせておきます。被せは、発芽が完了するまでの間5日~6日もあれば充分かと思います。この間は水分補給が必要なんですが、雨で土が水分を含んでますので多少は融通が利きそうです。毎度の事ながら種蒔きの最適条件を見いだすのが困難で、今回のようにラッキーな時は少ないですね。
小生の苗床、少量多品種でやっております。

雨上がりの種蒔きが一番ですね。数日曇天が続けば最高ですが。

続いて購入したブロッコリーとキャベツの苗、可愛らしい苗がポットで育っています。土ごと抜き出して50センチ間隔位で植え込みます。両者とも比較的大きくなるので株間の充分な確保が必要ですね。上述しましたが、モンシロチョウはアブラナ科に属する野菜類が大好物で沢山の卵を産み付けます。大きくなったのが青虫、この食害が激しいですね。ネットで遮断するのと最悪の場合は農薬使用で防除するしか無さそうです。無論、薬量やタイミングは慎重に計測します。最近の農薬は進化してまして、残留性が3日とか5日とか短期の物もあるようですね。
まだ固定してませんが、アブラナ科の野菜にはネットが必要です。

ブロッコリーが覗いています、青虫に食われるなよ。

半日掛かりで種蒔きと植栽とを終えました。画像でご覧頂いたらおわかりかと思いますが。結構小さな苗床です。商品化の予定もないので、少量多品種で栽培するように留意してます。いろんな物があったほうが楽しいですよね。それと時期をずらした種蒔きも収穫期が延びますので重宝します。まだスペースは余っていますので残余部分に何を植え込むか、楽しき悩みが続きそうです。
2010年09月15日
エビス草の収穫
実りの秋は収穫の秋、各地で秋祭りが開催される所以でもある。当地でも例外ではない、米の収穫がメインとなるのだが、他の産物も収穫期を迎える。マイ農園で最初の収穫物となったのがエビス草、例のハブ茶の原料である。漢方の本場である中国では「決明子」と呼ばれて薬草として利用されているようだ。物の本によると効能は、疲労回復、便通、食欲増進、高血圧予防、眼精疲労の除去・・・・・・・といった内容であるとか。こうした効能を狙っている訳ではないのだが、自給自足を理想とする生活上の理念から、お茶の自給を目論んだものである。大先輩U氏の存在も大きい、全く知らなかったハブ茶なる物を紹介し種を分けてくれたのも彼だった。
エビス草、青いのと完熟したのとごちゃ混ぜですね。

小生のエビス草の畑。僅か1坪強位のスペースですが充分ですよ。

6月に三度目の種蒔きをしたエビス草が収穫期を迎えた。エビス草は一斉に完熟し収穫となるのではない。同じ種蒔きであっても茎によって或いは場所によって微妙に違って来る。全部が収穫適期となるのを待ってたら、早い実は弾け飛んでしまう。従って青い鞘でもお構いなしに収穫してしまう。袋の中で完熟していただくのだ。画像でご覧頂いた方がわかりやすいかと思う、青々しい鞘や完熟した焦げ茶の鞘など見事にバラバラ。この鞘の中に10個~20個程度の実が詰まっている。
採取したエビス草の鞘、隣の玄米袋が一杯となりました。

地域によってはこちらの茎や葉を利用する所も。

当地では鞘の中にあるエビス草の実を採取してハブ茶とするのだが、高知県の山間部では茎や葉を利用するとか。地域によって利用方法も種々なんですね。この夏は完全にハブ茶で過ごしました。農作業や山仕事或いは自宅にいる時など冷蔵庫で冷やしたハブ茶が最良のお友達、上述の効能の故か暑さ厳しき中でも体調不良とはなりませんでした。昨年収穫したエビス草の実がまだ沢山残っています。これから寒くなる季節、熱いハブ茶は馴染めるかどうか様子見の段階ですね。夏場のように欠かせぬアイテムとなって欲しいものです。
採取したエビス草の実です、種蒔きした残りですがお茶に出来ます。

エビス草は一坪強のスペースに植え込んでましたが、収穫してみたら玄米袋一杯となりました。これだけの分量がありますと私宅の1年分位は賄えそうです。無論、ハブ茶の存在で緑茶やコーヒー等が消え去る訳ではありませんが、お茶も自給自足が可能だと判明しただけでも大きな収穫です。味はさっぱり系のウーロン茶風、癖が無くて飲みやすく、飲用後におかしな余韻が残りません。一度お試しあれ。
ハブ茶のパイオニアであるU氏、彼の故郷では一般的な飲み物だった?

エビス草、青いのと完熟したのとごちゃ混ぜですね。

小生のエビス草の畑。僅か1坪強位のスペースですが充分ですよ。

6月に三度目の種蒔きをしたエビス草が収穫期を迎えた。エビス草は一斉に完熟し収穫となるのではない。同じ種蒔きであっても茎によって或いは場所によって微妙に違って来る。全部が収穫適期となるのを待ってたら、早い実は弾け飛んでしまう。従って青い鞘でもお構いなしに収穫してしまう。袋の中で完熟していただくのだ。画像でご覧頂いた方がわかりやすいかと思う、青々しい鞘や完熟した焦げ茶の鞘など見事にバラバラ。この鞘の中に10個~20個程度の実が詰まっている。
採取したエビス草の鞘、隣の玄米袋が一杯となりました。

地域によってはこちらの茎や葉を利用する所も。

当地では鞘の中にあるエビス草の実を採取してハブ茶とするのだが、高知県の山間部では茎や葉を利用するとか。地域によって利用方法も種々なんですね。この夏は完全にハブ茶で過ごしました。農作業や山仕事或いは自宅にいる時など冷蔵庫で冷やしたハブ茶が最良のお友達、上述の効能の故か暑さ厳しき中でも体調不良とはなりませんでした。昨年収穫したエビス草の実がまだ沢山残っています。これから寒くなる季節、熱いハブ茶は馴染めるかどうか様子見の段階ですね。夏場のように欠かせぬアイテムとなって欲しいものです。
採取したエビス草の実です、種蒔きした残りですがお茶に出来ます。

エビス草は一坪強のスペースに植え込んでましたが、収穫してみたら玄米袋一杯となりました。これだけの分量がありますと私宅の1年分位は賄えそうです。無論、ハブ茶の存在で緑茶やコーヒー等が消え去る訳ではありませんが、お茶も自給自足が可能だと判明しただけでも大きな収穫です。味はさっぱり系のウーロン茶風、癖が無くて飲みやすく、飲用後におかしな余韻が残りません。一度お試しあれ。
ハブ茶のパイオニアであるU氏、彼の故郷では一般的な飲み物だった?

2010年09月11日
仲間の衆の進捗度合いは
秋深し隣は何をする人ぞ・・・・・・・初秋ではありますが、気になるのは一緒。仲間の進捗度は気掛かりな事項でもあります。お互いにこそっと覗き見しながら己の作業を修正して・・・・そこらが仲間の良いところでしょう。本日は早朝から快晴、台風一過という訳でもないでしょうが、見事な程の青空です。当然、日差しはきつく大汗が玉のようで水分の補給が追っ付かない状態。いつまでこんな状況が続くのでしょうか。ぼやいても始まりません。作業を続行している仲間の姿を遠望してますと、遅れを取ってはならじ、と気分は焦ってきますね。
秋深し隣は何をする人ぞ・・・・・・・ワシャしらんぞ、といった風情でしょうか。

目が覚めるような青空が広がっています。当然に無性に暑い。

連日の猛暑で種蒔きは不可との判断をしてますが、見回ってますと工夫しながらの種蒔きが。やはりタイミングを逸するのが怖いようです。種蒔きは1週間ずれると発育と収穫に大きく響きます。そこらを勘案して暑さ除けを講じながらの種蒔きの実施となったみたいですね。微妙なのがニンジン、種蒔き後1週間程度は水やりが必要なんですが、この日照りの中で水を確保出来るのかな。ワラの使用で水分の蒸発は押さえられるものの、水そのものは必要です。畑の横を水路が走ってはいるものの、どうかすると水が止まってしまうのですね。上流域の方が流水量以上を消費しておられるようです。
種蒔きいつでもOKのスタンバイ状態ですね。

オッ、キャベツ苗の準備かな。早い。

どうやらこの中で生育させる考えのようです。アブラナ科は蝶の好物。

本日作業中の先輩方は、小生より一回り以上年配の方々です。にもかかわらずといえば失礼ですが、頑健で体力旺盛な事、とてもじゃないけど追っつけません。暑い、しんどい、もうアカン・・・・・・口では悲鳴をあげておられますが作業は中断しません。どこからエネルギーが湧いてくるのか、一番若い小生はへばりながら弱い頭で考えるのですが、要因が掴めないですね。焼夷弾の嵐の下をかいくぐってきた体験の強みでしょうか。この先輩方が亡くなられて我々の世代が高齢者となったら、途端に平均寿命が低下するかもしれませんね。
秋祭りの準備で忙しいのに、ジャガイモの植え付け準備みたいです。

画像ではわかりにくいですが、画面右上で別の仲間達が煙をあげています。
夏野菜の残骸を始末しているようですね。

各位の畑でもサツマイモが随分と成長しています。もうしばらくで収穫ですね。ハヤトウリもツルが伸びて来ました。米も稲穂が充実して随分と垂れ下がっております。雑草が多いので週明けには草抜きとの指令も出ております。収穫の秋、食欲の秋、祭りの秋・・・・・・美味しいものを沢山食べて秋祭りに興じましょうかな。
ニンジンのようですね。ワラで囲って水分蒸発を塞ぎます。

ハヤトウリも大きくなって来ました。1本のツルで100個位の収穫が。

秋深し隣は何をする人ぞ・・・・・・・ワシャしらんぞ、といった風情でしょうか。

目が覚めるような青空が広がっています。当然に無性に暑い。

連日の猛暑で種蒔きは不可との判断をしてますが、見回ってますと工夫しながらの種蒔きが。やはりタイミングを逸するのが怖いようです。種蒔きは1週間ずれると発育と収穫に大きく響きます。そこらを勘案して暑さ除けを講じながらの種蒔きの実施となったみたいですね。微妙なのがニンジン、種蒔き後1週間程度は水やりが必要なんですが、この日照りの中で水を確保出来るのかな。ワラの使用で水分の蒸発は押さえられるものの、水そのものは必要です。畑の横を水路が走ってはいるものの、どうかすると水が止まってしまうのですね。上流域の方が流水量以上を消費しておられるようです。
種蒔きいつでもOKのスタンバイ状態ですね。

オッ、キャベツ苗の準備かな。早い。

どうやらこの中で生育させる考えのようです。アブラナ科は蝶の好物。

本日作業中の先輩方は、小生より一回り以上年配の方々です。にもかかわらずといえば失礼ですが、頑健で体力旺盛な事、とてもじゃないけど追っつけません。暑い、しんどい、もうアカン・・・・・・口では悲鳴をあげておられますが作業は中断しません。どこからエネルギーが湧いてくるのか、一番若い小生はへばりながら弱い頭で考えるのですが、要因が掴めないですね。焼夷弾の嵐の下をかいくぐってきた体験の強みでしょうか。この先輩方が亡くなられて我々の世代が高齢者となったら、途端に平均寿命が低下するかもしれませんね。
秋祭りの準備で忙しいのに、ジャガイモの植え付け準備みたいです。

画像ではわかりにくいですが、画面右上で別の仲間達が煙をあげています。
夏野菜の残骸を始末しているようですね。

各位の畑でもサツマイモが随分と成長しています。もうしばらくで収穫ですね。ハヤトウリもツルが伸びて来ました。米も稲穂が充実して随分と垂れ下がっております。雑草が多いので週明けには草抜きとの指令も出ております。収穫の秋、食欲の秋、祭りの秋・・・・・・美味しいものを沢山食べて秋祭りに興じましょうかな。
ニンジンのようですね。ワラで囲って水分蒸発を塞ぎます。

ハヤトウリも大きくなって来ました。1本のツルで100個位の収穫が。

2010年09月10日
小さな土砂崩れ
土砂崩れ発生、別に台風9号の影響ではございません。台風は来たのか来ないのか解らぬ程度で終了しました。災害が無くて有り難いのですが、期待の雨も降らず種蒔きは又々延期となりそうです。何で土砂崩れやねん・・・・・そんなツッコミが来そうですが、水の浸食作用によるものです。「水は方円の器に随う」との箴言がありますが、全くもって自由奔放、自在に動き回ります。畑の地下を駆け巡ってるようで、間の悪いことに通路の中央部に陥没を作り土砂を洗い流してしまったようです。此処は師匠夫妻が奥のミカン畑に通われる通勤路、早急に修復が必要です。
大変です、通路の真ん中に陥没が。モグラの仕業?

かといって小生に土木工事の知識・経験があるわけでもなし、思案の末、とりあえずバラス(土木用の砂利)を購入して陥没を塞ごうとの発案に。搬送して陥没現場に運び込んでるところに運良く師匠が登場、相談してみるとまずは土嚢の作成だとか。師匠自ら倉庫から土嚢袋を持ち出し、土を詰め込んでの土嚢作りです。出来上がった土嚢を水路側に積み上げ、合間にバラスを詰め込みます。その上に雑草の生えた土を再度被せてカケヤで仕上げ・・・・・・・こんな手順で完成しました。振り返って考えると大半が師匠の作業で小生は見ていただけ、何ともはや。さすがに百姓(100の姓)の異名を取る師匠だけの事はあります。
現場を横から眺めると。水路の水が抉ったのか?

陥没の修復用に砂利を購入し搬送、間に合うか。

師匠の技が光っています。どんな分野でもOKのようで。

修復された通路、広く見えますが1メートルもありません。

それにしても農の実践とは、あらゆる分野の知識と経験が要求されますね。本職である農のプロは長年の経験と学びとで幅広い技術を習得しておられるようです。自然界が相手の商売、マニュアルはありませんし、あっても役に立たないでしょう。師匠の技に感嘆しつつ午後の作業は完了、種蒔きの予定でしたが当分は無理なようす。通路も修復できたし畝作りに邁進するとしますか。
大汗の中で畝作りを終えたKさんは、のんびりとナスの収穫のようです。秋ナスは美味、嫁に食わすかどうかは別として奥方への手土産ですかな。農作業を終えて汗をぬぐいながら土産を手に帰路につく、至福の一時でしょう。自宅では冷たいビールがお待ちかねでしょうから。
奥方への手土産かな、ナスの収穫が楽しそうなKさん。

優雅にみえますが、その前には汗だくの畝立て作業への取り組みが。

大変です、通路の真ん中に陥没が。モグラの仕業?

かといって小生に土木工事の知識・経験があるわけでもなし、思案の末、とりあえずバラス(土木用の砂利)を購入して陥没を塞ごうとの発案に。搬送して陥没現場に運び込んでるところに運良く師匠が登場、相談してみるとまずは土嚢の作成だとか。師匠自ら倉庫から土嚢袋を持ち出し、土を詰め込んでの土嚢作りです。出来上がった土嚢を水路側に積み上げ、合間にバラスを詰め込みます。その上に雑草の生えた土を再度被せてカケヤで仕上げ・・・・・・・こんな手順で完成しました。振り返って考えると大半が師匠の作業で小生は見ていただけ、何ともはや。さすがに百姓(100の姓)の異名を取る師匠だけの事はあります。
現場を横から眺めると。水路の水が抉ったのか?

陥没の修復用に砂利を購入し搬送、間に合うか。

師匠の技が光っています。どんな分野でもOKのようで。

修復された通路、広く見えますが1メートルもありません。

それにしても農の実践とは、あらゆる分野の知識と経験が要求されますね。本職である農のプロは長年の経験と学びとで幅広い技術を習得しておられるようです。自然界が相手の商売、マニュアルはありませんし、あっても役に立たないでしょう。師匠の技に感嘆しつつ午後の作業は完了、種蒔きの予定でしたが当分は無理なようす。通路も修復できたし畝作りに邁進するとしますか。
大汗の中で畝作りを終えたKさんは、のんびりとナスの収穫のようです。秋ナスは美味、嫁に食わすかどうかは別として奥方への手土産ですかな。農作業を終えて汗をぬぐいながら土産を手に帰路につく、至福の一時でしょう。自宅では冷たいビールがお待ちかねでしょうから。
奥方への手土産かな、ナスの収穫が楽しそうなKさん。

優雅にみえますが、その前には汗だくの畝立て作業への取り組みが。

2010年09月08日
台風接近
待ちに待った(?)台風がようやく接近の模様です。別に災害を望むわけではありませんが、こうも晴天続きだと作物が育ちませんし種蒔きも出来ません。既に冬野菜の種蒔きシーズンにはいってるんですが、早めに実施された方は種苗が死滅したようですね。タイミングを計ってましたが、台風到来なら間違いなく雨、この機会を逃す手はないと畑に出向いたら仲間の衆もご出勤。皆さん考えることは同じようです。予想進路は日本海(東海ではありませんぞ)側の海岸線に添った沖合を南から北へ進むようです。当地に最も接近するのは若狭の沖合あたり、ということは多分に大阪には雨台風でしょう。
台風接近の前触れ?・・・・・・・・何やら怪しげな雲行きが。

耕耘作業は終了してますので、とりあえず最優先のニンニクとラッキョウの畝作り。長柄の鍬とスコップで二ヶ所を作り上げていきます。仲間の衆が作るような高畝にはなかなか到達しません。耕耘機と培土機とのセットがあれば・・・・・・・・・・つい機械力を頼りますね。軟弱派の小生、力仕事は苦手でありまして、楽な手法をすぐに考えてしまいます。棚田の跡地の狭い畑、機械力の活用がうまく出来ないのが難点ですね。平地の1枚あたり100坪以上もあるような条件なら耕作は楽なんですが、そうした場所はなかなか借用出来ないですよね。我々のような棚田跡地の畑作ですと、ミニ耕耘機か小型耕耘機が最適な機械力です。当然、培土機の使用などは望み難いですね。
ニンニクを植え込んだら若干の球根が余ってしまいました。

植栽中のニンニク畑、球根の仮配置です。

半日がかりで、とにかくニンニクとラッキョウは植え込みました。これで予想どおり明日が雨となれば万々歳です。葉物類や大根、ニンジン、カブ、ブロッコリー等はもう少し待った方がと考えてます。ここ1週間ぐらいで、もう少々気温が下がるのではとの予感がありますし、畝立てがまだ完成出来てない事情もあります。なかなか気象条件にうまく併せる事が難しいのですが、暑さ寒さも彼岸までの諺は今も健在でしょう。
台風8号は韓国に大きな被害をもたらしたようですが、9号は日本海を素直に北上し、雨だけを当地にもたらしてくれることを願っています。
ラッキョウも植え込みましょう。三杯酢は夏の食欲増進剤。

台風接近の前触れ?・・・・・・・・何やら怪しげな雲行きが。

耕耘作業は終了してますので、とりあえず最優先のニンニクとラッキョウの畝作り。長柄の鍬とスコップで二ヶ所を作り上げていきます。仲間の衆が作るような高畝にはなかなか到達しません。耕耘機と培土機とのセットがあれば・・・・・・・・・・つい機械力を頼りますね。軟弱派の小生、力仕事は苦手でありまして、楽な手法をすぐに考えてしまいます。棚田の跡地の狭い畑、機械力の活用がうまく出来ないのが難点ですね。平地の1枚あたり100坪以上もあるような条件なら耕作は楽なんですが、そうした場所はなかなか借用出来ないですよね。我々のような棚田跡地の畑作ですと、ミニ耕耘機か小型耕耘機が最適な機械力です。当然、培土機の使用などは望み難いですね。
ニンニクを植え込んだら若干の球根が余ってしまいました。

植栽中のニンニク畑、球根の仮配置です。

半日がかりで、とにかくニンニクとラッキョウは植え込みました。これで予想どおり明日が雨となれば万々歳です。葉物類や大根、ニンジン、カブ、ブロッコリー等はもう少し待った方がと考えてます。ここ1週間ぐらいで、もう少々気温が下がるのではとの予感がありますし、畝立てがまだ完成出来てない事情もあります。なかなか気象条件にうまく併せる事が難しいのですが、暑さ寒さも彼岸までの諺は今も健在でしょう。
台風8号は韓国に大きな被害をもたらしたようですが、9号は日本海を素直に北上し、雨だけを当地にもたらしてくれることを願っています。
ラッキョウも植え込みましょう。三杯酢は夏の食欲増進剤。

2010年09月04日
秋ナスは嫁に食わすな
真っ青に澄みきった蒼空が何所までも広がっております。空を見上げる限り、確かに秋の気配。但しアキアカネ(アカトンボ)は久しく見かけず、灼熱の太陽は容赦なく照りつけます。それでも野菜達は体内時計によるものか、秋の装いを始めましたね。これからは秋ナスのシーズン、美味の代表とも言える農産物です。ナスに関しては、「秋ナスは嫁に食わすな」との箴言がありますね。解釈は分かれるようで、美味なる物は他人である嫁に食べさせないでおこう、体を冷やすナスは妊娠・出産を控えた嫁には適当でない食べ物・・・・・・・・・・・どちらを取るかはお好みですが、小生的には後者を採用したいですね。
露地栽培中のプロ農家の作品です。実に見事なナスですね。

青々とした葉っぱ達、茶色への変色や虫食いなど皆無ですね。

さてその秋ナスですが、当地でも露地栽培のナスが実り始めました。プロ農家の作品を画像でご紹介しますが見事すぎる位の出来映えです。恐らく長年の経験からくる栽培技術と適正な水管理(ナスは水分を大量に要求します)が執行されているのでしょう。と同時に忘れてならないのが、農薬の使用。何れの農産物も害獣や害虫に襲われ、無防備のままではまず立派な作物には育ってくれません。防除・防疫とも呼ばれる農薬使用が避けては通れない道なんですね。とりわけナスに関しては多くの農薬が使用されるようで、全く使用しないKさんのナス畑と画像を比較対象して頂いたら一目瞭然かと思います。小生の秋ナスも無農薬で栽培中ですが虫食いだらけですね。方法論は理由があって選択されるもの、一概に農薬悪玉論を振りかざす訳にもいきませんが、考えさせられる一面ですね。
プロ農家のナス畑です。お見事としか言いようがないですね。

無農薬栽培にこだわるKさんのナス畑。害虫と病気にやられてますね。

ただ言えることは、消費者の方が求められる「綺麗で形良くて安価で手軽に購入出来る品・・・・・・・・・・・」そうした条件をクリアーしようと思えば、農薬使用は避けては通れない道かと思われます。何処らへんでバランスを取るか、難しい判断が要求されそうですね。
冬野菜の準備もボチボチと進んではいますが、こう暑すぎると種蒔きしても種が即死となりかねないです。雨が欲しいのですが、科学が進んだ現代でもこればかりは願い通りにはならないようです。週間天気予報は快晴の日々が続いています、アア・・・・・・・。
無農薬栽培にこだわって、炎天下の作業を続けるKさん。本日も35度超。

季節は秋でも現場は夏?、夏の花ヒマワリが満開です。


露地栽培中のプロ農家の作品です。実に見事なナスですね。

青々とした葉っぱ達、茶色への変色や虫食いなど皆無ですね。

さてその秋ナスですが、当地でも露地栽培のナスが実り始めました。プロ農家の作品を画像でご紹介しますが見事すぎる位の出来映えです。恐らく長年の経験からくる栽培技術と適正な水管理(ナスは水分を大量に要求します)が執行されているのでしょう。と同時に忘れてならないのが、農薬の使用。何れの農産物も害獣や害虫に襲われ、無防備のままではまず立派な作物には育ってくれません。防除・防疫とも呼ばれる農薬使用が避けては通れない道なんですね。とりわけナスに関しては多くの農薬が使用されるようで、全く使用しないKさんのナス畑と画像を比較対象して頂いたら一目瞭然かと思います。小生の秋ナスも無農薬で栽培中ですが虫食いだらけですね。方法論は理由があって選択されるもの、一概に農薬悪玉論を振りかざす訳にもいきませんが、考えさせられる一面ですね。
プロ農家のナス畑です。お見事としか言いようがないですね。

無農薬栽培にこだわるKさんのナス畑。害虫と病気にやられてますね。

ただ言えることは、消費者の方が求められる「綺麗で形良くて安価で手軽に購入出来る品・・・・・・・・・・・」そうした条件をクリアーしようと思えば、農薬使用は避けては通れない道かと思われます。何処らへんでバランスを取るか、難しい判断が要求されそうですね。
冬野菜の準備もボチボチと進んではいますが、こう暑すぎると種蒔きしても種が即死となりかねないです。雨が欲しいのですが、科学が進んだ現代でもこればかりは願い通りにはならないようです。週間天気予報は快晴の日々が続いています、アア・・・・・・・。
無農薬栽培にこだわって、炎天下の作業を続けるKさん。本日も35度超。

季節は秋でも現場は夏?、夏の花ヒマワリが満開です。


2010年09月03日
牛蒡を引き抜いて
炎天下の毎日、相変わらず畑の手入れを続けています。夏野菜の残骸を撤去し、耕耘機を掛けて下ごしらえを行い冬野菜の植栽準備にはいる・・・・・・・・それが目的なんですが、作業時間よりも休息時間のほうが長かったりして。とりあえず格納庫から小型耕耘機を引っ張り出して作業を始めたのはよろしいが、彼方此方に栽培中の野菜が残っています。それらを避けながらの耕耘作業ですので、やりにくいのなんの。本日はど真ん中の牛蒡に邪魔されてしまいました。耕耘作業を継続しようと思えば抜くしかない、但し牛蒡は成長途上・・・・・・・困った。迷っても仕方がないので、結局は牛蒡を引き抜くことに。
全部と言っていいほど、中途で折れています。

ご存じの方も多いかと思いますが、牛蒡なんて素直に抜けませんよね。プロ農家は木製の箱内やビニール袋の中で栽培します。収穫期に入ったら箱や袋をあけて土を出し牛蒡を抜き取るのですね。これなら完全な姿で収穫出来ます。小生の牛蒡収穫はクワとスコップ、出来るだけ周囲を深く掘り下げてスコップをテコ代わりに使用するのですが、結果は画像のとおりです。概ね中間部で折れてしまいます。牛蒡の根元まで掘り下げるのが不能なんですね。かくして折れた牛蒡の山がてんこ盛り、無論賞味加減に変わりはないので持ち帰りますが、山の神の叱責が飛びそうですね。
小生の牛蒡畑・・・・・・・・耕耘作業の邪魔になりますねん。

折れた牛蒡がてんこ盛り。

ともあれ牛蒡が消えますと耕耘作業は捗ります。エンジンの音を響かせながらノンビリと作業してますと、Kさんもご出勤。暑いなあ・・・・・・・・・最初に飛び出す言葉は同じもの。連日35度以上の気温のようですから、農作業をやる方がどうかしてるのかも知れませんね。熱中症で倒れて畑で日干しになってるで、そんなニュースが流れないことを願っています。別に即身成仏の希望も願望も持ち合わせておりませんので。
有機石灰です。速効性はありませんが、種蒔きも同時でOKです。


耕耘作業がひととおり終了しますと、有機石灰や鶏糞等を使っての地拵え。いわゆる土作りですね。今日はとりあえず有機石灰を準備しました。畑に満遍なく散布していきます。アルカリ性なので酸性土壌の中和と元肥としての働きを持っています。原料は貝殻のようですね。散布後すぐに雨が降ってくれれば万々歳なんですが、天気予報は快晴続き、ため息だけが飛び出します。台風でもこないかと不謹慎な思いも出て来ますが、韓国の方へ行ったみたいですね。
耕耘作業が終了した場所には石灰散布を。

全部と言っていいほど、中途で折れています。

ご存じの方も多いかと思いますが、牛蒡なんて素直に抜けませんよね。プロ農家は木製の箱内やビニール袋の中で栽培します。収穫期に入ったら箱や袋をあけて土を出し牛蒡を抜き取るのですね。これなら完全な姿で収穫出来ます。小生の牛蒡収穫はクワとスコップ、出来るだけ周囲を深く掘り下げてスコップをテコ代わりに使用するのですが、結果は画像のとおりです。概ね中間部で折れてしまいます。牛蒡の根元まで掘り下げるのが不能なんですね。かくして折れた牛蒡の山がてんこ盛り、無論賞味加減に変わりはないので持ち帰りますが、山の神の叱責が飛びそうですね。
小生の牛蒡畑・・・・・・・・耕耘作業の邪魔になりますねん。

折れた牛蒡がてんこ盛り。

ともあれ牛蒡が消えますと耕耘作業は捗ります。エンジンの音を響かせながらノンビリと作業してますと、Kさんもご出勤。暑いなあ・・・・・・・・・最初に飛び出す言葉は同じもの。連日35度以上の気温のようですから、農作業をやる方がどうかしてるのかも知れませんね。熱中症で倒れて畑で日干しになってるで、そんなニュースが流れないことを願っています。別に即身成仏の希望も願望も持ち合わせておりませんので。
有機石灰です。速効性はありませんが、種蒔きも同時でOKです。


耕耘作業がひととおり終了しますと、有機石灰や鶏糞等を使っての地拵え。いわゆる土作りですね。今日はとりあえず有機石灰を準備しました。畑に満遍なく散布していきます。アルカリ性なので酸性土壌の中和と元肥としての働きを持っています。原料は貝殻のようですね。散布後すぐに雨が降ってくれれば万々歳なんですが、天気予報は快晴続き、ため息だけが飛び出します。台風でもこないかと不謹慎な思いも出て来ますが、韓国の方へ行ったみたいですね。
耕耘作業が終了した場所には石灰散布を。

2010年09月01日
耕耘機を引っ張り出して
気温は多分35度前後はあるようです。畑に立ってるだけで汗はだらだら、時としてめまいが出るほどの環境ですね。何を好きこのんで田畑に・・・・・・・そんな自問自答を繰り返しつつも、農作業は季節との勝負。待ったなしの勝負が多いものですから、麦わら帽子をかぶっての戦闘開始です。本日の予定は夏野菜を焼却した残骸を撤去し、耕耘機をかけること。まずもって共同の野小屋(ゲストハウスと称しています)からマイ畑まで搬送しなければなりません。高い位置にある細めの農道をローギヤでゆっくりと自走します。およそ10分以上もかかって小生の畑に到着。これから数日は彼の一人舞台でしょう。
巻き付いた雑草を除去する手間はありますが、さすがに速い。

シオカラトンボが様子見にやってきました。縄張り確保でしょうか。

夏野菜の残骸は大半撤去しましたが、土は固く引き締まり、一~二度耕耘機を掛けたぐらいでは柔らかくなりそうにもありません。土作りが出来ていない証拠ですね。土の中に有機物が足りないのでしょう。有機物が多くて微生物が活躍してますと、柔らかくてふんわりした土となります。聞き及ぶ中国の農地よりは遙かにましですが、固いのには相違ありません。中国では人糞と農薬の多用で土は死に体であるとか、土地が自分の物でないこと、収奪と貧困の連鎖・・・・・・・そんな状況で将来に希望が持てないのでしょね。人様の事をあまりとやかくも言えませんが。
耕耘前の畑です。極めて硬い土が一目瞭然ですね。

耕耘機をサッと走らせると、一変に柔らかくなります。

さてマイ畑ですが、耕耘機を動かして少しづつ土壌を柔らかくしていきます。画像で紹介しておきますが、耕耘前と耕耘後とは土の状況がまるで違っていますね。これで有機石灰と鶏糞とを購入して、土の中に鋤込んでいけば下準備はOKですか。ようやく種蒔きや植栽の目処が見えてきたようです。明日にでも石灰と鶏糞とを搬送しておきましょう。冬野菜の植え付けシーズンとなってるのですが、これだけ晴天続きで気温が高いと、播いた種もミイラと化するかも知れませんね。気象条件を左右することは出来ませんが、何らかの形で太陽光線を遮断しないと。寒冷紗などを使用して日陰を作って種蒔きしましょうかな。それでもニンジンなどには厳し過ぎる環境ですね。
仲間の衆は既に石灰を散布して中和の作業に、段取り早し。

同好の士のブログなどをよく拝見してますが、皆さん苦労されてますね。世界的な異常気象で、個人では対応不能な状況かと思いますが、それでも植え付けをやらざるを得ないですね。いっそのこと、南国の野菜を栽培した方が環境に適応できるかもしれませんね。大阪でもマンゴーやパパイヤ、パイナップルなどがそこら中の農地でてんこ盛りだったりして。
9月になってもまだまだ真夏の気候ですね。

巻き付いた雑草を除去する手間はありますが、さすがに速い。

シオカラトンボが様子見にやってきました。縄張り確保でしょうか。

夏野菜の残骸は大半撤去しましたが、土は固く引き締まり、一~二度耕耘機を掛けたぐらいでは柔らかくなりそうにもありません。土作りが出来ていない証拠ですね。土の中に有機物が足りないのでしょう。有機物が多くて微生物が活躍してますと、柔らかくてふんわりした土となります。聞き及ぶ中国の農地よりは遙かにましですが、固いのには相違ありません。中国では人糞と農薬の多用で土は死に体であるとか、土地が自分の物でないこと、収奪と貧困の連鎖・・・・・・・そんな状況で将来に希望が持てないのでしょね。人様の事をあまりとやかくも言えませんが。
耕耘前の畑です。極めて硬い土が一目瞭然ですね。

耕耘機をサッと走らせると、一変に柔らかくなります。

さてマイ畑ですが、耕耘機を動かして少しづつ土壌を柔らかくしていきます。画像で紹介しておきますが、耕耘前と耕耘後とは土の状況がまるで違っていますね。これで有機石灰と鶏糞とを購入して、土の中に鋤込んでいけば下準備はOKですか。ようやく種蒔きや植栽の目処が見えてきたようです。明日にでも石灰と鶏糞とを搬送しておきましょう。冬野菜の植え付けシーズンとなってるのですが、これだけ晴天続きで気温が高いと、播いた種もミイラと化するかも知れませんね。気象条件を左右することは出来ませんが、何らかの形で太陽光線を遮断しないと。寒冷紗などを使用して日陰を作って種蒔きしましょうかな。それでもニンジンなどには厳し過ぎる環境ですね。
仲間の衆は既に石灰を散布して中和の作業に、段取り早し。

同好の士のブログなどをよく拝見してますが、皆さん苦労されてますね。世界的な異常気象で、個人では対応不能な状況かと思いますが、それでも植え付けをやらざるを得ないですね。いっそのこと、南国の野菜を栽培した方が環境に適応できるかもしれませんね。大阪でもマンゴーやパパイヤ、パイナップルなどがそこら中の農地でてんこ盛りだったりして。
9月になってもまだまだ真夏の気候ですね。

2010年08月28日
狼煙を上げて
天気上々、風無し、付近に人影無し・・・・・・・・・こうなってきますと、得意の狼煙上げの作業日和ですね。何そうたいしたことではありません。刈り取って天日干しとしていた雑草類を焼却処分するだけの話。晴天続きで結構乾燥してるかと思いきや、表面のみで下敷きとなった雑草類は半生状態。従って火を付けても勢いよく燃え上がるとはならず、くすぶり状態。画像をご覧いただきたいが、こうした状況を狼煙上げと仮称しております。付近に民家があったら大事ですね。師匠のお宅が比較的近いのですが、そこはそれ、おおらかに見守って下さいます。有り難いことです。
さあて狼煙を打ち上げましょうかな。

付近一帯が煙に包まれていきます。

夏野菜の撤去が概ね片付いて、残骸を彼方此方に積み上げているのですが、完全に焼却して灰とし畑に戻してあげる必要があります。この作業でやっかいなのが、均等に乾燥させること。本当は日々残骸の山をひっくり返して太陽光にさらす面を交代させるのが望ましいのですが、なかなか実行出来ないですよね。結果、半生状態の残骸が出現します。対策は灯油をぶっかけての強制焼却、これしかないですね。本日も灯油の力を借りました。
作業中にシマヘビが一匹ニョロリ・・・・・・・何を勘違いしたのか、火を扱ってる小生の方へ近づいてきます。蛇に好まれてもどうしようもないので、長柄のクワで追い払うことに。これがマムシであれば脳天直撃でしょうが、マムシ以外は殺生しないようにしています。
こちらは意外と火がよくとおっています。暑いですね。


澄みきった青空に白い煙がたなびいて、標題どおりの狼煙上げ、風情があってなかなかいいものです。但し、炎天下で火を使う結果、相当に暑いので脱水症などの可能性があります。水分補給をお忘れ無く、水分はがぶ飲みするのではなく少量づつを頻繁に取る方が体にはいいようですね。小生のは冷やしたハブ茶がメインです。無論自家製のお茶で、この夏は茶葉を購入することなくマイ農園の茶畑で賄いました。本年度分のエビス草(ハブ茶の原料)も健やかに育っています、間もなくの収穫ですね。
この真っ青な青空に狼煙が数丈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

灰が出来つつありますね、貴重な農耕用の肥料となります。

さあて狼煙を打ち上げましょうかな。

付近一帯が煙に包まれていきます。

夏野菜の撤去が概ね片付いて、残骸を彼方此方に積み上げているのですが、完全に焼却して灰とし畑に戻してあげる必要があります。この作業でやっかいなのが、均等に乾燥させること。本当は日々残骸の山をひっくり返して太陽光にさらす面を交代させるのが望ましいのですが、なかなか実行出来ないですよね。結果、半生状態の残骸が出現します。対策は灯油をぶっかけての強制焼却、これしかないですね。本日も灯油の力を借りました。
作業中にシマヘビが一匹ニョロリ・・・・・・・何を勘違いしたのか、火を扱ってる小生の方へ近づいてきます。蛇に好まれてもどうしようもないので、長柄のクワで追い払うことに。これがマムシであれば脳天直撃でしょうが、マムシ以外は殺生しないようにしています。
こちらは意外と火がよくとおっています。暑いですね。


澄みきった青空に白い煙がたなびいて、標題どおりの狼煙上げ、風情があってなかなかいいものです。但し、炎天下で火を使う結果、相当に暑いので脱水症などの可能性があります。水分補給をお忘れ無く、水分はがぶ飲みするのではなく少量づつを頻繁に取る方が体にはいいようですね。小生のは冷やしたハブ茶がメインです。無論自家製のお茶で、この夏は茶葉を購入することなくマイ農園の茶畑で賄いました。本年度分のエビス草(ハブ茶の原料)も健やかに育っています、間もなくの収穫ですね。
この真っ青な青空に狼煙が数丈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

灰が出来つつありますね、貴重な農耕用の肥料となります。

2010年08月25日
南瓜を藪から掘り出して
8月も終盤となりました、夏もそろそろ終わりですね。マイ農園でも夏野菜の撤去作業にはいっています。最後の仕事が南瓜の掘り出し作業。南瓜を掘り出す?・・・・・何じゃソレ・・・・てな案配でしょうね。無理からぬ話です。通常は南瓜は収穫とは言っても掘り出すとは表現しないですよね。実は地形的な条件と小生の手抜き栽培とが重なって、現状を適正に表現しますとまさに掘り出すとしか言いようが無いのです。くどくど説明しないで画像をご覧になっていただきましょう。1枚の絵が数十枚の原稿用紙に匹敵しますよね。
どう見ても南瓜畑には想像できませんよね。

藪の中を這いずり回っていた南瓜のツル達です。

いかがでしょうか。完全な藪の中で畑とは想像できかねる現場ですよね。しかしながらここが小生の南瓜畑。簡単に説明しますと、斜面に南瓜のツルを這わせたのはいいのだが、草刈りが出来なくて藪となった次第。従いまして藪の中から南瓜を掘り出してあげないと収穫とはいかないのです。活躍するのは刈払機、無論、何気なく振り回しますと肝心の南瓜がなます切りとなります。雑草の上段、中段、下段、と3段階に分けて注意深く切り込みます。おかげさまで南瓜には全くの被害無し。残存していた南瓜全部を無事に救出致しました。
藪の中から救出した栗カボチャです。

本日中にはご近所へと嫁入りかな。

午前中かかって南瓜の救出は完了したのですが、サトイモに被害が出ていました。どうやら下手人はハクビシンかシシかといった状況です。折角伸びきったサトイモの茎が見事に切断され、根元の芋も掘り出した形跡があります。人間様が早堀りしても中秋の名月の頃なのに、この季節では満足な芋でもなかろうに。余程にお腹を空かしていたのか、小生への腹いせか。何れにしても谷間の農園では野菜類の栽培は困難となってきました。完全に連中の思うがままの状況です。
順調に育っていたのに・・・・・・・・サトイモが蹂躙されていました。

西瓜、トマト、キューリ、サツマイモ、ショウガ、・・・・・・・・・何もかもが全滅です。

いずれにしても連中からの被害を防御しようと思えばそれなりの対応策が必要ですね。最強は電気柵の設置でしょうが、コストの問題、手間暇、感電防止、等々を勘案しますとなかなか踏み切れません。ネットではハクビシン相手だと効果無しのようです。周囲の田畑が全て耕作を中断(再開の見込みは無さそうです)されているのも無理からぬ話のようですね。
どう見ても南瓜畑には想像できませんよね。

藪の中を這いずり回っていた南瓜のツル達です。

いかがでしょうか。完全な藪の中で畑とは想像できかねる現場ですよね。しかしながらここが小生の南瓜畑。簡単に説明しますと、斜面に南瓜のツルを這わせたのはいいのだが、草刈りが出来なくて藪となった次第。従いまして藪の中から南瓜を掘り出してあげないと収穫とはいかないのです。活躍するのは刈払機、無論、何気なく振り回しますと肝心の南瓜がなます切りとなります。雑草の上段、中段、下段、と3段階に分けて注意深く切り込みます。おかげさまで南瓜には全くの被害無し。残存していた南瓜全部を無事に救出致しました。
藪の中から救出した栗カボチャです。

本日中にはご近所へと嫁入りかな。

午前中かかって南瓜の救出は完了したのですが、サトイモに被害が出ていました。どうやら下手人はハクビシンかシシかといった状況です。折角伸びきったサトイモの茎が見事に切断され、根元の芋も掘り出した形跡があります。人間様が早堀りしても中秋の名月の頃なのに、この季節では満足な芋でもなかろうに。余程にお腹を空かしていたのか、小生への腹いせか。何れにしても谷間の農園では野菜類の栽培は困難となってきました。完全に連中の思うがままの状況です。
順調に育っていたのに・・・・・・・・サトイモが蹂躙されていました。

西瓜、トマト、キューリ、サツマイモ、ショウガ、・・・・・・・・・何もかもが全滅です。

いずれにしても連中からの被害を防御しようと思えばそれなりの対応策が必要ですね。最強は電気柵の設置でしょうが、コストの問題、手間暇、感電防止、等々を勘案しますとなかなか踏み切れません。ネットではハクビシン相手だと効果無しのようです。周囲の田畑が全て耕作を中断(再開の見込みは無さそうです)されているのも無理からぬ話のようですね。
2010年08月19日
種蒔きより始めよ
花卉栽培の初任者研修があるとのこと、メインは野菜の栽培だが何野菜も花卉もたいして違わぬだろう・・・・・・・・・・この大胆ないいかげんさが小生の特徴でもあるのだが、反面、救われる一面もなきにしもあらず。60名余の熱心な受講生に紛れ込む不届き者1名、素知らぬ顔で種蒔きからの指導を受ける。実は不細工な話なんだが、エビス草の種蒔き・発芽に2回ほど失敗しているのだ。三度目の正直は梅雨で救われたような感じ、小生の力量ではあるまい。他にもニンジンや大葉或いはニラにカブにレタスなど失敗の事例も少なくない。講師の話にもあったのだが、発芽の条件は「水」と「光」と「温度」とか。この三条件がうまくマッチしないと何れも発芽には失敗するそうだ。
概要の講義を終え、実習場へと急ぐ仲間達。

実物を使っての解説が、手話通訳付きです。

対象物によって上記の三条件は異なってくるようだが、何れにも要求されるのが土壌の質、いわゆる団粒構造を保持せよとの基本的な教え。これが実に難しい。耕耘機をかけるのは簡単だが、それだけでは団粒にはならないようだ。土作りであろう。水持ちが良くて尚水捌けがいい土壌、これが団粒構造の土らしいが、時間をかけての堆肥の積み重ねしか無さそうですね。本日はそんな悠長な事は出来ないので、市販の培土を使用する。通称蜂の巣ポットと読んでいるセルトレイを利用しての種蒔きだ。秋に花を咲かせ冬場を持たせ尚春先にも花を望みたいという欲張った計画。従って暑い最中での種蒔きとなった。
各位に提供された種蒔きの4点セット。

市販の培土ピートモスを蜂の巣ポットに盛り込みます。

爪楊枝を使ってのセルトレイへの種蒔き風景です。

講師の教えに従って各位が自分のセルトレイに種蒔き、一人150粒の提供だ。小さすぎる種なので折り曲げた紙に種を出し爪楊枝で1個づつセルトレイに埋め込んでいく。完了したら薄く覆土を被せてスプリンクラーで水撒きだ。その後は冷蔵庫(18度に設定)に5日間寝かせ、発芽を確認して太陽光線の下へと運び出す。午前中は太陽にあて午後は西日を避けての保管とか。次回の講習日には全員のトレイから青い若葉が覗いているはずなんだが。それにしても研究所だけあって設備が整っている。これで失敗したら笑い者だろう。
種蒔きが終了したら覆土の散布です。種の1倍~2倍ぐらい。

完了したセルトレイをスプリンクラーで水やりします。

18度の冷蔵庫で5日間保管、発芽させます。

半日講習を受けてみて、小生がエビス草の発芽に2回失敗したのは、水の条件が一番大きかったようだ。最初の水撒きで種は発芽の開始と目覚め、あとは水分と気温と光線のバランスで若葉へと変化していくようだ。エビス草は4月に失敗、5月に失敗、6月でようやく成功。どうやら水分と気温のバランスが一番よかったようですね。手間暇を考えると市販苗を購入した方が早いのですが、種からの発芽は安価ですし喜びも大きいですよね。温度については、20度~25度の範囲であれば大半の種が発芽するとか、要はビニールや寒冷紗或いはマルチ等で20度~25度を如何に確保するか、この点に勝負どころがありそうですね。
最後には自作スプリンクラーの作り方講習会まで。

タイマー付きでも2万円ぐらいで自作可能とのお話。

概要の講義を終え、実習場へと急ぐ仲間達。

実物を使っての解説が、手話通訳付きです。

対象物によって上記の三条件は異なってくるようだが、何れにも要求されるのが土壌の質、いわゆる団粒構造を保持せよとの基本的な教え。これが実に難しい。耕耘機をかけるのは簡単だが、それだけでは団粒にはならないようだ。土作りであろう。水持ちが良くて尚水捌けがいい土壌、これが団粒構造の土らしいが、時間をかけての堆肥の積み重ねしか無さそうですね。本日はそんな悠長な事は出来ないので、市販の培土を使用する。通称蜂の巣ポットと読んでいるセルトレイを利用しての種蒔きだ。秋に花を咲かせ冬場を持たせ尚春先にも花を望みたいという欲張った計画。従って暑い最中での種蒔きとなった。
各位に提供された種蒔きの4点セット。

市販の培土ピートモスを蜂の巣ポットに盛り込みます。

爪楊枝を使ってのセルトレイへの種蒔き風景です。

講師の教えに従って各位が自分のセルトレイに種蒔き、一人150粒の提供だ。小さすぎる種なので折り曲げた紙に種を出し爪楊枝で1個づつセルトレイに埋め込んでいく。完了したら薄く覆土を被せてスプリンクラーで水撒きだ。その後は冷蔵庫(18度に設定)に5日間寝かせ、発芽を確認して太陽光線の下へと運び出す。午前中は太陽にあて午後は西日を避けての保管とか。次回の講習日には全員のトレイから青い若葉が覗いているはずなんだが。それにしても研究所だけあって設備が整っている。これで失敗したら笑い者だろう。
種蒔きが終了したら覆土の散布です。種の1倍~2倍ぐらい。

完了したセルトレイをスプリンクラーで水やりします。

18度の冷蔵庫で5日間保管、発芽させます。

半日講習を受けてみて、小生がエビス草の発芽に2回失敗したのは、水の条件が一番大きかったようだ。最初の水撒きで種は発芽の開始と目覚め、あとは水分と気温と光線のバランスで若葉へと変化していくようだ。エビス草は4月に失敗、5月に失敗、6月でようやく成功。どうやら水分と気温のバランスが一番よかったようですね。手間暇を考えると市販苗を購入した方が早いのですが、種からの発芽は安価ですし喜びも大きいですよね。温度については、20度~25度の範囲であれば大半の種が発芽するとか、要はビニールや寒冷紗或いはマルチ等で20度~25度を如何に確保するか、この点に勝負どころがありそうですね。
最後には自作スプリンクラーの作り方講習会まで。

タイマー付きでも2万円ぐらいで自作可能とのお話。

2010年08月18日
サツマイモのツル返し
谷底のサツマイモ畑はハクビシンにやられて壊滅状態ですが、共同農園は幸いに獣害もなくすくすくと成長致しております。こうなって来ますと、気になるのがツルの生育状況。勢いよく伸びるのはよろしいんですが、彼方此方に根を下ろし肝心の芋の方へ養分が届かぬ恐れがあります。そこで要求されるのがツル返し、ツルの恩返しではありませんぞ。あちらは木下順二氏の戯曲でお馴染みでしょうが、こちらは文字通りの百姓仕事です。画像でご覧頂いた方が早いかと思いますので、順次、ご覧になって下さい。新天地で根を生やしたものをはぎ取り、光合成による栄養分は全て元々の芋の方に回るように処理するのがツル返しです。
手前がサツマイモ畑です。雑草に埋もれてますね。

伸びた先で根を下ろすツルを地面から引き離します。

地面から引き離したツルは他のツルの上に。

夏場の暑い最中に数回はやっておく必要がありますね。小生は本日で2回目、芋ヅルも結構伸びまして新天地で根を生じておtります。このまま放置しますと。新天地で新たな芋作りが始まり、元々の芋は大きくなれません。栄養分は一ヶ所に重点投資、大きな芋作りの秘訣ですよね。師匠によると、芋は滋養分の少ない土壌が良く合うようで、飢饉用の作物とも言われる所以かも知れません。栄養分の多い土地では、葉とツルが茂るのみで芋は着きにくいようです。師匠の造語かとも思いますが、ハナカリサンという隠語があります。当地の方言でトイレのことを「はばかりさん」とも呼びますが、中の本体は昔と違い使い道がなくて困る代物ですよね。従って、役に立たないどうしようも無い作物との意味を込めて、出来の悪いサツマイモをハバカリさんとも蔑称するようです。ハバカリさんとは葉ばかりで芋がないとの意味もあるようですね。
草抜きした結果が次々と雑草の山を築いていきます。

うまく乾燥したら焼却処分なのですが・・・・・・・・・・なかなかですね。

さてツル返しと一緒にといいますか、同時期にやらねばならないのが、草抜き作業。刈払機を使った草刈りではありませんぞ。野菜類の間に伸びまくった雑草を鎌で根こそぎにする作業です。風呂場で使用する腰掛けを持ち込んで、座りながら実施します。中腰では体が持ちません。彼方此方に積み上げて乾燥させ、焼却処分にしてやろうと考えてるんですが、暑いのに思うようには乾燥しませんね。草抜きが完了すれば耕耘機を持ち出して冬野菜の準備をと狙ってますが、まだまだのようです。
夏の終わりを知ってかオクラの花が咲き始めました。何とも上品で清楚な装いを持った綺麗な花です。淡い黄色の花が青空に映えて、夏の暑さを多少は和らげてくれてるようですね。
オクラの花が咲き始めました、夏場も終焉期ですね。

花は良いのですが、オクラは収穫が1日遅れるとお化けとなります。

手前がサツマイモ畑です。雑草に埋もれてますね。

伸びた先で根を下ろすツルを地面から引き離します。

地面から引き離したツルは他のツルの上に。

夏場の暑い最中に数回はやっておく必要がありますね。小生は本日で2回目、芋ヅルも結構伸びまして新天地で根を生じておtります。このまま放置しますと。新天地で新たな芋作りが始まり、元々の芋は大きくなれません。栄養分は一ヶ所に重点投資、大きな芋作りの秘訣ですよね。師匠によると、芋は滋養分の少ない土壌が良く合うようで、飢饉用の作物とも言われる所以かも知れません。栄養分の多い土地では、葉とツルが茂るのみで芋は着きにくいようです。師匠の造語かとも思いますが、ハナカリサンという隠語があります。当地の方言でトイレのことを「はばかりさん」とも呼びますが、中の本体は昔と違い使い道がなくて困る代物ですよね。従って、役に立たないどうしようも無い作物との意味を込めて、出来の悪いサツマイモをハバカリさんとも蔑称するようです。ハバカリさんとは葉ばかりで芋がないとの意味もあるようですね。
草抜きした結果が次々と雑草の山を築いていきます。

うまく乾燥したら焼却処分なのですが・・・・・・・・・・なかなかですね。

さてツル返しと一緒にといいますか、同時期にやらねばならないのが、草抜き作業。刈払機を使った草刈りではありませんぞ。野菜類の間に伸びまくった雑草を鎌で根こそぎにする作業です。風呂場で使用する腰掛けを持ち込んで、座りながら実施します。中腰では体が持ちません。彼方此方に積み上げて乾燥させ、焼却処分にしてやろうと考えてるんですが、暑いのに思うようには乾燥しませんね。草抜きが完了すれば耕耘機を持ち出して冬野菜の準備をと狙ってますが、まだまだのようです。
夏の終わりを知ってかオクラの花が咲き始めました。何とも上品で清楚な装いを持った綺麗な花です。淡い黄色の花が青空に映えて、夏の暑さを多少は和らげてくれてるようですね。
オクラの花が咲き始めました、夏場も終焉期ですね。

花は良いのですが、オクラは収穫が1日遅れるとお化けとなります。

2010年08月12日
アライグマとハクビシン
ニューフェイス登場といえば聞こえがいいのだが、事はそんなに甘いものではない。これまで当地の害鳥獣はシシがダントツで二番手にアライグマと野ウサギ、三番手にカラスやキジといったランク付けであった。ハクビシンなど全く想定外。地域の噂にすら上っていなかった。ところが小生の被害状況をブログに掲載したところ、関西野生生物研究所さんからコメントを頂き、ハクビシンではないかとのご指摘。気になって調べて見ますと、どうやら野菜の被害状況がハクビシンによるものとソックリですね。スイカの抉り具合など他のHPの画像で紹介されているものと全く一致しています。これまでアライグマの仕業だとばかり思い込んでいたのですが、とんだ冤罪で、人権侵害との被害届が出そうな感じですね。犯人がアライグマであれハクビシンであれ、耕作者が困るのは一向に変わりないので、どうやって対処するか思案中ではあります。
21年度の被害状況です。

22年度の被害状況です。

ネット情報によりますと、アライグマは「外来生物法」により人的被害や環境影響から駆除出来ると定められているようです。現に自治体によっては一匹いくらといった駆除の助成金を出している団体もあるやに聞いています。反してハクビシンの場合は外来生物法による特定外来生物の指定を受けておらず、勝手に駆除することは禁止行為のようですね。果樹や野菜類等に被害が生じた場合、例外的に許可を受けて駆除が出来るだけの模様。何れも繁殖力が旺盛で天敵もないようですから、ネズミと同じようにどんどんと増加し続けるのではないでしょうか。
ハクビシンは大きな穴を空け頭を突っ込んで食害するそうで・・・・・・・・

率直なところ、当地ではハクビシンの名前を聞いたことはありませんでした。無論、アライグマもハクビシンも現物と対面したことはありません。夜行性の故もあってか、画像で知るのみで、ネコか狸程度の大きさという漠然としたイメージだけですね。群馬の赤城山で知人が農的暮らしをやっておりますが、彼の地はハクビシンが横行し農作物の大半に被害が生じていると嘆いていました。ハクビシンの暗躍はかように東日本方面だと安心しきっておったのですが。母を訪ねて三千里ではないですが、はるばるとアルプスの山塊を越えて関西まで出張ってきたのでしょうか。それとも元々在来種として生存していたが、アライグマの陰に隠れてしまっていたのでしょうか。
21年度の被害ですが、こちらは鳥害では?と思っています。

嫌らしいのは、少しづつ彼方此方のトマトを囓ること。

アライグマもハクビシンもシシも電気柵が一番効果的な防御策のようですね。ただ広い農地の全面に電気柵を設置するとなりますと、それなりの投下資金が要求されます。農作物の生産や換価で回収出来る程度であれば結構なのですが、そうは問屋が卸さぬようですね。当地で電気柵の設置が少ないのも、こうした費用対投資効果理論で躊躇される方が多いのでしょう。そして例外的だとは存じますが、電気柵で感電死したご老人の事例もあるとかないとか。一番いいのは彼等の出没地では農作業を止めるという決断でしょうか。豊臣秀吉ではないですが兵糧作戦による飢餓戦法ですね、最も中山間地の農業は壊滅するかも知れませんが。
21年度の被害状況です。

22年度の被害状況です。

ネット情報によりますと、アライグマは「外来生物法」により人的被害や環境影響から駆除出来ると定められているようです。現に自治体によっては一匹いくらといった駆除の助成金を出している団体もあるやに聞いています。反してハクビシンの場合は外来生物法による特定外来生物の指定を受けておらず、勝手に駆除することは禁止行為のようですね。果樹や野菜類等に被害が生じた場合、例外的に許可を受けて駆除が出来るだけの模様。何れも繁殖力が旺盛で天敵もないようですから、ネズミと同じようにどんどんと増加し続けるのではないでしょうか。
ハクビシンは大きな穴を空け頭を突っ込んで食害するそうで・・・・・・・・

率直なところ、当地ではハクビシンの名前を聞いたことはありませんでした。無論、アライグマもハクビシンも現物と対面したことはありません。夜行性の故もあってか、画像で知るのみで、ネコか狸程度の大きさという漠然としたイメージだけですね。群馬の赤城山で知人が農的暮らしをやっておりますが、彼の地はハクビシンが横行し農作物の大半に被害が生じていると嘆いていました。ハクビシンの暗躍はかように東日本方面だと安心しきっておったのですが。母を訪ねて三千里ではないですが、はるばるとアルプスの山塊を越えて関西まで出張ってきたのでしょうか。それとも元々在来種として生存していたが、アライグマの陰に隠れてしまっていたのでしょうか。
21年度の被害ですが、こちらは鳥害では?と思っています。

嫌らしいのは、少しづつ彼方此方のトマトを囓ること。

アライグマもハクビシンもシシも電気柵が一番効果的な防御策のようですね。ただ広い農地の全面に電気柵を設置するとなりますと、それなりの投下資金が要求されます。農作物の生産や換価で回収出来る程度であれば結構なのですが、そうは問屋が卸さぬようですね。当地で電気柵の設置が少ないのも、こうした費用対投資効果理論で躊躇される方が多いのでしょう。そして例外的だとは存じますが、電気柵で感電死したご老人の事例もあるとかないとか。一番いいのは彼等の出没地では農作業を止めるという決断でしょうか。豊臣秀吉ではないですが兵糧作戦による飢餓戦法ですね、最も中山間地の農業は壊滅するかも知れませんが。
2010年08月07日
頂き物はマクワウリ
イノシシが出た、アライグマが荒らし回っている、モグラの穴だらけ・・・・・・・・・・そんな事をわめいているせいか、仲間の衆は気の毒に思われたのだろう。頂き物を頂戴した。しかも偶然なんだが同じ物を同じ日に。最初は登り屋のKzさん、続いて物知り博士のKさん、ほんの1時間ほどの時間差であった。登り屋のKzさん、さっさと畑の手入れを済ませ、マクワウリ2個を手土産に渡すと金剛山へと直行。畑仕事の後に山登りだ、最も彼の日課だから登らないと体が変調をきたすようだ。Kさんは何時もどおりの重役出勤、概ね10時前後となりますね。これまたマクワウリをご持参いただき、家で食べてや・・・・・・・・・・・とのありがたいお言葉。
頂き物はマクワウリ・・・・・・実に立派な作品ですね。

我々が子どもの時分、3丁目の夕日が描き出すような時代背景だった。敗戦後の混乱期で甘い物など殆ど無く、マクワウリなど貴重な果物(野菜ではなく)と解していた。夏の暑い盛りに井戸で冷やした西瓜やマクワウリなどは貴重なおやつであったように思う。それが最近は子ども達に見向きもされないようだ。Kさんもお孫さんに託送しても全く賞味してくれないとか、ぼやいておられる。どうやら味覚が全く変化してしまったようですね。幼い時分から過度の調味料や香辛料などに馴染んでしまい、野菜や果物が本来持っている薄めの味では物足りないのでしょう。個人的には、炭酸飲料やスナック菓子等の多用が子ども達の味覚のみならず脳細胞まで変化させているのでは・・・・・・・そんな気がしています。
Kzさんのマクワウリ畑、きちんと鳥除けのネットを張り巡らしています。

立派なウリが収穫を待っていますね。

いただきましたマクワウリ、大事に冷蔵庫で冷やしまして朝食の食卓へとのぼらせます。私宅では、毎朝某かの野菜と果物を添えるのが習慣となっています。幸いにして、畑で栽培できる物や頂き物がありまして、あまり不自由しないところが有り難いところ。農作業の労苦も吹っ飛びますね。自分や仲間達が作った物であれば、余計な心配など全く不要ですよね。フードマイレージなんて限りなくゼロに近いでしょうし。後、シシやアライグマ達がもう少し温和しくしてくれたら万々歳なんですが。
彼は野菜のみならず花の栽培も、風雅な御仁です。

透き通るような青空ですね、作業を止め思わず空に吸い込まれそうに。

頂き物はマクワウリ・・・・・・実に立派な作品ですね。

我々が子どもの時分、3丁目の夕日が描き出すような時代背景だった。敗戦後の混乱期で甘い物など殆ど無く、マクワウリなど貴重な果物(野菜ではなく)と解していた。夏の暑い盛りに井戸で冷やした西瓜やマクワウリなどは貴重なおやつであったように思う。それが最近は子ども達に見向きもされないようだ。Kさんもお孫さんに託送しても全く賞味してくれないとか、ぼやいておられる。どうやら味覚が全く変化してしまったようですね。幼い時分から過度の調味料や香辛料などに馴染んでしまい、野菜や果物が本来持っている薄めの味では物足りないのでしょう。個人的には、炭酸飲料やスナック菓子等の多用が子ども達の味覚のみならず脳細胞まで変化させているのでは・・・・・・・そんな気がしています。
Kzさんのマクワウリ畑、きちんと鳥除けのネットを張り巡らしています。

立派なウリが収穫を待っていますね。

いただきましたマクワウリ、大事に冷蔵庫で冷やしまして朝食の食卓へとのぼらせます。私宅では、毎朝某かの野菜と果物を添えるのが習慣となっています。幸いにして、畑で栽培できる物や頂き物がありまして、あまり不自由しないところが有り難いところ。農作業の労苦も吹っ飛びますね。自分や仲間達が作った物であれば、余計な心配など全く不要ですよね。フードマイレージなんて限りなくゼロに近いでしょうし。後、シシやアライグマ達がもう少し温和しくしてくれたら万々歳なんですが。
彼は野菜のみならず花の栽培も、風雅な御仁です。

透き通るような青空ですね、作業を止め思わず空に吸い込まれそうに。

2010年08月06日
アライグマエレジー
エレジーとは悲歌、哀歌、といった意味だそうだが、勿論アライグマへの悲しみなど毛頭無い。否、アライグマに翻弄される悲しき人間達への哀歌でありましょう。発端はペットとしての輸入だったようだが、最後まで面倒見るような常識は備えておらず、飽きたらポイ、これが大多数の実態なんでしょうか。ペットの動物も飼い主の放棄で殺処分される事例が相当数あるようです。宮崎県の口蹄疫のモウ君達のみではありませんよね。最もアライグマについては殺処分して欲しいのが本音ではありますが。師匠の話では棚田1枚に付き1匹のアライグマが生存してるとか。数量的な正否はともかくとしても、相当な数が生息しているのは事実のようです。わが谷間の農園も連日のように荒らされている。トマトもキューリもピーマンも西瓜も・・・・・・・・・・何故か実を付けないなと案じていたら、彼方此方に証拠物件が散乱していた。
朝顔につるべ取られてもらい水・・・・・加賀の千代女の奥ゆかしさがアライグマ
にも備わって欲しいのだが・・・・・・・・・・・無理でしょうな。

せっかくのスイカがこの有り様です。見事に抉っていますね。

キューリ畑から遠く離れた場所に散乱していました。

最悪だったのはシシ除けにネットを張り巡らしたサツマイモ畑、確かにシシは寄りつかなかったのだが、画像をご覧あれ。見事に掘り返されていますね。無論、ネットは全く破損していません。考えられるのは乗り越えたと言うことでしょう。シシはそんな器用な真似は出来ません。明らかに木登り名人でもあるアライグマの仕業ですね。スイカの画像もアップしておきますが、見事にえぐり出しています。カラスなら突いて穴を空けるのみですが、状況は両手を使ってえぐった跡ですね。
サツマイモ畑はシシ除けにネットを張り巡らしたのですが。

乗り越えて侵入したようです。ツルを掘り返し引きちぎっています。

アライグマが頻繁に出没するようでは果菜類や根菜類も栽培不可となります。彼等に襲撃されない品目、あるのでしょうか。栽培中の品目ではシソ類かエビス草或いはニラ類位でしょうか。こうなってきますと畑としての機能が失われてしまいますね。いよいよ果樹園への変更を図るべきでしょうが、木登り名人の連中のこと、通常の果樹では同じ結果が予測されます。小生が栽培したくて連中が好まない果樹木、何だろう。果樹木の植栽期は一般的には秋から春先に掛けて、半年ほどの猶予がありますので研究を続けた上で結論を出さないと。
一輪のみのツユ草・・・・・・・・・我が農園の将来を暗示しているようで。

朝顔につるべ取られてもらい水・・・・・加賀の千代女の奥ゆかしさがアライグマ
にも備わって欲しいのだが・・・・・・・・・・・無理でしょうな。

せっかくのスイカがこの有り様です。見事に抉っていますね。

キューリ畑から遠く離れた場所に散乱していました。

最悪だったのはシシ除けにネットを張り巡らしたサツマイモ畑、確かにシシは寄りつかなかったのだが、画像をご覧あれ。見事に掘り返されていますね。無論、ネットは全く破損していません。考えられるのは乗り越えたと言うことでしょう。シシはそんな器用な真似は出来ません。明らかに木登り名人でもあるアライグマの仕業ですね。スイカの画像もアップしておきますが、見事にえぐり出しています。カラスなら突いて穴を空けるのみですが、状況は両手を使ってえぐった跡ですね。
サツマイモ畑はシシ除けにネットを張り巡らしたのですが。

乗り越えて侵入したようです。ツルを掘り返し引きちぎっています。

アライグマが頻繁に出没するようでは果菜類や根菜類も栽培不可となります。彼等に襲撃されない品目、あるのでしょうか。栽培中の品目ではシソ類かエビス草或いはニラ類位でしょうか。こうなってきますと畑としての機能が失われてしまいますね。いよいよ果樹園への変更を図るべきでしょうが、木登り名人の連中のこと、通常の果樹では同じ結果が予測されます。小生が栽培したくて連中が好まない果樹木、何だろう。果樹木の植栽期は一般的には秋から春先に掛けて、半年ほどの猶予がありますので研究を続けた上で結論を出さないと。
一輪のみのツユ草・・・・・・・・・我が農園の将来を暗示しているようで。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン