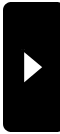2010年12月31日
古城趾で餅つきを
楠公さん縁の古城趾で恒例の餅つきが始まりました。毎年暮れの29日に有志が集まっての賑やかなイベントです。電動式餅つき器がある現代に、臼や杵を持ち出しての餅つきなど何故にと思う方もおられましょう。手間暇かかり非効率的な手法ですが、欠点を補って余りあるメリットがあるかと信じております。普段はすれ違いで終始してしまうような方々とも共同作業で打ち解けあい、餅の試食で笑い転げる・・・・・・・こうした時間は何物にも代え難いものでしょう。仲間達が細い山道を登って古城まではせ参じてくるのは、皆の衆にも同じ想いが潜んでいるから、そう推察致しておるのですが。
人間は炎の扱いを習得したから文明が発達したようですね。

へっついさんでは餅米が次々と蒸し上がっていきます。

伝統的餅つきはご存じの方も多いでしょう。水洗いして準備した餅米を蒸し器やせいろで蒸し上げ、杵と臼でつきあげていくものです。ポイントは如何に効率よく蒸し上げるか、この点に成否がかかっています。その為には、へっついさんと呼称される土製竈を前もって暖めておくことに尽きるでしょう。暖めるには1時間ほどの加熱を要し、この作業をいかに早い時間帯に完了させるかで1日の作業は左右されます。本日はU氏とOk氏の活躍もあり、追加分も含めた33臼の餅つきが順序よく粛々と完了しました。8時半から始めて5時半の打ち止め、どちら様もお疲れさまでした。
餅米が蒸し上がりましたね、早速つき始めましょうかな。

裏方さんも大変です。薪の管理にお湯沸かし、その合間には豚汁の準備を。

餅には角餅と丸餅があるようで、関西から西は基本的に丸餅が多いようです。本日のリクエストを見てましても大半が丸餅、一部ネコ餅と呼ばれる筒状形式の餅が少々といった案配でしょうか。ネコ餅は画像でおわかりのように、円筒形の形状をしており薄くスライスして使用します。いわば角餅の一種でもありましょうか。形はどうあれ餅は腹持ちが良く、消化吸収もよろしいようで、非常に便利な食物です。雑煮が代表的な食文化でしょうが、日常おやつ代わりにも賞味でき、緊急時には代用食としても使えます、ある程度保存も効きますので非常食料としての備蓄も可能でしょうね。
若手のホープが一番バッター、流石にリキが違いますね。

超ベテランはマイペースで、落ち着いた動作が絵になっています。

蘊蓄はともあれ、集まった30名ほどの仲間達も堪能して餅をお持ち帰り願えたようです。正月まであとわずか、元旦の雑煮は本日のお餅が主役を務めてくれるでしょう。一家団欒の中心に餅があり、その餅は仲間の絆によって作りあげられたもの、1年間の米作りの苦労が報われる一瞬かも知れませんね。
これが噂のネコ餅です、当地の代表的な餅の形態でしょうか。

一人黙々と洗浄作業を・・・・・・Kz氏は最後まで裏方作業に専念?
調理師学校に通学中の故か、洗いが基本の原則に忠実なご様子で。

人間は炎の扱いを習得したから文明が発達したようですね。

へっついさんでは餅米が次々と蒸し上がっていきます。

伝統的餅つきはご存じの方も多いでしょう。水洗いして準備した餅米を蒸し器やせいろで蒸し上げ、杵と臼でつきあげていくものです。ポイントは如何に効率よく蒸し上げるか、この点に成否がかかっています。その為には、へっついさんと呼称される土製竈を前もって暖めておくことに尽きるでしょう。暖めるには1時間ほどの加熱を要し、この作業をいかに早い時間帯に完了させるかで1日の作業は左右されます。本日はU氏とOk氏の活躍もあり、追加分も含めた33臼の餅つきが順序よく粛々と完了しました。8時半から始めて5時半の打ち止め、どちら様もお疲れさまでした。
餅米が蒸し上がりましたね、早速つき始めましょうかな。

裏方さんも大変です。薪の管理にお湯沸かし、その合間には豚汁の準備を。

餅には角餅と丸餅があるようで、関西から西は基本的に丸餅が多いようです。本日のリクエストを見てましても大半が丸餅、一部ネコ餅と呼ばれる筒状形式の餅が少々といった案配でしょうか。ネコ餅は画像でおわかりのように、円筒形の形状をしており薄くスライスして使用します。いわば角餅の一種でもありましょうか。形はどうあれ餅は腹持ちが良く、消化吸収もよろしいようで、非常に便利な食物です。雑煮が代表的な食文化でしょうが、日常おやつ代わりにも賞味でき、緊急時には代用食としても使えます、ある程度保存も効きますので非常食料としての備蓄も可能でしょうね。
若手のホープが一番バッター、流石にリキが違いますね。

超ベテランはマイペースで、落ち着いた動作が絵になっています。

蘊蓄はともあれ、集まった30名ほどの仲間達も堪能して餅をお持ち帰り願えたようです。正月まであとわずか、元旦の雑煮は本日のお餅が主役を務めてくれるでしょう。一家団欒の中心に餅があり、その餅は仲間の絆によって作りあげられたもの、1年間の米作りの苦労が報われる一瞬かも知れませんね。
これが噂のネコ餅です、当地の代表的な餅の形態でしょうか。

一人黙々と洗浄作業を・・・・・・Kz氏は最後まで裏方作業に専念?
調理師学校に通学中の故か、洗いが基本の原則に忠実なご様子で。

2010年12月30日
縁の下の力持ちさん
経営管理のセミナー等を受講すると、よく持ち出される話に「15:70:15の法則」なる言葉が存在する。何でも如何なる組織といえども構成メンバーはこの割合にて分類され、どのように組織替えを行ってもこの比率は変わらないとの哲理だそうな。もう少し詳細に述べると、イノベーションを引き起こしてリーダーシップを取り組織を牽引するのが15パーセントのメンバー、可もなく不可もなく後から付いていくのが70パーセントのメンバー、組織にぶら下がり前85パーセントのメンバーの足を引っ張るのが15パーセントの者、この構成内容はいかなる組織でも不変の原理であるとか。読者の皆様も様々な組織体に所属しておられるかと思いますが、如何でしょうか。
まずは窯の補修から、粘土をこねてひび割れ部分に貼り付けます。

持尾城趾にあります仲間達の拠点です。山の上なので結構寒いです。

さてそんな堅苦しい話は横に置いときまして、年末でもありますし餅つきの話でも致しましょうかな。実は29日が某氏の生誕記念日、俗に言う誕生日ですね。この日を選んで餅をつくのが里山倶楽部有志の習わし、今年もシーズンとなりました。何分つきます餅が半端ではない、本年も70キロの餅米を準備しております。木臼で28回もペッタラコとつかねばなりませんね。多分、早朝から夕刻遅くまでの長丁場となりますでしょう。準備も大変ですが数名のメンバーが集まってくれました。窯の補修作業から始まって機材の準備、米の水洗い、薪集め、臼の搬入、借用物の調達、と手分けしながら作業を進めていきます。昼過ぎには大まかな目処がつき、コーヒーをいただく余裕も少々。たき火を囲みながら1年間を振り返りますが、時間の過ぎ去るのが恐ろしく早いというのが皆の実感。まさに、少年老いやすく学成り難し・・・・一寸の光陰軽んずべからず、でしょうか。
木臼が搬入されました、古民家で眠っていた年代物です。

餅米の計量です。バケツ一杯に5キロの餅米が。

山の清水で餅米を洗います。冷たくて手が千切れそうな感じ。

それにしても、例年の餅つきを眺めていて、事前準備に集まってくれるメンバーはいつも同じであることに気づかされます。本番当日は結構な賑わいとなりますが、地味な事前準備には広い度量と深い洞察力に恵まれた少数のメンバーが意識して参加されてるようですね。まさに裏方さん、縁の下の力持ちと言っても過言ではないでしょう。かっては何処の集団においても少なからざる力持ちさん達が存在しました。最近は皆さん利口になられて、巧妙に避けて通るのが当世流であるかのようですね。お世話になった力持ちさん達に感謝しながら明日は餅つきに精出す事と致しましょう。間もなくお正月、何方様もご家族ともども健やかな新春をお迎え下さいますように。
準備が終わりました、明日の本番を待つだけですね。

冷え込んだ体には薪の炎が一番、ほっこりと暖まります。

ロウバイでしょうか、驚いたことにもう全部が開花していました。

まずは窯の補修から、粘土をこねてひび割れ部分に貼り付けます。

持尾城趾にあります仲間達の拠点です。山の上なので結構寒いです。

さてそんな堅苦しい話は横に置いときまして、年末でもありますし餅つきの話でも致しましょうかな。実は29日が某氏の生誕記念日、俗に言う誕生日ですね。この日を選んで餅をつくのが里山倶楽部有志の習わし、今年もシーズンとなりました。何分つきます餅が半端ではない、本年も70キロの餅米を準備しております。木臼で28回もペッタラコとつかねばなりませんね。多分、早朝から夕刻遅くまでの長丁場となりますでしょう。準備も大変ですが数名のメンバーが集まってくれました。窯の補修作業から始まって機材の準備、米の水洗い、薪集め、臼の搬入、借用物の調達、と手分けしながら作業を進めていきます。昼過ぎには大まかな目処がつき、コーヒーをいただく余裕も少々。たき火を囲みながら1年間を振り返りますが、時間の過ぎ去るのが恐ろしく早いというのが皆の実感。まさに、少年老いやすく学成り難し・・・・一寸の光陰軽んずべからず、でしょうか。
木臼が搬入されました、古民家で眠っていた年代物です。

餅米の計量です。バケツ一杯に5キロの餅米が。

山の清水で餅米を洗います。冷たくて手が千切れそうな感じ。

それにしても、例年の餅つきを眺めていて、事前準備に集まってくれるメンバーはいつも同じであることに気づかされます。本番当日は結構な賑わいとなりますが、地味な事前準備には広い度量と深い洞察力に恵まれた少数のメンバーが意識して参加されてるようですね。まさに裏方さん、縁の下の力持ちと言っても過言ではないでしょう。かっては何処の集団においても少なからざる力持ちさん達が存在しました。最近は皆さん利口になられて、巧妙に避けて通るのが当世流であるかのようですね。お世話になった力持ちさん達に感謝しながら明日は餅つきに精出す事と致しましょう。間もなくお正月、何方様もご家族ともども健やかな新春をお迎え下さいますように。
準備が終わりました、明日の本番を待つだけですね。

冷え込んだ体には薪の炎が一番、ほっこりと暖まります。

ロウバイでしょうか、驚いたことにもう全部が開花していました。

2010年12月29日
歳末商戦かな
当地も小雪混じりの季節となりました。めっきりと冷え込みますね。幸い農作業の大半は完了しており、雪景色の中で田畑作業に格闘中というシーンを演じる必要も無く、のんびりと過ごしています。野菜の収穫を終えて直売所に立ち寄りますと、商戦まっただ中、皆さん正月用品のお買い求めのようですね。年末にお節料理を作り来たるべき新春に備える・・・・・こんな風習はもう廃れてしまったのかと思ってましたが、どうしてどうして。買い物籠の中身を覗いてますとソレっぽい品々ばかりです。伝統行事とまでは申しませんが、祖父母から父母へそして孫達へ・・・・・・地域の食材を使ったお節料理が引き継がれていくのは嬉しいものです。
歳末商戦が始まったようですね。並ぶのも正月用品が大半。

葉ボタンが、いかにもそれっぽく飾り付けられていますね。

お節料理は地域によって特色がありますようで、料理に疎い小生には明確な表現が出来ませんが、いわゆるお国柄とでもいいますかローカルカラーの豊かさは列記とした文化だと思います。風土の中で生まれて育まれた土地の料理、それが凝縮されてお節となっているのでしょう。聞くところに寄りますと、お節は年末まで働きづめだった主婦の方々を数日間だけでも骨休めしていただく・・・・そんな想いが込められているとか。単に賞味するだけでなくそうした意味合いを深く語り合うのも正月の良さかも知れませんね。
当地でも注連縄を自作する方はめっきりと減少しました。

正月用の花々でしょうね、新春に花芽が開花かな。

買い物籠から飛び出した大根や白菜、手作りコンニャクや水菜達、今夜は鍋料理でしょうか。鍋を囲んでの家族そろって一家団欒・・・・・・・・楽しそうな風景が想像できますね。個食や孤食といった侘びしい言葉がありますが、せめて朝夕の食卓だけでも家族全員で囲みたいもの、当地で作られた野菜達が多少なりともお役に立ちましたら光栄です。正月を控え、売り子さんの声も一段と高くなるようです。残すところ数日、並んだ野菜達を完売して除夜の鐘を迎えたいものですね。
朝から小雪混じりの天候となりました。野菜の収穫も冷たいのなんのって。

白菜もうっすらと雪化粧、これから甘くなりますね。

歳末商戦が始まったようですね。並ぶのも正月用品が大半。

葉ボタンが、いかにもそれっぽく飾り付けられていますね。

お節料理は地域によって特色がありますようで、料理に疎い小生には明確な表現が出来ませんが、いわゆるお国柄とでもいいますかローカルカラーの豊かさは列記とした文化だと思います。風土の中で生まれて育まれた土地の料理、それが凝縮されてお節となっているのでしょう。聞くところに寄りますと、お節は年末まで働きづめだった主婦の方々を数日間だけでも骨休めしていただく・・・・そんな想いが込められているとか。単に賞味するだけでなくそうした意味合いを深く語り合うのも正月の良さかも知れませんね。
当地でも注連縄を自作する方はめっきりと減少しました。

正月用の花々でしょうね、新春に花芽が開花かな。

買い物籠から飛び出した大根や白菜、手作りコンニャクや水菜達、今夜は鍋料理でしょうか。鍋を囲んでの家族そろって一家団欒・・・・・・・・楽しそうな風景が想像できますね。個食や孤食といった侘びしい言葉がありますが、せめて朝夕の食卓だけでも家族全員で囲みたいもの、当地で作られた野菜達が多少なりともお役に立ちましたら光栄です。正月を控え、売り子さんの声も一段と高くなるようです。残すところ数日、並んだ野菜達を完売して除夜の鐘を迎えたいものですね。
朝から小雪混じりの天候となりました。野菜の収穫も冷たいのなんのって。

白菜もうっすらと雪化粧、これから甘くなりますね。

2010年12月22日
五穀豊穣の祈り
奈良の市街地を山里と呼ぶには少々抵抗があるが、若草山の山麓と考えれば違和感は生じないかもしれない。所用があって奈良市街地を走っていたのだが、やけに観光客が多く尋常ならざるような賑わい、警備の方に訪ねると春日大社の若宮おん祭りの神事であるとか。知らぬ事とはいえ、偶然にも祭礼の日時と遭遇してしまったようだ。ある意味チャンスとばかり車を駐車場に放り込んで取材活動へ、所用はしばし脇に置いておきましょう。これまた案内放送によれば、本年は875回目の神事に当たるそうだ。毎年1回、この時期に延々と900年近く続けられてきた神事、流石に古都奈良らしき伝統行事である。
スタンバイ中の出演車達、集合地ヘ移動中のようですね。

流石に子ども達です、僅かな時間も戯れていますね。

春日大社の若宮に奉納するための武者行列や流鏑馬或いは宝蔵院流槍術の模範演武などが主な内容のようだ。パレードの通路は沢山の観光客で埋まり外国人の姿も数多い。武者行列は参勤交代の大名を思わせるような演出で、奴さんが舞いながら行進する様は圧巻、いずれもボランティアの方々がこの日の為に修練を重ねられたようです。それにしても900年近くも伝統行事を守り続ける奈良市民の情熱には感動します。継続は力との箴言がありますが、時代の風雪を越えて生き延びてきた慣習や行事或いは書籍などは、無言の存在感を示しているようですね。昨今、急に現れて急に消えていく事物や人間が多いものですが、年月に耐え抜いた事物や人物を選択したいものです。
巨大な刀を持った集団、いわゆる太刀持ちを表現してるんでしょう。

パレードでは奴さん達が様々な舞いを演じながらの行進です。

興福寺から猿沢の池方面に回りますと、見渡す限りの露店街、いわずと知れた縁日風景ですね。あまりにも数が多くて圧倒され、撮影するのを忘れてしまうほど。あらゆる品目の露店が軒を連ねているようです。露店ではありませんが餅つきをやっているお店があって、思わず覗き込んでしまいました。餅つきの手際よさとそのスピードに圧倒されたからです。つきたての草餅を買い込み、パクつきながら本来の所用に戻りましょうかな。
若き騎馬武者、見事に矢は的を射抜きました。

奈良は槍術の発祥地のようですね、多分宝蔵院流の槍術でしょう。

スタンバイ中の出演車達、集合地ヘ移動中のようですね。

流石に子ども達です、僅かな時間も戯れていますね。

春日大社の若宮に奉納するための武者行列や流鏑馬或いは宝蔵院流槍術の模範演武などが主な内容のようだ。パレードの通路は沢山の観光客で埋まり外国人の姿も数多い。武者行列は参勤交代の大名を思わせるような演出で、奴さんが舞いながら行進する様は圧巻、いずれもボランティアの方々がこの日の為に修練を重ねられたようです。それにしても900年近くも伝統行事を守り続ける奈良市民の情熱には感動します。継続は力との箴言がありますが、時代の風雪を越えて生き延びてきた慣習や行事或いは書籍などは、無言の存在感を示しているようですね。昨今、急に現れて急に消えていく事物や人間が多いものですが、年月に耐え抜いた事物や人物を選択したいものです。
巨大な刀を持った集団、いわゆる太刀持ちを表現してるんでしょう。

パレードでは奴さん達が様々な舞いを演じながらの行進です。

興福寺から猿沢の池方面に回りますと、見渡す限りの露店街、いわずと知れた縁日風景ですね。あまりにも数が多くて圧倒され、撮影するのを忘れてしまうほど。あらゆる品目の露店が軒を連ねているようです。露店ではありませんが餅つきをやっているお店があって、思わず覗き込んでしまいました。餅つきの手際よさとそのスピードに圧倒されたからです。つきたての草餅を買い込み、パクつきながら本来の所用に戻りましょうかな。
若き騎馬武者、見事に矢は的を射抜きました。

奈良は槍術の発祥地のようですね、多分宝蔵院流の槍術でしょう。

2010年12月16日
クリスマスも不況かな
歳末ともなりますと、恒例の二大イベントが待ち構えておりますね。年賀状とクリスマスでしょうか。年賀状はクリスマスが過ぎないと気分が乗らないし、クリスマスはどうかすると11月から前哨戦が始まっております。何とも商魂逞しいというのか、祭り好きなのか、真意の程はよくわかりませんが盛り上がっております。ただ言えることは、誰もクリスマスが宗教行事だなどと考えていないことだけは確かなようですね。当地でも華やかな電飾が夜道を照らし、何所ぞの歓楽街ではと思える程の一角があります。自分でやるのは面倒だしセンスも無いしで、専ら覗きに回るのですが、今年は少々異変が生じているようですね。
SL号が走っていますね、目的地は夢の国かな。

夢の国の幻想的な風景を表現しておられるのでしょうか。

例年、電飾の飾り付けに創意工夫をこらし、ご近所で競い合っておられたように見受けたのですが、本年はさっぱり。僅か数軒程のお宅が為さっておられただけでした。ご不幸があったのか、競争にお疲れになったのか、飽きられたのか・・・・・・・推測の域を出ませんが多分に不況の影響が大ではと思っています。1ドル83円程度、円高進行で輸出関連産業は青息吐息、菅さんご一家には為す術がなさそうで、批判するだけのヤジ馬集団と言う正体が明らかになったようですね。「空き缶(管)」との厳しい評価もやむを得ないようです。こうした世相に、無駄な出費は控えて生活防衛に、と走るのが庶民のささやかな航海術なんでしょう。電飾が減少するのも致し方無しのようでございまして。
門衛に立つ番兵さんのようでもあります。

番兵さんのお隣には緑(青?)の樹木が。

イルミネーションの最大の効用は防犯機能にある、と言えば該当のお宅には叱られますかな。夜道の街路を赤々と照らし出し、見物客を引き寄せる程の明るさは、犯罪者にとって邪魔者以外の何物でも無いでしょう。出来うる事なら夜明けまで点滅を継続して欲しいものです。それにしても、外国の宗教行事にかくも異なった関心を持ち、多大なエネルギーを消費する日本人、外国人から見たら魔詞不思議な存在なんでしょうね。
森の中で親に寄り添うバンビでしょうか、幻想的な世界です。

夢の世界のようでありますし、歓楽街のようにも見えますし・・・・・・・

SL号が走っていますね、目的地は夢の国かな。

夢の国の幻想的な風景を表現しておられるのでしょうか。

例年、電飾の飾り付けに創意工夫をこらし、ご近所で競い合っておられたように見受けたのですが、本年はさっぱり。僅か数軒程のお宅が為さっておられただけでした。ご不幸があったのか、競争にお疲れになったのか、飽きられたのか・・・・・・・推測の域を出ませんが多分に不況の影響が大ではと思っています。1ドル83円程度、円高進行で輸出関連産業は青息吐息、菅さんご一家には為す術がなさそうで、批判するだけのヤジ馬集団と言う正体が明らかになったようですね。「空き缶(管)」との厳しい評価もやむを得ないようです。こうした世相に、無駄な出費は控えて生活防衛に、と走るのが庶民のささやかな航海術なんでしょう。電飾が減少するのも致し方無しのようでございまして。
門衛に立つ番兵さんのようでもあります。

番兵さんのお隣には緑(青?)の樹木が。

イルミネーションの最大の効用は防犯機能にある、と言えば該当のお宅には叱られますかな。夜道の街路を赤々と照らし出し、見物客を引き寄せる程の明るさは、犯罪者にとって邪魔者以外の何物でも無いでしょう。出来うる事なら夜明けまで点滅を継続して欲しいものです。それにしても、外国の宗教行事にかくも異なった関心を持ち、多大なエネルギーを消費する日本人、外国人から見たら魔詞不思議な存在なんでしょうね。
森の中で親に寄り添うバンビでしょうか、幻想的な世界です。

夢の世界のようでありますし、歓楽街のようにも見えますし・・・・・・・

2010年11月07日
文化祭の季節
11月ですね、この季節は文化の日がある故かよくわかりませんが各地で文化祭が開催されます。当地も例外ではないようでございまして、各市町村とも趣向を凝らした祭典が開かれています。あいにく芸術関係は疎いので専門的なものは憚られます。音楽祭なら聴衆に紛れ込んで聞いてればボロが出ることもなかろうと、とある街のホールに飛び込んでみました。管楽器の演奏会かと思いきやコーラスグループの発表会のようでしたね。かって数十年の昔、各地でママさんコーラスなるものがフィーバーしてましたが、その発展段階でしょうか。司会者の話では創立30年~40年というグループが多々あるそうです。全部で16グループの参加でしたが男声合唱団が一組、混成が一組、残り全ては女性合唱団でした。
ラストシーンは全出演者による混声合唱でした。曲目はモルダウの我が祖国より。

ピアノ伴奏者は各合唱団のメンバーからです。

年齢的にはやはりシルバー世代が中心のようです。壮年層は子育て、仕事、転勤、子弟の教育問題等でなかなか地域集団の中へはいり込めないようです。子育てが完了し定年期を迎える頃にようやく自分の時間が見つかるのかも知れませんね。その点、女性軍は地域社会に根が生えてるようで、家事に追われつつも上手にコミニティーを形成しておられるようです。女性合唱団などその典型ではないでしょうか。16組のうち14組が女性合唱団という比率は、こうした社会の実態を如実に証明しているようですね、男性軍頑張って下さい。
出演者中で唯一の男声合唱団。

同じく唯一の混声合唱団です。

声を出して歌うことは脳細胞を活性化するようです。音痴に近い小生には真似が出来ませんが、せめて楽器の一つでもと願いつつも、空しく時間だけが過ぎ去っていきます。何しろ譜面が全く読めませんので。その点、若い方は男女を問わず器用に楽器をこなし歌を楽しんでおられるようですね、うらやましい限りです。3時間ほどの音楽祭、存分に楽しませて頂きました。曲の内容やレベル等はわかりませんが、多くの方々が生活の中に音楽を取り込み、楽しみながら張りのある日常を送っておられる事は充分に了解できました。出演者の方々は、多分、生活習慣病や認知症などとは縁遠いところで生涯を全うされるのではないでしょうか。
何といっても華やかなのは女性合唱団、コスチュームもプロ顔負けです。

例によって名称も存じませんが、ホールへの道すがらに咲き誇っていました。
開演間近で時間も無かったのですが、ついカメラでパチリ。

ラストシーンは全出演者による混声合唱でした。曲目はモルダウの我が祖国より。

ピアノ伴奏者は各合唱団のメンバーからです。

年齢的にはやはりシルバー世代が中心のようです。壮年層は子育て、仕事、転勤、子弟の教育問題等でなかなか地域集団の中へはいり込めないようです。子育てが完了し定年期を迎える頃にようやく自分の時間が見つかるのかも知れませんね。その点、女性軍は地域社会に根が生えてるようで、家事に追われつつも上手にコミニティーを形成しておられるようです。女性合唱団などその典型ではないでしょうか。16組のうち14組が女性合唱団という比率は、こうした社会の実態を如実に証明しているようですね、男性軍頑張って下さい。
出演者中で唯一の男声合唱団。

同じく唯一の混声合唱団です。

声を出して歌うことは脳細胞を活性化するようです。音痴に近い小生には真似が出来ませんが、せめて楽器の一つでもと願いつつも、空しく時間だけが過ぎ去っていきます。何しろ譜面が全く読めませんので。その点、若い方は男女を問わず器用に楽器をこなし歌を楽しんでおられるようですね、うらやましい限りです。3時間ほどの音楽祭、存分に楽しませて頂きました。曲の内容やレベル等はわかりませんが、多くの方々が生活の中に音楽を取り込み、楽しみながら張りのある日常を送っておられる事は充分に了解できました。出演者の方々は、多分、生活習慣病や認知症などとは縁遠いところで生涯を全うされるのではないでしょうか。
何といっても華やかなのは女性合唱団、コスチュームもプロ顔負けです。

例によって名称も存じませんが、ホールへの道すがらに咲き誇っていました。
開演間近で時間も無かったのですが、ついカメラでパチリ。

2010年10月23日
ムラの秋祭り
今年も豊年満作で、村は総出の大祭り、どんどんひゃららどんひゃらら・・・・・・・・こんな歌詞の唱歌を幼い頃に習ったような記憶があるが、いまも歌われているのだろうか。若い人達に文部省唱歌などといったら、何を古くさいと侮蔑されるかも知れないが、日本人の心情と感性にぴったり来るのは少々古くさいとも思えるこうした歌曲ではなかろうか。かって農が社会の基幹産業で集落にコミニティーが存在していた頃は当たり前の風景であったのだろう。集落は存在するもののコミニティーは崩壊し、バラバラとなった個々人が単に同一地域に居住するだけ・・・・・こうした現状であってもどうも祭りは別らしい。
若い衆の勢いが祭りを盛り上げます。流石にパワフル。

喉に自慢の衆はマイク担当、数え歌が延々と続きます。

岸和田市ほどの華やかさはないが、当地も秋祭りは結構賑やかだ。集落が集落たる価値を発揮する唯一の場面かも知れませんね。老若男女、3世代から4世代もの人々が共通の目的に向かって力を合わせ、祭りを運営する。宵宮から始まって延べ3日、実際の準備段階からカウントすれば相当な日数であろう。祭りの準備や運行或いは他の集落との調整や行政や警察との交渉、時によっては酒の上でのトラブル解決など、年長者が年少者に伝えなければならないことは実に多い。祭りはノウハウであり文化でもある。年に一度の秋祭り、人によっては為政者によるガス抜きなどといった穿った見解が無きにしもあらずだが、素直に楽しみましょうや。
こちらは未来の担当者かな、爺様に先導されて。

さあ神様の御前です。パフォーマンスを始めますぞ。

さて当地の秋祭りは例年10月の第三週末、水分神社(スイブンジンジャ)とも呼ばれる建水分神社(タケミクマリジンジャ)への宮入がハイライトである。神社が高台で地車が宮入出来ないので、神様が下手の広場にお移りになるという珍しい形式、金ぴかの御輿に神様が座乗してお移りになる様は圧巻ですぞ。仮安置された神様の前での奉納、許される範囲での派手なデモンストレーションがあって観衆を沸かしてくれます。毎年大勢の観客が祭り見物に参集されるのも、集落毎の演舞を楽しみにしておられるのでしょう。
袖には次の集落が出番を待っていますね。

さあ演舞が始まりました。ある意味集落の対抗合戦ですね。

稲刈りの最中にちょっと抜け出して撮影した数枚の画像、祭りの雰囲気は伝わってますでしょうか。家族の範囲を超えた集落としての大家族、そんな小さなコミニティーが瞬間的ですが出来上がっています。秋祭りを介して集落の人々が一体となれる貴重な行事でしょうね。大事に継承していきたいものです。
宮入を追えた地車は整列して他の集落に御前を明け渡します。

だいぶご祝儀も集まったようですね。飲み過ぎないように。

若い衆の勢いが祭りを盛り上げます。流石にパワフル。

喉に自慢の衆はマイク担当、数え歌が延々と続きます。

岸和田市ほどの華やかさはないが、当地も秋祭りは結構賑やかだ。集落が集落たる価値を発揮する唯一の場面かも知れませんね。老若男女、3世代から4世代もの人々が共通の目的に向かって力を合わせ、祭りを運営する。宵宮から始まって延べ3日、実際の準備段階からカウントすれば相当な日数であろう。祭りの準備や運行或いは他の集落との調整や行政や警察との交渉、時によっては酒の上でのトラブル解決など、年長者が年少者に伝えなければならないことは実に多い。祭りはノウハウであり文化でもある。年に一度の秋祭り、人によっては為政者によるガス抜きなどといった穿った見解が無きにしもあらずだが、素直に楽しみましょうや。
こちらは未来の担当者かな、爺様に先導されて。

さあ神様の御前です。パフォーマンスを始めますぞ。

さて当地の秋祭りは例年10月の第三週末、水分神社(スイブンジンジャ)とも呼ばれる建水分神社(タケミクマリジンジャ)への宮入がハイライトである。神社が高台で地車が宮入出来ないので、神様が下手の広場にお移りになるという珍しい形式、金ぴかの御輿に神様が座乗してお移りになる様は圧巻ですぞ。仮安置された神様の前での奉納、許される範囲での派手なデモンストレーションがあって観衆を沸かしてくれます。毎年大勢の観客が祭り見物に参集されるのも、集落毎の演舞を楽しみにしておられるのでしょう。
袖には次の集落が出番を待っていますね。

さあ演舞が始まりました。ある意味集落の対抗合戦ですね。

稲刈りの最中にちょっと抜け出して撮影した数枚の画像、祭りの雰囲気は伝わってますでしょうか。家族の範囲を超えた集落としての大家族、そんな小さなコミニティーが瞬間的ですが出来上がっています。秋祭りを介して集落の人々が一体となれる貴重な行事でしょうね。大事に継承していきたいものです。
宮入を追えた地車は整列して他の集落に御前を明け渡します。

だいぶご祝儀も集まったようですね。飲み過ぎないように。

2010年07月20日
白蓮の咲く頃
夏休みの頃となりますと訪ねたいのが蓮華の花咲くお寺さん。「蓮華は汚泥の中に咲く」との言葉もありますように、仏教と蓮華とは深い縁に結ばれてるようで、蓮華を栽培するお寺さんは多いようですね。当地では知りうる限りでは二ヶ所ほど存在します。今回訪ねますのは、山中にある曹洞宗のとある寺院。蓮池の美しい所です。年によって多少の相違はありますが、7月の初旬から中旬に咲き始めます。特徴は白蓮であること。真っ白な蓮の花が咲き誇るのは、仏教で言う清浄な世界を意味するようで、何とも心惹かれるものがあります。蓮華は早朝に咲き、昼頃には閉じるとか聞きます。午前中の早めの時間帯が訪問のタイミングでしょうね。
ここは白蓮の里、修行の厳しさで知られる曹洞宗ならばでしょうか。

境内には大きな蓮池がひろがっています。

手持ちのカメラが通常のデジカメで、望遠レンズを準備してなかったのでうまくは撮れてませんが、数枚をアップしておきましょう。おおよその雰囲気は伝わるかと思います。山里に住んでますと、こうした地域の持つ恩恵をフルに享受できる事をとても嬉しく思います。何気ないことですが、地域の方々が丹精こめて守り伝えて来られた物が、有形無形の影響を及ぼし、魂の共鳴を呼び起こしてくれるようです。人間も又自然界の一部、実感としてそう感じさせられますね。
同じ蓮の花でも1個づつ表情が異なってきますね


多少のご恩返しが出来ればと願い、森林ボランティアの世界に身を投じておりますが、まだまだ受ける恩恵の方が大きいようです。「愛は受けるものではなく、与え続けるもの」・・・・・・・・・主人公にそんな台詞を語らせていた作家がおられるようですが、まだまだ届かぬ境地ですね。雨上がりの蓮池、真っ白い白蓮に癒されながら本日も刈払機を握ることとしましょうかな。真夏の最盛期、待ったなしでの雑草の伸び盛りです。
羅漢さんの姿形があまりにも面白かったので、ついパチリ。


ここは白蓮の里、修行の厳しさで知られる曹洞宗ならばでしょうか。

境内には大きな蓮池がひろがっています。

手持ちのカメラが通常のデジカメで、望遠レンズを準備してなかったのでうまくは撮れてませんが、数枚をアップしておきましょう。おおよその雰囲気は伝わるかと思います。山里に住んでますと、こうした地域の持つ恩恵をフルに享受できる事をとても嬉しく思います。何気ないことですが、地域の方々が丹精こめて守り伝えて来られた物が、有形無形の影響を及ぼし、魂の共鳴を呼び起こしてくれるようです。人間も又自然界の一部、実感としてそう感じさせられますね。
同じ蓮の花でも1個づつ表情が異なってきますね


多少のご恩返しが出来ればと願い、森林ボランティアの世界に身を投じておりますが、まだまだ受ける恩恵の方が大きいようです。「愛は受けるものではなく、与え続けるもの」・・・・・・・・・主人公にそんな台詞を語らせていた作家がおられるようですが、まだまだ届かぬ境地ですね。雨上がりの蓮池、真っ白い白蓮に癒されながら本日も刈払機を握ることとしましょうかな。真夏の最盛期、待ったなしでの雑草の伸び盛りです。
羅漢さんの姿形があまりにも面白かったので、ついパチリ。


2010年03月27日
さくら祭りのご案内
今年は暖冬だったのかサクラの咲き具合が早いようですね。当地は例年ですと4月の上旬が先頃ですが、既に咲き始めており、4月にはいれば満開となるのではと思われます。気になるのが入学式、8日~10日頃が多いと思うのですが、ひょっとしたら散ってしまってるのでは・・・・・・・・・・・・子ども達がかわいそうですよね。無論、ヤエザクラは間に合うでしょうが、入学式にはソメイヨシノが定番。サクラ吹雪の下で親子のツウショット、これに勝る記念品はないでしょう。さてサクラが咲き始めると花見の季節、日本人にとって避けては通れぬ風物詩、昔のような陣取り合戦まではいかないでしょうが、彼方此方で宴会が始まりますね。何とも楽しそうで横から眺めているだけでも愉快になります。
当地でも既にサクラが咲き始めました。来週末は最適かも。


当地でも例年4月の最初の土日あたりがさくら祭り、弘川寺周辺での花見大会となります。ここはご存じのとおり、サクラをこよなく愛した西行法師の終焉の地、桜並木の麓で法師は静かに眠っておられます。さくら祭りは、本年は4月3日(土)の開催と決まりました。時間は午前9時半から午後3時まで、会場は弘川寺歴史と文化の森で、駐車場は河内小学校となります。例年、小学校から会場まではシャトルバスが運行されております。車やバスでさくら坂の河内小学校までお出でになり、シャトルバスで会場へというのが一般的なルートでしょう。富田林駅まで電車をご利用頂くと駅前からバスで概ね30分程度の乗車でしょうか。3日(土)は快晴のお天気を願いたいものです。
さくら祭りのご案内です。

当日は、お弁当持参でサクラを愛でながら昼食とされるのがいいかと思います。各種の露店やイベントなども開設されますので、飲食物も入手可能かと思いますが、基本的には商店など存在しない地域です。むしろ何もない田舎の風情を楽しんで頂ければと願っています。元気な方には植樹ツアーも企画されています。少々山の上で1時間ほどのハイキングとなりますが、弘川城趾でのヤマザクラ等の植樹作業です。参加をご希望の方は運動靴や軽登山靴などと歩きやすい服装それに手荷物はリュックの中にが便利かと思います。詳細は河南町役場までお問い合わせ下さい。
いろんなイベントが企画されています。お楽しみ下さい。



たくさんのボランティアが参画した市民参加型のお祭り、無論、里山倶楽部の面々も多数参加しております。現場で機嫌良くはしゃぎ回っている万年青年達(?)が見受けられたら、里山倶楽部のメンバーとご解釈下さい。いちびり(大阪弁で何にでも首を突っ込む嬉しがり屋)の傾向が濃い面々ですので、当人達の方が祭りを楽しんでいるかも知れません。愉快な一日を過ごしたいものです。河南町の山奥まで、是非にお出かけ下さい。野山で心身を解放すれば、明日への活力が生まれるかも知れませんよ。
シロバナタンポポが咲きました。春ですね。

当地でも既にサクラが咲き始めました。来週末は最適かも。


当地でも例年4月の最初の土日あたりがさくら祭り、弘川寺周辺での花見大会となります。ここはご存じのとおり、サクラをこよなく愛した西行法師の終焉の地、桜並木の麓で法師は静かに眠っておられます。さくら祭りは、本年は4月3日(土)の開催と決まりました。時間は午前9時半から午後3時まで、会場は弘川寺歴史と文化の森で、駐車場は河内小学校となります。例年、小学校から会場まではシャトルバスが運行されております。車やバスでさくら坂の河内小学校までお出でになり、シャトルバスで会場へというのが一般的なルートでしょう。富田林駅まで電車をご利用頂くと駅前からバスで概ね30分程度の乗車でしょうか。3日(土)は快晴のお天気を願いたいものです。
さくら祭りのご案内です。

当日は、お弁当持参でサクラを愛でながら昼食とされるのがいいかと思います。各種の露店やイベントなども開設されますので、飲食物も入手可能かと思いますが、基本的には商店など存在しない地域です。むしろ何もない田舎の風情を楽しんで頂ければと願っています。元気な方には植樹ツアーも企画されています。少々山の上で1時間ほどのハイキングとなりますが、弘川城趾でのヤマザクラ等の植樹作業です。参加をご希望の方は運動靴や軽登山靴などと歩きやすい服装それに手荷物はリュックの中にが便利かと思います。詳細は河南町役場までお問い合わせ下さい。
いろんなイベントが企画されています。お楽しみ下さい。



たくさんのボランティアが参画した市民参加型のお祭り、無論、里山倶楽部の面々も多数参加しております。現場で機嫌良くはしゃぎ回っている万年青年達(?)が見受けられたら、里山倶楽部のメンバーとご解釈下さい。いちびり(大阪弁で何にでも首を突っ込む嬉しがり屋)の傾向が濃い面々ですので、当人達の方が祭りを楽しんでいるかも知れません。愉快な一日を過ごしたいものです。河南町の山奥まで、是非にお出かけ下さい。野山で心身を解放すれば、明日への活力が生まれるかも知れませんよ。
シロバナタンポポが咲きました。春ですね。

2010年03月14日
寺内町のひな祭り
富田林の駅前付近に広がる寺内町、ここは戦国時代に作られた宗教都市の面影を持つ街並みである。石川の河川敷周辺に広がっていた荒れ地を、興正寺別院という浄土真宗の寺院の為に開発されたのが発端のようだ。以来、織豊時代を通じて自治を誇っていたが、幕藩期には通常の市街地として体制に組み込まれたようです。この街、なかなかに趣があって散策に適した場所なんですが、古民家が保存されていること、街並み景観に皆で尽力されていること、イベント開催で街に人を集めておられること・・・・・・・そうした努力が報われて、年々歳々来訪客が増加しているようです。
子ども達の手作りひな人形です。市販品よりも優れた出来映え?

寺内町の街並み。板塀と格子戸の家並みが続きます。

今月はひな祭りの季節、無論、寺内町もひな祭りイベントが開催されました。ここのひな祭りの特徴は街をあげてのお祭りで、各戸のひな人形を玄関先に並べ、扉をあけておいて自由に参観させてくれるところにあります。ご近所の方は勿論、観光客も気軽に出入りして、伝統の或いは手作りのひな人形を眺めさせていただきます。何とも愉快なシステムです。街並みは板塀や格子戸が続き、江戸時代にでもトリップしたかのような雰囲気で、ひな祭りをいやが上にも盛り上げます。そこかしこには露店等が開かれ、地元の名品や甘酒、弁当、或いは農産物等も並んでいます。さながら朝市の開催とでもいった趣向でしょうか。
民家の玄関先にひな人形の陳列が。どなたにもオープンで。

自由に参観できます。

街並みを散策してますと、トモロス仲間のMtさんご夫妻に遭遇しました。自宅から歩いて来られたとか、そう言えば彼は富田林の在住でした。他市からの転入組なので、地元のお祭りでも物珍しいのでしょう。南河内の伝統と風物を楽しんでいただきたいものです。歩きついでに立ち寄ったのが「紅梅蔵」との名称が付いた、蔵を改造した複合ショップ。何でも古民家を数グループで借り受け、改装して中を細かく仕切って店舗としたようです。農産物やドライフラワー或いはスープやパン、それに団扇や染め物なども並んでいます。お店としての統一感はありませんが、ミニグループのアンテナショップ的な運営でしょうか。地域には空き家が多いそうなので、こうした外部からの進出組も大歓迎なのでしょう。
グループの出店街「紅梅蔵」、古民家の改装のようです。

店内内部のインテリアはこんな感じで。

公園では餅つきも実施されてました。どうやら草餅を作って販売するようです。ぜんざいや汁粉おかきに団子など甘党好みの品々も多数用意されてました。ここの特徴は幼稚園や小学校の子ども達が作った手作り雛の展示、何とも言えぬ愛らしさで市販品とは違った趣です。伝統あるひな人形もよろしいが、子ども達の簡素な手作りひなには捨てがたい味がありますね。少々の小雨がパラつきましたが、客足は衰えず、このイベントもすっかり定着したようです。聞くところによりますと、まだ4回目の開催だとか。
公園ではモモの花が満開でした。

つきたての草餅、美味しそうですね。

幼稚園の子ども達が作ったひな人形です。

寺内町で忘れられない人物は石上露子(いそのかみつゆこ)でしょう。明星派の歌人で、与謝野晶子や鉄幹等と同時期に活躍したようです。寺内町の造り酒屋の娘さんで本名を杉山孝と言ったそうですが、生家が今も現存しています。有料ですが公開されてますので関心をお持ちの方はお訪ねになってみて下さい。もう一点が興正寺別院で浄土真宗のお寺さんです。寺内町はここを中心に発展した街で、いわばシンボル的な存在でしょう。本日は門前にひな人形が飾ってありました。織豊期の石山本願寺攻めには本願寺派に所属せず、中立を保って織田信長から安堵状を貰ったとか。時代の趨勢を読んだ戦略眼があったのか、個別の事情なのかは不明ですが、なかなかの動きのようです。
郷土の歌人、石上露子の紹介です。

子ども達の手作りひな人形です。市販品よりも優れた出来映え?

寺内町の街並み。板塀と格子戸の家並みが続きます。

今月はひな祭りの季節、無論、寺内町もひな祭りイベントが開催されました。ここのひな祭りの特徴は街をあげてのお祭りで、各戸のひな人形を玄関先に並べ、扉をあけておいて自由に参観させてくれるところにあります。ご近所の方は勿論、観光客も気軽に出入りして、伝統の或いは手作りのひな人形を眺めさせていただきます。何とも愉快なシステムです。街並みは板塀や格子戸が続き、江戸時代にでもトリップしたかのような雰囲気で、ひな祭りをいやが上にも盛り上げます。そこかしこには露店等が開かれ、地元の名品や甘酒、弁当、或いは農産物等も並んでいます。さながら朝市の開催とでもいった趣向でしょうか。
民家の玄関先にひな人形の陳列が。どなたにもオープンで。

自由に参観できます。

街並みを散策してますと、トモロス仲間のMtさんご夫妻に遭遇しました。自宅から歩いて来られたとか、そう言えば彼は富田林の在住でした。他市からの転入組なので、地元のお祭りでも物珍しいのでしょう。南河内の伝統と風物を楽しんでいただきたいものです。歩きついでに立ち寄ったのが「紅梅蔵」との名称が付いた、蔵を改造した複合ショップ。何でも古民家を数グループで借り受け、改装して中を細かく仕切って店舗としたようです。農産物やドライフラワー或いはスープやパン、それに団扇や染め物なども並んでいます。お店としての統一感はありませんが、ミニグループのアンテナショップ的な運営でしょうか。地域には空き家が多いそうなので、こうした外部からの進出組も大歓迎なのでしょう。
グループの出店街「紅梅蔵」、古民家の改装のようです。

店内内部のインテリアはこんな感じで。

公園では餅つきも実施されてました。どうやら草餅を作って販売するようです。ぜんざいや汁粉おかきに団子など甘党好みの品々も多数用意されてました。ここの特徴は幼稚園や小学校の子ども達が作った手作り雛の展示、何とも言えぬ愛らしさで市販品とは違った趣です。伝統あるひな人形もよろしいが、子ども達の簡素な手作りひなには捨てがたい味がありますね。少々の小雨がパラつきましたが、客足は衰えず、このイベントもすっかり定着したようです。聞くところによりますと、まだ4回目の開催だとか。
公園ではモモの花が満開でした。

つきたての草餅、美味しそうですね。

幼稚園の子ども達が作ったひな人形です。

寺内町で忘れられない人物は石上露子(いそのかみつゆこ)でしょう。明星派の歌人で、与謝野晶子や鉄幹等と同時期に活躍したようです。寺内町の造り酒屋の娘さんで本名を杉山孝と言ったそうですが、生家が今も現存しています。有料ですが公開されてますので関心をお持ちの方はお訪ねになってみて下さい。もう一点が興正寺別院で浄土真宗のお寺さんです。寺内町はここを中心に発展した街で、いわばシンボル的な存在でしょう。本日は門前にひな人形が飾ってありました。織豊期の石山本願寺攻めには本願寺派に所属せず、中立を保って織田信長から安堵状を貰ったとか。時代の趨勢を読んだ戦略眼があったのか、個別の事情なのかは不明ですが、なかなかの動きのようです。
郷土の歌人、石上露子の紹介です。

2010年02月04日
お寺さんの節分
本日は立春いわば新年元旦に相当する日付けでもありますね。その前日即ち大晦日に当たるのが節分のようで、節目の日でもあります。鬼は外の行事でも有名ですよね。当地でも様々な趣向で節分の行事が執り行われた来ましたが、最近はちと下火のようです。当地でも、かっては門柱に柊と鰯の供えが飾り付けてありましたが、近年はさっぱりと見なくなりました。伝統的な行事が消えていくのは寂しいものです。生活の中から季節感が失われ、ハウス栽培の食品や冷凍食品などで日常生活が営まれ、旬の産物に感謝と驚きが無くなったせいかも知れませんね。食生活の重要性が改めて再認識されます。
ここは信仰の場、やはり敬虔な祈りが餅まきよりも先のようです。

節分星祭りと命名された一大イベントです。

さて節分ですが、当地のとある古刹では毎年星祭りと称して節分行事が実施されます。ご祈祷や福豆の授与が中心ですが、豆まきや餅まきの行事もあり、近在の方々の楽しみでもあります。無論、物見高い小生が見逃すはずもなく毎年参加して多少のお裾分けに預かっております。昨年は雨天で参加者も少なく、小生の戦利品も多かったのですが、今年は晴天に恵まれた故か競争厳しく僅かな収穫に留まりました。餅には番号の記された物もあり、別途記念品が出るようですが、今だかって該当した試しがありません。クジ運はあまり良くないようですね。余計な話はその程度にしまして、参拝された皆様の状況を覗いてまいりましょう。
櫓の上は地域の有力者や檀家の役員さんでしょう、餅まき当番です。

こっちへ投げて・・・・・・おばさまの黄色い声も届いたかどうか。

メインディッシュならぬイベントはやはり豆まき・餅まきでありましょう。紅白に包まれた櫓の上から、鬼は外、のかけ声と共に豆や餅が降ってきます。押し合いへし合いの争奪戦で、年配の方など圧死の可能性すら感じるほど、小さな子どもさんは遠慮した方が良さそうです。土足で踏まれた餅や袋の破れた豆を押し合いながらむしり取ります。弱肉強食の世界かな。カメラ片手に走り回りましたが収穫品は4個の餅のみでした。福豆の授与は大変な行列で、並ぶのが嫌な小生は最初からギブアップ、これまた福引き付きのようで福豆と他の景品とを抱えたおばさま方がニンマリした表情で引き上げて行かれます。でかい布団類があたって四苦八苦しながら車まで運んでおられる御仁も、お寺さんもなかなか商売上手なようです。
福引き付きの福豆の授与です、大変な行列で頂くのは諦めました。

お寺さんといえばやはり信仰の場、ご祈祷を依頼される方も多いようです。30分単位で実施されてるようで、こちらも行列でした。祈祷まではいかない方も、お賽銭をあげ鈴を鳴らしながら静かに祈っておられます。何だかんだと言ってもDNAの中には神仏への帰依の精神が残っているのかも知れませんね。お寺に来ると線香とローソクが定番のようですが、これまた不思議と人の心を落ち着かせる作用があるようです。あまり信仰心も持っていない小生ですら、線香の煙に包まれますと神妙な面持ちになって両手を合わせてしまいます。不思議な現象です。
お寺さんではここの雰囲気が一番ですね、癒されます。

節分となれば何故か太巻きの寿司となりますね。大阪が発祥の地らしいのですが、バレンタインのチョコレートと同じで商魂逞しき知恵者がおられたのでしょう。私宅でも太巻きに鰯が食卓に上りました。生け垣全部が柊なので、あえて柊まで食卓には載せませんが、鬼にとっては嫌な家でしょうね。もっともこの場合の鬼は邪気を指すようで、季節の変わり目だから体調の激変に留意しなさいとの警告の意味なんでしょう。先人達の智慧を大事に伝え残したいものです。
屋台の定番はこれでしょうね、白い鯛焼きが人気らしいですが。

椿専門の苗木屋さんのようです。春近しの感ですね。

ここは信仰の場、やはり敬虔な祈りが餅まきよりも先のようです。

節分星祭りと命名された一大イベントです。

さて節分ですが、当地のとある古刹では毎年星祭りと称して節分行事が実施されます。ご祈祷や福豆の授与が中心ですが、豆まきや餅まきの行事もあり、近在の方々の楽しみでもあります。無論、物見高い小生が見逃すはずもなく毎年参加して多少のお裾分けに預かっております。昨年は雨天で参加者も少なく、小生の戦利品も多かったのですが、今年は晴天に恵まれた故か競争厳しく僅かな収穫に留まりました。餅には番号の記された物もあり、別途記念品が出るようですが、今だかって該当した試しがありません。クジ運はあまり良くないようですね。余計な話はその程度にしまして、参拝された皆様の状況を覗いてまいりましょう。
櫓の上は地域の有力者や檀家の役員さんでしょう、餅まき当番です。

こっちへ投げて・・・・・・おばさまの黄色い声も届いたかどうか。

メインディッシュならぬイベントはやはり豆まき・餅まきでありましょう。紅白に包まれた櫓の上から、鬼は外、のかけ声と共に豆や餅が降ってきます。押し合いへし合いの争奪戦で、年配の方など圧死の可能性すら感じるほど、小さな子どもさんは遠慮した方が良さそうです。土足で踏まれた餅や袋の破れた豆を押し合いながらむしり取ります。弱肉強食の世界かな。カメラ片手に走り回りましたが収穫品は4個の餅のみでした。福豆の授与は大変な行列で、並ぶのが嫌な小生は最初からギブアップ、これまた福引き付きのようで福豆と他の景品とを抱えたおばさま方がニンマリした表情で引き上げて行かれます。でかい布団類があたって四苦八苦しながら車まで運んでおられる御仁も、お寺さんもなかなか商売上手なようです。
福引き付きの福豆の授与です、大変な行列で頂くのは諦めました。

お寺さんといえばやはり信仰の場、ご祈祷を依頼される方も多いようです。30分単位で実施されてるようで、こちらも行列でした。祈祷まではいかない方も、お賽銭をあげ鈴を鳴らしながら静かに祈っておられます。何だかんだと言ってもDNAの中には神仏への帰依の精神が残っているのかも知れませんね。お寺に来ると線香とローソクが定番のようですが、これまた不思議と人の心を落ち着かせる作用があるようです。あまり信仰心も持っていない小生ですら、線香の煙に包まれますと神妙な面持ちになって両手を合わせてしまいます。不思議な現象です。
お寺さんではここの雰囲気が一番ですね、癒されます。

節分となれば何故か太巻きの寿司となりますね。大阪が発祥の地らしいのですが、バレンタインのチョコレートと同じで商魂逞しき知恵者がおられたのでしょう。私宅でも太巻きに鰯が食卓に上りました。生け垣全部が柊なので、あえて柊まで食卓には載せませんが、鬼にとっては嫌な家でしょうね。もっともこの場合の鬼は邪気を指すようで、季節の変わり目だから体調の激変に留意しなさいとの警告の意味なんでしょう。先人達の智慧を大事に伝え残したいものです。
屋台の定番はこれでしょうね、白い鯛焼きが人気らしいですが。

椿専門の苗木屋さんのようです。春近しの感ですね。

2010年01月26日
確定申告の季節
どうやら頭の痛い季節がやってきたようです。私宅にも召集令状がまいりました。例の、昨年中の収入と必要経費等を申告しなさいという・・・・・・・・・・・・・・・・・いつもの奴ですね。余計な話ですがUSAでパソコンが大量に販売されるのは、大半が確定申告用だそうです。聞くところによりますと、彼の地では源泉徴収などどいった便利な(課税当局にとって)システムは存在しないようで、時期になると全国民が一斉にパソコンに向かうようですね。最もその方が納税の意義が掴みやすく、使途についても厳しい視線を持てるようです。我が国では税を納めるという発想は少ないようで、大半が取られるという発想ですよね。原因は源泉徴収のシステムにあるのではないでしょうか。
当地のお代官所、富田林税務署です。リフォームのようですね。


企業に所属してますと会社の経理課等で全てを代行してくれ、殆どのビジネスマンにとって確定申告などご縁のない存在でしょう。だがひとたび組織を離れてフリーランスとなりますと、終生この義務がついて回ります。練習の意味で年末調整を断って、この時期に確定申告を為さってみるのもいい経験かと思います。小生も最初は戸惑いましたが、毎年続けてますとそれなりに習熟してまいります。まあっ、記載項目が少ないということもありましょうが、短時間で仕上げられます。最近はインターネットを使用して電子申告とかも流行のようですが、遠くなければ代官所(税務署)まで出頭するのが早道でしょう。資料を準備して出向けば記載の方法なども丁寧に教授して頂けます。最近の代官所は対応もソフトで怖がる必要はないようです。
我々のように何が本業かわからぬ不逞の輩は雑所得となるようです。

さて仕上げた申告書を早速に提出してきました。時期的に早いと言うこともあって、そう混雑もしてないようです。3月の15日が締め切りのようですが、遅くなるほど混雑するようです。何でも先手必勝、早めの申告が気分的にも落ち着きますし、間違いがあっても余裕で修正申告が可能です。税務署では受け付けるだけで、審査は後日となるようです。おかげさまで最近はフリーパス、申告通りでOKとなっています。
届きました召集令状、電子申告のお勧めも同封されてました。

この税金で思い出しますのは、トップの鳩山さん。毎月母親から1500万の子ども手当を頂きながら無申告。誰がどう考えても贈与税の対象ですよね、知らぬ存ぜぬでほおかぶりしておられたようだが、結果的には世論に押されて修正申告だとか。無申告加算税や延滞金等は附帯するにしても、トップがこの有り様では、バレなければ何をやってもOKなんだという風潮を国民に植え付けて仕舞ったようです。右へ習え・・・・・・・・・上の振り見て我が身を直せでしょうか。反面教師ではなく、良いお手本をお示しいただいたようです。今年から贈与税の申告書がぐっと減少するのではないでしょうか。
どうやら申告相談は別会場のようですね、申告書は税務署で受理のようです。

当地のお代官所、富田林税務署です。リフォームのようですね。


企業に所属してますと会社の経理課等で全てを代行してくれ、殆どのビジネスマンにとって確定申告などご縁のない存在でしょう。だがひとたび組織を離れてフリーランスとなりますと、終生この義務がついて回ります。練習の意味で年末調整を断って、この時期に確定申告を為さってみるのもいい経験かと思います。小生も最初は戸惑いましたが、毎年続けてますとそれなりに習熟してまいります。まあっ、記載項目が少ないということもありましょうが、短時間で仕上げられます。最近はインターネットを使用して電子申告とかも流行のようですが、遠くなければ代官所(税務署)まで出頭するのが早道でしょう。資料を準備して出向けば記載の方法なども丁寧に教授して頂けます。最近の代官所は対応もソフトで怖がる必要はないようです。
我々のように何が本業かわからぬ不逞の輩は雑所得となるようです。

さて仕上げた申告書を早速に提出してきました。時期的に早いと言うこともあって、そう混雑もしてないようです。3月の15日が締め切りのようですが、遅くなるほど混雑するようです。何でも先手必勝、早めの申告が気分的にも落ち着きますし、間違いがあっても余裕で修正申告が可能です。税務署では受け付けるだけで、審査は後日となるようです。おかげさまで最近はフリーパス、申告通りでOKとなっています。
届きました召集令状、電子申告のお勧めも同封されてました。

この税金で思い出しますのは、トップの鳩山さん。毎月母親から1500万の子ども手当を頂きながら無申告。誰がどう考えても贈与税の対象ですよね、知らぬ存ぜぬでほおかぶりしておられたようだが、結果的には世論に押されて修正申告だとか。無申告加算税や延滞金等は附帯するにしても、トップがこの有り様では、バレなければ何をやってもOKなんだという風潮を国民に植え付けて仕舞ったようです。右へ習え・・・・・・・・・上の振り見て我が身を直せでしょうか。反面教師ではなく、良いお手本をお示しいただいたようです。今年から贈与税の申告書がぐっと減少するのではないでしょうか。
どうやら申告相談は別会場のようですね、申告書は税務署で受理のようです。

2010年01月10日
えべっさん信仰
大阪ではえべっさん信仰が夙に名高い。代表格が今宮戎であろう。毎年1月10日前後に祭礼が行われ、大層な人出で賑わう。季節の風物詩でもあるようだ。えべっさんは調べてみると、本来は海の神様、漁業の神様であるようだ。一説によると、「えびす」とは異邦人のことを指し、外来の神との暗示的な意味も込められているようだ。大阪は商都、それがどうして漁業の神であるえべっさん信仰と結びつくのか不思議な現象だが、オオサカジンに於いては商売繁盛の神様との位置づけのようだ。ニュースを見ていると今宮戎神社で笹をいただき、ここに各種の吉兆と呼ばれる飾り物を付けて持ち帰り、神棚に祭っておくと運気が高まるそうな。まさに商売繁盛、笹もってこいこい・・・・・・・・・・であろう。
当地のえべっさん、出合戎です。笹のシンボルは同じですね。


もうひとつ不可解なのが当地のえべっさん、地元地千早赤阪村のとある地区にえべっさんが祭られており、同様に1月10日前後に祭礼が実施される。村は、別称「小さな絵本のような村」とも称されるように、純山村といった雰囲気の自治体である。当然、商店街など無きに等しく、商売に携わる方々など微々たるものであろう。無論、漁業とは縁もゆかりもない存在だ。地域の方がどうしてえべっさんを祭られるのか地元の方に問うてみたが要領を得なかった。楠公さんの時代から続いてるで・・・・・・古老の証言である。あえて推理の世界に飛んでみれば、かの楠公さんは現在で言う流通業・運送業に従事されていたとか、業の繁栄を願われたのだろうか。当地のえべっさんは楠公さんの産まれ在所に鎮座しておられる。
えべっさんの神殿です、簡素な作りが微笑ましいですね。

社務所では福引きが実施されてました。1等賞も出たようで。

さて物見高い小生のこと、早速にえべっさんを訪ねてみる。無論、本場の今宮戎のように大勢の参拝者が押しかけるような超名所ではない。地元の限られた人々がひっそりと信仰を守っておられる・・・・・・・・そんな印象であろうか。余所者の参拝は小生位なものであろう。ジジババと思しき方々が孫の手を引いて参拝に、というのが一般的なパターン。本職の神職はおられないようで、諸役も氏子さん達がお勤めのようだ。どことなく隠れキリシタン的な雰囲気が漂って、小生にとっては興味津々。地元の方には恐縮だが、かっこうの被写体でもある。さすがに正面切ってレンズを向けることは叶わないのだが。
所在地は楠公さんの産まれ在所のほん近くです。

孫の手を引いて続々と参拝に。ジジババ冥利に尽きるのでしょう。

どうも端から見てると、当地のえべっさんは地域の親睦会的な役割も果たしておられるようだ。まず参拝者が地域の人々に限定されるようで他地域の方は見かけないようだ。それに笹の授与と吉兆の販売は無いようだが、代わりに福引きを実施しておられた。多分事前に抽選券等が配布されているのだろう。役職者と参拝者は顔なじみの方々ばかりのようで、どう見ても集落固有の限られた祭礼のようだ。祭礼の根拠やいわれなど定かではないが、集落の方々が親睦を深め複数世代が共に楽しめる場が存在することは素晴らしいことであろう。山村の小さな集落のえべっさんにエールを贈りたいと思う。
軽トラ屋台が1台だけ出張っていました。いじらしいですね。

当地のえべっさん、出合戎です。笹のシンボルは同じですね。


もうひとつ不可解なのが当地のえべっさん、地元地千早赤阪村のとある地区にえべっさんが祭られており、同様に1月10日前後に祭礼が実施される。村は、別称「小さな絵本のような村」とも称されるように、純山村といった雰囲気の自治体である。当然、商店街など無きに等しく、商売に携わる方々など微々たるものであろう。無論、漁業とは縁もゆかりもない存在だ。地域の方がどうしてえべっさんを祭られるのか地元の方に問うてみたが要領を得なかった。楠公さんの時代から続いてるで・・・・・・古老の証言である。あえて推理の世界に飛んでみれば、かの楠公さんは現在で言う流通業・運送業に従事されていたとか、業の繁栄を願われたのだろうか。当地のえべっさんは楠公さんの産まれ在所に鎮座しておられる。
えべっさんの神殿です、簡素な作りが微笑ましいですね。

社務所では福引きが実施されてました。1等賞も出たようで。

さて物見高い小生のこと、早速にえべっさんを訪ねてみる。無論、本場の今宮戎のように大勢の参拝者が押しかけるような超名所ではない。地元の限られた人々がひっそりと信仰を守っておられる・・・・・・・・そんな印象であろうか。余所者の参拝は小生位なものであろう。ジジババと思しき方々が孫の手を引いて参拝に、というのが一般的なパターン。本職の神職はおられないようで、諸役も氏子さん達がお勤めのようだ。どことなく隠れキリシタン的な雰囲気が漂って、小生にとっては興味津々。地元の方には恐縮だが、かっこうの被写体でもある。さすがに正面切ってレンズを向けることは叶わないのだが。
所在地は楠公さんの産まれ在所のほん近くです。

孫の手を引いて続々と参拝に。ジジババ冥利に尽きるのでしょう。

どうも端から見てると、当地のえべっさんは地域の親睦会的な役割も果たしておられるようだ。まず参拝者が地域の人々に限定されるようで他地域の方は見かけないようだ。それに笹の授与と吉兆の販売は無いようだが、代わりに福引きを実施しておられた。多分事前に抽選券等が配布されているのだろう。役職者と参拝者は顔なじみの方々ばかりのようで、どう見ても集落固有の限られた祭礼のようだ。祭礼の根拠やいわれなど定かではないが、集落の方々が親睦を深め複数世代が共に楽しめる場が存在することは素晴らしいことであろう。山村の小さな集落のえべっさんにエールを贈りたいと思う。
軽トラ屋台が1台だけ出張っていました。いじらしいですね。

2010年01月06日
餅と雑煮
正月の松の内と言えば餅と雑煮について触れておかねばならないでしょうね。かといって特別な蘊蓄などあろうはずもないのですが、そこはそれ何とかの横好きとか申しまして・・・・・・・・・。餅ないしは餅に似た食物は我が国の専売特許ではなくして、東南アジア各国にも見られるようです。稲作文化がベースになっているのでしょう。国によって作り方や食べ方は異なっているようですが、我が国はつく文化ですね。練った餅はあまり見られないようです。臼と杵を使った伝統的手法、最近は電化製品の餅つき器でしょうか。手間暇を厭わなければ臼と杵を使用しての餅作りをお勧めします。食感や餅の風味やのどごし等が微妙に異なるようですね。我々もこだわる訳ではありませんが、自家栽培の餅米を臼と杵を使ってつきあげています。純日本風の餅作りです。
関西より以西は丸餅が主体のようです。

長老の叱咤激励の下に丸餅を作り上げます。

さてこの餅、かってはハレの日の特別な食物だったようです。それがいつしか日常食へと変化し、最近ですと年中販売されていますね。ただ独断と偏見に基づきますと、どうも米粉を練って固めた餅もどきのような気がするんですが・・・・・・・・・・。腹持ちがいいし軽いしで軍事用の携行食とししても活用されたようです。山登りの予備食としても利用できそうですね。正月ですと、お雑煮がもっぱらでしょうか。この雑煮も地域によって作り方が異なっており、お国柄が忍ばれます。下記に画像をアップしておきますが私宅の雑煮です。山の神が九州の僻村出身なので在所の風習を引き継いだものでしょう。いわゆるすまし風というのでしょうか、煮干しや鰹節で出汁を取り醤油で味付け、餅とかまぼこと野菜が少々といった作りです。当地の大阪は味噌仕立てが大半のようですね。
私宅の雑煮です、ルーツは九州の山深い僻村。

小生も餅は好物で、昼食など餅数個で代用してしまう程です。ふっくらと焼き上げて砂糖醤油で戴くと至福の一瞬となります。典型的な日本人かも知れませんね、ご飯と餅が主食のようですから。うるち米よりも餅米をたくさん作る方が私宅にとってはありがたいかな。餅の形状も関西と関東とでは異なるようですね。関西から西は丸餅が主、関東以北は角餅が主と聞きましたが相違はないでしょうか。当地には猫餅という方式もあって、丸餅文化ながら角張った餅も食されています。お隣の中国ではちまきが餅に相当するんでしょうかね。丸こい餅みたいな物が中華料理にはありますが、素材は餅米ではないようですね。
当地の餅作り、いわゆる猫餅です。2~3日後にカットします。

子どもの頃は、あんこ餅、きなこ餅、かき餅、よもぎ餅等々バリエーションも豊富に作られて賞味してましたが、最近は普通の丸餅を砂糖醤油味というのが大半です。まれに栃餅やわらび餅等を戴くこともありますが、シンプルなのが一番なようです。変わったところでは東北のずんだ餅或いは信州の五平餅でしょうか。信州には出かけることも多いので、五平餅はしばしば頂きます。これは餅米ではなくうるち米を練って固めて味噌味に仕上げた物のようですね、結構な美味です。こんな事を書いてますと、信州に出かけたくなってきますね、真っ白な雪景色の風景かと思いますが。
焼き餅はシンプルですが一番美味なようです。

関西より以西は丸餅が主体のようです。

長老の叱咤激励の下に丸餅を作り上げます。

さてこの餅、かってはハレの日の特別な食物だったようです。それがいつしか日常食へと変化し、最近ですと年中販売されていますね。ただ独断と偏見に基づきますと、どうも米粉を練って固めた餅もどきのような気がするんですが・・・・・・・・・・。腹持ちがいいし軽いしで軍事用の携行食とししても活用されたようです。山登りの予備食としても利用できそうですね。正月ですと、お雑煮がもっぱらでしょうか。この雑煮も地域によって作り方が異なっており、お国柄が忍ばれます。下記に画像をアップしておきますが私宅の雑煮です。山の神が九州の僻村出身なので在所の風習を引き継いだものでしょう。いわゆるすまし風というのでしょうか、煮干しや鰹節で出汁を取り醤油で味付け、餅とかまぼこと野菜が少々といった作りです。当地の大阪は味噌仕立てが大半のようですね。
私宅の雑煮です、ルーツは九州の山深い僻村。

小生も餅は好物で、昼食など餅数個で代用してしまう程です。ふっくらと焼き上げて砂糖醤油で戴くと至福の一瞬となります。典型的な日本人かも知れませんね、ご飯と餅が主食のようですから。うるち米よりも餅米をたくさん作る方が私宅にとってはありがたいかな。餅の形状も関西と関東とでは異なるようですね。関西から西は丸餅が主、関東以北は角餅が主と聞きましたが相違はないでしょうか。当地には猫餅という方式もあって、丸餅文化ながら角張った餅も食されています。お隣の中国ではちまきが餅に相当するんでしょうかね。丸こい餅みたいな物が中華料理にはありますが、素材は餅米ではないようですね。
当地の餅作り、いわゆる猫餅です。2~3日後にカットします。

子どもの頃は、あんこ餅、きなこ餅、かき餅、よもぎ餅等々バリエーションも豊富に作られて賞味してましたが、最近は普通の丸餅を砂糖醤油味というのが大半です。まれに栃餅やわらび餅等を戴くこともありますが、シンプルなのが一番なようです。変わったところでは東北のずんだ餅或いは信州の五平餅でしょうか。信州には出かけることも多いので、五平餅はしばしば頂きます。これは餅米ではなくうるち米を練って固めて味噌味に仕上げた物のようですね、結構な美味です。こんな事を書いてますと、信州に出かけたくなってきますね、真っ白な雪景色の風景かと思いますが。
焼き餅はシンプルですが一番美味なようです。

2009年12月31日
年の終わりに
早いものですね。平成21年も余すところ19時間程になってしまいました。「少年老い易く学なり難し、一寸の光陰軽んずべからず」・・・・・・先人の貴重な遺産なのですが、どうも言葉を記憶するのみで実践が伴わないようす。この1年間を振り返っても、さていかほどの成長ありしやと問われれば赤面するしかないでしょう。許された持ち時間も残り僅かとなっておりますのに、この有り様では閻魔大王に追い返されるかも知れませんね。修行が足りぬぞよ・・・・・そんな言葉で追い出され、チューブを繋がれたベッドの上で断末魔の苦しみに喘ぎながらのたうち回るのではないだろうか。いやはや。
当地のスイセンの里です。既に咲き始めています。

咲き始めですがどうやら満開の風情ですね。何度でも咲くのかな。

多少の懺悔の気持ちもあって、白く清純なスイセンの里を訪ねて見ました。毎年この季節には訪問するうに心がけています。スイセンは基本的には2月の花、但し生命力が強いのか年末から咲き始めますね。そして春先まで延々と咲き続けてくれるようです。スイセンと言えば西国では越前海岸や淡路島が夙に有名ですが、何、知られてないだけで当地にも名所があります。小さな絵本のような村、千早赤阪村の二河原辺地区にあります奉建塔の周辺です。休耕地を活用してスイセンを植え込んであるようで、シーズンともなれば多くのカメラマンで賑わいます。さすがに年末では訪問者もなく、小生の独り占め。のんびりと散策しながら何枚かの画像を納めました。
中央部の柱が目障りですが、傾斜地の斜面を旨く活用しています。

階段の上部が楠公さんの奉建塔です。是非お訪ねを。

あまり重視されてないようですが、スイセンには毒性があるそうです。所属が彼岸花科と言えばご想像いただけるでしょうか。最も、毒を有するのは球根部のようで、間違って食用としない限り大丈夫のようです。花が咲いてる時は一目瞭然ですが、茎のみなら場合によってはニラやノビルなどと間違え兼ねないですね。山菜取りの折にはご注意を。ここは楠公さんの出自の場所でもあり、近隣には楠公さん関係の名所旧跡が多々存在します。ただ何分にも歴史が古く、形ある物としては遺産が少ないだけに想像力と洞察力とが要求されます。山間部で少々冷え込みますが、正月休みにでもお訪ねされたらいかがでしょうか。米軍の占領政策の故か近隣諸国のプロパガンダの故か歪んだ教育の故かは知りませんが、日本と日本人の解体が見事な程に進捗しているようです。ここ半世紀ほどの間に全く異質な日本人に変身してしまったかのようですね。新春、奉建塔を訪ねられて刻まれた楠公さんの言葉「非理法権天」の文字を熟読・吟味されるのもお勧めかと思いますが。
トトロの住む森のようですね。宮崎駿氏が当地に来訪されたかは不明ですが。

当地のスイセンの里です。既に咲き始めています。

咲き始めですがどうやら満開の風情ですね。何度でも咲くのかな。

多少の懺悔の気持ちもあって、白く清純なスイセンの里を訪ねて見ました。毎年この季節には訪問するうに心がけています。スイセンは基本的には2月の花、但し生命力が強いのか年末から咲き始めますね。そして春先まで延々と咲き続けてくれるようです。スイセンと言えば西国では越前海岸や淡路島が夙に有名ですが、何、知られてないだけで当地にも名所があります。小さな絵本のような村、千早赤阪村の二河原辺地区にあります奉建塔の周辺です。休耕地を活用してスイセンを植え込んであるようで、シーズンともなれば多くのカメラマンで賑わいます。さすがに年末では訪問者もなく、小生の独り占め。のんびりと散策しながら何枚かの画像を納めました。
中央部の柱が目障りですが、傾斜地の斜面を旨く活用しています。

階段の上部が楠公さんの奉建塔です。是非お訪ねを。

あまり重視されてないようですが、スイセンには毒性があるそうです。所属が彼岸花科と言えばご想像いただけるでしょうか。最も、毒を有するのは球根部のようで、間違って食用としない限り大丈夫のようです。花が咲いてる時は一目瞭然ですが、茎のみなら場合によってはニラやノビルなどと間違え兼ねないですね。山菜取りの折にはご注意を。ここは楠公さんの出自の場所でもあり、近隣には楠公さん関係の名所旧跡が多々存在します。ただ何分にも歴史が古く、形ある物としては遺産が少ないだけに想像力と洞察力とが要求されます。山間部で少々冷え込みますが、正月休みにでもお訪ねされたらいかがでしょうか。米軍の占領政策の故か近隣諸国のプロパガンダの故か歪んだ教育の故かは知りませんが、日本と日本人の解体が見事な程に進捗しているようです。ここ半世紀ほどの間に全く異質な日本人に変身してしまったかのようですね。新春、奉建塔を訪ねられて刻まれた楠公さんの言葉「非理法権天」の文字を熟読・吟味されるのもお勧めかと思いますが。
トトロの住む森のようですね。宮崎駿氏が当地に来訪されたかは不明ですが。

2009年12月30日
餅つき大会
不安だった時間配分も何とか調整がつき、朝から参加できることに。昨日の不参加の分も取り返さなければならない。いさんで会場の山城へと車を走らせる。さすがにリーダーのU氏は到着済みで、既に湯が沸騰している状態、旧海軍の5分前主義どころではないようだ。他のメンバーとも分担しながら、水汲みや餅米の準備或いはたき火の火おこし等を進めていく。心なしか餅米の蒸れ上がるスピードが少々遅いようだ。どうも蒸し器が借り物ばかりで、微妙にサイズが異なってるようで蒸気の回りが不自然な模様。時間が掛かりそうな嫌な予感がしますね。それでも次第に蒸れ上がってくるので、餅つきが始まった。普段使わぬ筋肉を使用するからか、単に体力不足なのか、簡単にギブアップする御仁も。
先陣を切るのは仲良し三人組、腰が痛いとぼやくのはどなた。

見事な餅がつきあがりました。丸餅の作成ですね。

餅をついたら食べたくなるのが人間の心情、始めの仕上がり分は試食用に回ってしまう。つきたてだけに絶妙なおいしさで、小生も思わず3個ほどを平らげてしまった。たくさんの子ども達も参加してるので、試食後は餅つき体験を実践してもらう事に。さすがに一人で杵をふるうのは上級生、小さなお子達はじいじと一緒に餅つきだ。途中、怪しげな歌まではいって、餅が腐りはしないかと心配にもなるが、滞りなく作業は進捗する。各家庭によって餅の形状は様々、関西は基本的に丸餅なんだが、当地の風習で猫餅という作り方があることを始めて知った。手順としては簡単で、つき上がった餅を箱の中に流し込み固めるだけである。2~3日してから包丁でカットするそうだ。一種のかき餅なんだろう。画像でご確認下さい。
これが当地特有の猫餅です。2~3日後にカットするようです。

長老の指導をあおぎながら餅の丸め方をマスターしていきます。

鏡餅の要望も結構にあり、餅のつき方に細かい注文がはいる。表面をツルツルに見栄え良くなるようにつき上げて欲しいそうだ。これはつき方もあるが、米の蒸し具合が大きく影響する模様。蒸し器に事情があって微調整は困難だが努力はしよう。つき上がった餅は丸めて行くのだが、ここは長老の経験が物を言う活躍場所だろう。Onさんの母君が若い衆を陣頭指揮しながら次々と仕上げていかれる。御年うん十歳のはずなんだが、疲れ知らずで作業を進められる。きれいな丸餅が仕上がって行く様はなかなかの壮観ですね。
借り物ばかりの蒸し器、微妙にサイズが異なり苦労しました。

怪しげな歌を歌いながら餅をつきはる御仁も。労働歌でしょうか。

全部で30臼程つきあげました。メンバーが多かったので負担にはならなかったものの。早朝から始めて終了したのが真っ暗になった6時頃、作業ライトを点けながらの餅つきでした。長時間の餅つき大会となりましたが、皆が喜んで餅を土産に帰宅するのは恒例行事とは言え嬉しいものです。自宅では餅を囲んだ一家団欒が待っていることでしょう。新年も壮健で野良仕事や山仕事に邁進して戴きたいものです。
例によってKさんが豚汁の振る舞いを。暖かくて美味しかったです。

ぜんざい用に餅を焼いておこうかな。

先陣を切るのは仲良し三人組、腰が痛いとぼやくのはどなた。

見事な餅がつきあがりました。丸餅の作成ですね。

餅をついたら食べたくなるのが人間の心情、始めの仕上がり分は試食用に回ってしまう。つきたてだけに絶妙なおいしさで、小生も思わず3個ほどを平らげてしまった。たくさんの子ども達も参加してるので、試食後は餅つき体験を実践してもらう事に。さすがに一人で杵をふるうのは上級生、小さなお子達はじいじと一緒に餅つきだ。途中、怪しげな歌まではいって、餅が腐りはしないかと心配にもなるが、滞りなく作業は進捗する。各家庭によって餅の形状は様々、関西は基本的に丸餅なんだが、当地の風習で猫餅という作り方があることを始めて知った。手順としては簡単で、つき上がった餅を箱の中に流し込み固めるだけである。2~3日してから包丁でカットするそうだ。一種のかき餅なんだろう。画像でご確認下さい。
これが当地特有の猫餅です。2~3日後にカットするようです。

長老の指導をあおぎながら餅の丸め方をマスターしていきます。

鏡餅の要望も結構にあり、餅のつき方に細かい注文がはいる。表面をツルツルに見栄え良くなるようにつき上げて欲しいそうだ。これはつき方もあるが、米の蒸し具合が大きく影響する模様。蒸し器に事情があって微調整は困難だが努力はしよう。つき上がった餅は丸めて行くのだが、ここは長老の経験が物を言う活躍場所だろう。Onさんの母君が若い衆を陣頭指揮しながら次々と仕上げていかれる。御年うん十歳のはずなんだが、疲れ知らずで作業を進められる。きれいな丸餅が仕上がって行く様はなかなかの壮観ですね。
借り物ばかりの蒸し器、微妙にサイズが異なり苦労しました。

怪しげな歌を歌いながら餅をつきはる御仁も。労働歌でしょうか。

全部で30臼程つきあげました。メンバーが多かったので負担にはならなかったものの。早朝から始めて終了したのが真っ暗になった6時頃、作業ライトを点けながらの餅つきでした。長時間の餅つき大会となりましたが、皆が喜んで餅を土産に帰宅するのは恒例行事とは言え嬉しいものです。自宅では餅を囲んだ一家団欒が待っていることでしょう。新年も壮健で野良仕事や山仕事に邁進して戴きたいものです。
例によってKさんが豚汁の振る舞いを。暖かくて美味しかったです。

ぜんざい用に餅を焼いておこうかな。

2009年12月29日
友を選ばば書を読みて
かなり古い歌曲なんだが、ある種の感慨を込めて口ずさむ方も多いのではなかろうか。
妻をめとらば才たけて みめ美わしく情ある
友を選ばば書を読みて 六分の侠気四分の熱
恋の命をたずぬれば 名を惜しむかな男ゆえ
友の情けをたずぬれば 義のあるところ火をも踏む
汲めや美酒うたひめに 乙女の知らぬ意気地あり
簿記の筆とる若者に まことの男君を見る
ああわれダンテの奇才なく バイロンハイネの熱なきも
石を抱きて野にうたう 芭蕉のさびをよろこばず・・・・・・・・・・
与謝野鉄幹の作詞によるものらしいが、歌手の名前は覚えていない。タイトルは「人を恋うる歌」だったかと記憶するのだが。昨今のお若い方には想像もつかない世界かも知れない。だが、かっての青年達はこの歌を口ずさみながら大きな夢(野望かな?)に燃えていた。
うら若き乙女ながらチェーンソーの腕前はピカイチのNs嬢。

冬場はこれが一番ですね、体の芯から温まります。

大きな野望に燃えながら志を同じくする友を捜したようだが、判断基準が二行目の歌詞だったのだろう。間違っても六分の狂気ではなかっただろうと思う。何でこんな古い話を持ち出したのかと怪訝な顔をする方も多いかも知れないが、歌詞を実感するような場面に遭遇してしまったのだ。実は本日と明日とで餅つき大会を開催するのが里山倶楽部の有志の習わし。本日は餅つきの準備で早朝から山城(本拠地が楠公さんの山城の城跡にあるもんで)に集まって作業開始の予定、小生も参加のつもりで餅米も精米し万端の準備を整えていた。ところがやんごとなき事情が発生して身動き取れない状況に。山城までの往復の時間ぐらいは融通がつくが作業時間は取れそうにない。明日も参加できるか予断が許さぬ・・・・・・・・・・切羽詰まってリーダーのUさんに電話。事情を話してドタキャンで恐縮だが参加を辞退したいと申し出たところ、餅米だけ持参してくれたら餅つきやっとくで・・・・・・・との返事、不覚にも涙しそうになった。
餅つき大会の主役であるリーダーのU氏。

懐が深くて暖かな心情の持ち主ばかり・・・・・・山男ですな。

この時ふっと脳裏に浮かんだのが上記の歌詞である。そしてお言葉に甘えて城跡まで餅米を運んだ。Uさんも他のメンバーの方も快く引き受けてくれて、明日、出来上がった餅を引き取りに来ればいいで・・・・・・・との心配りに返す言葉を失ってしまう。それにしても、いつも土壇場に追い詰められた時こうして人の情けを頂戴してしまう、全くもって恵まれた人生なのかも知れない。天の配慮としか考えようがないが、有り難い話である。小生がお返しを出来るような場面は出現するのだろうか。物事はプラスとマイナスとが作用しながら継続し、決算時には収支ゼロであるのが原則だとか。とすればプラスのみのような小生にはどこかで大きなマイナスが作用するかも知れませんね。
へっついさんからは湯気が沸き立っています。一杯いかがかな。

炭焼きもイヤになるほど堪能しました。最近はご無沙汰のようで。

せっかくだから城跡の餅つき準備を若干は紹介しておきましょう。早朝から働いてかなりの準備は仕上がっているようです。餅米も洗い終え、明日は蒸し上げるだけのようですね。大量に積みあげた薪が活躍してくれるのかな(これは商品だったか)。へっついさん(かまど)ではお湯が沸き立っています。熱いコーヒーでもと勧められましたが、皆の衆の気持ちだけで充分であり、大好きなコーヒーもはいりそうにありません。感謝しながら退散しました。さて明日の餅つき大会、多少でも時間が取れればいいのだが。
古民家の蔵の中から引っ張り出しました。

木製ですぞ、今時何処を捜しても見つからない品々ですね。

妻をめとらば才たけて みめ美わしく情ある
友を選ばば書を読みて 六分の侠気四分の熱
恋の命をたずぬれば 名を惜しむかな男ゆえ
友の情けをたずぬれば 義のあるところ火をも踏む
汲めや美酒うたひめに 乙女の知らぬ意気地あり
簿記の筆とる若者に まことの男君を見る
ああわれダンテの奇才なく バイロンハイネの熱なきも
石を抱きて野にうたう 芭蕉のさびをよろこばず・・・・・・・・・・
与謝野鉄幹の作詞によるものらしいが、歌手の名前は覚えていない。タイトルは「人を恋うる歌」だったかと記憶するのだが。昨今のお若い方には想像もつかない世界かも知れない。だが、かっての青年達はこの歌を口ずさみながら大きな夢(野望かな?)に燃えていた。
うら若き乙女ながらチェーンソーの腕前はピカイチのNs嬢。

冬場はこれが一番ですね、体の芯から温まります。

大きな野望に燃えながら志を同じくする友を捜したようだが、判断基準が二行目の歌詞だったのだろう。間違っても六分の狂気ではなかっただろうと思う。何でこんな古い話を持ち出したのかと怪訝な顔をする方も多いかも知れないが、歌詞を実感するような場面に遭遇してしまったのだ。実は本日と明日とで餅つき大会を開催するのが里山倶楽部の有志の習わし。本日は餅つきの準備で早朝から山城(本拠地が楠公さんの山城の城跡にあるもんで)に集まって作業開始の予定、小生も参加のつもりで餅米も精米し万端の準備を整えていた。ところがやんごとなき事情が発生して身動き取れない状況に。山城までの往復の時間ぐらいは融通がつくが作業時間は取れそうにない。明日も参加できるか予断が許さぬ・・・・・・・・・・切羽詰まってリーダーのUさんに電話。事情を話してドタキャンで恐縮だが参加を辞退したいと申し出たところ、餅米だけ持参してくれたら餅つきやっとくで・・・・・・・との返事、不覚にも涙しそうになった。
餅つき大会の主役であるリーダーのU氏。

懐が深くて暖かな心情の持ち主ばかり・・・・・・山男ですな。

この時ふっと脳裏に浮かんだのが上記の歌詞である。そしてお言葉に甘えて城跡まで餅米を運んだ。Uさんも他のメンバーの方も快く引き受けてくれて、明日、出来上がった餅を引き取りに来ればいいで・・・・・・・との心配りに返す言葉を失ってしまう。それにしても、いつも土壇場に追い詰められた時こうして人の情けを頂戴してしまう、全くもって恵まれた人生なのかも知れない。天の配慮としか考えようがないが、有り難い話である。小生がお返しを出来るような場面は出現するのだろうか。物事はプラスとマイナスとが作用しながら継続し、決算時には収支ゼロであるのが原則だとか。とすればプラスのみのような小生にはどこかで大きなマイナスが作用するかも知れませんね。
へっついさんからは湯気が沸き立っています。一杯いかがかな。

炭焼きもイヤになるほど堪能しました。最近はご無沙汰のようで。

せっかくだから城跡の餅つき準備を若干は紹介しておきましょう。早朝から働いてかなりの準備は仕上がっているようです。餅米も洗い終え、明日は蒸し上げるだけのようですね。大量に積みあげた薪が活躍してくれるのかな(これは商品だったか)。へっついさん(かまど)ではお湯が沸き立っています。熱いコーヒーでもと勧められましたが、皆の衆の気持ちだけで充分であり、大好きなコーヒーもはいりそうにありません。感謝しながら退散しました。さて明日の餅つき大会、多少でも時間が取れればいいのだが。
古民家の蔵の中から引っ張り出しました。

木製ですぞ、今時何処を捜しても見つからない品々ですね。

2009年12月27日
歳末商戦の始まりか
いつもお世話になっている道の駅かなんを覗いて見たらごった返ししてますね。早いところでは年末休暇にはいった模様で、お正月の準備に余念がないようです。河南町は農産物の宝庫、あらゆる種類の野菜等が栽培されており、とりわけ伝統野菜の復活に尽力されていることで著名な地域でもあります。篤農家も多く、農を生業とすることに誇りと意欲を充ち満ちておられるようですね。さっそく徘徊してみますと、やはり正月用品と思しき品々が多いようです。最も各地の直売所同様の傾向ですが、農産物が主体であり、魚介物や肉類は殆ど見あたりません。ここらは注意してショッピングを楽しむべきでしょう。農産物と一言でくくっても地域の特性があり、各直売所を覗き回るのは結構ローカルカラーがあって興味深いものです。
道の駅かなんです、歳末商戦の始まりのようですね。

梅の盆栽は正月用品として好まれるようです。沢山あります。

陳列棚には地産の野菜類がてんこ盛りとなっています。売れ行き次第で何度でも搬入されるようで、バイクに積み込んだ野菜と一緒に爺様がご登場という場面も結構見られます。長年、農にこだわり続けられたのか、なかなか品のあるいい表情をなさっています。エブラハム・リンカーンの言葉、「男は40歳を過ぎたら自分の顔に責任がある」・・・・・・・・・そんな一言を思い出してしまいます。画像に納めたいのですが、さすがに真正面からレンズを向けるわけにはいかないでしょうね。幾つかの野菜類をご紹介しましょうか。伝統野菜がウリの河南町、この季節だと田辺大根に天王寺かぶらでしょうか。何れも大阪市内の南部で(大阪市内もかっては農地がふんだんにありました)作られていた野菜ですが、農地の消滅と並行して栽培も消え去ったようです。従って伝統野菜とも呼称されているのですが、河南町の篤農家により復活されています。
伝統野菜の代表格である田辺大根です。大阪市内の南部で栽培されてました。

同じく天王寺かぶらです。

正月用品と思える品々も多く、出店例では注連縄や鏡餅或いは梅の盆栽や葉ボタンなども沢山そろっています。こうした事物を見てますと、歳末の雰囲気が醸し出されてきますね。もう幾つ寝るとお正月、4~5回かな。思わぬ物はおでんの販売、熱々のおでんは如何にもおいしそうで、熱燗で一杯となりそうです。道の駅だから、お酒の提供はないようですが、おでんはお勧めですよ。
お若いカップルが販売中のようです。撮影の了解を求めたら、おでんだけなら・・・・・・・・・・・残念です。
熱々のおでん、美味しそうでね。販売中のカップルを撮影したかったのですが。

この季節の販売商品でしょう。無論地場産の餅米使用です。

かってはどこでも自宅で作っておられたのですが・・・・・・・・・・・・。

さてここに参りますと、仲間の衆の焼き芋屋を覗いておかないと呵られますね。本日もOmさんが当番のようで、にこやかな笑顔と一緒にさりげなく売り上げを伸ばしておられるようです。しばらく観察してましたが、やはりご婦人方と子どもさんがメインのようですね。子ども達が100円玉を何個か握りしめて走ってくるのは、見ていても微笑ましいものです。計量もついつい甘くなってしまうようですね、無理もない話ですが。いい芋が程よく焼けています。時間的にはお昼前、いま芋を食べますと昼食が無理となりますか。次の機会と致しましょう。それにしても栽培していたサツマイモ、まだ足りているのかな。少々心配になってきます。芋農家の大先輩Uさんの芋畑もそう大きくはなかったと思うのですが。
Omさん微妙な温度調節にチャレンジ中のようです。職人魂?。

お買い上げありがとうございます。思わず笑みが。

道の駅かなんです、歳末商戦の始まりのようですね。

梅の盆栽は正月用品として好まれるようです。沢山あります。

陳列棚には地産の野菜類がてんこ盛りとなっています。売れ行き次第で何度でも搬入されるようで、バイクに積み込んだ野菜と一緒に爺様がご登場という場面も結構見られます。長年、農にこだわり続けられたのか、なかなか品のあるいい表情をなさっています。エブラハム・リンカーンの言葉、「男は40歳を過ぎたら自分の顔に責任がある」・・・・・・・・・そんな一言を思い出してしまいます。画像に納めたいのですが、さすがに真正面からレンズを向けるわけにはいかないでしょうね。幾つかの野菜類をご紹介しましょうか。伝統野菜がウリの河南町、この季節だと田辺大根に天王寺かぶらでしょうか。何れも大阪市内の南部で(大阪市内もかっては農地がふんだんにありました)作られていた野菜ですが、農地の消滅と並行して栽培も消え去ったようです。従って伝統野菜とも呼称されているのですが、河南町の篤農家により復活されています。
伝統野菜の代表格である田辺大根です。大阪市内の南部で栽培されてました。

同じく天王寺かぶらです。

正月用品と思える品々も多く、出店例では注連縄や鏡餅或いは梅の盆栽や葉ボタンなども沢山そろっています。こうした事物を見てますと、歳末の雰囲気が醸し出されてきますね。もう幾つ寝るとお正月、4~5回かな。思わぬ物はおでんの販売、熱々のおでんは如何にもおいしそうで、熱燗で一杯となりそうです。道の駅だから、お酒の提供はないようですが、おでんはお勧めですよ。
お若いカップルが販売中のようです。撮影の了解を求めたら、おでんだけなら・・・・・・・・・・・残念です。
熱々のおでん、美味しそうでね。販売中のカップルを撮影したかったのですが。

この季節の販売商品でしょう。無論地場産の餅米使用です。

かってはどこでも自宅で作っておられたのですが・・・・・・・・・・・・。

さてここに参りますと、仲間の衆の焼き芋屋を覗いておかないと呵られますね。本日もOmさんが当番のようで、にこやかな笑顔と一緒にさりげなく売り上げを伸ばしておられるようです。しばらく観察してましたが、やはりご婦人方と子どもさんがメインのようですね。子ども達が100円玉を何個か握りしめて走ってくるのは、見ていても微笑ましいものです。計量もついつい甘くなってしまうようですね、無理もない話ですが。いい芋が程よく焼けています。時間的にはお昼前、いま芋を食べますと昼食が無理となりますか。次の機会と致しましょう。それにしても栽培していたサツマイモ、まだ足りているのかな。少々心配になってきます。芋農家の大先輩Uさんの芋畑もそう大きくはなかったと思うのですが。
Omさん微妙な温度調節にチャレンジ中のようです。職人魂?。

お買い上げありがとうございます。思わず笑みが。

2009年12月25日
山里のクリスマス
本日はクリスマスだそうな。無論、敬虔な信仰者の方はともかくとして大多数の日本人にとっては一過性のイベントに過ぎないだろう。それにしても他国の宗教行事を何故にかくも盛大に祝賀するのだろうか。幼稚園や保育園といった公的施設ですら、学園行事に組み込まれている模様で、無論、公的施設における宗教活動うんぬん・・・・・・・・そんな野暮な話は致しませんが。何とも不思議な現象である。翻ってお釈迦様の誕生日である4月8日の花祭りが盛大に開催されると言う話は寡聞にしてあまり聞かない。この違いはマーケティング能力の差異によるものだろうか。遠因はどうも昭和20年代の占領政策にあったのでは、とも想像する。かの時期、食糧難に喘いでいた我が国に、余剰物資を大量に売りつけた米国が同時にかの国の文化をも持ち込んだのであろう。


早い話が、刷り込まれた幼児期の体験やメディアの情報や学校園での教えをそのまま引きずって、現在の我々が存在するのではないだろうか。そう言えば当該時期に、「米を食べれば頭が悪くなる、パンを食べよう」との、とんでもない刷り込みが盛んに行われたようだ。巧妙な販売戦略である。いきさつはどうであれ、クリスマスは現在の我が国では年末の風物詩であろう。商店街の何とかセールはともかくとして、子どもさんのおられるご家庭では実施せざるを得ないでしょうね。

当地でも風に任せて彼方此方の集落を夜半に歩いて見れば、クリスマス用の電飾が花盛り。ご近所で競い合っておられるのでは、そんな思いを抱かせるような光景もしばしばだ。早い家は11月の末位から始まり、年末まで続く。手の込んだ家も多く、相当な手間暇と多大な経費が掛かっている模様。それに何よりも飾り付けのセンスが要求されるので、それなりの職業の方かプロへの依頼ではなかろうか。きらびやかな電飾が輝くので防犯用には打って付け、一人の部外者に過ぎない小生にとっては治安対策の効用が一番有り難い。年々装飾が派手になるようで、該当のお家の方も次のプランニングに悩まれるのではなかろうか。

覗いて回った幾つかを紹介しておきましょう。何とも豪華絢爛です。我が家でするのは面倒だし、飾り付けのセンスも無いし、もっぱら他家の飾り付けを覗いて回る方が楽勝なようですね。無精な性格もありますか。それにしてもクリスマスが何故にかくも人の心を引きつけるのか不思議でなりません。単なるマインドコントロールのみではなさそうですね。




早い話が、刷り込まれた幼児期の体験やメディアの情報や学校園での教えをそのまま引きずって、現在の我々が存在するのではないだろうか。そう言えば当該時期に、「米を食べれば頭が悪くなる、パンを食べよう」との、とんでもない刷り込みが盛んに行われたようだ。巧妙な販売戦略である。いきさつはどうであれ、クリスマスは現在の我が国では年末の風物詩であろう。商店街の何とかセールはともかくとして、子どもさんのおられるご家庭では実施せざるを得ないでしょうね。

当地でも風に任せて彼方此方の集落を夜半に歩いて見れば、クリスマス用の電飾が花盛り。ご近所で競い合っておられるのでは、そんな思いを抱かせるような光景もしばしばだ。早い家は11月の末位から始まり、年末まで続く。手の込んだ家も多く、相当な手間暇と多大な経費が掛かっている模様。それに何よりも飾り付けのセンスが要求されるので、それなりの職業の方かプロへの依頼ではなかろうか。きらびやかな電飾が輝くので防犯用には打って付け、一人の部外者に過ぎない小生にとっては治安対策の効用が一番有り難い。年々装飾が派手になるようで、該当のお家の方も次のプランニングに悩まれるのではなかろうか。

覗いて回った幾つかを紹介しておきましょう。何とも豪華絢爛です。我が家でするのは面倒だし、飾り付けのセンスも無いし、もっぱら他家の飾り付けを覗いて回る方が楽勝なようですね。無精な性格もありますか。それにしてもクリスマスが何故にかくも人の心を引きつけるのか不思議でなりません。単なるマインドコントロールのみではなさそうですね。


2009年12月18日
初冠雪の朝
冷え込んできましたね。師走も中旬、当たり前の現象でしょうが、寒さに弱い小生には堪えます。あまりにも冷え込んでるなと思ってましたら周囲の山々が真っ白でした。毎朝駄犬と一緒に散歩してるんですが、金剛山や岩湧山がよく見えるんです。真っ白になった山々がとても綺麗で立ち止まってしまいますね。どうやら初冠雪のようです。東北や北海道の方にとっては見慣れた光景でしょうが、当地では雪の降る日は珍しい程です。白くなった稜線を眺めていますと、山仕事もしばらく中断かな・・・・・・との心境にもなってきますが、どうしてどうして。週末は定例の作業日です。トモロスの定例の作業が月に4回程度、これに臨時の行事が多々はいってきます。可能な範囲で出席してますが、なかなか皆さん精勤で、集合時刻の30分前に到着したら、「これで全員集合だ」との会話もしばしば。皆の衆の意気込みが感じ取れますね。
我らがフィールドの岩湧山も真っ白く化粧しました。初冠雪ですね。

岩湧山から金剛山への尾根筋いわゆるダイトレも白銀の世界です。

冬場の積雪となりますと。足場の状態が芳しくないですね。通常は好みにより地下足袋、長靴、安全靴、登山靴+スパッツ、などの使用が大半です。当然スパイク付きの物となりますが、これも一長一短で、積雪状態では利便性が高いのですが岩場になると逆に滑りやすくなってきます。オールマイティとはいかないようで、選択に苦労します。雪国の方はどんな装備で作業をしておられるのか気になりますね。外気温も低いですし、風などで体感温度もどんどん下がります。体が冷え込みますと動作が鈍くなりますし判断力も低下します。事故への可能性が高まりますので、保温の工夫が必要ですね。軽くて暖かくて動きやすい物、某衣料品チェーン店のヒートテックが評判が高いようですので、試してみようかとも思っています。
山間部の住宅街もなんだか縮こまっているようですね。

かすかな紅葉の名残も冷え込んでしまいました。

各種の装備類はリュックに詰めて背中に、これが原則ですね。両手を空けておかないと移動中に不足の事態になりかねません。このリュックですが、作業中は一箇所において動くのですが、置き場所不明となって大騒ぎすることがしばしばあります。山の中で状況が似通った場所ばかりなので、混乱するのでしょう。以前に画像をアップしましたが、木ぎれを使ってリュックを地上1メートル位の幹に引っ掛ける手法が有益かと思います。リュックも鮮やかな原色の物が利便性が高いようです。総体に山仕事の用具類ははでな色彩の方が視認度が高く、見失っても発見の度合いが楽なようですね。そして忘れてならないのが暖かい飲み物、軽量化されたテルモス等が安価に提供されてますので、お茶やコーヒーなどを詰めてベルトに下げておくと作業中にも一息つけます。チョコレートや飴なども便利なようです。
新聞も金剛山の降雪を伝えています。

森林ボランティアの現場は当然のことながら山の中、服装や用具類は登山用の物が活用できます。又、参加される方は山好きな方が多いようで、ある程度は既に持っておられるようですね。師走から春先の3月位まで、当地も例外ではなく冷え込みが激しくなります。山中での作業には、体力の温存と動きやすい行動体勢の確立が必要です。各位の工夫が要求されますが、これもまた一つの楽しみ、どのように展開されるのか仲間の衆の動きを観察するのも一考ですね。初冠雪の早朝のひととき、駄犬と歩き回りながら装備のことをあれこれと思い巡らしてみました。技術革新が激しい世の中、たまには街に降りて山道具屋さんや職人さんの店などを覗いて回る必要性が高いようですね。
雑木林も寒そうです。小鳥たちは何処に避難しているのやら。

我らがフィールドの岩湧山も真っ白く化粧しました。初冠雪ですね。

岩湧山から金剛山への尾根筋いわゆるダイトレも白銀の世界です。

冬場の積雪となりますと。足場の状態が芳しくないですね。通常は好みにより地下足袋、長靴、安全靴、登山靴+スパッツ、などの使用が大半です。当然スパイク付きの物となりますが、これも一長一短で、積雪状態では利便性が高いのですが岩場になると逆に滑りやすくなってきます。オールマイティとはいかないようで、選択に苦労します。雪国の方はどんな装備で作業をしておられるのか気になりますね。外気温も低いですし、風などで体感温度もどんどん下がります。体が冷え込みますと動作が鈍くなりますし判断力も低下します。事故への可能性が高まりますので、保温の工夫が必要ですね。軽くて暖かくて動きやすい物、某衣料品チェーン店のヒートテックが評判が高いようですので、試してみようかとも思っています。
山間部の住宅街もなんだか縮こまっているようですね。

かすかな紅葉の名残も冷え込んでしまいました。

各種の装備類はリュックに詰めて背中に、これが原則ですね。両手を空けておかないと移動中に不足の事態になりかねません。このリュックですが、作業中は一箇所において動くのですが、置き場所不明となって大騒ぎすることがしばしばあります。山の中で状況が似通った場所ばかりなので、混乱するのでしょう。以前に画像をアップしましたが、木ぎれを使ってリュックを地上1メートル位の幹に引っ掛ける手法が有益かと思います。リュックも鮮やかな原色の物が利便性が高いようです。総体に山仕事の用具類ははでな色彩の方が視認度が高く、見失っても発見の度合いが楽なようですね。そして忘れてならないのが暖かい飲み物、軽量化されたテルモス等が安価に提供されてますので、お茶やコーヒーなどを詰めてベルトに下げておくと作業中にも一息つけます。チョコレートや飴なども便利なようです。
新聞も金剛山の降雪を伝えています。

森林ボランティアの現場は当然のことながら山の中、服装や用具類は登山用の物が活用できます。又、参加される方は山好きな方が多いようで、ある程度は既に持っておられるようですね。師走から春先の3月位まで、当地も例外ではなく冷え込みが激しくなります。山中での作業には、体力の温存と動きやすい行動体勢の確立が必要です。各位の工夫が要求されますが、これもまた一つの楽しみ、どのように展開されるのか仲間の衆の動きを観察するのも一考ですね。初冠雪の早朝のひととき、駄犬と歩き回りながら装備のことをあれこれと思い巡らしてみました。技術革新が激しい世の中、たまには街に降りて山道具屋さんや職人さんの店などを覗いて回る必要性が高いようですね。
雑木林も寒そうです。小鳥たちは何処に避難しているのやら。

2009年10月18日
水分神社の秋祭り
本日は当地での最後の秋祭りである。トリを飾るのはおなじみの水分神社、正式には建水分神社(タケミクマリジンジャ)と呼ぶのだが、誰しも水分神社で通してしまう。ご祭神はたくさんおられるが楠木正成公の氏神さんと言った方がわかりやすいだろう。金剛山から流れいずる千早川の段丘にあり、流域の農業用水の分岐点でもある。従って祭りともなれば下流域の集落に存する地車が全てここに集結する。水を支配する農業の神様と言っても過言ではないかも知れない。昨晩から盛り上がっていた模様で、本日も早朝から祭り太鼓が賑々しかった。
建水分神社の秋祭りが始まりました。当地では最後の祭りとなります。

こちらは稲刈りの真っ最中なんだが、何せ宮入の場所と田圃とが超接近の間柄、作業の合間も気になってしょうがない。途中、とうとう抜け出して1時間ほど見物させていただいた。まだ宮入の時間ではなかったので、地車も近場の集落のものだけだったが雰囲気は伝わるかと思うのでご紹介しよう。例によって大勢の老若男女が地車を曳き、達者な者が唄や太鼓、鉦、笛などを担当する。身の軽い者は屋根の上でパフォーマンスだ。集落単位で得て不得手を考慮して役割分担が決まっている模様。
神社の存する地元集落の地車です。大きな集落なので引き手も多いですね。

ここの祭りの特徴は、神社が急坂の階段と言うこともあって、神様が広場へ一時的にお移りになること。そこで地車の奉納を受けられるようだ。昼前になるとお移りの儀式が始まる。稚児が乗った先導車を筆頭に神官や御神輿などが続いて行く。所定の場所に収まっていただくと、御輿が練り回してお祓い・お清めの儀式となるようだ。無論、地車の奉納はあるのだが午後となるようですね。周囲は露店のオンパレード、これが楽しみで集まってくる人々も多いようだ。それとなく見ていたら他府県ナンバーの車も結構あった。
神様の引っ越し行列が到着しました。広場への移動です。




地車の運行は交通妨害となるのだが、そこはそれ祭りのことだからお互いさんで皆が納得している。地車も、集落の長老を筆頭に老壮青の役割分担で統制の取れた動きを見せてくれる。意思の疎通が見事に図られているようだ。壇上の数人はマイク片手に歌い続ける、歌詞はよくわからないがどうやら数え歌のようでもある。地域固有の民謡的なものが存在するのだろう。集落によって皆歌っている内容が異なっている。無論カンニングペーパーなどを保持する者は誰もいない。長い歌詞を諳んじているのだから凄い能力である、小生などには到底真似の出来ない芸当だ。
歌詞は違えどもどこの地車も歌い続けております。

あいにく昼前から雨がポツポツ降ってきた。稲刈りをほっぽり出しての祭り鑑賞なので急いで戻らねば。午前中には天日干しの段取りを終了したい。次の現場で稲刈りの準備をしてくれてる仲間も帰って来るだろう。昼ご飯を食べて資材の搬送だ。
広場では御神輿の練りが始まりました。神様の着座です。

建水分神社の秋祭りが始まりました。当地では最後の祭りとなります。

こちらは稲刈りの真っ最中なんだが、何せ宮入の場所と田圃とが超接近の間柄、作業の合間も気になってしょうがない。途中、とうとう抜け出して1時間ほど見物させていただいた。まだ宮入の時間ではなかったので、地車も近場の集落のものだけだったが雰囲気は伝わるかと思うのでご紹介しよう。例によって大勢の老若男女が地車を曳き、達者な者が唄や太鼓、鉦、笛などを担当する。身の軽い者は屋根の上でパフォーマンスだ。集落単位で得て不得手を考慮して役割分担が決まっている模様。
神社の存する地元集落の地車です。大きな集落なので引き手も多いですね。

ここの祭りの特徴は、神社が急坂の階段と言うこともあって、神様が広場へ一時的にお移りになること。そこで地車の奉納を受けられるようだ。昼前になるとお移りの儀式が始まる。稚児が乗った先導車を筆頭に神官や御神輿などが続いて行く。所定の場所に収まっていただくと、御輿が練り回してお祓い・お清めの儀式となるようだ。無論、地車の奉納はあるのだが午後となるようですね。周囲は露店のオンパレード、これが楽しみで集まってくる人々も多いようだ。それとなく見ていたら他府県ナンバーの車も結構あった。
神様の引っ越し行列が到着しました。広場への移動です。




地車の運行は交通妨害となるのだが、そこはそれ祭りのことだからお互いさんで皆が納得している。地車も、集落の長老を筆頭に老壮青の役割分担で統制の取れた動きを見せてくれる。意思の疎通が見事に図られているようだ。壇上の数人はマイク片手に歌い続ける、歌詞はよくわからないがどうやら数え歌のようでもある。地域固有の民謡的なものが存在するのだろう。集落によって皆歌っている内容が異なっている。無論カンニングペーパーなどを保持する者は誰もいない。長い歌詞を諳んじているのだから凄い能力である、小生などには到底真似の出来ない芸当だ。
歌詞は違えどもどこの地車も歌い続けております。

あいにく昼前から雨がポツポツ降ってきた。稲刈りをほっぽり出しての祭り鑑賞なので急いで戻らねば。午前中には天日干しの段取りを終了したい。次の現場で稲刈りの準備をしてくれてる仲間も帰って来るだろう。昼ご飯を食べて資材の搬送だ。
広場では御神輿の練りが始まりました。神様の着座です。

2009年10月13日
金剛山紅葉祭り
体育の日には金剛山が賑わう。ここは富士山とトップを争うような登山者数の多い山で、年中いつでもどこでも登山者だらけだ。大阪で一番高い山といっても、標高はたかだか1125メートル、どこにでもあるような低山である。沢山の愛好家を集めるのはスタンプ制度が大きいのではなかろうか。どこにも知恵者がおられるもので、1回登頂したらスタンプ帳に判を押すと言う制度を設け、100回を筆頭に節目の階数毎に表彰する制度をつくられた。これが大化けしたようだ。山頂の売店付近には掲示板があり、登山回数の順に記名板が並んでいる。早い話、受験生の成績順位表みたいなものである。
金剛山頂、大阪府と奈良県の境界線でもあります。

至る所でお地蔵様が登山者の安全を見守っておられます。

ライバルとの競争に燃えるのは何処の世界も同様とみえ、対抗心丸出しで競っておられる方も多い。それと健康志向で、毎日登るのが日課という方も少なからずおられる。年に数回は大きなイベントがあり、この日は格段の登山者数となるようだ。愛好者の集い「金剛錬成会」は5000名近くの会員がおられるのではなかろうか。本日は紅葉祭りと称するイベントの一つで、弁当やお茶の配給もあり演芸会まで催される。普段はサボり気味のなまくら会員である小生もこんな日には山頂へ。
こんな丸太の階段が大半です。歩きにくいデス。

大半の方は登山口周辺の駐車場に車を止め、正面道と称するルートを選択されるようだ。利便性の高いルートだがほとんどは丸太を組んだ階段であり、歩幅が合わず非常に歩きにくい。山頂まで1時間半から2時間程度、中には40分程度で駆け登る猛者もいる。視界は効かず快適とも思えないのだが、このルートの人気は抜群で、かく言う小生もこのルート使用が多い。理由は9合目附近のブナ林で、ここを散策するために金剛山に登るようなもの。画像を数枚アップしておきますのでご覧下さい。現場に行かれたら多分はまり込んでしまうと思います。
金剛山のブナ林です。心身が解放され心が和らぎます。



山頂ではスタンプ帳への押印と会費の支払いを済ませ弁当類をいただく。国見城跡と呼ばれる広場は楠公さんが築城した山城の跡である。現在は登山者の弁当広場であり、イベント会場でもある。仲間達の姿を探すも人が多すぎて不明、小生も端のほうで座り込み弁当を広げよう。演芸会は1時から始まった。ロックバンドの若者、奈良の千都祭のキャンペーン嬢、通天閣の歌姫、ストリートミュージシャン・・・・の4組が出演だ。最も印象的だったのはストリートミュージシャンを自称されるオカリナ奏者。正式にはコンドルサカタという芸名らしいが、名称どおりで南米のペルー音楽が大好きだとのこと。本日の演奏でビックリしたのは坊ヶツル賛歌が飛び出してきたことだ、彼の地は高校山岳部時代のホームグラウンドであった。法華院温泉の露天風呂に浸かりながら満天の星空を眺めていた多感な時代を思い出してしまった。仲間達と一緒になって歌っていた坊ヶツル賛歌、当時のメンバーは健在だろうか。
オカリナ奏者のコンドルサカタ氏、敬虔なクリスチャンだそうな。

大和路ラプソディーの歌姫さん、曲に合わせ一緒に踊り出す方も。

山頂付近は大混雑となりました。

金剛山頂、大阪府と奈良県の境界線でもあります。

至る所でお地蔵様が登山者の安全を見守っておられます。

ライバルとの競争に燃えるのは何処の世界も同様とみえ、対抗心丸出しで競っておられる方も多い。それと健康志向で、毎日登るのが日課という方も少なからずおられる。年に数回は大きなイベントがあり、この日は格段の登山者数となるようだ。愛好者の集い「金剛錬成会」は5000名近くの会員がおられるのではなかろうか。本日は紅葉祭りと称するイベントの一つで、弁当やお茶の配給もあり演芸会まで催される。普段はサボり気味のなまくら会員である小生もこんな日には山頂へ。
こんな丸太の階段が大半です。歩きにくいデス。

大半の方は登山口周辺の駐車場に車を止め、正面道と称するルートを選択されるようだ。利便性の高いルートだがほとんどは丸太を組んだ階段であり、歩幅が合わず非常に歩きにくい。山頂まで1時間半から2時間程度、中には40分程度で駆け登る猛者もいる。視界は効かず快適とも思えないのだが、このルートの人気は抜群で、かく言う小生もこのルート使用が多い。理由は9合目附近のブナ林で、ここを散策するために金剛山に登るようなもの。画像を数枚アップしておきますのでご覧下さい。現場に行かれたら多分はまり込んでしまうと思います。
金剛山のブナ林です。心身が解放され心が和らぎます。



山頂ではスタンプ帳への押印と会費の支払いを済ませ弁当類をいただく。国見城跡と呼ばれる広場は楠公さんが築城した山城の跡である。現在は登山者の弁当広場であり、イベント会場でもある。仲間達の姿を探すも人が多すぎて不明、小生も端のほうで座り込み弁当を広げよう。演芸会は1時から始まった。ロックバンドの若者、奈良の千都祭のキャンペーン嬢、通天閣の歌姫、ストリートミュージシャン・・・・の4組が出演だ。最も印象的だったのはストリートミュージシャンを自称されるオカリナ奏者。正式にはコンドルサカタという芸名らしいが、名称どおりで南米のペルー音楽が大好きだとのこと。本日の演奏でビックリしたのは坊ヶツル賛歌が飛び出してきたことだ、彼の地は高校山岳部時代のホームグラウンドであった。法華院温泉の露天風呂に浸かりながら満天の星空を眺めていた多感な時代を思い出してしまった。仲間達と一緒になって歌っていた坊ヶツル賛歌、当時のメンバーは健在だろうか。
オカリナ奏者のコンドルサカタ氏、敬虔なクリスチャンだそうな。

大和路ラプソディーの歌姫さん、曲に合わせ一緒に踊り出す方も。

山頂付近は大混雑となりました。

2009年10月12日
秋祭り始まる
「祭り太鼓は土の中」・・・・・・・師匠の名言である。最もこれはソラマメの作付時期を教えた伝承であり、祭りそのものが対象ではない。当地では10月の10日前後から18日位にかけてが祭りのクライマックス、この時期にはソラマメの種は畑の土の中に存在する、との例えである。そのお祭りがいよいよ始まった。早朝から祭り太鼓の賑やかなこと、地の方にとっては1年間待ち望んだ待望の秋祭りであろう。リオのカーニバルではないが、この日の為に1年が存在すると言っても過言ではないそうだ。
篠笛の君、お祭りを側面から盛り上げます。

外来人の小生も、そこはかとなく祭りの中に紛れ込む。好奇心旺盛な人間の故、血が騒ぐのであろう。相棒のカメラ1台がお供なのだ。とある駅前の交差点に陣取った。ここは数カ所の集落から地車が集まる場所、撮影には格好のポイントであろう。案の定、何台もの地車が侵入待ちのようだ。ドライバーがいらいらしながら祭りの若者に怒鳴っているが、何、火事と葬儀とお祭りは最優先事項、しばしの猶予を楽しまれたい。お祭りは集落あげての最大イベント、幼児からお年寄りまでが地車のロープを引っ張っている。なかなかいい光景なのだ。
地車も女性パワーが主力なようです。

主役は大工方と呼ばれる屋根上の方、パフォーマンスを展開します。

交差点などでは観客の視線を考慮するのか、地車の引き回しが始まる。無論、こんな場面では幼児やお年寄りはしばし離れるようだ。岸和田ほどの豪壮さはないが、アルコールもはいってるのだろう、結構きわどい場面もあり緊張する。危ない、と思う直前にリーダーから中止の指令がはいるようだ。見事な統率ぶりである。集落の中で築かれた人間関係、緊張の中にも信頼があって、阿吽の呼吸が集団をまとめているようだ、うらやましい限りである。
引き回しが始まりました。祭りのハイライトか。



かれこれ2時間ほど陣取っていたが、地車達は近場の旧道から国道へと回遊するのか何度も参入してくる。やはり駅前がメインのお立ち台のようだ。それにしても疲れ知らずの彼ら、エネルギッシュに地車を引き回す。かのエネルギーはどこから出てくるのだろうか。祭りは、かって為政者達が、住民パワーの発散を図って政への関心を反らしたとの伝承もあるが、あながち誤りでもなさそうだ。百姓一揆によって国(藩)がつぶれた事例もあるが、恐るべしは民衆の力、だろうか。
裏方さんもひっそりと活躍中、ゴミ類を回収しています。

さて肝心の楠公さん、正成公を祭る水分神社は今度の週末が秋祭りである。ここは文字通りで水を配分する権能も持っておられるのか、流域の各集落からたくさんの地車が集結する。あまりにも台数が多いので神社に入りきれず、神様を一時的に引っ越ししていただいて大きな広場で奉納する。特筆すべきは「河内にわか」と称される寸劇が地車上で上演されることだ。伝統芸能でもあろう。またまた走る回る日々が続きそう、カメラの手入れも入念にやっておかないと。
どうやらご祝儀もたくさん集まっている模様ですね。


△△△ お詫びと訂正 △△△
読者の方からのご指摘で判明しましたが、9月23日付け記事「未知なる樹木との遭遇」にて誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。記事中、ウラジロガシと記述した画像が存在しますが正式にはシラカシの誤りでした。それにしても一目で識別される眼力に、ただ驚嘆の小生です。これからもご叱声をよろしくお願いします。
篠笛の君、お祭りを側面から盛り上げます。

外来人の小生も、そこはかとなく祭りの中に紛れ込む。好奇心旺盛な人間の故、血が騒ぐのであろう。相棒のカメラ1台がお供なのだ。とある駅前の交差点に陣取った。ここは数カ所の集落から地車が集まる場所、撮影には格好のポイントであろう。案の定、何台もの地車が侵入待ちのようだ。ドライバーがいらいらしながら祭りの若者に怒鳴っているが、何、火事と葬儀とお祭りは最優先事項、しばしの猶予を楽しまれたい。お祭りは集落あげての最大イベント、幼児からお年寄りまでが地車のロープを引っ張っている。なかなかいい光景なのだ。
地車も女性パワーが主力なようです。

主役は大工方と呼ばれる屋根上の方、パフォーマンスを展開します。

交差点などでは観客の視線を考慮するのか、地車の引き回しが始まる。無論、こんな場面では幼児やお年寄りはしばし離れるようだ。岸和田ほどの豪壮さはないが、アルコールもはいってるのだろう、結構きわどい場面もあり緊張する。危ない、と思う直前にリーダーから中止の指令がはいるようだ。見事な統率ぶりである。集落の中で築かれた人間関係、緊張の中にも信頼があって、阿吽の呼吸が集団をまとめているようだ、うらやましい限りである。
引き回しが始まりました。祭りのハイライトか。



かれこれ2時間ほど陣取っていたが、地車達は近場の旧道から国道へと回遊するのか何度も参入してくる。やはり駅前がメインのお立ち台のようだ。それにしても疲れ知らずの彼ら、エネルギッシュに地車を引き回す。かのエネルギーはどこから出てくるのだろうか。祭りは、かって為政者達が、住民パワーの発散を図って政への関心を反らしたとの伝承もあるが、あながち誤りでもなさそうだ。百姓一揆によって国(藩)がつぶれた事例もあるが、恐るべしは民衆の力、だろうか。
裏方さんもひっそりと活躍中、ゴミ類を回収しています。

さて肝心の楠公さん、正成公を祭る水分神社は今度の週末が秋祭りである。ここは文字通りで水を配分する権能も持っておられるのか、流域の各集落からたくさんの地車が集結する。あまりにも台数が多いので神社に入りきれず、神様を一時的に引っ越ししていただいて大きな広場で奉納する。特筆すべきは「河内にわか」と称される寸劇が地車上で上演されることだ。伝統芸能でもあろう。またまた走る回る日々が続きそう、カメラの手入れも入念にやっておかないと。
どうやらご祝儀もたくさん集まっている模様ですね。


△△△ お詫びと訂正 △△△
読者の方からのご指摘で判明しましたが、9月23日付け記事「未知なる樹木との遭遇」にて誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。記事中、ウラジロガシと記述した画像が存在しますが正式にはシラカシの誤りでした。それにしても一目で識別される眼力に、ただ驚嘆の小生です。これからもご叱声をよろしくお願いします。
2009年10月06日
中秋の名月
10月の3日は旧暦で言うと8月の15日、即ち中秋の名月である。先般のニュースによれば、20代の若者にアンケート調査したら中秋の名月を存じている者は10パーセント程度だったとか。まさかとは思うが、意外と真実だったりして。従来は月の行動を主体とした太陰暦を使用していたが、明治政府の開国政策でいわゆるグローバルスタンダードの太陽暦に変更されたのはご存じのとおりである。この太陰暦、意外と便利な暦で農作業等には向いているのかも知れない。太陽暦と太陰暦との間にはおおよそ30~50日程度の時差があり、古典などを読破するときには要注意である。
雲の切れ間から一寸だけ顔を出してくれましたが。

例えば日本人の大好きな忠臣蔵、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りしたのは元禄14年12月14日の雪の日となっている。これは無論旧暦表示で、実際には新暦表示に換算すると1月の20日前後に相当する。そうでないと、なんぼ江戸(東京)でも12月中旬では雪は降らないでしょうね。かように古典類は素直に読み込むと背景がわからなくなります。多少の翻訳はやったうえでの読破が必要なようです。
やがて次第に薄暗くなってきました。

そのうちに段々とお隠れ遊ばして。

さてこのお月見の風習、いつ頃から始まったのか定かではありませんが、当地には観月祭と言うイベントが存在します。なんでも南北朝時代の後村上天皇が諸般の事情で当地の金剛寺での生活を余儀なくされ、都を忍びながら夜ごと月を愛でておられたとの故事に基づくようです。少なくとも当時には月見の風習があったようですが、実際には縄文期あたりまで遡るのではないでしょうか。日本人の本来の感性を鑑みると、数千年の昔からお月見や観梅或いは桜の花見などの風習があったものかと推測されます。
再び、お出ましになられましたようで。

さて当夜は残念ながら当地は分厚い雲に覆われました。何とか粘りまして、雲の隙間から顔を覗かせた姿が掲載の画像です。ややぼんやりしてますが、望遠レンズの手持ち撮影のためお許し下さい。本来なら古式にのっとり、ススキやお団子を供えて祭壇的なものをセッティングすべきでしょうが、諸般の事情でご勘弁を。心的には祭壇を祭った縁側でのお月見風景と心得ております。望遠レンズでしつこく覗いて見ましたが、残念ながらウサギさんが餅つきする姿は確認できませんでした。子ども達には見えても、汚れた大人なの眼では見させてもらえないのかも知れないですね。
だいぶ出てきやはりましたね。

当地の観月祭ですが、会場の金剛寺が改装工事のため10年近く開催不能とか伺いました。本年は参加できなかったのですが、昨年始めて観覧させていただき王朝絵巻のような」雰囲気を楽しませていただきました。しばらくのお預けは残念ですが、何、田圃の畦からでもお月見は可能です。毎年、旧暦8月15日を探しながら満月の姿を拝見したいと願っています。出来うるならば、ウサギさんとのご対面も。
正式な再登場です。ウサギさんはどうやっても発見出来ませんでした。

雲の切れ間から一寸だけ顔を出してくれましたが。

例えば日本人の大好きな忠臣蔵、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りしたのは元禄14年12月14日の雪の日となっている。これは無論旧暦表示で、実際には新暦表示に換算すると1月の20日前後に相当する。そうでないと、なんぼ江戸(東京)でも12月中旬では雪は降らないでしょうね。かように古典類は素直に読み込むと背景がわからなくなります。多少の翻訳はやったうえでの読破が必要なようです。
やがて次第に薄暗くなってきました。

そのうちに段々とお隠れ遊ばして。

さてこのお月見の風習、いつ頃から始まったのか定かではありませんが、当地には観月祭と言うイベントが存在します。なんでも南北朝時代の後村上天皇が諸般の事情で当地の金剛寺での生活を余儀なくされ、都を忍びながら夜ごと月を愛でておられたとの故事に基づくようです。少なくとも当時には月見の風習があったようですが、実際には縄文期あたりまで遡るのではないでしょうか。日本人の本来の感性を鑑みると、数千年の昔からお月見や観梅或いは桜の花見などの風習があったものかと推測されます。
再び、お出ましになられましたようで。

さて当夜は残念ながら当地は分厚い雲に覆われました。何とか粘りまして、雲の隙間から顔を覗かせた姿が掲載の画像です。ややぼんやりしてますが、望遠レンズの手持ち撮影のためお許し下さい。本来なら古式にのっとり、ススキやお団子を供えて祭壇的なものをセッティングすべきでしょうが、諸般の事情でご勘弁を。心的には祭壇を祭った縁側でのお月見風景と心得ております。望遠レンズでしつこく覗いて見ましたが、残念ながらウサギさんが餅つきする姿は確認できませんでした。子ども達には見えても、汚れた大人なの眼では見させてもらえないのかも知れないですね。
だいぶ出てきやはりましたね。

当地の観月祭ですが、会場の金剛寺が改装工事のため10年近く開催不能とか伺いました。本年は参加できなかったのですが、昨年始めて観覧させていただき王朝絵巻のような」雰囲気を楽しませていただきました。しばらくのお預けは残念ですが、何、田圃の畦からでもお月見は可能です。毎年、旧暦8月15日を探しながら満月の姿を拝見したいと願っています。出来うるならば、ウサギさんとのご対面も。
正式な再登場です。ウサギさんはどうやっても発見出来ませんでした。

2009年09月08日
大ヶ塚八朔市
大ヶ塚(南河内郡河南町)は石川の右岸沿いの高台にある。遠くから遠望すれば城郭のような地形なのだ。ここは寺内町とも呼ばれ、一種の宗教都市として栄えた歴史を持つ。いわばバチカン市国や高野山のような存在であろうか。無論、規模的にはそんなに大きなものではない。かって貝原益軒が著書で大ヶ塚の賑わいを紹介したそうだが、村に500戸もの民家があり・・・・・・・・・との表現だそうで、当時としては大層な繁盛ぶりであったのだろう。ここの中心は顕証寺で戦国時代の創建のようだ。本尊が阿弥陀如来だそうだから、浄土真宗いわゆる門徒衆に属する寺院であろう。町教委の資料によれば、江戸時代中期に皇室から拝領した人形を飾って一般に見せたのが八朔市の始まりであるとか。
何処も祭りの主役は子ども達でしょう。浴衣姿が絵になります。

顕証寺の正門です。一種独特な形ですね。

地元の古老に伺ってみると、それはそれは年に一度の大きな楽しみであったとか。サーカスや芝居小屋までかかり、9月の初旬の三日間、大勢の参拝客で昼夜を問わず大層賑わったようだ。現在は諸般の事情で9月の第一土日と決められているようです。往事の賑わいはないが、地元では保存会まで作られ大事に継承されている。好奇心旺盛な小生のこと、時間を作って覗いてみたのはいいが、少々早すぎたようです。露店などは店開きの準備中で、参拝客もまばら、やはり夕闇迫る頃が良さそうでした。
ただいま開店準備中のようですね。昼にはオープンのはずなんだが。

丁度昼時、ラーメン食べたかったなあ。屋台とラーメンは不思議と似合います。

門徒衆はかって加賀の国や伊勢の国で時の権力者に抵抗を続けた輝かしい歴史があります。独立自尊の気風が強いのでしょうか。大ヶ塚では神社仏閣を中心とした街作りのようですが、堺のような自治権を持った独立国家或いは抵抗勢力としての存在では無かったように思われます。顕証寺と一須賀神社を中心に自然発生的に広がって栄えた街・・・・・・そんな性格が強いようですね。八朔市も地域住民のイベントとして或いは生活用具の購入場所として維持発展してきたようです。無論、人の集まるところに宗教活動ありで、布教等も行われたのでしょう。顕証寺に参拝したら、法話を人形で表現する舞台が設置されてました。下記の画像です。
法話が人形で表現されています。布教活動の道具だったのでしょう。


祭りのハイライトとも言える夕暮れ時に再度出直ししようと思っていたのですが、時間が取れずじまいでした。残念ながら来年に期待をつなぎたいと思います。忘れないように日時を控えておきましょう。例年、9月の第一の土日が祭礼日だそうです。祭りは伝統として継承されてきた無形の資産、大事に次の世代へと送り届けて行きたいものです。
八朔市は9月の第一の土日、忘れないように記録しておこう。

明治中期の町内地図です。

何処も祭りの主役は子ども達でしょう。浴衣姿が絵になります。

顕証寺の正門です。一種独特な形ですね。

地元の古老に伺ってみると、それはそれは年に一度の大きな楽しみであったとか。サーカスや芝居小屋までかかり、9月の初旬の三日間、大勢の参拝客で昼夜を問わず大層賑わったようだ。現在は諸般の事情で9月の第一土日と決められているようです。往事の賑わいはないが、地元では保存会まで作られ大事に継承されている。好奇心旺盛な小生のこと、時間を作って覗いてみたのはいいが、少々早すぎたようです。露店などは店開きの準備中で、参拝客もまばら、やはり夕闇迫る頃が良さそうでした。
ただいま開店準備中のようですね。昼にはオープンのはずなんだが。

丁度昼時、ラーメン食べたかったなあ。屋台とラーメンは不思議と似合います。

門徒衆はかって加賀の国や伊勢の国で時の権力者に抵抗を続けた輝かしい歴史があります。独立自尊の気風が強いのでしょうか。大ヶ塚では神社仏閣を中心とした街作りのようですが、堺のような自治権を持った独立国家或いは抵抗勢力としての存在では無かったように思われます。顕証寺と一須賀神社を中心に自然発生的に広がって栄えた街・・・・・・そんな性格が強いようですね。八朔市も地域住民のイベントとして或いは生活用具の購入場所として維持発展してきたようです。無論、人の集まるところに宗教活動ありで、布教等も行われたのでしょう。顕証寺に参拝したら、法話を人形で表現する舞台が設置されてました。下記の画像です。
法話が人形で表現されています。布教活動の道具だったのでしょう。


祭りのハイライトとも言える夕暮れ時に再度出直ししようと思っていたのですが、時間が取れずじまいでした。残念ながら来年に期待をつなぎたいと思います。忘れないように日時を控えておきましょう。例年、9月の第一の土日が祭礼日だそうです。祭りは伝統として継承されてきた無形の資産、大事に次の世代へと送り届けて行きたいものです。
八朔市は9月の第一の土日、忘れないように記録しておこう。

明治中期の町内地図です。

2009年08月25日
地蔵盆の頃
8月24日は地蔵盆である、地蔵菩薩への信仰というより子ども達を喜ばす習俗といったほうが実態に近いかも知れない。小生は地方のローカルな地域で育ったのだが、附近に地蔵盆の慣習はなかった。従って大阪へ出てきてビックリしたのがこの地蔵盆である。どこの地域でも盛大に祭られており、夏休みの末期ともあって子ども達の一大イベントのようだ。元々、地蔵菩薩は子ども達の守り神であり、賽の河原で子ども達が地獄の鬼達に責められるのを救ってくださるそうだ。
お地蔵様です。なんとも柔和な表情を為さっておられます。

地蔵信仰は仏教の六道輪廻の思想が根底にあるのだろう。すなわち、地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道の六つの世界だが、すべての生命はこの6個の世界に生まれ変わりを繰り返すそうだ。、この6個の世界で悩める生命の支援者であり救済者であるのが地蔵菩薩なんだろう。最も、地蔵盆でいうところの「地蔵」は、お寺にある地蔵菩薩ではなく道祖神としてのお地蔵さんであろう。民話の笠地蔵のお話といった方がわかりやすいかも知れない。無論、子ども達にはそんなお話よりはお供えされた果物やお菓子やジュース類がお目当てなんだろう。
祭り提灯もお供えも見あたりませんでした。当然か。

こちらも平常時モードですね。お祭りは土日のようで。

24日に数カ所を回ってみたが何処も静まりかえっている。平常通りで祭りの気配などみじんもない。地元の方に聞き出してみると、すでに終わったよとの事。24日が縁日で本来はこの日の開催なのだが、世話役さんの都合や子ども達の日程等も考慮して前後の土日に変更されるケースが多いとのこと。そういえば24日は月曜日、22日か23日に既に終了した模様。祭りの習俗を撮影したかったのだが、来夏まで待つしかなさそうだ。
どこのお地蔵様も手入れが行き届いています、信仰が厚いようで。

当地でも笠地蔵ではないですが、六地蔵があちこちで祭られています。やはり六道輪廻の世界観は日本人の意識を超えた無意識の世界にまで溶け込んでしまっているようですね。
当地のとあるお寺の山門に控えておられる六地蔵です。

お地蔵様です。なんとも柔和な表情を為さっておられます。

地蔵信仰は仏教の六道輪廻の思想が根底にあるのだろう。すなわち、地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道の六つの世界だが、すべての生命はこの6個の世界に生まれ変わりを繰り返すそうだ。、この6個の世界で悩める生命の支援者であり救済者であるのが地蔵菩薩なんだろう。最も、地蔵盆でいうところの「地蔵」は、お寺にある地蔵菩薩ではなく道祖神としてのお地蔵さんであろう。民話の笠地蔵のお話といった方がわかりやすいかも知れない。無論、子ども達にはそんなお話よりはお供えされた果物やお菓子やジュース類がお目当てなんだろう。
祭り提灯もお供えも見あたりませんでした。当然か。

こちらも平常時モードですね。お祭りは土日のようで。

24日に数カ所を回ってみたが何処も静まりかえっている。平常通りで祭りの気配などみじんもない。地元の方に聞き出してみると、すでに終わったよとの事。24日が縁日で本来はこの日の開催なのだが、世話役さんの都合や子ども達の日程等も考慮して前後の土日に変更されるケースが多いとのこと。そういえば24日は月曜日、22日か23日に既に終了した模様。祭りの習俗を撮影したかったのだが、来夏まで待つしかなさそうだ。
どこのお地蔵様も手入れが行き届いています、信仰が厚いようで。

当地でも笠地蔵ではないですが、六地蔵があちこちで祭られています。やはり六道輪廻の世界観は日本人の意識を超えた無意識の世界にまで溶け込んでしまっているようですね。
当地のとあるお寺の山門に控えておられる六地蔵です。

2009年08月24日
秋の味覚
空の蒼さも一際鮮やかになってきました。暦は8月真夏ですが、季節は限りなく秋へと近づいているようです。本日も飛行機雲が何回も青空を横切り、澄み渡った空と真っ白い飛行跡とが見事なコントラストでした。こうなってきますと秋の味覚がボチボチと・・・・・・・・・・・。やはり代表的なものは栗と柿でしょう。特に栗は来月に入ると収穫が可能です。そんなにおいしいとは思いませんが、年に数回は食べておきたい果実ですね。ある意味タケノコと同じでしょうか、季節を感じる旬の食材として。
はや色づき始めましたね、マイ果樹園の栗の木です。

割と大粒の実が沢山付いていますね、丹波栗の木が2本あります。

柿も実をつけてくれているようですが、こちらはもう少し後のようです。樹によって毎年実を付けるのと隔年なのとがあるようです。気をつけたいのが、摘果をしないでたくさん実らせたままだと、翌年は実を付けないケースが多いようです。柿の木が自分なりに判断して限られた栄養素をうまく配分しているようですね。私宅の庭の柿の木がこのパターンでした、毎年実っていましたが今年は1個も実を付けていません。
谷間の農園の柿の木です。今年の実の付きは少なめなようです。

これ以外にも梨やリンゴがあるのですが、梨は昨秋に2本植え込んだものの若葉を数枚出しただけで成長の兆しが見えません。土地にあわず枯れたのかも知れないですね。リンゴの木は同じく2本あって品種も違えてますが、開花はあっても結実まではいきませんでした。こちらも気象条件からみて栽培が困難な果樹かも知れませんね。当地では柑橘類が栽培しやすく収穫物も喜ばれます。但し、幹に穴を開けて食い破るゴマダラカミキリの被害が多くて、消毒を的確に実施しないと収穫に結びつきにくいのが難点です。
おもしろいですね、竜巻みたいな雲が広がりました。

作業の合間に雲を眺めて休んでいたら、おもしろい造形物を見せてくれます。瞬時に変化していくので、カメラを手元に置いとかないとチャンスを逃がしますが、なかなか楽しいものです。本日の一押しはこの竜巻模様。台風のニュースはありませんので、気象条件からくるものではなく、単なる風の悪戯かとおもいますが。それともう一点が次の飛行機雲、谷間の農園の上空は飛行路になっているのかジェット旅客機や戦闘機がよく飛び交います。本日も白煙を残しながら戦闘機が飛び去っていきましたが、アキアカネが必死になって追いかけていました。そのちぐはぐな動きがおもしろくて、はいパチリ。
アキアカネが戦闘機を追いかけています、何とも健気な。

アキアカネ(赤とんぼ)は白い飛行跡の一番先の少し下側です。発見されましたでしょうか。
はや色づき始めましたね、マイ果樹園の栗の木です。

割と大粒の実が沢山付いていますね、丹波栗の木が2本あります。

柿も実をつけてくれているようですが、こちらはもう少し後のようです。樹によって毎年実を付けるのと隔年なのとがあるようです。気をつけたいのが、摘果をしないでたくさん実らせたままだと、翌年は実を付けないケースが多いようです。柿の木が自分なりに判断して限られた栄養素をうまく配分しているようですね。私宅の庭の柿の木がこのパターンでした、毎年実っていましたが今年は1個も実を付けていません。
谷間の農園の柿の木です。今年の実の付きは少なめなようです。

これ以外にも梨やリンゴがあるのですが、梨は昨秋に2本植え込んだものの若葉を数枚出しただけで成長の兆しが見えません。土地にあわず枯れたのかも知れないですね。リンゴの木は同じく2本あって品種も違えてますが、開花はあっても結実まではいきませんでした。こちらも気象条件からみて栽培が困難な果樹かも知れませんね。当地では柑橘類が栽培しやすく収穫物も喜ばれます。但し、幹に穴を開けて食い破るゴマダラカミキリの被害が多くて、消毒を的確に実施しないと収穫に結びつきにくいのが難点です。
おもしろいですね、竜巻みたいな雲が広がりました。

作業の合間に雲を眺めて休んでいたら、おもしろい造形物を見せてくれます。瞬時に変化していくので、カメラを手元に置いとかないとチャンスを逃がしますが、なかなか楽しいものです。本日の一押しはこの竜巻模様。台風のニュースはありませんので、気象条件からくるものではなく、単なる風の悪戯かとおもいますが。それともう一点が次の飛行機雲、谷間の農園の上空は飛行路になっているのかジェット旅客機や戦闘機がよく飛び交います。本日も白煙を残しながら戦闘機が飛び去っていきましたが、アキアカネが必死になって追いかけていました。そのちぐはぐな動きがおもしろくて、はいパチリ。
アキアカネが戦闘機を追いかけています、何とも健気な。

アキアカネ(赤とんぼ)は白い飛行跡の一番先の少し下側です。発見されましたでしょうか。
2009年08月11日
夏祭りの頃
夏休みも中盤にはいり子ども達も少々だれ気味なようですね。頃合いを見計らったように、各地で夏祭りが開催されます。当地は河内の国、言わずと知れた河内音頭の本場でもあります。各集落には名人クラスがおられるようで、中にはセミプロとしてギャラを頂いて各地を回る猛者もあるようです。夏祭りは盆踊りが定番で、組まれた櫓を中心に輪になって踊るのですが、最近は踊りを知らない方々が多いようです。かくいう小生も全くダメな口で、もっぱら外側からレンズを向ける役割ですね。踊っておられるのは、やはり年配のご婦人方が多いようです。浴衣がけの若い娘さんなどが踊りにはいってくれたら絵になるんですが、期待薄なようですね。子ども達はもっぱらゲームや屋台での買い食いのようです。
夕闇迫り、祭りは佳境を迎えるようです。親子連れが楽しそうですね。

何を釣っているのでしょうか、釣り竿らしき用具のようですが。

近くの集落の夏祭りを覗いてみました。圧倒的に子どもが多く、どこにこんな子ども達がいたのか、と不思議に思うくらい。普段、子ども達に接する機会が少ないだけにびっくりします。本日に限っては少子化問題どこ吹く風よ・・・・・・・の心境でしょうか。多分、あちこちの集落からも集まって来ているのでしょう。夏休みの子ども達にとっては、かっこうの気分転換ですね。飲み物も食べ物もあり、親の監視も今夜は緩め、大いに羽目を外しているようです。
夏祭りに最適なのはやはり浴衣ですね。絵になります。

これはヨーヨー釣りのようですね。かすかな記憶があります。

多くは各集落の自治会(町内会)で取り組まれているようです。担当して下さる役員さん達は早くから企画を練り準備を続けて下さったのでしょう。たった1日の祭りではありますが、住民の親睦と憩いの場になっています。とりわけ子ども達にとっては久方ぶりの夢の世界ではと想像しております。こうした機会を通じて、集団生活の意味やルールなども学んでいくのではないでしょうか。大変な取り組みを有り難く受け止めています。
盆踊りは踊り手が少なく、少々寂しげでした。前の少年も踊りたいようですね。

裏方さんは少々お疲れ気味の模様、ご苦労様です。

大人達が子ども達の幸福を願って必死になって何事かに取り組んでいる・・・・・・・そうした想いと活動は必ずや子ども達に伝わっていると信じます。家族や周囲の大人達から大事にされ愛されて育った子ども達は、横道に逸れることは絶対にあり得ない・・・・・・・確信をもってそう言い切れるかと思います。
夕闇迫り、祭りは佳境を迎えるようです。親子連れが楽しそうですね。

何を釣っているのでしょうか、釣り竿らしき用具のようですが。

近くの集落の夏祭りを覗いてみました。圧倒的に子どもが多く、どこにこんな子ども達がいたのか、と不思議に思うくらい。普段、子ども達に接する機会が少ないだけにびっくりします。本日に限っては少子化問題どこ吹く風よ・・・・・・・の心境でしょうか。多分、あちこちの集落からも集まって来ているのでしょう。夏休みの子ども達にとっては、かっこうの気分転換ですね。飲み物も食べ物もあり、親の監視も今夜は緩め、大いに羽目を外しているようです。
夏祭りに最適なのはやはり浴衣ですね。絵になります。

これはヨーヨー釣りのようですね。かすかな記憶があります。

多くは各集落の自治会(町内会)で取り組まれているようです。担当して下さる役員さん達は早くから企画を練り準備を続けて下さったのでしょう。たった1日の祭りではありますが、住民の親睦と憩いの場になっています。とりわけ子ども達にとっては久方ぶりの夢の世界ではと想像しております。こうした機会を通じて、集団生活の意味やルールなども学んでいくのではないでしょうか。大変な取り組みを有り難く受け止めています。
盆踊りは踊り手が少なく、少々寂しげでした。前の少年も踊りたいようですね。

裏方さんは少々お疲れ気味の模様、ご苦労様です。

大人達が子ども達の幸福を願って必死になって何事かに取り組んでいる・・・・・・・そうした想いと活動は必ずや子ども達に伝わっていると信じます。家族や周囲の大人達から大事にされ愛されて育った子ども達は、横道に逸れることは絶対にあり得ない・・・・・・・確信をもってそう言い切れるかと思います。
2009年06月13日
蛍の里
知人の奥さんから素敵なニュースが飛び込んできた。河内長野の奥の方で蛍が乱舞していると・・・・・・・・・・・・・もっとも知人の奥様は街のご出身。辺境のど田舎で育った小生から見ると、乱舞という表現にはいささか誇大表現では、との思いはあった。何せこのご時世、清流など望みがたい環境だからだ。蛍はご存じの方も多いだろうが、とてもデリケートな昆虫(?)、ちょっとした環境悪化で死滅してしまう。幼虫の食料であるカワニナが生息できるのは清流で緩やかな流れそして水草などがたくさん繁っているような場所、なかなかそんな環境は南河内といえ少ないのだ。半信半疑ではあったが、夕闇迫るのをまって出発し、午後8時過ぎに現場に到着した。田舎育ちの小生には乱舞とは言い難い状態だが、確かにたくさんの蛍が飛び交っている。
蛍の生息地を示す立て看板、市役所による設置なようです。

石見川の清流です。透き通ってますね。

ご存じの方も多いとみえ、たくさんの家族連れが散策しておられる。現場公表は控えたいが、蛍をまだ見ぬ方もおられるだろう。南海三日市駅と延命寺とを結ぶ道路で、道半ばより少し駅よりの地点、東片添町あたりである。民家の周辺には石川の支流である石見川が流れ、それ以外にも用水路があって水際を蛍が飛び交っているのだ。地域の小学生がガイド役を買って出てくれて細やかな解説付きだ。何でも午後9時過ぎあたりが一番多い時間帯らしい、雨上がりの翌日くらいが良い環境だとか。彼によると雄と雌との識別が可能なようだが、小生が見てもさっぱりわからなかった。蛍は非常にデリケートな生き物、できるだけ眺めるだけで触れるのは避けておきたい。捕虫網など以ての外である。
この付近はハイキングコースでもあります。紅葉時にはごった返しますよ。

せめて画像をとシャッターをおすが露光不足で真っ黒けだ。バルブ解放でとも思ったが三脚も持参していない。残念ながら小生の技量では蛍の微妙な輝きを映像化するのは困難なようです。それにしてもテレビドキュメントで蛍の生息を見たことがあるが、どうしてあんな画像が撮れるのかとても不思議である。プロとアマとの違いと言ってしまえばそれまでなんだが。
何十枚も撮ったなかでかろうじて光が写っていたものを下記に登載しておきます。説明なしでは蛍とわかんないですね。
かろうじて蛍の光を捕捉しました。

散策中のじいさまが話しかけてこられた。何でも、ここより花の文化園近くが蛍が多いとか。そういえば二十年位まえになるが、滝畑ダムの下流域である日野地区に蛍見学に出掛け、それこそ乱舞する姿に驚喜したものだ。数年通ったが次第に蛍も少なくなり、最近は消滅したのではと想像していた。どうやら又復活してくれていたようだ。河内長野には蛍の会というボランティア団体があって蛍の復活に尽力されているとか。彼の人々の功績によるものかも知れない。生活用水特に合成洗剤の使用や田畑での農薬の使用、或いは河川がコンクリートで固められる等々の環境悪化で、蛍の生息条件は極めて厳しくなってきている。里山の景観保全や蛍の復活には我々の生活スタイルを根本から見直す必要性があるようですね。今、すぐには困難かも知れませんが、一人が変わり二人が変わり・・・・・・・・・・・・地道な活動の連鎖で蛍との共存を叶えたいものです。
水底が見えますね。蛍にはこうした環境が必要不可欠なんです。

水と生活とが一体化しています。民家の周辺ですがゴミ一つありません。

蛍の生息地を示す立て看板、市役所による設置なようです。

石見川の清流です。透き通ってますね。

ご存じの方も多いとみえ、たくさんの家族連れが散策しておられる。現場公表は控えたいが、蛍をまだ見ぬ方もおられるだろう。南海三日市駅と延命寺とを結ぶ道路で、道半ばより少し駅よりの地点、東片添町あたりである。民家の周辺には石川の支流である石見川が流れ、それ以外にも用水路があって水際を蛍が飛び交っているのだ。地域の小学生がガイド役を買って出てくれて細やかな解説付きだ。何でも午後9時過ぎあたりが一番多い時間帯らしい、雨上がりの翌日くらいが良い環境だとか。彼によると雄と雌との識別が可能なようだが、小生が見てもさっぱりわからなかった。蛍は非常にデリケートな生き物、できるだけ眺めるだけで触れるのは避けておきたい。捕虫網など以ての外である。
この付近はハイキングコースでもあります。紅葉時にはごった返しますよ。

せめて画像をとシャッターをおすが露光不足で真っ黒けだ。バルブ解放でとも思ったが三脚も持参していない。残念ながら小生の技量では蛍の微妙な輝きを映像化するのは困難なようです。それにしてもテレビドキュメントで蛍の生息を見たことがあるが、どうしてあんな画像が撮れるのかとても不思議である。プロとアマとの違いと言ってしまえばそれまでなんだが。
何十枚も撮ったなかでかろうじて光が写っていたものを下記に登載しておきます。説明なしでは蛍とわかんないですね。
かろうじて蛍の光を捕捉しました。

散策中のじいさまが話しかけてこられた。何でも、ここより花の文化園近くが蛍が多いとか。そういえば二十年位まえになるが、滝畑ダムの下流域である日野地区に蛍見学に出掛け、それこそ乱舞する姿に驚喜したものだ。数年通ったが次第に蛍も少なくなり、最近は消滅したのではと想像していた。どうやら又復活してくれていたようだ。河内長野には蛍の会というボランティア団体があって蛍の復活に尽力されているとか。彼の人々の功績によるものかも知れない。生活用水特に合成洗剤の使用や田畑での農薬の使用、或いは河川がコンクリートで固められる等々の環境悪化で、蛍の生息条件は極めて厳しくなってきている。里山の景観保全や蛍の復活には我々の生活スタイルを根本から見直す必要性があるようですね。今、すぐには困難かも知れませんが、一人が変わり二人が変わり・・・・・・・・・・・・地道な活動の連鎖で蛍との共存を叶えたいものです。
水底が見えますね。蛍にはこうした環境が必要不可欠なんです。

水と生活とが一体化しています。民家の周辺ですがゴミ一つありません。

2009年05月29日
春季大祭
滝谷不動明王寺は南河内の古刹である。弘法大師の開山とも伝えられおよそ1200年程の歴史を誇るようだ。毎月28日は月例祭として賑わい、大勢の善男善女の参拝が続く。なかでも5月の28日は特別な日とされ、本尊御縁日として山伏による護摩供養が実施される。今回、初めてその全容を拝見させていただいた。結界を張られた境内の一画には既に多くの信者と覚しく人々が詰め、早くも頭を垂れて祈りを捧げる人達も。小生は運良く正面の一番前に陣取る事が出来た。檜で作られた祭壇(?)が目の前である。弘法大師で知られるように、ここは真言宗の智山派に属する寺院である。彼の楠木正成の信仰も厚かったようだ。一般的には眼の神様として信心を集めているようで、小生も老眼の進行が早いようなので参拝の必要性が高いかも。
護摩供養の開始です。敬虔な祈りが捧げられます。

お寺のお坊様がたも参列と読経を。

先達と覚しき老行者の司会によって始まった。まずは山伏の入場と読経、続いて当山の僧侶の方々の入場と読経と続いていく。開会のセレモニーなのだろう。ここからは修験道の独特な世界となるようで、大峰山から来訪された行者を結界に入れるか入れないかで問答となり、無事に入場を果たして又読経・・・・・・・・・荘厳な男性合唱団の如き読経の声が境内に響き渡る。何度聞いてもいいものだ。四方に矢を打ち込む儀式や斧で護摩を切り開く儀式など不思議なパフォーマンスが続いていく。やがて松明に点火していよいよ護摩供養の開始だ。モクモクと舞い上がる煙に圧倒される。それでも行者は動かず読経が続いていく。息苦しくは無いのだろうか。
数珠捌きにも独特な意味合いがあるのでしょうね。

東西南北(?)に矢を打ち込みます。

ある程度煙が納まったら護摩木の投入だ。ここでも修験者らしく一定の作法に則って信者の書かれた護摩木を炎の中へと投入する。当然その間も読経の声は延々と続いている。見ていると意味は不明だが、両手で戒を切るとでもいうのだろうか、独特な作法で護摩木を受け取り、二礼して炎の中へと投入される。修験者にとって護摩木は特別な存在であり尊重すべき対象なのかも知れない。彼らは修行者でもあり宗教者でもあるのだろう。信者の願いを受け止め、目に見えぬ神々の世界へと橋渡しを行う仲介者でもあるようだ。自宅から持ち込んだ数珠などを護摩の炎にかざしてくれるよう頼み込む人々も多い。護摩供養の炎によって邪険なものが焼き払われる、というような意味合いなのだろうか。
護摩に点火されました。檜の枝が強烈な煙を吹き出します。



それにしても相当な数量の護摩木だ。何万本もあるのではなかろうか。檜か杉を長方形に削った木片、これに願い事をかいてご本尊に備え春季大祭の護摩供養で燃やすようだ。供養料が1本300円、数万本として売り上げが7桁~8桁、しかも宗教法人は非課税・・・・・・・・・・・・・・・・・と、つい下世話な事を考えてしまう。邪念の持ち主のようだ。行く末は地獄界であろうか。こうした事例を見ていると、日本人の7割が無宗教だが無神論者ではない、という説も肯定できるようだ。言葉をかえれば宗教界が人々を引き寄せるだけの魅力を持ち得ていないという事かも知れない。宗教界には、葬祭執行業者としての存在以上の役割を担い得る可能性が充分に秘められていると想像しているのだが。
信者の願い事が書かれた護摩木を炎の中に投入します。

膨大な護摩木が数カ所に山積みされています。

およそ2時間の護摩供養、充分に堪能させていただいた。それにしてもホラ貝の音が混じった読経の声は何とも涼やかなものである。優秀なグリークラブの歌声よりも数段上の雰囲気を醸し出しているのではなかろうか。何度遭遇しても聞き惚れてしまう。次は7月に金剛山で又修験者の皆さん方にお会いしましょう、護摩供養とともに今度こそは火渡りの儀式に参加しなければと期待を込めている。
真っ赤な炎は全てを焼き尽くしてくれます。邪念も消滅でしょう。

護摩供養の開始です。敬虔な祈りが捧げられます。

お寺のお坊様がたも参列と読経を。

先達と覚しき老行者の司会によって始まった。まずは山伏の入場と読経、続いて当山の僧侶の方々の入場と読経と続いていく。開会のセレモニーなのだろう。ここからは修験道の独特な世界となるようで、大峰山から来訪された行者を結界に入れるか入れないかで問答となり、無事に入場を果たして又読経・・・・・・・・・荘厳な男性合唱団の如き読経の声が境内に響き渡る。何度聞いてもいいものだ。四方に矢を打ち込む儀式や斧で護摩を切り開く儀式など不思議なパフォーマンスが続いていく。やがて松明に点火していよいよ護摩供養の開始だ。モクモクと舞い上がる煙に圧倒される。それでも行者は動かず読経が続いていく。息苦しくは無いのだろうか。
数珠捌きにも独特な意味合いがあるのでしょうね。

東西南北(?)に矢を打ち込みます。

ある程度煙が納まったら護摩木の投入だ。ここでも修験者らしく一定の作法に則って信者の書かれた護摩木を炎の中へと投入する。当然その間も読経の声は延々と続いている。見ていると意味は不明だが、両手で戒を切るとでもいうのだろうか、独特な作法で護摩木を受け取り、二礼して炎の中へと投入される。修験者にとって護摩木は特別な存在であり尊重すべき対象なのかも知れない。彼らは修行者でもあり宗教者でもあるのだろう。信者の願いを受け止め、目に見えぬ神々の世界へと橋渡しを行う仲介者でもあるようだ。自宅から持ち込んだ数珠などを護摩の炎にかざしてくれるよう頼み込む人々も多い。護摩供養の炎によって邪険なものが焼き払われる、というような意味合いなのだろうか。
護摩に点火されました。檜の枝が強烈な煙を吹き出します。



それにしても相当な数量の護摩木だ。何万本もあるのではなかろうか。檜か杉を長方形に削った木片、これに願い事をかいてご本尊に備え春季大祭の護摩供養で燃やすようだ。供養料が1本300円、数万本として売り上げが7桁~8桁、しかも宗教法人は非課税・・・・・・・・・・・・・・・・・と、つい下世話な事を考えてしまう。邪念の持ち主のようだ。行く末は地獄界であろうか。こうした事例を見ていると、日本人の7割が無宗教だが無神論者ではない、という説も肯定できるようだ。言葉をかえれば宗教界が人々を引き寄せるだけの魅力を持ち得ていないという事かも知れない。宗教界には、葬祭執行業者としての存在以上の役割を担い得る可能性が充分に秘められていると想像しているのだが。
信者の願い事が書かれた護摩木を炎の中に投入します。

膨大な護摩木が数カ所に山積みされています。

およそ2時間の護摩供養、充分に堪能させていただいた。それにしてもホラ貝の音が混じった読経の声は何とも涼やかなものである。優秀なグリークラブの歌声よりも数段上の雰囲気を醸し出しているのではなかろうか。何度遭遇しても聞き惚れてしまう。次は7月に金剛山で又修験者の皆さん方にお会いしましょう、護摩供養とともに今度こそは火渡りの儀式に参加しなければと期待を込めている。
真っ赤な炎は全てを焼き尽くしてくれます。邪念も消滅でしょう。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン